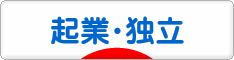| 経営者とは 稲盛和夫とその門下生たち |
| クリエーター情報なし | |
| 日経BP社 |
口先だけの人は多い。
見せかけの成果を誇る人も結構多い。
でも、実際に行動する人は少なく、
成果をあげる人はもっと少ない。
稲盛和夫氏が支持されるのは、
誰にも成し遂げられなかったことを
成し遂げてきたからです。見せかけではなく。
成果を上げられる人になりたいと思って
稲盛和夫関連の著作を読む。
盛和塾という稲盛和夫氏が主宰する経営塾があります。
稲盛氏を慕う経営者のあつまりですが、
稲盛氏はこの塾生たちを「ソウルメイト」といって
とても大切にしています。
海千山千の創業型経営者だけでなく
悩める2代目、3代目の経営者も塾の門をたたくと言います。
「経営者とは何か」について深く考えないまま
経営者に就いたすえの行き詰まり。
稲盛氏自身が盛和塾に人が集まる理由を3点あげています。
①孤独な経営者が悩みを吐露できる場である
②経営者の人間的魅力を高めるという方向性
③経営者として向上するには「思いやり」が大切だというベース―利他の精神
宗教じみていると思われる方もいらっしゃると思いますが
実際のところ、稲盛氏は65歳の時に臨済宗妙心寺派円福寺で得度しています。
本書には、門下生7人の話も掲載されています。
「ブックオフ」や「俺のフレンチ」で有名な坂本孝氏や
地元で確固たる地位を築き上げている企業経営者、
中国人経営者までさまざまな方たちです。
それぞれが稲盛氏とのかかわりをのべておられます。
にほんブログ村