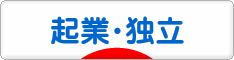最近、盛んに言われ始めているストーリー戦略。
手っ取り早く言うと、
顧客の共感を得るような物語を創り出すことで
購買意欲を高めようとする戦略らしいです。
イノベーションによって新規の市場ができたら、
「新しいということ」が差別化につながりますが、
古い市場で、どこも同じような商品・サービスでは
一体どれを選んだら良いのか顧客側も迷ってしまうし、
売るほうも差別化をアピールすることができません。
そこで、考え出されたのが「ストーリー」というわけですが
顧客の共感を得るというところがミソです。
単なる自慢話や、ここがすごい!という物語では
なかなか共感を得にくいはず。
そこで本書の著者は、「葛藤」を書けといいます。
今まで最も辛かったときの話が、
最も共感を得やすいというわけです。
要点をまとめると
・会社の物語に顧客を巻き込み、
商品を・サービスを購入してもらう手法。
・小さな会社が、従来の性能・品質や価格などの競争から離れたところで、
No1、オンリー1のポジションを手に入れるための戦略
・記憶に残る魅力ある物語をつくるための方法。
「ヒーローズ・ジャーニー」を応用して、
明確でシンプルなビジョンを物語にする方法。
・ソーシャルメディアを中心とした
Webツールを活用した物語の伝え方。
・物語の作り方
目標を掲げて何かを始める
挫折・葛藤がある
乗り越えるきっかけができてブレイク・スルー
徐々にうまくいき宝を得る
さらに高い志を持ち、次の旅へ向かう
・大切なのは物語に〝葛藤"をつくること
人から見て、最も興味深い話は、今まで最も辛かったときの話
それが多くの共感者をつくる秘訣

にほんブログ村
手っ取り早く言うと、
顧客の共感を得るような物語を創り出すことで
購買意欲を高めようとする戦略らしいです。
イノベーションによって新規の市場ができたら、
「新しいということ」が差別化につながりますが、
古い市場で、どこも同じような商品・サービスでは
一体どれを選んだら良いのか顧客側も迷ってしまうし、
売るほうも差別化をアピールすることができません。
そこで、考え出されたのが「ストーリー」というわけですが
顧客の共感を得るというところがミソです。
単なる自慢話や、ここがすごい!という物語では
なかなか共感を得にくいはず。
そこで本書の著者は、「葛藤」を書けといいます。
今まで最も辛かったときの話が、
最も共感を得やすいというわけです。
 | なぜ桃太郎はキビ団子ひとつで仲間を増やせるのか?~儲かる会社は知っている! ~ |
| クリエーター情報なし | |
| TAC出版 |
要点をまとめると
・会社の物語に顧客を巻き込み、
商品を・サービスを購入してもらう手法。
・小さな会社が、従来の性能・品質や価格などの競争から離れたところで、
No1、オンリー1のポジションを手に入れるための戦略
・記憶に残る魅力ある物語をつくるための方法。
「ヒーローズ・ジャーニー」を応用して、
明確でシンプルなビジョンを物語にする方法。
・ソーシャルメディアを中心とした
Webツールを活用した物語の伝え方。
・物語の作り方
目標を掲げて何かを始める
挫折・葛藤がある
乗り越えるきっかけができてブレイク・スルー
徐々にうまくいき宝を得る
さらに高い志を持ち、次の旅へ向かう
・大切なのは物語に〝葛藤"をつくること
人から見て、最も興味深い話は、今まで最も辛かったときの話
それが多くの共感者をつくる秘訣
にほんブログ村