京都大学の客員準教授として学生に講義する著者が
20代の若者に向けて書いた、
本物の資本主義社会で生き抜く考え方を示した本です。
先の見えない混沌とした世の中で
正規軍的な戦いではなく
臨機応変に戦術を変える
「ゲリラ」的な戦いをせよ、
そのために、投資家的な考え方を身につけよ
というのが著者の主張内容です。
著者によれば、
自分では何も考えず、
ただ人に使われているだけの人は
コモディティ化するという。
コモディティ化とは個性のない状態、
平準化された状態をいいます。
コモディティ化された人材は
いつでも交代可能なので
「安いことが売り」の人材になるしかないのだと。
主体的に稼ぐ人間になるためには
次の6タイプのいずれかになるのが近道だという。
①トレーダー
商品を遠くに運んで売ることができる人
②エキスパート
自分の専門性を高めて、高いスキルによって仕事をする人
③マーケター
商品に付加価値をつけて、市場に合わせて売ることができる人
④イノベーター
まったく新しい仕組みをイノベーションできる人
⑤リーダー
自分が起業家となり、みんなをマネージしてリーダーとして行動する人
⑥インベスター
投資家として市場に参加している人
このうち価値を失っていくタイプが2つあるそうです。
それは、なにか?
本書を読んでください(笑)
説得力はあります。
もっとも、本書の内容にはつっこみどころがたくさんあります。
私の専門?のフランチャイズについて
書かれた箇所について少し述べておきます。
第8章 「投資家として生きる本当の意味」において
フランチャイズ加盟は「ハイリスク・ローリターン」の
最悪なビジネスとコテンパンの言われようでした(笑)
フランチャイズビジネスの負の側面は
経済誌などでよく書かれていることなので
著者の言わんとするところはわかります。
しかし、実際にフランチャイジーとして経営している者からすると
一方的な断定と判断の偏りがあるように思いました。
私の感覚では
本書に書かれているような「自分で商売を始めるよりも、
本部の言う通りやった方が楽だから」という気持ちで
FC加盟というハイリスクな投資をする人は
ほとんどいないんじゃないかなと思います。
もし仮に、そう思って加盟するならば
どんな仕事をしたって失敗しますよ。
フランチャイズに加盟するから失敗するわけではない。
そういう心構えで加盟するから失敗するのです。
フランチャイズも契約の世界なので
契約内容によっては自由度の大きい経営を行うことは可能です。
拘束力が強いのは、そういう契約を自ら選んだ判断によって生じています。
これは自分で商売する場合でも
取引先との契約内容によっては
大きな拘束力を生むケースが考えられるので、
フランチャイズビジネスを最悪のビジネスというには根拠が薄弱でしょう。
フランチャイズの仕組みも説明していましたが
加盟金とロイヤリティを混同しているのではないか
と思える節があるのと、
FC契約にも様々な内容のものがあり、
本書に取り上げられている内容のものだけではないにもかかわらず、
それをもってFCビジネス全般を評価しているのも安直にすぎるでしょう。
フランチャイズビジネスのメリットの一つには
FC本部の「ブランド」を利用できる点にあります。
同じ程度のブランド力=信用力を作り上げるのには
やっぱり時間と資金と手間がかかってしまいます。
FC本部はそのブランドを構築するのに長い労力をかけており
そのブランドの利用料として適正な対価を支払うのは、
ビジネスとして当然だと思いますが、
著者はそうは思わないらしい。
また、そのブランドを維持するために
店舗運営上の質を加盟店に求めるのも
ビジネスとしては当然の要請だと思うのですが、
これまた著者はそう思わないらしい。
フランチャイジーでも、工夫次第では
著者のいう③~⑥になりうる可能性はあります。
若者に武器を配りたいという、
その方針自体は素晴らしいと思いますが
はたしてその武器は本当に戦える武器といえるのかどうか。
本書を鵜呑みにするのではなく
批判的に検討することがかえって「戦える武器」を
持つことにつながるんじゃないかなぁ
と思う次第です。
日経を鵜呑みにするな
という著者の主張と同じです。
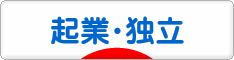 にほんブログ村
にほんブログ村


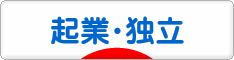 にほんブログ村
にほんブログ村























