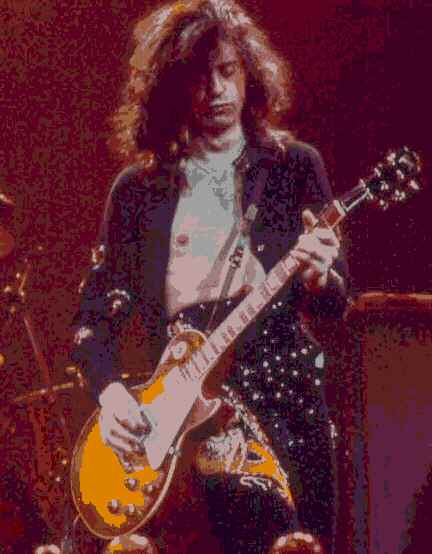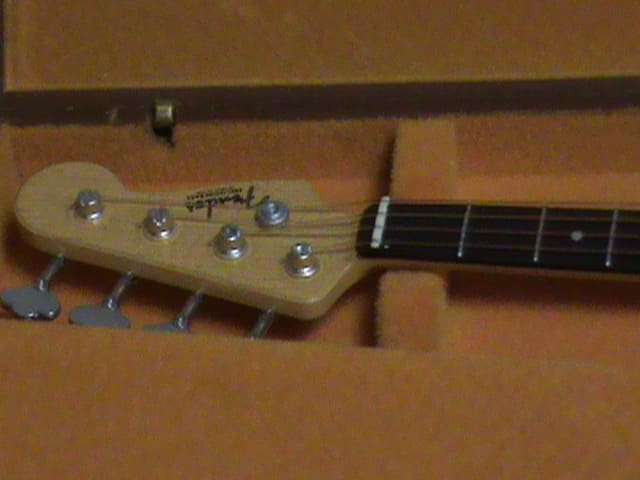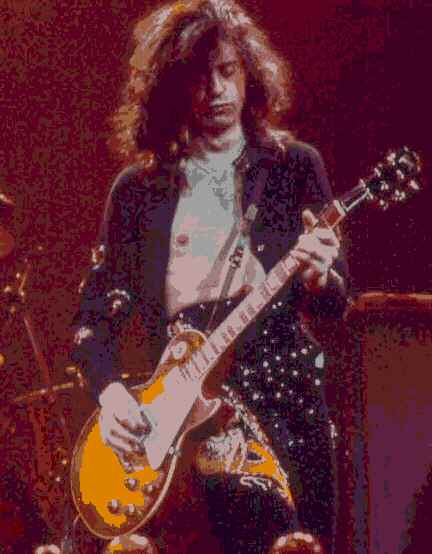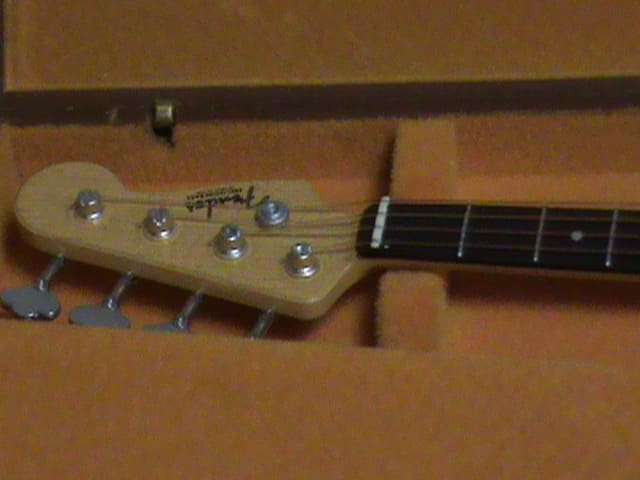早いもので・・もう12月なのだ
読者の皆さんも何かと忙しい時期だと思うが
お時間をみつけて遊びにきていただきたいと思うのだ

滑り込み的に購入したギブソンだが・・
良いタイミングで良い個体をゲットできたと大満足しているのだ
前回はトーカイにダンカンピックアップを合わせたところまでご紹介したと思う

とりあえずピックアップに付着したテープやハンダ(カバー取り付け時)をキレイに除去したのだ

トーカイのボディから純正のピックアップを取り外すのだ

一部の部品は後で使うので紛失しないように区別しておくのだ

とりあえず、ピックアップを取り外したザクリの中にピックアップを置いてイメージを確認してみるのだ

右側に青いビニールテープが確認できると思う
これはブリッジのポスト(支柱)の位置が変わらないようする工夫なのだ
取り付けが完了したあとに全体的な調整をするのだが『ベストの設定』は極力維持したいのだ
ボディ裏のふたを取り外してキャビティ内の配線を確認するのだ

画像では分かり難いと思うが・・
オレンジドロップのコンデンサーの位置を確認していただきたい
コンデンサーの足が各トーンポットとボリュームポットに連結されているのだ
通常の配線ではコンデンサーはトーンポットの端子と背面にアース接続されているのだ
つまりはボリュームにコンデンサーは不要という事なのだ
ハイ落ちを軽減する為に『ハイパス』を取り付ける事もあるが・・
ある意味では通常のギターの常識からすれば『特殊配線』という事になるのだ
これがいわゆる『ギブソン配線』なのだ
ヴィンテージ配線、ヴィンテージ接続、ギブソン接続etc・・・
呼び名は色々なのだ
すでに数十年前からギブソンではこの接続方法が純正として採用されているそうだ
実はこの配線方法は非常に優れている点が多いのだ
ボリュームとトーンをコンデンサーで接続する事でハイパスのような効果を狙っているのだ
ハイパスを別途でボリュームポットに取り付けるよりも配線が簡略化できるメリットも大きい
さらにハイパスを取り付けるよりも音の変化が自然なのだ
私も何度かハイパスの取り付けにチャレンジしたが・・
結局のところ、扱い難さ故に現在はすべて取り外しているのだ
謳い文句のようにハイ成分は残るのだが同時にボリュームポットのカーブが激変してしまうのだ
以前にもお話したが・・
ハイパス化を検討している方の為に再度簡単に特徴をご説明したい
通常はボリュームを絞ると音量の減少と共にトーンの高音域も削られてしまうのだ
ある意味ではこれも音作りの一環と考えられるが・・・
ロック系のようにソロもバッキングも常に芯がある音(抜ける音)が欲しいと言う場合には不都合があるのだ
フルテンで歪み、ボリュームを少し絞ってアルペジオでクリーンという使い方も多い
つまり、ボリュームを絞ったアルペジオやカッティングの際に『シャラシャラ感』を残すという改造なのだ
ブルースやジャズなどをメインに演奏する人には不要な改造なのだ
ロック限定という感じだろうか?
話は戻るが・・
ギブソン配線は特殊な配線方法で適度にバランスさせているのだ
「先人にも優れた人がいるんだなぁ・・・」
という感じでちょっと感動したのだ
巷にレスポールのコピーギターは多いが・・
すべてのコピーモデルがこの配線を採用しているわけではないようだ
いわゆる、ギブソンのコピーモデルという立ち位置を明確にしているギター限定なのだ
さらにはそれなりのコンデンサー性能が不可欠になるので低価格帯には採用できない(されない?)のだ
私のグラスレスポールのような安レスポールや以前に所有していたエピフォンなどは通常配線なのだ
各トーンにショボいコンデンサーが二個という配線なのだ
実はこの配線方法を知ったのは私もつい最近の事なのだ
ピックアップの交換の為にキャビティを開けて気付いたのだ
とりあえず、ハンダ作業の前に楽器店のお兄さんに口頭で質問したのだ
とにかくギター博士であるお兄さんはギターに関して知らないことがないのだ
「ネットで調べるからいいよ・・」
という方も多いと思う
私の見解ではネットの意見や情報の多くは思い込みや間違った情報だと判断しているのだ
あるいは単なるカタログスペックを復唱しているだけのものが多い
質問者が求めているものに対する明確で的確な情報は少ないように感じられる
読者の皆さんもお時間がある時にQ&Aコーナーなどを覗いていただきたい
場合によると180度くらい答えが違っている事も多々あるのだ
「現在はギターを持っていないのですが・・・」
「質問の件に関して僕なりに調べてみました・・」
こんな流れに私は違和感を覚えるのだ
「何だかなぁ・・調べた情報を答えにするの?」
「まぁ、こんな感じなんだろうなぁ・・・・」
素人ギター弾きの間では・・
異常と思えるほどギターを知り尽くしている人と無知な人の両極端が混在しているのだ
丁度良い・・という層は意外に少ないように感じられる
読者の皆さんはどちらだろうか?
私のブログの常連読者の方はご友人よりは確実に知識が増していると思うのだ

脱線してしまったが・・・
ギブソン配線の秀逸さをご理解いただけたと思うのだ
トーカイから取り外したパーツも単体で簡単な清掃をしておくのだ
こういうタイミングで手が届かない部分をキレイにするのだ
弦交換のタイミングも良いと思うのだ

今回は弦も新しくしたのだ
安レスポールでは作業の度に弦を交換することが惜しいように感じたので『荒業』で対処したが・・
ギブソンやトーカイのようなギターではむしろ良い弦を頻繁に交換すべきだと思うのだ
とりあえずピックアップの取り付けが完了したレスカスなのだ

角度を変えてもう一枚・・

さらにピックアップ部を拡大してみる

ブラックが剥き出しのルックスはサンバースト系には似合わないが・・・
何故だかオールブラックのボディには絶妙に似合ってしまうのだ

若い頃にホワイトスネークのジョンサイクスに憧れた時期もあるのでこのルックスに違和感がないのだ

全体的なバランスをご覧いただきたい

先日、購入した『レスポール辞典』からプロの愛器をご覧いただきたい

かなりの確率でオープンタイプに換装されているのだ
余談だが・・
読者の方々の中にもかなりギターが上手い方も多いと思う
それなりにコピーなども演奏できるレベルになったならば別角度から知識を蓄えることをお薦めしたい
プロの使用機材や楽曲(演奏)の『経緯』について考えてみるのだ
ジェフベックやクラプトンも若い頃はレスポール弾きだったのだ
現在はストラト使いになっているが演奏スタイルも大きく変化しているのだ
ジミーペイジに至ってはレスポール一筋だがアルバムごとに音が違うのだ
レスポール≒マーシャルという考えが定着しているが・・
それも一つの定番的な音作りだがペイジなどは変幻自在に各種アンプを使い分けているのだ
特に注目すべき点は意外にもフェンダー系ギターの使用頻度が多い点なのだ
ツェッペリンのデビューアルバムにおいてはすべての楽曲がテレキャスターで演奏されているのだ
あの有名な『天国への階段』のアルペジオ&ソロもテレキャスなのだ
音源がお手元にある方は改めて聴き返していただきたい
レスポールではあのジャキっとした感じは出ないのだ
ライブ映像などではギブソンのダブルネックを使用しているが・・
実はレコーディングではフェンダーの12弦タイプを使用しているのだ
ライブでのパフォーマンスと緻密なレコーディングを明確に区別しているのだ
個人的にはこれらの情報は以前から知っていたが・・
最近になってそれが確証に変わったのだ

以前にご紹介したがこの二冊は完全保存版レベルの良い書籍なのだ
各1500円などのでお手頃なのだ
是非とも楽器店にてご注文いただきたい
貴重な写真あり、歴史ありと内容も盛り沢山なのだ
”エレキの上達テク・・・”
的な教則本は1~2冊で十分だと思う
私にも経験があるが上達しない理由を教則本に押し付ける傾向があるのだ
読者の皆さんにも経験があるのでは?
一冊を克服する前に次の教則本に手を出すのだ
気付けばかなりの数の教則本が本棚に並んでいるという状況に陥るのだ
実は教則本にも旬のようなものがあって次々に出版される書籍は秀逸なのだ
現在流行っているテクを積極的に取り入れるという意欲も忘れないのだ
執筆側(教える側)もかなり研究しているという成果が感じられる
古い教則本に飽きて、次々に新しいものを購入するのも決して悪いことではない気もするが・・
まぁ、新旧問わず教則本はその域を出ないのも事実なのだ
スィープ奏法を巧みにこなすが・・・
弦交換やオクターブ調整が苦手という人も少なくないのだ
「この弦高で良く速弾きができるね~」
と楽器店のお兄さんが苦笑しているシーンを見かけるのだ
師匠が無いままに独自の変な癖が付いてしまった例なのだ
上記のような書籍を読む事でレイヴォーンの特異な弦高とゲージの秘密が理解できるのだ
三大ギタリストも現在は円熟の領域に達し迷いは感じられないが・・
若い頃にはあらゆるギターやアンプの組み合わせを試行錯誤していた事が窺い知れるのだ
歴史を知る事で今後のギター選びやギターとの接し方の参考にもなるのだ
まぁ、私の場合にはそういう感じなのだ

話は変わるが・・
ギブソンレスポールも徐々に私の書斎に馴染んでいるようだ

不思議な事にどんなギターでも必ずネックが動くのだ
”ネックが動く・・”
というのはネックが反ることを指しているのだが・・・
微妙に反るという感じをイメージしていただきたい
ダメなギターのネックが暴れまわって収拾がつかない・・
という類のものとは区別したい
ネックが動くという事を私は前向きに捉えているのだ
その殆どが木材というギターだけに温度や湿度の影響を受けるのは当然なのだ
むしろ、反応が良いという証だと考えているのだ

ギブソンに張ってあった弦は新しいのだが指板の保湿も含めて弦交換したのだ
指板の保湿はこの時期の『必須事項』なのだ
楽器店のお兄さんは店頭のギターには年に4回くらいオイルを塗布しているという
個人的には少ないように感じられる
おそらくフレットの痛みを考慮した最低ラインだと考えられるのだ
個人使用の場合にはフレットよりも指板やネックを最優先させるべきだと考えているのだ
湿度が高い季節は気が向いた時・・という感じだがこの時期は頻繁にオイルを塗っているのだ
弦交換二回に一回くらいというのが私流なのだ
何だか車のオイル交換&フィルター交換のサイクルのような感じだが・・

ギターのメンテのキモは『初期状態』なのだ
つまり、コンディションが良い状態の時にいかに効率よく的確にメンテを行うか?
が重要になってくるのだ
中古ギターの場合、前オーナーのメンテ記録など皆無なのだ
現状で判断するしかないのだ
現状のギターの状態を把握するにはかなりの経験と知識が必要なのだ
「新品のギブソンはちょっと無理なんで・・・」
「中古ならギリギリいけるかな?って感じです」
値段でギターを選ぶ『悪い例』なのだ
”○○年代の○○モデルを探していた・・”
という場合ならば中古しか選択肢はない
このような探し方をする人は中級以上で知識も豊富なのだ
場合によってはすでに同メーカーのレスポールを所有している場合も多々ある
追加のもう一本・・という感じなのだ
初心者の時にエピフォンを買ってレスポールタイプの面白さにハマっってしまった・・
その後、とにかくコツコツとお金を貯めて二本目のギターがギブソンという人も意外に多いようだ
私のようにギターで散財しているタイプと逆のタイプなのだ
しかしながら、新品購入まで待てずに二本目が中古レスポールというパターンも多いのだ
実際のところ、市場の影響もすくなからずあると思う
数年前よりも中古ギターの流通量も多くなっている
実際に中古の中から選べる機種も増えているのだ
値段だけ考えれば・・
一見、中古ギターがお得なように感じられるかもしれない
そこは商売なのだ
楽器店は十分に利益を上げているのだ
特に高級ギター系の中古は目利きが難しい
仮に読者の皆さんがギブソンやフェンダーを手に入れた場合、簡単に手放すだろうか?
手放すくらいなら最初から買わないような気がするが・・・
ちなみに衝動買い的存在の安ギターが別なのだ
市場に流通している中古ギターの多くは『訳あり・・』なのだ
その訳が良いか?悪いか?を判断するのは購入者なのだ
プロである楽器店は多くの場合、コンディションを含む大凡の状況は把握している
場合によっては消耗した部品を新品に交換して販売する場合も多い
フレットの使用感の割にナットやブリッジのサドルが新しい場合・・
ボディのキズや打痕の割にフレットが新しい場合・・・
ボディとネックの焼け具合が大きく異なる場合(ボルトタイプのネック)・・
簡単な例だが・・
この程度の状況に違和感を感じられるレベルの人が手を出すギターなのだ
ちょっと脱線気味だが・・
中古レスポールの場合、ネックのメンテを怠っていたケースが多い
もちろん、展示の前に楽器店でネックの調整や保湿、フレットの微調整などを行うが・・
生き物であるギターの場合、ダメージを完全に払拭はできないのも事実なのだ
中古の車と一緒なのだ
前のオーナーが一度も洗車&ワックスがけなどをしなかった
長期間に渡り紫外線に晒されていた
この時点で塗装がダメージを受けているのだ
販売の為にキレイに磨き上げるがそれは『上塗り』なのだ
私も若い頃に何度も経験がある
磨いても磨いても期待した艶久感が蘇らないのだ
まぁ、車とギターは違うが・・・
初期メンテ&お手入れという点では一緒のように感じられる
最近は『レリック加工』いわゆる中古仕様だが・・
少し汚れたギターもかなり人気がるようだ
ギブソンやフェンダーのような一流メーカーも真剣に新品のギターを汚す?時代なのだ
ボディのダメージは好みならば味になる場合も多いと思う
しかしながらネックの状態は少々異なる
ネック周辺の状態が悪いギターは楽器のとしての品質が大きく低下しているのだ
長年反りまくっていたギターを楽器店が買い取り、
最近になって販売の為にネックを最良の状態にした中古ギターがあった場合をイメージしていただきたい
何度も言うが・・木材は生き物なのだ
「あれ?俺の背骨って急激に修正されたけど・・」
「ちょっと猫背の方が楽だんだよね~」
ギターの気持ちになって擬人化してみたのだ
お買い得のレスポールを購入したと喜んで自宅に持ち帰るも数日後にはネックが急変するのだ
もちろん、ロッドで調整すれば元に戻るが・・・
数週間後には同じ状態なのだ
さらには長年の反り癖がついたネックは実はその状態がもっとも鳴る状態なのだ
それを無理やりに真っ直ぐにした状態はある意味では木材に負担をかけているという事になるのだ
ギターにとっては反った状態が居心地が良く・・・
真っ直ぐ状態のネックは常に負担を抱えた状態という事になる
もちろん、もともとは出荷時には適正な状態だったので時間をかければ元に戻るが・・
その周期は数年とかなり長いサイクルになることを覚悟すべきなのだ
そもそも、長期間もギターケースを開けないような人の元で過ごしたギターはボディも死んでいる
乾燥によるシーズニングは進行しているが弾き込みによるエージングが皆無というアンバランスさなのだ
これも、次期オーナーの努力と愛情で乗り越えられるが・・
手に馴染むには数年の歳月が必要となるのだ
結局のところ、車もギターも『ワンオーナー』が最良なのだ
しかも初期メンテを入念に行ったギターはその後に多少手抜きをしても大丈夫なのだ
私のブログを読んでいる方々は・・
「ギターって超面倒臭いね・・・」
「買うのやめようかな?時間ないし」
まぁ、楽器店のお兄さんや私はちょっとばかり入れ込むタイプなので異例なのだ
ここまで愛情を注げば完璧!という一例などでご参考までに・・・

話は変わるが・・
ネックのトラスロッドにも二種類の形状がある
これはトーカイとギブソンの専用レンチなのだ

レンチがメスになっているのだ
外径は殆ど一緒なのだが内径と形状が異なるのだ
ちなみにアイバニーズもこのタイプなのだ
通常のオスタイプレンチのとの違いを楽器店のお兄さんに質問してみたのだ
「とくにメリットとデメリットというのはないと思いますよ・・」
「特にギブソンタイプはヴィンテージの形状に拘っているんですよね」
確かにギブソンはロッドの材質や形状(仕込み角度)などが年度ごとに変化しているが・・
開発当初の形状を現代にまで継続しているのだ
個人的には高級ギターはメスレンチ仕様、それ以外は・・・というイメージなのだ
しかしながら疑問が浮上するのだ
それなりに高価なストラトは安ギターと同じオスレンチ仕様なのだ
「ストラトはとにかくメンテを最優先した設計なんです」
「レンチカバーすら無いでしょう? コンセプトなんです」
私がさらに質問するのだ
「だけど・・ストラトのレンチっ他のものより異様に細いけど・・」
「ロッドも細いの? なんか頼りないっていうか・・・」
お兄さんが苦笑するのだ
「それももメンテ向上の考えなんですよ~」
「ロッドの差し込み口は小さいですけど内部のロッドは通常サイズです」
つまり、目に見える部分は極細なのだが内部は強度を維持する専用設計という事なのだ
コストがかかる仕様だけに安ストラトでは再現できない部分なのだ
こういう細かい部分にメーカーの拘りとギターの深さを感じるのだ
”作りが粗い・・”
という評判のレギュラーラインのレスポールだが個人的には満足しているのだ
バインディングとフレットの接合部分の拡大画像をご覧いただきたい

演奏中に目に飛び込んでくる部分でもあるし、常に指先が触れる部分だけに重要なのだ
先にも述べたがネック周辺のコンディションと作り込みが最も重要なのだ
さらにはメーカーの技術力が現れる部分なのだ

こトーカイもこのタイプなのだが非常に難しい工法らしい
フレットのエッジ部分とバインディングがシームレスで結合しているのだ
いわゆる安レスポールでは手間を軽減する為にバインディングの上にフレットを延長させているのだ
いわゆる『オーバーバインディング工法』といわれるタイプなのだ
エピフォンやグラスがこのタイプなのだ
演奏上特に問題はない
考えてみればノンバインディングのギターはすべて同じフレット形状なのだ
ネックの端から端までフレットが伸びている
ギブソンタイプのバインディングのメリットは『豪華さ』だけなのだ
安ギターとの差別化であり、伝統の忠実な継承だと感じられる
手抜きしたくなる部分だが緻密に作り込まれているのだ
「粗い部分はないの?」
と思われる方も多いと思う
実は気になるほどではないが・・・
バインディングの側面が微妙に凸凹しているのだ
指先で撫でると感じられるほど微妙なものだが・・・

これも品質自慢のトーカイとの比較で感じられるという微細な違いなのだ
トーカイを経験していない人ならば感じないような『許せる粗さ』なのだ
音質や演奏性の大きく関係しているブリッジとテールピースを横から撮影してみたのだ

これがテールピースを下げられる限界なのだ
トーカイの場合、もっと下側までテールを下げられるのだ
その違いは何か?
「ネックの仕込み角度がギブソンは他と違うんですよ」
ネックの『仕込み角度』については検索していただきたい
ボディに対して斜めにネックが取り付けられているということなのだ
これも歴史を調べると年代によって仕込み角度が異なるなのだ
「ボディに真っ直ぐにネックを付ければいいんじゃない?」
と思う方も多いと思う
以前は私もそう思っていたのだ
実はネックの仕込み角度が演奏性に及ぼす影響力は想像以上に大きなものなのだ
大雑把な表現だが・・
ネックが傾いているほどに弦にかかるテンションが強くなるのだ
つまり真っ直ぐのネックのギターと同じ弦を張った場合ギブソンの方が張りが強く感じられるのだ
弦の張りが強くなる事でピックへの当たりも違った感じになってくる
さらには弦振動にも大きく影響しているのだ
「そんなに良いなら他も真似すれば?」
という考えもあるが・・・
これもい違いにどちらが良いかはメーカーの考え方なのだ
トーカイなどは配線やボディ材、ボディ構造などは1968年製の本家のレスカスを忠実にコピーしている
しかしながら、唯一ネック周辺、つまりはネックの仕込み角度には持論があるようだ
ギブソンほどの強い『傾斜』を求めていないのだ
ギブソンとトーカイに同じ弦を張った場合、レスポールとストラトとのテンションの差を感じるのだ

ネックのジョイント(結合部分)に関しても独自の考えの違いがあるようだ
『ディープジョイント』という言葉を聞いたことがあるだろうか?
非常に手間がかかる工法なのだ
ネックの端をフロントピックアップの下側まで深く差し込む工法なのだ
これによって格段に豊かな鳴りと音の伸びが得られるのだ
トーカイの場合このあたりも本家を忠実に再現しているのだ
ギブソンは当然なのだ
ネックの接着にもメーカー間の拘りが感じられる
実はどんな接着方法を採用するか?で音色が大きく変化するようだ
2013年モデルからのカスタム製レスポールではあえて50年前の接着方法を再現sているという
『ニカワ』をボンドの代用として使用しているのだ
強度面では強力な接着剤に軍配が上がるが・・・
音質面やその後のメンテ(ネックの取り外し)では昔ながらのニカワの方が良いらしい
トラスロッドも強度最優先の2012年までを逸脱したようだ
レギュラーラインも含めて音質重視の仕込みに変わったそうだ
話は変わるが・・・
レスポールの最大の魅力はボディトップのアーチ型の形状にあると思う
まさにヴァイオリンを彷彿とさせる美しいカーブなのだ
生産性を重視したストラトのフラットな形状とは一線を画す

同時にレスポール独自のメイプルトップの木目も最大の魅力の一つなのだ

実は天然のメイプル材は『劣悪な自然環境』で生成されるものらしい
つまりは木にとって良い環境ではメイプル柄は生まれないというのだ
いわゆるプレーンの自然な木目は良い環境で木が生育したという事実の証なのだ
一方のメイプルは温度、湿度、栄養素etc・・
とにかく木にとっては劣悪な条件が揃うことで生まれる天然の模様なのだ

色々な表情がある

こういう素直な木目も魅力的だと思う

TAK氏が使用しているような柄は『キルトメイプル』なのだ
魚のウロコのような柄が特徴な派手な木目なのだ
これはいわゆるトラ杢よりもさらに過酷で劣悪な条件で生育していた事を意味するのだ
読者の皆さんも木目が美しいギターをお持ちだと思う
あるいは狙っているギターがあると思う
良質なメイプルか?否か?の簡単な判断方法をご紹介したい
天然の良質なメイプル材は見る角度でメイプルの模様が変化するのだ
上から、下から・・側面から・・・・
場合によっては見る角度によってメイプル柄が消える瞬間がある
突然、プレーンになってしまうのだ
サンバーストの境目が消える個体もある
シールの場合は何処から見てもメイプル柄が消えることがない

私の愛用のアリアはプリントシールではないのだ
本物のメイプルを削り出したものだが極薄らしい
つまり、木材の奥行きがまったくないという状態なのだ
どこから見てもこの柄を維持しているのだ

ブックマッチ風?の2ピースだが・・・
一枚板を二分割するほどの厚さもないし必要性もない
薄~くスライスしたメイプルをキレイに貼り合わせているのだ
グラムあたり数万円するようなAAAAAランクのステーキも300gは高価だが・・
テレビの企画などで極薄にスライスすればリーズナブルで手に入るのだ
まぁ、一般人がお願いしても門前払いだと思うが・・・
低価格帯のギターには『知恵』がある
一方の高級ギターには『余裕』が感じられる
トーカイのようなレスカスコピーの場合には見えない部分の拘りが大きいのだ
色つきの塗装でコーティングするだけにボディ構成を少々誤魔化せる
基本的にはメイプルトップのブックマッチ(見えなくても・・)が基本なのだ
この辺りで低価格帯のレスポールタイプは異なるサイズの部位を合体させることも多い
さらには異なる材質を使うこともある
マホガニーの使用量を軽減する為にべニアで『嵩増し』(かさまし)している事も多々ある
もちろん、耳が肥えたギター弾きは騙せない
レスポールの王道以外の組み合わせの材には簡単に気付いてしまう
まぁ、初心者を甘くみているのだと思う
粗悪なボディバックに良質(そうな)ボディトップも王道の組み合わせなのだ
特にルックスを重視する日本人は見た目にやられてしまうのだ
モデル並みに美しいが・・・
常識もなく、片付けられない・・という女性にハマってしまうのも日本人気質なのだ
実はギターと女性はまったく無関係に感じると思うが・・
ギターのボディは女性の体のラインをイメージして設計されたという逸話がある
実際のところ、ストラトは機能美優先のメカに感じるがレスポールにはギターを感じる
さらには先にも述べたボディトップのふくよかなラインなども何処となく女性的に感じられる
レスポールに萌える人は自分では気付いていないようだが・・
同時に女性好きなのだ
少なくとも私はそういう感じなのだ
人前ではあまり口にしないが・・
ギターにセクシーさを感じているのだ
特にギブソンを眺めていると非常に癒されるのだ
以前にお兄さんが言っていた言葉が蘇るのだ
「上質なワインとチーズを肴にレスポールを眺めるって最高ですよ♪」
ギターを眺めるの?という感じだったが・・
あまり弾かないギターがあっても良いと感じるようになってきたのだ
まぁ、私の場合には観賞的な要素と道具としての要素が絶妙にバランスしているが・・
読者の皆さんの中にもギブソン、あるいは良質なコピーモデルをお探しの方がいると思う
ギター選びのポイントを幾つかご紹介したいのだ
必ず試奏すべきなのだ
楽器店で購入する重要性がご理解いただけると思う
たかが一本のギターの為に数日間も要し界隈の楽器店をすべて徘徊し
数十本の中からようやく一本のギターを見つけたと豪語している人のブログを見かけたことがある
気持ち(入れ込み)は理解できる
”時は金なり・・”
ギター弾きとしてすべき事は他にあるのだ
休日に超長文を書いている私が言うのも何だが・・・
まぁ、この手の人はかなりの暇人なのだと思う
ギター選びも就職活動と一緒なのだ
ダラダラと欲張っている者に勝利はない
とにかくポイントを絞り込むのだ
楽器を買う前に不可欠なのは『お店選び』なのだ
品揃えが豊富な楽器店しか目に入らないのは素人なのだ
必要最小限のギターがあれば良いと思う
むしろラインナップに目を配るべきなのだ
直射日光が当たるような店頭の安ギターはどこも一緒なのだ
10万円から20万円未満のランナップに注目するのだ
この辺りのゾーンが充実している楽器店はギターが選びやすいと思う
狙っているレスポールの色違いが2~3本で十分なのだ
巷で一部の人が騒いでいるほど品質にバラつきはないと思う
あとは微妙な個体差(音の好み)だけなのだ
むしろ、午前中に数十軒も楽器店を廻り、昼食を摂って午後も楽器店廻り
最後のお店に気にいったレスポールがあれば良いが・・・
また、最初のお店に戻りの悪循環なのだ
「店長? あのお客さんまた来ましたよ~」
「まぁ、買わないだろうなぁ・・あんな感じは・・」
こんな印象を持たれた楽器店とは末長いお付き合いはできない
男女の出会いと一緒なのだ
一期一会、第一印象が重要なのだ
ギター選びの際の直感もギター弾きの能力の一部なのだ
即決できない人は結局のところ、経験不足であり芯がぶれている証なのだ
ギター選びで悩みまくる人はデートでもメニューが決められない人なのだ
オクターブ調整には執着するがチョーキングが微妙というパターンなのだ
いわゆる『徒労タイプ』なのだ
ギターの出会いには繊細さと男らしさが絶妙に同居する必要があるのだ
如何だろうか?
まぁ、20歳も肥えれば人間の性格は変わらないが・・
こんな事をい意識しているだけでも何かが違うと思うのだ


都内にはギブソン&フェンダーの専門店がある
こういう専門店で購入するのも悪くはないが・・・
一般の楽器店ならばハイクラスに分類されるレギュラーレスポールが安ギター扱いなのだ
おそらく面食らうと思う
「最近のレギュラーは品質が悪いですよね・・」
「カスタムなんて如何ですか? 相談に乗りますよ」
レギュラーの予算を手付けにしてローンを組めばカスタムショップも手に入る
当初よりも高い買い物をする可能性もあるのだ
それでも初志貫徹でレギュラーを押し通せば、ちょっとした変人扱いになってしまうのだ
さらには試奏の際にも恥ずかしい思いをすることが多いと思う
専門のショップに足を踏み入れる人は自身もかなりのプレーヤーである場合が多い
自称プロレベルなのだ
プロを目指しているような凄腕もうろうろしているのだ
演奏力はそれほどでもないが『知識オタク』的な人もウヨウヨいるのだ(怖いね)
そんな人々の前で歪みマックスのフルテンで2音リフを弾いた場合、暗黙の袋叩き状態なのだ
背中に刺すような冷たい視線を浴びせられるのだ

地方の地元では有名なギター弾きでも都内ではただの人なのだ
「何だよ~俺はただギターを買いにきただけなのに・・・」
・・という理由で専門店はレギュラーを数年間くらい使った後の買い替えに利用することをお薦めする
異常な話だが70万円くらい用意しなければカスタム系ショップでは楽しめない現実がある
ヴィンテージが数千万円も異常だが・・
新品のエレキが70万円超えの現実にも違和感を感じるのだ
庶民が集う楽器店は何かと安心で楽しいのだ
稀に何を間違ったのか庶民のお店でカスタムショップ製のレスポールを見かけることがある
値段を見てすべての人が素通りしてしまう
カスタムショップの高級ギターが肩身の狭い思いをしているのだ
「俺も仲間がいるショップに行きたいよ~」
ギターがそんな事を呟いているかは知らないが・・・
私には声が聴こえてくるのだ(そんな気がしている)
まぁ、そんな感じなのだ
何だか長文の割に終わりがグダグダになってしまったが・・・
言いたい事、思う事を羅列したらこんなブログになってしまったのだ
おそらく、文章の長さでは本日のgooブログのダントツ1位だと思う


最近は訪問者が急増しているのだ
ギター好きで文章好きが多い事を嬉しく感じているのだ
まぁ、ツイッターの呟き異常の文字数を受け付けないような人にはギター演奏の向上も期待できないが・・
私のブログを読むようになった初心者~中級者の方はかなりの『ギター博士』になっているのではないだろうか?
差し障りがなければご友人などにも私のブログをご紹介しただきたいと思うのだ
実はここまで書いても、まだまだ書きたい事が山のようにあるのだ

流石にマシンガンタイピングの私でも今日は疲れたのだ
この後にちょっと家族と買い物に出かけるのだ
夕食の後にギター磨きでもしようかな?と思っているのだ
「レスポールの音源はどうしたの?」
という方も多いと思うが・・・
真面目な性格の私はドラム、ベース、エレキ重ね録り、鍵盤・・
という感じでサンプルとは言いながらも完成度の高い音を追求してしまうのだ
根っからサービス精神が旺盛なタイプなのだ
楽器店のお兄さんはこう言うのだ
「ブログに音源が付いているだけでも凄いですよ」
「ギターだけでもいいんじゃないですか?」
「こんなリフを作ったぜ~みたいな・・・」
お兄さんの場合、無料には入れ込まないタイプなのだ
私と正反対の合理主義なのだ
私の場合、昔からお金にならないようなボランティア的な事に入れ込む癖があるのだ
自分でもも良く分からないのだ
まぁ、拘り派の私を気長に見守っていただきたいのだ
納得のサウンドが完成しない事には録音に至れない自分がいるのだ
「俺って何だろうな・・?」
と思う日々なのだ