ニューヨークのシンシン刑務所内の芸術活動による更生プログラム(RTA)に参加した収監者を描いた、実話に基づく作品。主要登場人物の85%が元収監者で実名で本人を演じている。ディヴァインGはRTAの「舞台演劇」のグループに所属し、仲間と共に作り上げていく演劇に生きがいを感じていた。ある日、刑務所で札付きの問題児として恐れられている男、ディヴァイン・アイことクラレンス・マクリン(本人)が演劇グループに参加することになった。最初はプログラムに反発していたアイだったが、Gの熱心な働きかけにより徐々に心を開いていき、演劇の世界に目覚めていく。
『ショーシャンクの空に』 (94)では受刑者の過激な暴力が描かれていたが、この作品の受刑者達はみんなやさしい。一体どちらが本当なのかと思ってしまう。アイはプログラムを通じて尊厳を取り戻し、協調性を身につけ、仲間との友情を深めていく。
Gは無実の罪で長い間収監されていた。すでに亡くなった人の証言を録音したテープを証拠として採用してもらえるように頼んだが受け入れられず、再審請求を却下されたようだ。結局、アイの方が先に出所することになり、Gは絶望して自暴自棄になるが、アイが寄り添い励まし勇気づける。演劇の当日を迎え、収監者たちは観客から盛大な拍手を浴びる。やがてアイは出所し、時は流れて、ついにGが出所する時が来た。
この映画は元受刑者が実名で登場しているために、プライバシーの問題があるのだろうか。個々の受刑者の犯した罪の詳細は描かれていない。Gは無実の罪で収監されているとのことなので、観客は当然冤罪の追求を期待する。だが詳しい事情はわからず、無実の証明もなされていない。本作品はRTAによる更生がテーマではあるが、冤罪とか再審とかいうことになれば、どうしても観客の関心は冤罪の解決に向いてしまう。どうやら出所後の現在もGは無罪の判決を勝ち取っていないようなので、感動の無罪判決というストーリーにはできなかったのかもしれないが、裁判の経過や刑罰等に関してもう少し言及があってもよかったかなと思う。
ディヴァインGを演じたコールマン・ドミンゴや、収監者たちに演技指導を行う劇作家ブレント・ビュエルを演じたポール・レイシーはそれぞれプロの俳優で、どちらの演技も素晴らしかったが、アイを自ら演じたクラレンス・マクリンの存在感は際立っていた。クラレンス・マクリンはすでに舞台には出ていたが、映画は今回が初めてだったようだ。自分自身を演じる時に「自分の内面を深めることを考えた」と言っているのが興味深い。「自分自身を掘り下げて、内面から感情と行動を表現する」というスタニスラフスキーの演劇論と通じるものがある。「役になりきる」というメソッドは自分で自分の役を演じる時により有効なのだろう。
アイがG に語った「刑務所を出ても、またギャングになるしかない」という言葉が印象的だった。元受刑者であるアイ本人が語っているだけにリアリティがある。アイは自分の息子も刑務所に入っていると言う。貧困や犯罪の連鎖を断ち切るのはむずかしい。アメリカでは刑務所出所後の3年以内の再犯率は60%を超えるらしいが、RTAに参加した受刑者の再犯率は3%以下だという。アイの嘆きを救うのがRTAのプログラムなのだ。
再犯を繰り返すのは本人の意志が弱いからだけではなく、元受刑者に対する社会的偏見があるからだろう。偏見や差別が受刑者の社会復帰を妨げていることは否めない。そうはいっても忘れてはならないのは被害者家族のことだ。シンシン刑務所には重罪を犯して収監されている人たちもたくさんおり、被害者及び被害者家族はこの映画を単なる感動の物語としては受け取れないだろう。被害者家族が受刑者に求めているのは反省と償いだが、自己肯定感がなく、尊厳を失った人は反省する気持ちすら起きてこないのではないだろうか。人間性を回復してこそ、自分の過ちを後悔し反省して、償いの人生を送ることができると思う。その意味でも更生プログラムの意義は大きい。(KOICHI)
原題:Sing Sing
監督:グレッグ・クウェダ―
脚本:グレッグ・クウェダ― クリント・ベントレー
撮影:パット・スコーラ
出演:コールマン・ドミンゴ クラレンス・マクリン ポール・レイシー ショーン・サン・ホセ
『ショーシャンクの空に』 (94)では受刑者の過激な暴力が描かれていたが、この作品の受刑者達はみんなやさしい。一体どちらが本当なのかと思ってしまう。アイはプログラムを通じて尊厳を取り戻し、協調性を身につけ、仲間との友情を深めていく。
Gは無実の罪で長い間収監されていた。すでに亡くなった人の証言を録音したテープを証拠として採用してもらえるように頼んだが受け入れられず、再審請求を却下されたようだ。結局、アイの方が先に出所することになり、Gは絶望して自暴自棄になるが、アイが寄り添い励まし勇気づける。演劇の当日を迎え、収監者たちは観客から盛大な拍手を浴びる。やがてアイは出所し、時は流れて、ついにGが出所する時が来た。
この映画は元受刑者が実名で登場しているために、プライバシーの問題があるのだろうか。個々の受刑者の犯した罪の詳細は描かれていない。Gは無実の罪で収監されているとのことなので、観客は当然冤罪の追求を期待する。だが詳しい事情はわからず、無実の証明もなされていない。本作品はRTAによる更生がテーマではあるが、冤罪とか再審とかいうことになれば、どうしても観客の関心は冤罪の解決に向いてしまう。どうやら出所後の現在もGは無罪の判決を勝ち取っていないようなので、感動の無罪判決というストーリーにはできなかったのかもしれないが、裁判の経過や刑罰等に関してもう少し言及があってもよかったかなと思う。
ディヴァインGを演じたコールマン・ドミンゴや、収監者たちに演技指導を行う劇作家ブレント・ビュエルを演じたポール・レイシーはそれぞれプロの俳優で、どちらの演技も素晴らしかったが、アイを自ら演じたクラレンス・マクリンの存在感は際立っていた。クラレンス・マクリンはすでに舞台には出ていたが、映画は今回が初めてだったようだ。自分自身を演じる時に「自分の内面を深めることを考えた」と言っているのが興味深い。「自分自身を掘り下げて、内面から感情と行動を表現する」というスタニスラフスキーの演劇論と通じるものがある。「役になりきる」というメソッドは自分で自分の役を演じる時により有効なのだろう。
アイがG に語った「刑務所を出ても、またギャングになるしかない」という言葉が印象的だった。元受刑者であるアイ本人が語っているだけにリアリティがある。アイは自分の息子も刑務所に入っていると言う。貧困や犯罪の連鎖を断ち切るのはむずかしい。アメリカでは刑務所出所後の3年以内の再犯率は60%を超えるらしいが、RTAに参加した受刑者の再犯率は3%以下だという。アイの嘆きを救うのがRTAのプログラムなのだ。
再犯を繰り返すのは本人の意志が弱いからだけではなく、元受刑者に対する社会的偏見があるからだろう。偏見や差別が受刑者の社会復帰を妨げていることは否めない。そうはいっても忘れてはならないのは被害者家族のことだ。シンシン刑務所には重罪を犯して収監されている人たちもたくさんおり、被害者及び被害者家族はこの映画を単なる感動の物語としては受け取れないだろう。被害者家族が受刑者に求めているのは反省と償いだが、自己肯定感がなく、尊厳を失った人は反省する気持ちすら起きてこないのではないだろうか。人間性を回復してこそ、自分の過ちを後悔し反省して、償いの人生を送ることができると思う。その意味でも更生プログラムの意義は大きい。(KOICHI)
原題:Sing Sing
監督:グレッグ・クウェダ―
脚本:グレッグ・クウェダ― クリント・ベントレー
撮影:パット・スコーラ
出演:コールマン・ドミンゴ クラレンス・マクリン ポール・レイシー ショーン・サン・ホセ











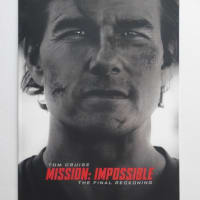

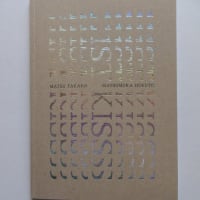
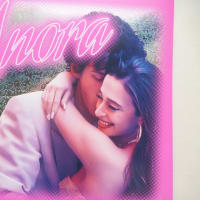
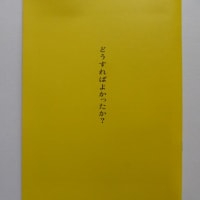




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます