
5月10日蓬莱山(三百名山)へ登る、天候は

 登山日和だ
登山日和だ

ビュッヒェで標高差1000mのピストンに備えます 


京都駅~( 湖西線)志賀駅へ
湖西線)志賀駅へ


8:45 志賀駅から民家の間を抜け「樹下 神社」へ
神社」へ

ウマノアシガタ
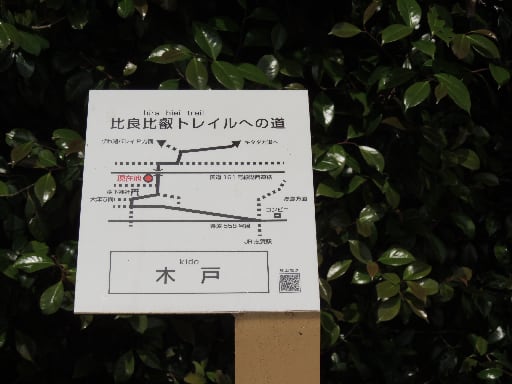
この先「湖西道路」をくぐれば登山道

イワウツギ

トウバナ:シソ科

9:10 キタダカ道 (打見山)と金毘羅道
(打見山)と金毘羅道 (蓬莱山)分岐
(蓬莱山)分岐
杉林を行きます、間伐された枝が靴に 引っかかる
引っかかる

 ナツトウダイ
ナツトウダイ

石堤前の 地蔵さん
地蔵さん 


 ヤマツツジ
ヤマツツジ

傾斜も急に、岩もゴロゴロ、タフな上りが 続きます
続きます

ミヤマカタバミと

シマ が道を
が道を
 横切りました
横切りました


10:10 「 天狗杉」
天狗杉」 到着、休憩
到着、休憩 ・
・ ・・
・・

この先オオイワ カガミの群生地に(杉の倒木帯でもあります)
カガミの群生地に(杉の倒木帯でもあります)

ミツバツツジと



足元は花崗岩砂礫に変わります





10:50 「クロトノハゲ」オブジェ(木戸峠分岐)
黒砥の禿?ピカピカに仕上げされた黒砥石(花崗岩製)の意味でしょうか?

”びわ湖バレーロープウェイ山頂駅”が 視
視 界
界 に入りました
に入りました

天命水

ケキツネノボタン

11:20 打見山

「ウッディ達」と琵琶湖を俯瞰しました

琵琶湖(右上は瀬田の唐橋)

蓬莱山です。
打見山と蓬莱山頂部は「びわ湖バレイ」冬はスキー場、夏は展望地に
(ちなみに夏季リフトは無料 とか話を聞きました)
とか話を聞きました)

11:50・12:10 蓬莱山:1174m(三百名山)
滋賀県大津市、JR湖西線蓬莱駅の北西4km、*比良山系南主稜の主峰。
比良山地:滋賀県と京都府にまたがる。北東~北西に連なる、主峰は武奈ケ岳:1214m

 打見山
打見山

12:10 下山開始、湖西線蓬莱駅へ降りる尾根です

笹原の丘陵地帯、鞍部が小女郎池 分岐or
分岐or 下降点です
下降点です
 直進すれば権現山:996mを経てアラキ峠(土・日
直進すれば権現山:996mを経てアラキ峠(土・日 あり)へ降りる登山道です
あり)へ降りる登山道です

 小女郎池へ寄りました(
小女郎池へ寄りました( 何もなし)
何もなし)

12:35 下山口 

 左へ
左へ

 崩壊気味の急登、足元に神経を集中して
崩壊気味の急登、足元に神経を集中して
 慎重に降りました
慎重に降りました

沢沿いの道、踏 跡はありますが
跡はありますが 荒れています
荒れています

放置されたM B、ここまで
B、ここまで 登って来たのか?
登って来たのか? 降りてきたのか?
降りてきたのか?

 沢を渡ります(
沢を渡ります( 度?だったかな)
度?だったかな)

 ニリンソウ
ニリンソウ

 ヨゴレネコノメ
ヨゴレネコノメ

13:30 「 薬師の滝」道が不明で
薬師の滝」道が不明で 近ずけなかった
近ずけなかった

13:35  林道と登山道(八屋戸経由)分岐、何れも蓬莱駅へ
林道と登山道(八屋戸経由)分岐、何れも蓬莱駅へ

視界のある林道、 琵琶湖です
琵琶湖です

湖西道路渡り・・・・・

光明寺通過 







 琵琶湖が目線のレベルに
琵琶湖が目線のレベルに

田植えは 終わってます。
終わってます。
14:10 蓬莱駅着、怪我もなく無事降りてきました。


*
行程:標高差1073m、12,3km、6,5時間
8:00 京都駅(湖西線) =8:45 志賀駅 ⇒9:10 登山口
⇒10:10 天狗杉 ⇒10:50 クロトノハゲ(木戸峠分岐)
⇒11:20 打見山 ⇒11:50・12:10 蓬莱山・昼食 ⇒12:30 小女郎池
⇒12:35(薬師の滝)下山道 ⇒13:30 薬師の滝 ⇒14:10 蓬莱駅
日本三百名山 蓬莱山33 完登
**
>> 空海 15
インドに起こった密教グループ、彼らは釈迦の仏教とは違い
精神が死に向って衰弱しがちな「解脱」の道を選ばなかった。
釈迦とは逆の道を選んだ。現世を肯定した
「解脱といっても、人間も虫も草も生命ある限り生きざるを得ないのではないか」
開き直った所から出発した。
彼らは自然の福徳に驚歎讃仰する立場をとり、自然に対して驚歎讃仰した。
生命を肯定する以上、人間は自然から福徳や知恵という利益を受けねばならない。
「虚空菩薩」という自然の本質は、それへ修法者が参入してゆきたいと請い願い、
かつ参入する方法を行ずるとき、その修法者に惜しみなく利益を与えてくれると
いうのである。















 里湯」帰りに寄りました
里湯」帰りに寄りました







 野菊と
野菊と

 オニシバリ:ジンチョウゲ科、別名:夏坊主(なつぼうず)
オニシバリ:ジンチョウゲ科、別名:夏坊主(なつぼうず)

 箱根の山々
箱根の山々

 トレランが多い
トレランが多い


 大山(ピークへは
大山(ピークへは 行きません)
行きません)
 富士山
富士山
 木花之佐久夜毘売(このはなさくやひめ)」と、
木花之佐久夜毘売(このはなさくやひめ)」と、 両参り」として大山も参拝したという。
両参り」として大山も参拝したという。 不動堂(現・阿夫利神社下社)、
不動堂(現・阿夫利神社下社)、 石尊大権現(現・阿夫利神社本社)
石尊大権現(現・阿夫利神社本社)
 不動像 ⇒10:55 不動越(林道と交差)ここまでは登山道
不動像 ⇒10:55 不動越(林道と交差)ここまでは登山道


 分岐)
分岐)


 メイン)
メイン)

 昼か?三つあるベンチも空いてないし、Goo
昼か?三つあるベンチも空いてないし、Goo

 甲斐方面から、
甲斐方面から、

 制」と刻まれている。
制」と刻まれている。



 垂れて
垂れて




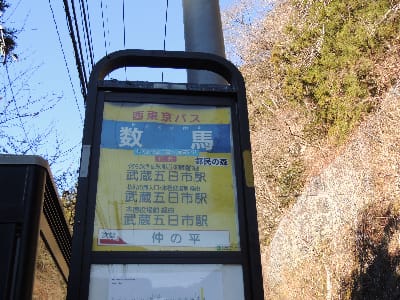













 アセビの道、左側には樹林越しに
アセビの道、左側には樹林越しに

 落葉樹林
落葉樹林



 12:20 大沢山:1482m
12:20 大沢山:1482m

 ムシカリ峠、ログハウスの東京都避難
ムシカリ峠、ログハウスの東京都避難 小屋
小屋






 遊歩道」を降ります
遊歩道」を降ります












 納得だ)
納得だ)

 塩
塩
 取れなかった)
取れなかった)



 雨が落ちていました
雨が落ちていました



 コマクサ
コマクサ の群生
の群生









 秋の装いです
秋の装いです






 ヘロヘロの状況で見上げた場所です
ヘロヘロの状況で見上げた場所です


 雪渓へ
雪渓へ
 滑らないように
滑らないように 踏ん張れない・・・・・。
踏ん張れない・・・・・。







 周年だそうです
周年だそうです
 不安定、外は雨が降ったりやんだり、
不安定、外は雨が降ったりやんだり、
 故加藤文太郎氏
故加藤文太郎氏 「不出世の登山家だ。日本の登山家を山に例えたとすれば富士山に相当するのが
「不出世の登山家だ。日本の登山家を山に例えたとすれば富士山に相当するのが 踏入る。
踏入る。





 幸せそうに ↑ ↓
幸せそうに ↑ ↓




 KTD
KTD







 あればもっと楽しめたけど・・・・・。
あればもっと楽しめたけど・・・・・。













 小雨が降ってます(まだ暗~~~い)
小雨が降ってます(まだ暗~~~い)

















 激しい、そろそろ
激しい、そろそろ 更新でしょうか?
更新でしょうか?




 大江町に
大江町に

 ツキノワグマもいます。
ツキノワグマもいます。

 響きの森)登山口戻ってきました
響きの森)登山口戻ってきました


