
四国八十八ヶ所巡り 三日目
今日は 太龍寺ロープウェイ麓の道の宿そわかを出発し、
第22番札所 平等寺、第23番札所 薬王寺へ
これで徳島は 「区切り打ち」となります

夜中に雨音で目が覚めました。外をのぞくと街灯だけでも雨が降っている様子が判るくらいの
本降りでした。朝までに上がると良いなぁと思いながら・・・・再びzzzzzz
朝、起きてみると、昨日ははっきりとその姿が見えていた山が靄に覆われています
まだ、ポツポツと雨も残ってました(7時少し前です)
でも、今日も、元気に朝ご飯を食べて、出発!!


出発前、道の駅 そわかの前で 花ちゃんとパチリ(そわかのわんちゃんです)



那賀川を渡る時に、ロープウェイが見えました。ただ、太龍寺の方はまだ、雲がかかってます
雨が降らなかったら良いなぁ~と思いながら、進みました

歩道のフェンスにも、お遍路さんが描かれています
車道から、お遍路道へ入ります
住宅地から、畑、山道へを続くのです
この道に入る所で、地元のおばあさんからも声をかけていただきました
「その先から、右へ入らないといけないよ」
丁度、お遍路道への分かれ道の所で、私達が道を間違えないかと、
心配そうに(かな?)見送って下さいました

だんだん、山道になってきましたが、まだまだ舗装された歩きやすい道です


しばらく歩くと、本格的な山道に入りました
ここは「大根峠」と言われ、標高約200メートル位
多くのお遍路さんは、私たちが昨日歩いた、鶴林寺・太龍寺の急な上り下りの後、
平等寺まで一日で歩かれます
丁度、足が疲れた夕方にこの峠を越えるので、ここも「お遍路ころがし」と言われています

私達は、まだ元気な朝一番でここを登りますが、山道は登り慣れないのと、
昨晩からの雨の為か足元も悪く、結構必死で歩いたかも(笑) 結構大変だった!!

雨の後の為でしょう、沢蟹(かな???)や大きなミミズ(太さは、中指位だった)が
歩く道のあちこちに出没 (@_@;)
巨大ミミズは、思わず見た時に「ひえ~~~っ」と声をあげてしまった
周りに人がいなかったから良かったが、私の声のほうが驚かれたかもですね




汗をフキフキ・・・・・


下りは割と緩やかだったけれども、木の根っこ、岩など 足元に注意しながら歩きました

雨は降らず(ラッキーですね)、段々明るくなって、木の間から、日も差してきました

ようやく峠を越えて、開けた所に出てきました これで、安心・安心です

お遍路小屋
ここで、ひとまず休憩 二人とも、汗びっしょりです


その後は、舗装された道路をテクテク歩き、見えてきました!
平等寺に到着


第22番札所 平等寺
平等寺は四国霊場第22番の札所で寺伝によると弘法大師がこの地で修行中、薬師如来を感得して自らその像を刻んで本尊として伽藍を建立し人々を平等に救うために寺号を平等寺としたといわれている。
また、その時に加持水を求めてこの地を掘ったところ、乳のような白い霊水が湧き出てきたために、山号を白水山としたという。ここから湧き出る水は万病の妙薬として、有名。本堂には、イザリ車やギブスなど、四国遍路によって健康をとりもどした人が使用していた品々がたくさん奉納されている。






正面に42段の男厄坂が左には緩やかな33段の女厄坂があり上り詰めると本堂が建ちます
相棒は、女厄坂を登り


 ぼくちゃんは、男厄坂を登りました
ぼくちゃんは、男厄坂を登りました


<本堂>

<大師堂>
 縦
縦
休憩所に「弘法の霊水」 もちろん、二人とも飲みました
ご利益あるよね


ここにも、有難いお接待です 二つ頂き、お賽銭入れに使わせて頂いています

平等寺のお参りも終わり、遍路道で、薬王寺へ・・・・では無くて、

今回は、平等寺から、最寄りの新野駅に向かい、JRで薬王寺の最寄駅 日和佐へ向かいます

新野駅は無人駅でした
12時少し前で、電車の待ち時間もあったので、お昼タイム
コンビニご飯とあきらめてたのに、ラッキー (#^.^#)なことに、
駅前の「タケノコ」という喫茶店がありました

本日のランチメニュー クリームコロッケ定食 ¥580 プラス200円で コーヒー付

相棒は、ビールを(大瓶だぞっ おつまみ付) ¥680 なぜか、ランチより高い(笑)

デザートのヨーグルトは、なぜか二ついただきました
ランチの注文は一つだったんだけどな・・・・ ありがとうございます。ご馳走様でした
新野駅から普通電車で



日和佐駅に到着

NHKの連続テレビ小説 「ウェルかめ」の舞台になった町です
ここまでくれば、第二十三番 薬王寺はもう目の前!

第23番札所 薬王寺
当山は行基菩薩の開基と伝えられる。弘法大師は、自他厄除のご誓願をこめられて、本尊厄除薬師如来を一刀三札して刻まれ、日本で唯一体の尊像といわれ、文治4年の火災の折、本尊は玉厨子山に飛び去って難をさけられ、後、再建され新しい本尊に入仏供養の折、又、飛び帰って後ろ向きに厨子に入る(俗に後向薬師という。)尊像は2体となったと伝えられる。
当時は、平城天皇以来、厄除根本道場の宮寺として、上下の尊信はきわめてあつく、参拝者も四季を通じて後を絶たず、寺宝も数多い。


ようやく、ようやく 到着です 長い道のりだったぁ



本堂まで 男厄坂42段、女厄坂33段 を登りました




本堂の前から、の日和佐の町を望む

<本堂>
文治4年(1188)堂宇全焼す
寛永16年(1639)江戸前期、本堂其の他殆ど消失す。
明治31年8月 方丈庫裡護摩堂、仮薬師堂消失。第18世 実善代。
現在の本堂は、明治41年の建立。

<大師堂>

瑜祇塔に向かいます


男女還暦厄坂61段。瑜祇塔落慶時に完成したそうです

結構急な階段で、てすりを持って、一歩一歩ゆっくり進んでいきました


阿波の23番薬王寺は、厄除けのお寺で有名だそうです
薬王寺境内には三つの厄坂があります。仁王門を入り、下から順に、女厄坂33段、絵馬堂から本堂への男厄坂42段、そして瑜祇塔へと続く男女還暦厄坂61段。厄坂石段の下には、小石に書かれた薬師如来の経文がおさめられているので、一段づつ一円玉を置きながら登って厄を落としていくのだそうです。
厄年ではない参拝者も、自分の年の数だけ一円玉を置きながら上がっていく方が多く、階段には何枚も一円玉がおいてありました。
私達も、お財布に入っていた一円玉を階段においてきました(何枚置いたかは秘密・・・ 年の数には到底足りませんでしたけど)



瑜祇塔 (高さ29m)
昭和38年9月建立
本尊金色五智如来
昭和39年は弘法大師が四国八十八ヶ所の霊場を開創してからちょうど1150年に当たり、また、翌40年は高野山開創1150年に当たるのでこれを記念して建立されたものである。
瑜祇塔は真言宗所依の経典である。
瑜祇経の教理を形にあらわしたものであり、経文には世の中のものみな二つの相対したものからできているが、これが一つになることによって世界の平和や家庭の幸福の基礎があると説かれている、天と地が和合して万物が豊かとなり、労使が相寄って社会の平和ともなる道理である。
瑜祇塔には上方に金剛智慧をあらわす五峯を示し、周囲に胎蔵の理論の表示である八柱を建て、これが不二を示すよう上の方が四角、下の方は円筒形の一重の塔となっている。
これで、 無事に、徳島を打ち終わることができました

今日の宿、「ウミガメ荘」へ向かいます
途中に、お遍路さんお接待所があり、「どうぞお入りください」と声をかけていただきましたので
入ることに・・・・・ そこで!!!!


一日目の恩山寺・立江寺から、その日の宿泊所の金子やさんへ歩いているときに出会った
山口県 萩のMさんがいらっしゃいました
偶然とはいえ、この再会は驚きでそしてとてもうれしいものでした
まさか、ここでお会いできるとは思いませんでしたので・・・・・ これも何かのご縁なのでしょうね

お接待所では、冷たい缶コーヒー、お茶、草餅、みかんをいただきました
本当にありがたいことです
草餅を持って帰ろうとすると、手作りのきんちゃくも「これに入れたらいいですよ」と・・・
ありがとうございました

後は、宿まで、ゆっくり歩いても5分程度です
疲れていましたが、二人で今日の出会いや無事に薬王寺まで到着できたことを
話しながらゆっくり歩いて行きました

今日のゴール!!!
そして、日和佐は「うみがめの来る町」で有名です
HPデス → http://www.town.minami.tokushima.jp/umigame/
あちらこちらで、うみがめが迎えてくれました
☆マンホールの蓋☆

☆観光協会にて☆


☆厄除橋にて☆


☆ウミガメの電話ボックス☆

☆日和佐うみがめ博物館カレッタ の所のプールで・・・

うみがめ荘のフロントで


これは、ウミガメではありません 笑!

夕食! 至福の時間です
もちろん、大浴場も満喫しました

今回の3日間の徳島巡礼が終わりました
マイペースで、マイペースでと言われた通りの3日間でした
自分たちで予定を組み、荷物を持って、そして山あり谷あり(谷は無かったかな 笑)の
歩きの旅行、初めてづくしの珍道中だったかな?
荷物を余計に持って行きすぎたり(重かったぁ~~)、
歩くのに思った以上に時間がかかったり
やってみなければ判らないことも沢山!!
下調べが足りずに、帰ってから見逃した所もあったことに気づいたり (>_<)
とりあえず、八十八か所巡り 徳島編はこれにて打ち止めですが、
ぼくちゃんと相棒のお遍路珍道中の旅はこれからも続く(予定)のです
今回、お会いした方々皆様に感謝・感謝です

今回、歩いて沢山のお寺をお参りすることができました
家族・お友達、などなど、周りの方の健康をお願いしました
もちろん、私達二人の健康もですけどね
健康でなくっちゃこれから先の”修行の旅”続けられないですから
これから先、どんな出会いが有るのか、とても楽しみ

そして、長い・長いブログを読んでいただきありがとうございました
お・し・ま・い





























































































 この枠から覗くと見えます
この枠から覗くと見えます
























































 お京さんの冥福を祈る位牌も奥に安置されていました
お京さんの冥福を祈る位牌も奥に安置されていました












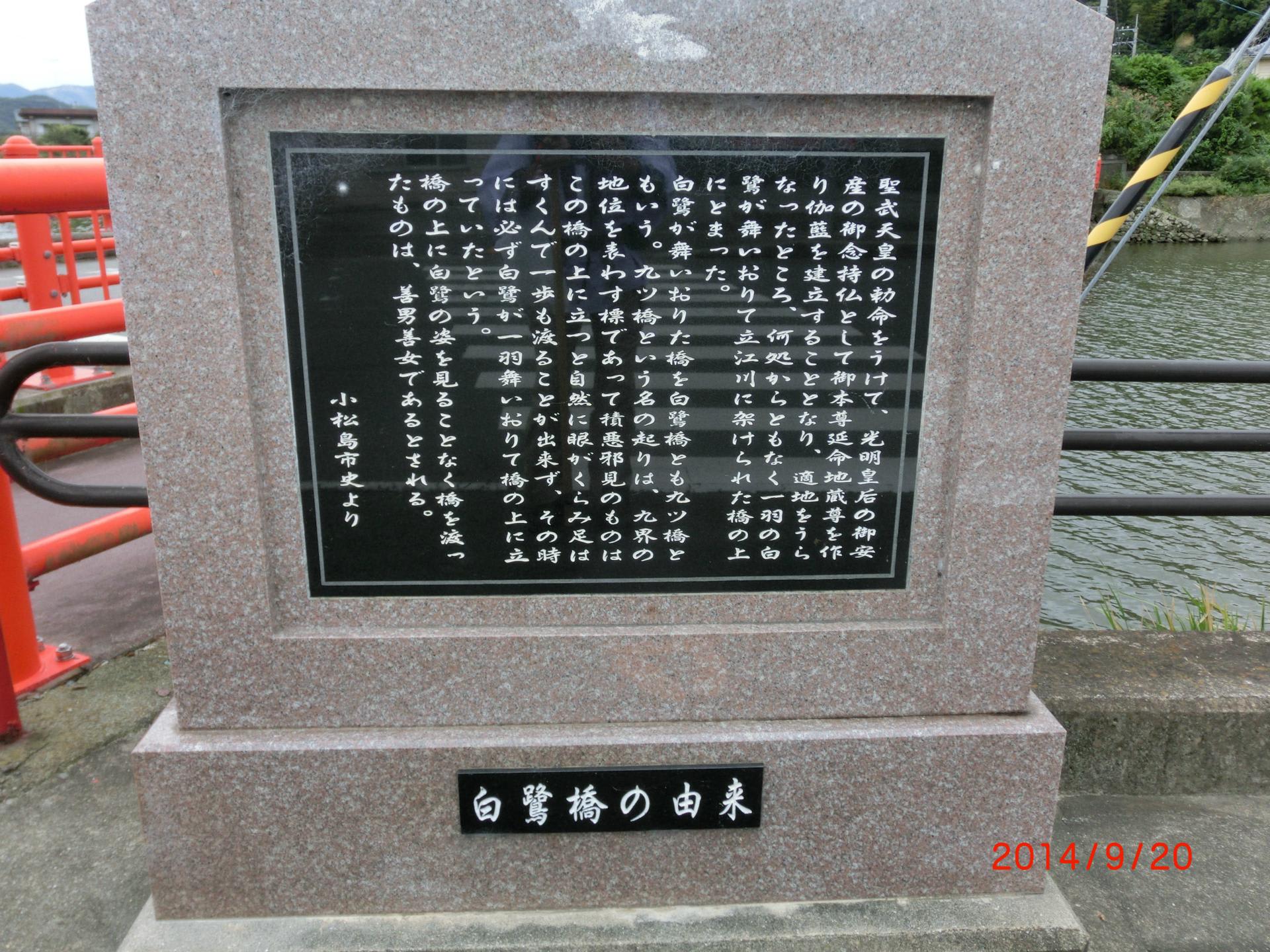



















 など
など

















 篠栗町商工会キャラクター
篠栗町商工会キャラクター

