6日金曜日は職場が休みだったので,皇居の「大嘗宮一般参観」と「令和元年秋季皇居乾通り一般公開」に出かけてきました。




















乗った電車のトラブルもあり,皇居外苑二重橋付近に着いたのが9時10分頃,そこから参入口となる坂下門に向かい,手荷物検査などを受けて参入したのが9時20分。

奥は諸行事が行われる宮殿です。入ることはできません。^ ^

宮内庁前を通り乾通りを進みます。
乾通りの紅葉は少しピークを過ぎた感じですかね。

乾通りに面した局門です。当時は大奥の女中さんたちが出入りする通用門だったそうです。

道灌濠もいい雰囲気です。

ここで乾通りと別れ,西桔橋(にしはねばし)を渡って(江戸城)本丸に向かいます。

乾通りをまっすぐ進んでしまうと,大嘗宮がある本丸に戻ることはできません。(坂下門から再参入)

(江戸城)本丸まで上がってくると,大嘗宮の一部が見えてきます。

本丸内の紅葉です。

◯大嘗祭
大嘗祭は,稲作農業を中心とした我が国の社会に古くから伝承されてきた収穫儀礼に根ざしたもので,天皇が即位の後,初めて,大嘗宮において,新穀を皇祖および天神地祇に供え,みずからも召し上がって,国家・国民のために安寧と五穀豊穣などを祈念する儀式です。
皇位の継承があったときは,必ず挙行すべきものとされ,皇室の長い伝統を受け継いだ皇位継承に伴う一世に一度の重要な儀式。(宮内庁HPより,平面図も)

9時50分,正門までやってきました。ここまでは比較的すんなりと進んできましたが,ここから写真(撮影)渋滞でなかなか進みません。
大嘗宮の屋根は本来茅葺きですが,今回は職人不足のためすべてが板葺きになったそうです?

長蛇の列ができた売店を過ぎると膳屋(かしわや)が見えてきます。

小忌幄舎(おみのあくしゃ)(右)と風俗歌国栖古風幄(ふぞくうたくずのいにしえぶりのあく)です。
小忌幄舎の上に「悠紀殿共饌の儀」が行われる悠紀殿(ゆきでん)の屋根が,風俗歌国栖古風幄の上には「主基殿共饌の儀」が行われる主基殿(すきでん)の屋根が少しだけ見えています。
小忌幄舎の上に「悠紀殿共饌の儀」が行われる悠紀殿(ゆきでん)の屋根が,風俗歌国栖古風幄の上には「主基殿共饌の儀」が行われる主基殿(すきでん)の屋根が少しだけ見えています。

10時に大嘗宮正面(南神門)に到着しました。
南神門の左右手前に少し見えているのが衛門幄(えもんあく),その奥が威儀幄(いぎあく),そして正面が殿外小忌幄舎(でんがいおみのあくしゃ)になります。
南神門の左右手前に少し見えているのが衛門幄(えもんあく),その奥が威儀幄(いぎあく),そして正面が殿外小忌幄舎(でんがいおみのあくしゃ)になります。

西神門と左奥が主基殿,その手前が楽舎(がくしゃ),さらに右に庭積帳殿(にわずみのちょうでん)が見えています。手前のふたつは,衛門幄と庭燎舎(ていりょうしゃ)です。

北側からみた大嘗宮です。
左に廻立殿(かいりゅうでん),右に主基殿を見ることができます。

大嘗宮を参観したあとは皇居東御苑を散策,雑木林など初冬のいい雰囲気でした。




【追 記】
一般参観および一般公開は12月8日(日)で終了しましたが,この間の参入者は,792,911人(大嘗宮参観:782,081人,乾通り公開:381,173人)だったそうです。











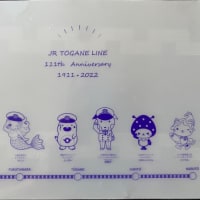












綺麗に紅葉していますね。この儀式に献上された反物は徳島県美馬市木屋平の麻が使われています。私は今から20年前に木屋平で3年間働いていました。僻地です。本当に山の中です💦
麻は天日干しや発酵などを経て8月上旬、美馬市内の神社で麻糸に紡ぐ「初紡式」を行うそうです。9月上旬に献上品の反物に仕上げられます。
当然ですが、相当に手の込んだ造りになっておられますね。
これを割りと短期間で此処まで仕上げられたかと記憶しております。
腕のよい職人さん(棟梁?)の方々の賜物かもしれないですね。
茅葺は職人さんもですが、おそらく材料とする萱そのものが不足しているのではと聞いた覚えがあります。
今全国でも茅葺屋根はなかなか無いでしょうし。
それにしてもこれだけの大掛かりな建築物、神道は新しきを旨とするのは存じておりますが、この後に取り壊されるのは、なんとも勿体無い気がするのは私だけでしょうか;。
解体した大嘗宮の材木はどうするのでしょうかね。何か記念の枡とか作ったら喜ばれそう。
勉強させていただきました。麁服の素材は徳島からの調進だったのですね。それも奈良時代から続いているとは・・・,阿波忌部のかたは地元の名士なんでしょうね。
徳島の僻地というと30年以上前でしたが,祖谷のかずら橋を訪れたことがあります。そこから小歩危・大歩危経由で高知まで行きましたが,道が狭くて・・・^^;
こういったものを目にする機会はそうそうないでしょうから,たまたま休みということもあって奥さんと出かけてきました。
茅葺き屋根がなくなれば茅萱の需要も減り,神社の茅の輪くらいでしょうか?^^;
実家は私が小学生くらいまでは藁葺き屋根でした。耐久性では茅葺きなんでしょうが,手に入りやすい麦藁で葺いていました。今はもう葺ける人もいないでしょう。
今回は,使用した木材も(一部)再利用されるようですよ。
乾通りが初めて公開された2014年の桜の時期にも行きましたが,その時に比べれば空いていたように思います。
これで春と秋一度ずつ行ったのでもういいかなと・・・,いつでも入れる東御苑あたりでも紅葉が楽しめますしね。^^;
平成のときはすべて燃やしたらしいですが,今回は一部は神事の一環で「おたきあげ」されるようですが,あとはバイオマス燃料として再利用されるようです。加工品となるとまた経費がかかるということなんでしょうね。
そこで風邪をもらってきたみたいですが…(笑)
初めて入りましたが中は広いですね~。石垣も立派で。
乾通りもちょうど紅葉していて、大嘗宮も外から見ました(`・∀・´)外から…、そうすごい長い列だったのでとても並べませんでした。親父さんしっかり並んでこんなに近くから細かく見られたのですね。写真どうもありがとうございます!私これで近くで見た気になれました(笑)
おー,イケネコさんも行かれましたか。
えっ,外から?本丸には入られたのかな?皇居の参入者が79万人で大嘗宮の参観者が78万人ですから,大嘗宮に参観しなかかった方もそれなりに(1万人)いらしたんですね。^ ^
まぁ,イケネコさんは先が長くない私と違って,また見る機会もあるでしょうしね。(^^)