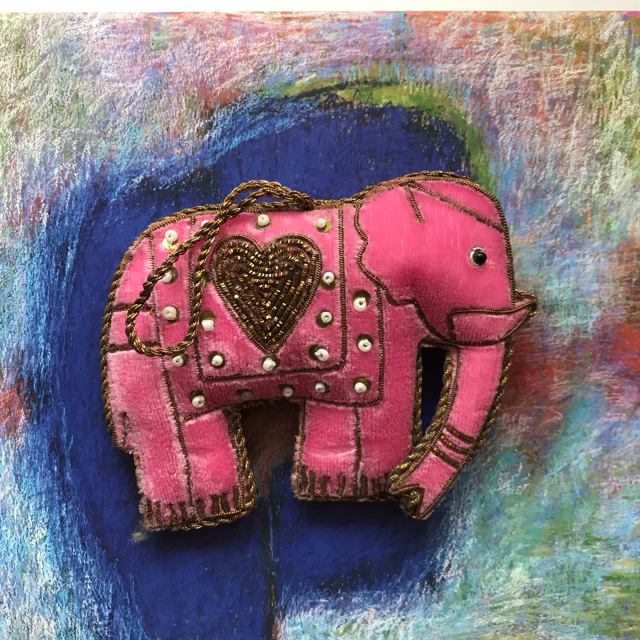『記憶に辿りつく絵画 ~亡き人を描く画家~』
きょうの日曜美術館は、ミョ~に感動して泣いてしまった。
すみません、存じあげませんでしたが、諏訪敦さんという写実画家、彼にきた作品制作の依頼。
「事故で突然亡くなった娘の肖像画を描いてほしい」
諏訪さんのスゴイと思ったところは、絵を描くにあたって徹底的に取材を重ねるということ。これまで描いてきた、舞踏家である「大野一雄」シリーズも、1年にわたる丹念な取材をもとに描かれている。
今回の作品を描くにあたっても、まず両親の顔をデッサンする。母親の骨格や肌ざわりを自分の手で触って確かめる。
絵を描くって、目の仕業と思っていたけど、触覚とかも関係あるのだなあ…、と。
途中、諏訪さんは、自分が解釈した、しかも超写実的な娘さんを描くことが、ご両親の思い出を壊してしまうことにならないか、と思い悩んだりもするのだけど、彼が得たあらゆる情報をもとに、まだ両親が見たことのない娘の肖像画をついに完成させるのだ。
その出来あがった作品を目にした時、うっと胸をつかれるものがあった。
何というのだろう… 「絵」とか「絵を描く」ことの素晴らしさ、ひと筆ひと筆重ねて作品をつくることの重みや重厚さ、人間が営々と絵を描き続けてきたことの尊さ、みたいなものがドドッと押し寄せてきた感じ。
諏訪さんの作品がある意味写真みたいだから(きっとご両親も、だから依頼したのではないでしょうか)、よけい絵画と写真の差が際立つようにも思うし、この亡くなった見ず知らずの女性を描く、という特別なシチュエーションもそのような思いをひとしおにしたのかもしれない。
画家ってすごいです。改めて思う。
この頃の日曜美術館は、けっこうライブ感があるように思っておもしろい。司会のお二人のしょっちゅうスタジオを飛び出しているし、今回のドキュメンタリータッチもすごく良かったです。
来週日曜日の夜8時から再放送。

きょうの日曜美術館は、ミョ~に感動して泣いてしまった。
すみません、存じあげませんでしたが、諏訪敦さんという写実画家、彼にきた作品制作の依頼。
「事故で突然亡くなった娘の肖像画を描いてほしい」
諏訪さんのスゴイと思ったところは、絵を描くにあたって徹底的に取材を重ねるということ。これまで描いてきた、舞踏家である「大野一雄」シリーズも、1年にわたる丹念な取材をもとに描かれている。
今回の作品を描くにあたっても、まず両親の顔をデッサンする。母親の骨格や肌ざわりを自分の手で触って確かめる。
絵を描くって、目の仕業と思っていたけど、触覚とかも関係あるのだなあ…、と。
途中、諏訪さんは、自分が解釈した、しかも超写実的な娘さんを描くことが、ご両親の思い出を壊してしまうことにならないか、と思い悩んだりもするのだけど、彼が得たあらゆる情報をもとに、まだ両親が見たことのない娘の肖像画をついに完成させるのだ。
その出来あがった作品を目にした時、うっと胸をつかれるものがあった。
何というのだろう… 「絵」とか「絵を描く」ことの素晴らしさ、ひと筆ひと筆重ねて作品をつくることの重みや重厚さ、人間が営々と絵を描き続けてきたことの尊さ、みたいなものがドドッと押し寄せてきた感じ。
諏訪さんの作品がある意味写真みたいだから(きっとご両親も、だから依頼したのではないでしょうか)、よけい絵画と写真の差が際立つようにも思うし、この亡くなった見ず知らずの女性を描く、という特別なシチュエーションもそのような思いをひとしおにしたのかもしれない。
画家ってすごいです。改めて思う。
この頃の日曜美術館は、けっこうライブ感があるように思っておもしろい。司会のお二人のしょっちゅうスタジオを飛び出しているし、今回のドキュメンタリータッチもすごく良かったです。
来週日曜日の夜8時から再放送。