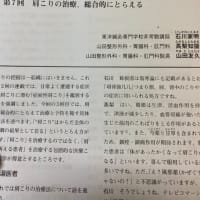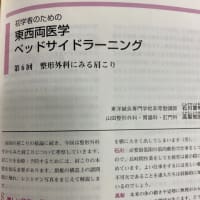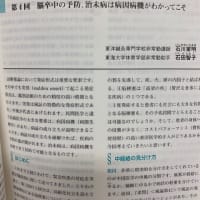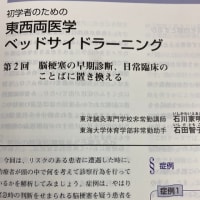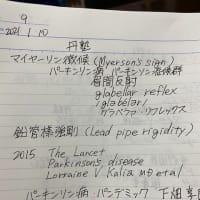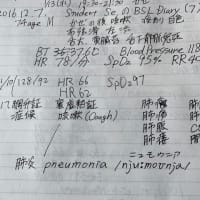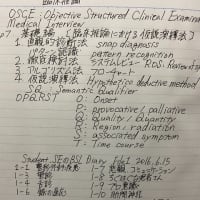『「スピリチュアル」の系譜を描き直す : ヒーリング技法「レイキ」の誕生から現代自己啓発言説まで』
平野直子
『応用社会学研究』
58号 81 - 92 2016-03-23
http://ci.nii.ac.jp/naid/120005746858
http://ci.nii.ac.jp/naid/120005746858
(全文無料オープンアクセス)
↑
早稲田大学の平野直子先生が『応用社会学』2016年に発表された論文は、「レイキ」研究だけでなく、代替医療全般の研究に影響を与えるものです。
アメリカ国立衛生研究所NIHの中にNCIIH(アメリカ国立補完統合衛生センター)があり、アメリカの補完医療・統合医療の中心となっています。
もともとは、1993年に北京中医薬大学で学んだデビッド・アイゼンバーグという医師が、『ニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディスン』に「アメリカ人の34パーセントが1年のうちに、非正統的医療(代替医療)を使用しているlこと」を報告し、それがきっかけで、アメリカ政府に「アメリカ国立補完代替医療センター(NCCAM)」が出来ました。
↓
Unconventional Medicine in the United States -- Prevalence, Costs, and Patterns of Use
Devid Eisenberg et a.
Volume 328:246-252 January 28, 1993 Number 4
New England Journal of Medicine
New England Journal of Medicine
デビッド・アイゼンバーグの『気との遭遇(Encounters with Qi: Exploring Chinese Medicine)』という本は、アイゼンバーグが中国で出合った気功や鍼灸、漢方のことが書かれており、面白いです。
↓
『気との遭遇―ハーバードの医学者が中国で「気の謎」に挑んだ! 』
デビッド アイゼンバーグ
http://www.amazon.co.jp/dp/4796600728
デビッド アイゼンバーグ
http://www.amazon.co.jp/dp/4796600728
原著はEncounters with Qi: Exploring Chinese Medicine Paperback – July 17, 1995
NCCAM(アメリカ国立補完代替医療センター)は、鍼灸やカイロプラクティックを研究しはじめたのですが、『セラピューティック・タッチ(Therapeutic touch)』というハンド・ヒーリングを研究していたことで、「税金でニセ科学を研究するな!」と猛批判を受けて、NCIIH(アメリカ国立補完統合衛生センター)に名称を変えられてしまいました。
↓
『続 アメリカ医療の光と影 第216回 セラピューティック・タッチ』
李 啓充
『続 アメリカ医療の光と影 第216回 セラピューティック・タッチ』
李 啓充
ハンド・ヒーリングの科学的研究は、いまだに危険な領域のようです。 『セラピューティック・タッチ』は、アメリカ神智学協会のプレジデントであるドーラ・クーンツ(Dora Kunz :1904ー1999)が始めました。ドーラ・クーンツは、チャクラやオーラと言うコトバを世界に広めた神智学協会のリードビーター(Charles Webster Leadbeater:1854ー1934)の直弟子です。ドーラ・クーンツの「セラピューティック・タッチ」は、ニューヨーク大学の看護学の教授ドロレス・クリーガー(Dolores Krieger)によって大学で看護師たちに教えられ、ニューヨークで大人気になっていました。個人的には、『セラピューティック・タッチ』がハンド・ヒーリング分野で一番、良い本だと思います。
↓
『セラピューティック・タッチ』
ドロレス クリーガー 春秋社 (1999/10)
http://www.amazon.co.jp/dp/4393710304
ドロレス クリーガー 春秋社 (1999/10)
http://www.amazon.co.jp/dp/4393710304
日本では、1990年代に、バーバラ・アン・ブレナン(Barbara Ann Brennan:1939ー)の『光の手(Hands of Light:1987)』などハンド・ヒーリングが流行っていました。ブレナンさんによれば、「HARA(腹)」が人体エネルギー・フィールドの中心だそうです。
ハンドヒーリング分野で真打ちとも言えるのが、「レイキ(Reiki)」です。1990年代から、「レイキ(Reiki)」は日本で大流行しました。
「レイキ(Reiki)」は日本の臼井 甕男(うすい・みかお:1865- 1926)が57歳のときに、1922年(大正11年)先生が、鞍馬山にこもって断食して、「臼井霊気療法」を開発しました。臼井 甕男先生は4年後の1926年(大正15年)に突然、亡くなります。
臼井 甕男先生の弟子の海軍大佐・林忠次郎(1879 - 1940)さんにより、東京で治療を受けたハワイ生まれの日系アメリカ人高田はわよ(1900-1980)さんは、1937年にハワイに帰りました。林忠次郎さんは1940年に自殺しています。
ハワイ在住の高田はわよ(1900-1980)さんは、1970年から1980年にかけて、22人の「レイキ・マスター」を育てて、それが西洋世界に拡がり、1980年代後半から1990年代の日本に逆輸入されました。
平野直子先生が『応用社会学』2016年に発表された論文では、臼井 甕男(うすい・みかお)が鞍馬山にこもって1922年(大正11年)に「レイキ(霊気)」を開発した同時代を描いています。
1916年に、アメリカの偽インド人ヨギ・ラマチャラカ(本名ウィリアム・ウォーカー・アトキンソン)の翻訳『最新精神療法』が出版され、「プラーナ」を「霊気」と翻訳しています。
1921年に、松本道別(まつもと・ちわき)は、『人体ラジウム療法』の中で「プラーナ」を「霊気」と翻訳しています。松本道別の弟子の1人が「整体」をつくった野口晴哉です。
1921年に、山田信一が出版した『山田式整体術 第1巻プラーナ療法』では、レイキ(霊気)と共通した考え方を述べています。山田信一が日本に最初にオステオパシーを紹介し、「整体」という言葉を使いました。
つまり、臼井 甕男(うすい・みかお)師の「臼井霊気療法」は、同時代の、霊術や整体と深い関わりがあるようです。これは2016年3月出版の『応用社会学研究』の論文ではじめて指摘されたことです。
「プラーナ(霊気)療法」を世界に広めたアメリカの偽インド人ヨギ・ラマチャラカ(本名ウィリアム・ウォーカー・アトキンソン)さんは、本名で以下の本も書いており、2007年に日本でベストセラーになりました。
↓
ウイリアム・ウォーカー・アトキンソン『引き寄せの法則』2007年
1910年代から1920年代にアメリカで流行した「ニューソート」や日本の「霊術」「療術」は、現代社会に大きな影響を与えています。