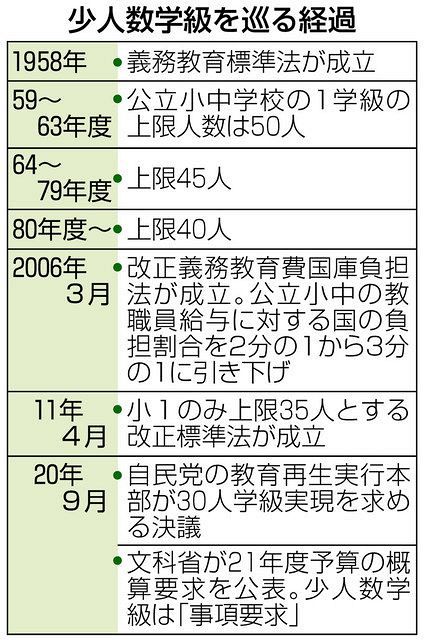「
比叡山に立て籠もって織田軍と対峙する(志賀の陣)。このとき信長は比叡山に自らに味方するよう求めたが無視された。また10月20日に織田・朝倉間で小規模な戦闘があり、信長は義景に日時を定めての決戦を求めたが義景は無視した(『言継卿記』『尋憲記』『信長公記』)。11月25日、信長は義景の退路を断つために堅田に別軍を送った。11月26日に朝倉・織田間で合戦になり痛み分けとなる。11月28日、足利義昭・二条晴良らが坂本に下向して和睦の調停を行なった。さらに信長は朝廷へ工作を行なったため、12月に信長と義景は勅命講和することになる。なおこの勅命講和の対象が延暦寺だけに限定されていたとする指摘もある[27]。
元亀2年(1571年)1月、信長は秀吉に命じて越前や近江間の交通を遮断・妨害した。6月11日、義景は顕如と和睦し、顕如の子・教如と娘の婚約を成立させた(『顕如上人御書札案留』)。7月に六角承禎が京都に侵攻しようとした際には、洛中で放火などしないようにという書状を送っている(『田川左五郎氏所蔵文書』)。8月、義景は浅井長政と共同して織田領の横山城、箕浦城を攻撃するが、逆に信長に兵站を脅かされて敗退した。この後、信長は前年に朝倉に協力した比叡山を焼き討ちした。
元亀3年(1572年)7月、信長は小谷城を包囲し、虎御前山・八相山・宮部の各砦を整備しはじめた。これを見た浅井氏は朝倉氏に「長島一向一揆が尾張と美濃の間を封鎖したので、今出馬してくれれば織田軍を討ち果たせる」と虚報を伝え、義景はこれを信じて支援に赴いた。しかし義景は攻勢には出ず、織田軍から散発的な攻撃を受けると、前波吉継や富田長繁ら有力家臣が信長方に寝返った。9月には砦が完成。信長は再び日時を決めての決戦を申し入れてきたが、義景はまた無視した。9月16日、信長は砦に木下秀吉を残し、横山城へと兵を引いた。
10月、甲斐国の武田信玄が西上作戦を開始し、遠江・三河方面へ侵攻し、徳川軍は次々と城を奪われた。この出兵の際、信玄は義景に対して協力を求めている。これを受けて信長が岐阜に撤退すると、義景は浅井勢と共同で打って出たが、虎御前山砦の羽柴隊に敗退。12月3日には部下の疲労と積雪を理由に越前へと撤退してしまい、そのため信玄から激しい非難を込めた文章を送りつけられる(伊能文書)。
元亀4年(1573年)2月16日、信玄は顕如に対して義景の撤兵に対する恨み言を述べながらも再度の出兵を求め、顕如もまた義景の出兵を求めている。3月に義昭が正式に信長と絶縁すると、義景の上洛の噂もあったというが(耶蘇会日本年報)、義景は動かなかった。
4月12日、朝倉家にとって同盟者であった武田信玄は陣中で病死し、武田軍は甲斐に引き揚げた。このため、信長は織田軍の主力を朝倉家に向けることが可能になった。
天正元年(1573年)8月8日、信長は3万の軍を率いて近江に侵攻する。これに対して義景も軍を率いて出陣しようとするが、数々の失態を犯し重ねてきた義景はすでに家臣の信頼を失いつつあり、「疲労で出陣できない」として朝倉家の重臣である朝倉景鏡、魚住景固らが義景の出陣命令を拒否する[注釈 4]。このため、義景は山崎吉家、河井宗清らを招集し、2万の軍勢を率いて出陣した。
8月12日、信長は暴風雨を利用して自ら朝倉方の砦である大嶽砦を攻める。信長の奇襲により、朝倉軍は敗退して砦から追われてしまう。8月13日には丁野山砦が陥落し、義景は長政と連携を取り合うことが不可能になった。このため、義景は越前への撤兵を決断する。ところが信長は義景の撤退を予測していたため、朝倉軍は信長自らが率いる織田軍の追撃を受けることになる。この田部山の戦いで朝倉軍は敗退し、柳瀬に逃走した[注釈 5]。
信長の追撃は厳しく、朝倉軍は撤退途中の刀根坂において織田軍に追いつかれ、壊滅的な被害を受けてしまう[注釈 6]。義景自身は疋壇城に逃げ込んだが、この戦いで斎藤龍興、山崎吉家、山崎吉延らの武将が戦死した。但し、斎藤龍興に関しては生存説が複数存在している。
義景は疋壇城から逃走して一乗谷を目指したが、この間にも将兵の逃亡が相次ぎ、残ったのは鳥居景近や高橋景業ら10人程度の側近のみとなってしまう。8月15日、義景は一乗谷に帰還した。ところが朝倉軍の壊滅を知って、一乗谷の留守を守っていた将兵の大半は逃走してしまっていた。義景が出陣命令を出しても、朝倉景鏡以外は出陣してさえ来なかった[注釈 7]。
このため義景は自害しようとしたが、近臣の鳥居・高橋に止められたという。8月16日、義景は景鏡の勧めに従って一乗谷を放棄し、東雲寺に逃れた。8月17日には平泉寺の僧兵に援軍を要請する。しかし信長の調略を受けていた平泉寺は義景の要請に応じずに、東雲寺を逆に襲ったため、義景は8月19日夕刻、景鏡の防備の不安ありとの勧めから賢松寺に逃れた。
一方、8月18日に信長率いる織田軍は柴田勝家を先鋒として一乗谷に攻め込み、居館や神社仏閣などを放火した。この放火は三日三晩続いたのである
従兄弟の朝倉景鏡の勧めで賢松寺に逃れていた義景であったが、8月20日早朝、その景鏡が織田信長と通じて裏切り、賢松寺を200騎で襲撃する。ここに至って義景は自刃を遂げた。享年41」
どこまで、今日は放送するのか。
天正と元亀。令和と平成。
紙一重の年数が災難が、幸運か、人にはある。
天正は、有名人が死ぬは、織田信長、明智光秀。
元亀と天正の境は、武田信玄の死。
元号で、変わる、人の人生。
元亀2年、令和二年。
ーーーー
「天正二年(1574年)1月1日、織田信長が、前年討ち取った浅井久政・長政及び朝倉義景の髑髏に漆を塗ったものを馬廻衆との宴に披露したと『信長公記』にあるが、『浅井三代記』ではこれらの髑髏を杯にしたとある。NHKの大河ドラマ『功名が辻』で使われた3人の黄金の髑髏杯が掛川城に展示してある。」
の場面、あるか、ないだろうな。
髑髏を杯。
敗者も、屈辱か、残るか。