お盆が近づいてきました。
お盆をきれいに迎えようと地区では、
毎年7月最後の日曜日に墓地・お宮・集会所周辺を、
区民総がかりで草刈りと大掃除をします。
小雨模様の中みなさん汗びっしょりになって、
地区の銀座通りをきれいにしていただきました。
その後は年度の折り返し地点でもあるため、
中途で発生した課題を協議する臨時総会を行いました。
お宮拝殿の修理に併せ天王社が壊れたため、
取替えの提案が社寺係から行われました。

天王というと大阪の四天王寺とか津島の天王祭りを思い浮かべますが、
地区とのかかわりはどうなんだろうと調べてみました。
それを紐解いてくれたのが、
既に亡くなって10年になる地区の古老が、
生涯かけて調べた入鹿史です。
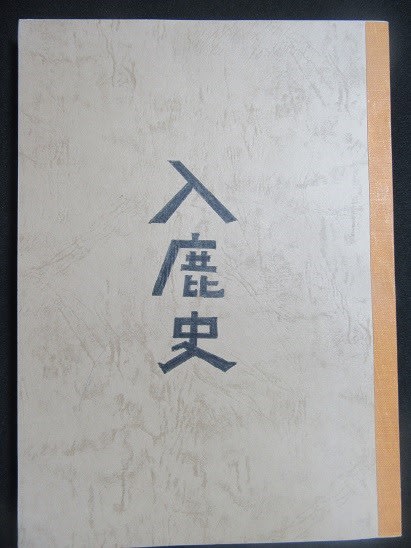
記述によれば
地区内に建立されたのが1840年(天保11年)とあります。
明治元年が1868年ですから177年前の江戸末期です。
天王信仰については
古代インドの宇宙論として小世界の中心に須弥山(シュミセン)があるとされ、
その中腹に住む四人の天王を指す。
聖徳太子が大阪に四天王寺を建立した。
本来、行疫の神、尼神である。
祇園祭や津島の天王祭はこの信仰の流れをくむ。
入鹿ではセキノ方送りと呼んで、
津島天王祭の前日に子供たちが竹笹をかつぎ、
村の中と二ヵ所の天王社を廻り、
村人たちは悪疫やけがれを一枚の紙に託して、
その笹に結び付けて村境へ二人のお供の人形とともに送り出していた。
子供の数が減り昭和の時代にこの行事は途絶え、
現在は津島神社のお札を祀って区民の無病息災を願っている。
と書かれていました。
宗教や信仰には詳しくありませんが、
先祖にあたる村人たちが、
疫やけがれを追い払い平安な暮らしを求めて、
この信仰に託していた様子がうかがえます。
科学が進歩した現代では無くていい分野かもしれませんが、
人間が歩んできた生活と暮らしの文化に違いありません。
過度な負担でない限り後世へ継承していきたいものです。
< 祠一つ古の暮らししのぶる >
お盆をきれいに迎えようと地区では、
毎年7月最後の日曜日に墓地・お宮・集会所周辺を、
区民総がかりで草刈りと大掃除をします。
小雨模様の中みなさん汗びっしょりになって、
地区の銀座通りをきれいにしていただきました。
その後は年度の折り返し地点でもあるため、
中途で発生した課題を協議する臨時総会を行いました。
お宮拝殿の修理に併せ天王社が壊れたため、
取替えの提案が社寺係から行われました。

天王というと大阪の四天王寺とか津島の天王祭りを思い浮かべますが、
地区とのかかわりはどうなんだろうと調べてみました。
それを紐解いてくれたのが、
既に亡くなって10年になる地区の古老が、
生涯かけて調べた入鹿史です。
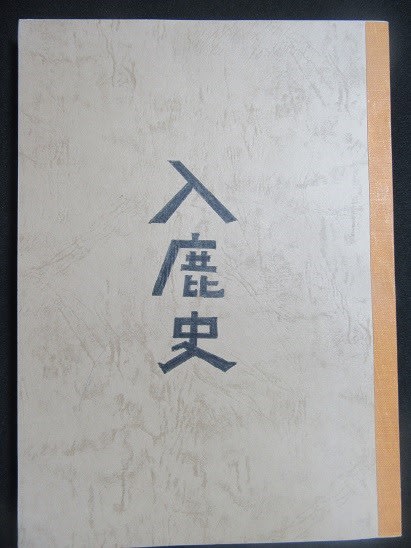
記述によれば
地区内に建立されたのが1840年(天保11年)とあります。
明治元年が1868年ですから177年前の江戸末期です。
天王信仰については
古代インドの宇宙論として小世界の中心に須弥山(シュミセン)があるとされ、
その中腹に住む四人の天王を指す。
聖徳太子が大阪に四天王寺を建立した。
本来、行疫の神、尼神である。
祇園祭や津島の天王祭はこの信仰の流れをくむ。
入鹿ではセキノ方送りと呼んで、
津島天王祭の前日に子供たちが竹笹をかつぎ、
村の中と二ヵ所の天王社を廻り、
村人たちは悪疫やけがれを一枚の紙に託して、
その笹に結び付けて村境へ二人のお供の人形とともに送り出していた。
子供の数が減り昭和の時代にこの行事は途絶え、
現在は津島神社のお札を祀って区民の無病息災を願っている。
と書かれていました。
宗教や信仰には詳しくありませんが、
先祖にあたる村人たちが、
疫やけがれを追い払い平安な暮らしを求めて、
この信仰に託していた様子がうかがえます。
科学が進歩した現代では無くていい分野かもしれませんが、
人間が歩んできた生活と暮らしの文化に違いありません。
過度な負担でない限り後世へ継承していきたいものです。
< 祠一つ古の暮らししのぶる >

















