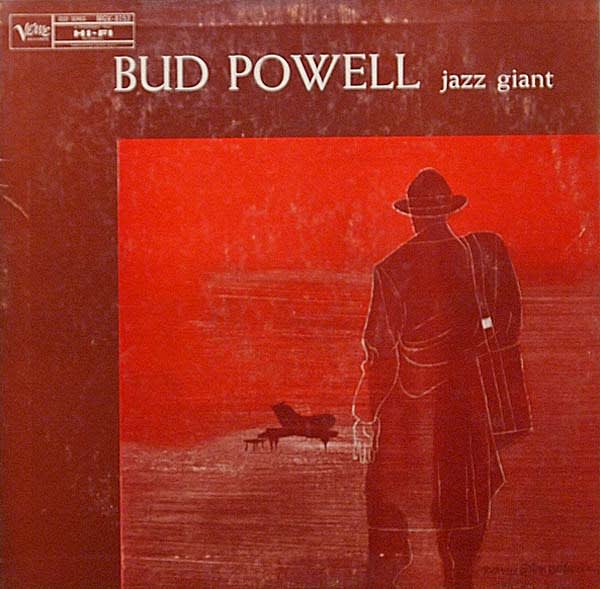Oscar Peterson & Dizzy Gillespie (Pablo MW2165, jp. reissue)
2014年もあと12時間あまりです。いろいろありましたが、自分自身に関してはは健康にも仕事にもめぐまれた一年だったと思います。周りでは、義父が入院したり母親が骨折したりで大変でしたが、がんばれる奴が支えるしかないのです。まだ、大晦日になっても家の掃除はオンゴーイングの状態、にもかかわらずこんな時間にPCに向かってブログを書いている自分を見つけられると大ひんしゅくなのかも知れません。
さて、今年最後のアルバムは以外にも?パブロです。パブロと言えば、モノクロ、年老いたジャズメンの大写しのジャケ写が有名ですが、考えてみると天然色(カラーとも言いますね)では見るに耐えない老いぼれを何とか商業ベースに載せるための苦肉の作だったのかもしれません。でも、こんだけ何枚も出せばレーベルイメージとしてのジャケ写としてある意味完成しているのかもしれません。勿論、若かりし時代にジャズの屋台骨を支えた名手ばかりですから、演奏は力強さ云々ではなく、枯れた味や円熟味をふんだんにいかしたプレイであり、寛いでジャズを聴くには却ってもってこいと言ったところです。パブロジャズメンの中心的存在、レーベルピアニストと言っても良いオスカー・ピーターソンはこのレーベルに5人のトランぺッターとそれぞれデュオアルバムを録音しています。Clark Terry, John Fadis, Harry Edison, Roy Eldridgeそして本日アップのDizzy Gillespieの5人です。
録音は74年、ロンドンです。選曲も寛ぎには欠かせないスタンダードばかり(Caravan, Autumn Leaves, Close Your Eyes, Alone Together, Con Alma etc.)で、ディジーの喉も生かせるように長尺のblues, "Blues For Bird"を収録し、バランスがとれた編成です。言うまでもなく、DizzyとOPの2人だけで綴って行きます。OPのスイング感は急速調でもスローでも抜群、からむガレスピーのラッパもミュート、ボーカルを交えて歌心満載です。こんなリラックスした演奏がやっぱり楽で良いですね。

録音が良いのもパブロの特徴ですよね。所有盤はポリドールがリリースした国内盤です。そういえば、年末に久々に針交換しました。少し、雑音が減っていい音になった気もしますが、いかんせんタコ耳ゆえ・・・。新しい針先はなかなかに美しいものですね。最後に、ブログを覗きに来てくれる皆さん、今年もお世話になりました。ジャズ、ワーゲン、自転車、キャンプ、ファッションなど、どれをとってもネタ切れは否めませんが思いついたら少しづつアップして行こうと思います。来年も宜しくお願いいたします。