◎松本市の将棋月報社と雑誌『将棋月報』
今月21日に、将棋研究家の越智信義(のぶよし)さんのことに触れた。私は一度、越智信義さんに、原稿の執筆をお願いしたことがある。そのころ、批評社から、歴史民俗学研究会が編集する『歴史民俗学』という雑誌が刊行されていた。同誌の編集に加わっていた礫川が、越智さんにエッセイの原稿をお願いしたのである。
いただいたのは、「銀座・夜店の古本屋」と題された味わい深いエッセイで、『歴史民俗学』第6号(1997年2月)の巻頭に置かれた。本日は、このエッセイを紹介させていただく。ただし、紹介は、前半のみ。
銀座・夜店の古本屋 越智信義
「信〈ノブ〉ちゃん、遠くからのお客さまを二時間もお待たせしていますよ」母の声に部屋へはいると、「松本から上京したので立ち寄った」と挨拶ずる、縞〈シマ〉の着物姿で坊主刈りの色黒い老人が、夕暮がただよう部屋のなかに、ポツネンとしてすわっていた。
北京郊外の蘆溝橋で、日中戦争が始まったこの年〔1937〕は、私にとっては、大阪行きの就職がきまった中学五年生の年であった。戦後、埋立られてしまったが、その頃の銀座は、北は京橋川・桜川、南は汐留川、東は三十間堀から西は外濠〈ソトボリ〉と堀川に囲こまれ、貸舟屋などもあって、夏にはボートも浮ぶ詩情あふれる街であった。
銀座の裏通りには、出世地蔵といわれた御地蔵尊(昭和四十三年に三越銀座店屋上に移転)の縁日が、三十間堀川〈サンジッケンホリカワ〉に沿って月三日あり、常店〈ジョウミセ〉の植木、金魚屋、虫屋など、多くの夜店が出てにぎわった。気合術の本を売るヒゲの先生とバナナの叩き売りは、いつも大爆笑の人垣きをあつめていた。店々のアセチレン瓦斯のにほひが、昨日のことのようになつかしい。
地べたにゴザを敷いて、平積みに並べている古本屋がいつも出ていた。古本というより、返本された娯楽雑誌の「講談倶楽部」や「少年俱楽部」などをバラに解体して、中身をいろいろとり混ぜて製本し、別の表紙絵をつけた「安づくりの雑誌」と、ゴムバンドで束ねた子供雑誌の附録だけを、雑然と置いている古雑誌屋である。
そのなかに、どうしたことか。B6版の薄い雑誌が一冊入りこんでいた。普通では書店に出廻ることのない、長野県の松本で出版されている同人雑誌「将棋月報」である。この日めぐりあわなかったら、一生この地方の同人雑誌を手にすることはなかったであろう。
黄色い無地で、薄いペラペラな安手の表紙。なかみはザラ紙で、天地を切りそろえていない。編輯はすべてベタに組んで、割付けは全く不揃いのお粗末なもの。それがかえって、珍しくて、十銭で買ったような記憶がある。「少年倶楽部」の定価五十銭とくらべて、「半年分送料とも壱円五拾銭」という安さと、書店には置かれることのない地方の同人雑誌社から、直接郵送されるという好奇心とで、気まぐれに購読の申込みをした。
長時間待たされた新規申込みの読者がまさか中学生とは、老人も拍子抜けしたことであろう。子供の私には、初めて「名刺」というものを手渡されて、並より大きかったこと、「松本市将棋月報社長阿部吉蔵」の太い活字のいかめしさが、今でも目に浮んでくる。将棋好きの初対面同士が、早速一局指さぬはずはないのだが、どうもその憶えはない。また、なにを話し合ったかも、夢のように消え去って、ただなつかしいのみである。
あとで、「月報」を読んで知ったことだが、「うちの印刷所は、田舎雑誌といわれる将棋月報を休んだ月の方が黒字なんですよ」と言いながらも、老人は折りがあれば、気軽に遠い各地の読者を訪ねて、将棋話に花を咲かせることが楽しみであったらしい。
この日の思い出とともに、戦後北支から復員した日に、三年余の出征中にも送られていた「月報」のなかから、「廃刊記念号」を見出したときの感慨は、忘れられない。【以下、略】
ウィキペディア「越智信義」の項によれば、越智さんが収集された文献は、生前、大阪商業大学・アミューズメント産業研究所に寄贈されたという。『将棋月報』のバックナンバーも、同研究所に収蔵されているはずである。
なお、今日、国立国会図書館サーチで、「図書」「雑誌」「雑誌記事等」の欄にチェックを入れ、「著者・編者」の欄に「越智信義」と記して検索すると、13件がヒットする。ただし、その13件には、『歴史民俗学』掲載の「銀座・夜店の古本屋」は含まれていない。

















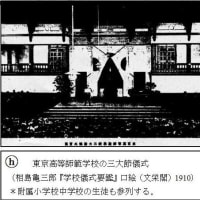
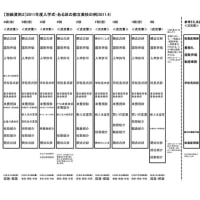
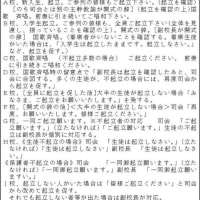








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます