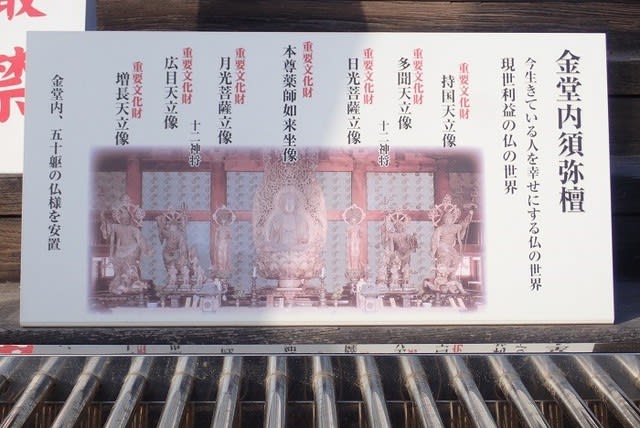ネリネ(ダイヤモンドリリー)は 2017/11/08 と翌年の2018/12/01 (失敗談を書いています。) に投稿しています。
今でも、覚えていますが、ネリネは良く調べて長い記事を書きました。昨年は、それに、失敗談を載せているだけでした。
今回も1回目の長い記事を読みやすく校正して、書かせていただきます。
学名:Nerine 科名:ヒガンバナ科 属名:ネリネ属 英名Nerine Diamond lily 原産地:南アフリカ
開花期:10~12月 分類:半耐寒性球根 花の色:白、赤、ピンク、紫、オレンジ、複色など
別名:ダイヤモンドリリー・姫彼岸花(ヒメヒガンバナ)
ネリネの学名は、Nerine(ギリシャ神話の水の精の名前に由来します)ダイヤモンドリリーは球根植物の多年草です。
キラキラと輝く花弁は、本当にすばらしいものです。また、花の咲いている期間が長く、秋に咲く球根植物としては
最高のものと言えます。
流通する園芸種の多くは、ネリネ・サルニエンシスをもとに改良されたもので、耐寒性がないので、冬は凍らないように
管理する必要があります。またリコリスは半日陰でも育ちますが、ネリネは日当たりを好むという点で栽培環境が異なります。
開花期間は長く、1か月間くらい花を楽しむことができますし、切り花やアレンジメントとしても花もちがよく
重宝します。地植えにしても良く増えました。夏(秋)植えのネリネは、鉢栽培になりますが、栽培は難しいことはなく
むしろ、とても簡単です。3~4年は植えっぱなしにしていますが、毎年、よく咲いてくれます。
40㎝ほどの花茎の先に10~12輪ほど咲かせます。花径は5~6㎝ほどで、花色は赤、赤紫、ピンク、白などです。
栽培方法 植え付けの深さ:球根の肩が見えるくらいの浅植えにします。
鉢植えの用土:過湿を嫌いますので水はけのよい用土に植えつけます。赤玉土などを使い、腐葉土や堆肥類は混ぜない方が
無難です。
置き場所:植えつけ後は涼しい半日陰に置き、葉が伸びてきたら日当たりのよいところに置きます。
株間:鉢の場合は6号鉢に3球が目安です。
植え替え:毎年植え替える必要はありません。3~4年たつと球根が混みあってきますので分球を兼ねて
9月頃に掘り上げすぐに植えつけます。
日常の管理休眠期の管理:5月頃葉が黄色くなってきますので灌水を減らし、鉢のまま雨のかからないところで休眠させます。
ただし、完全に乾燥させてしまうと球根がやせてしまいますので、たまに軽く水を与えます。鉢の表面が乾いたら水をやる様にし、
過湿にならないように注意します。花が終わって葉が伸びてきたら、勿論過湿は避けますが、かと言って、あまり乾燥
させすぎないように注意します。
休眠期の管理:5月頃葉が黄色くなってきますので灌水を減らし、鉢のまま雨のかからないところで休眠させます。
ただし、完全に乾燥させてしまうと球根がやせてしまいますのでたまに軽く水を与えます。今年は
一鉢それで失敗しています。場所が、目立たないところに置いていたため水を切らせすぎました。
周りが柔らかくなっていました。花は無理かもしれません。今、水を与えています。
冬の管理:耐寒性はそれほどありませんが、私は、軒下の霜の当たらないところに鉢を置いていますが、
それで冬を越しています。ですので、関東以西の暖地の場合、霜の当たらない軒下であれば、冬を越せるではないかと
思われます。その他の地域であれば室内に入れるようにします。
いずれの場合も、冬場は鉢土がなかなか乾かないので水やりは控えめにします。かなり乾いてから水やりをします。
肥料:ネリネはやせ地に強い植物ですので、肥料はほとんど必要ありません。むしろ、与えすぎるとよい結果は得られません。
ときどき、薄めの液肥を与えていますが、それで問題なく美しい花が楽しめます。
病気・害虫 : 特にありません。10年以上育てているネリネですが、この度、検索しましたら参考になるものばかりで
総まとめとして利用させて頂きました。手間いらずで簡単に花が咲くお花ですがポイントはしっかり把握しておかないと
いけませんね。
2人の友人は毎年、10輪以上の花を咲かし毎年、玄関に飾ってくれます。
(一人はこの春亡くなりました。沢山、咲かせて喜んでいたのを思い出します。今年も、この時期咲いていることでしょう。)

2019/11/02 に、初めて、咲いているのに気が付き撮影しました 他の画像はすべて本日(2019/11/09)の撮影です








玄関入口に 持ってきました