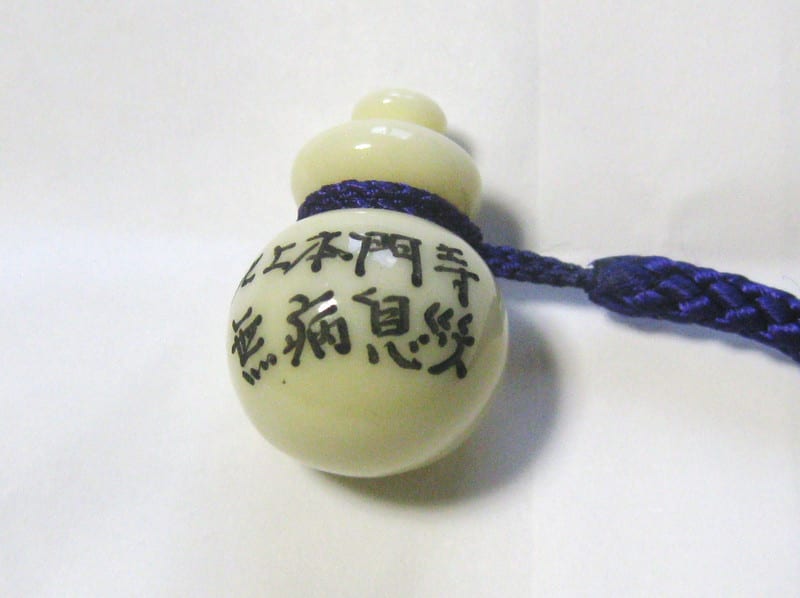ちよ 散歩、今回は旧東海道最初の宿場である品川宿を歩きます。
散歩、今回は旧東海道最初の宿場である品川宿を歩きます。
JR・京浜急行の品川駅から、スタートです。
 線路沿いを、南に下ります。
線路沿いを、南に下ります。
下には新幹線などの線路が通る、この八ツ山橋を渡ります。
八ツ山橋を渡った所が、旧東海道品川宿の入口です。
品川宿は、北から「歩行新宿(かちしんしゅく)」「北品川宿」「南品川宿」の3宿から成り立っていました。
京浜急行の踏切を渡って、いよいよ旧東海道へ入って行きます。


まずあるのが、土蔵相模跡です。
建物は残ってなく、石の道しるべ(左上)と土蔵相模跡の看板(右上)があるだけです。
旅籠相模屋は外壁がなまこ壁でしたので、土蔵相模と呼ばれていました。
幕末の1862(文久2年)攘夷派高杉晋作らが、イギリス公使館の焼き打ち事件を起こしました。
その際、密議をこらしたのがこの土蔵相模でした。
その中には、明治維新をになった若い時の伊藤博文や井上馨もいました。
旧道を左に曲がり八ツ山通りを渡って、江戸時代には海が広がっていた品川浦を見に行きます。



北品川橋から見た、品川浦船だまりです。(左上)
釣り舟や屋形船が繋がれていますが、周りの風景は高層ビルやマンションが立ち並び昔とは大きく変わってしまったのでしょう。
八ツ山通りを進んだ品川浦公園の一角にある、鯨塚です。(中上)
江戸時代、品川沖に迷い込み捕らえられた鯨の供養碑です。
江戸中の評判となり、ついには当時の将軍徳川家斉も上覧したそうです。
さらに奥へ行くと、台場小学校の所に御殿山下台場跡があります。(右上)
幕末に江戸防衛のため築かれた品川台場(砲台)の跡地で、発見された石垣を使って記念碑が建てられました。
上に建つ灯台は、明治になって第2台場に造られた品川灯台を模したものです。
現存する台場は第3と第6のふたつで、くわしくは「ちよ散歩⑭お台場」を見てください。
 ここで旧道にもどり、善福寺に向かいます。
ここで旧道にもどり、善福寺に向かいます。
この寺の本堂壁面には、漆喰鏝絵(しっくいこてえ)の龍が残されていると聞きます。
左官の名工・伊豆の長八作だそうですが・・・。
残念ながら、本堂改装中で見られませんでした。
気を取り直して、旧道を進みます。


品川宿の寺の中で、唯一旧道より海側に建つ一心寺があります。(左上)
さらに歩いて行くと、本陣跡の広い公園があります。
明治天皇が休息したため、聖蹟公園と名がつきました。
画像は、公園内にある御聖蹟の碑です。(右上)
ここで、右に曲がり北馬場通りから第1京浜を渡ります。



第1京浜に面した急な石段を上がった所にあるのが、品川神社です。(左上)
階段の途中、左手に富士講の人々が築いた富士塚があります。(中上)
その品川富士、山頂からの絶景です。(右上)
昔は、間近に海が広がっていたのでしょう。
富士信仰は根深く、これまでの街道散歩で至る所に富士塚を見つけました。


北品川宿の鎮守でもある、品川神社の本殿です。(左上)
裏には板垣退助の墓とともに、「板垣死すとも自由は死せず」という言葉の石碑があります。(右上)
これは自由民権運動をしていた板垣が、刺客に襲われた時に叫んだ有名な言葉です。
山手通りを渡り、目黒川沿いの小道を旧道にもどります。


途中、左手に南品川宿の鎮守である荏原神社があります。(左上)
品川宿は、目黒川を境に北・南品川宿に分けられますが。
ではなぜ、南品川宿鎮守の荏原神社が北品川宿側にあるのでしょうか。
素朴な疑問ですが、1928(昭和3年)まで目黒川はこの神社の北を流れていたそうです。
昔は、南品川宿側にちゃんと建っていたのです。
神社前の目黒川に架かる鎮守橋と、鎮守の森です。(右上)
 旧道にもどり、北・南品川宿に分ける品川橋を渡ります。
旧道にもどり、北・南品川宿に分ける品川橋を渡ります。
ちなみに、京浜急行も以前は北馬場・南馬場ふたつの駅に分かれていました。
高架工事の際統一されて、現在は新馬場駅ひとつとなっています。
これより、南品川宿に入って行きます。


目黒川 沿いを、第1京浜方向へ歩いて海徳寺に寄ります。
ここには、珍しいバットを持ったホームラン地蔵がいます。(左上)
旧道にもどると、街道松の広場があります。
この松は、東海道29番目の宿場浜松より寄贈されたものです。(右上)
品川宿には、このほか各地の宿場から贈られた松が植えられています。



しばらく旧道を歩いて行くと、品川寺(ほんせんじ)があります。(左上)
その門前にあるのが、江戸六地蔵第1番目の銅造地蔵菩薩坐像です。(中上)
江戸時代街道の安全を願い、各街道の入口に造立されたのが江戸六地蔵です。
旧中山道は、とげぬき地蔵そばの巣鴨真性寺にあり第3番目です。
品川寺には、洋行帰りの鐘と呼ばれる梵鐘があります。(右上)
この鐘は幕末のパリ万博に出品後行方不明となっていましたが、ジュネーヴ市で保管されているのがわかり無事に帰って来ました。
この事が縁で、品川宿とジュネーヴ市は友好関係に発展しました。
さて、この辺りで南品川宿は終わりとなります。
旧道を離れ、青物横丁駅前のジュネーヴ平和通りと命名された道を上がって行きます。



この坂は、上に江戸時代仙台藩伊達家の下屋敷があったことから仙台坂と呼ばれています。(左上)
伊達家下屋敷跡には、元祖仙臺味噌醸造所が建っています。(中上)
仙臺味噌はここで買えるのですが、残念ながら休みでした。
さらにこのタブの木はかつて下屋敷内にあったもので、山本周五郎「樅の木は残った」のモデルとされています。(右上)
この伊達下屋敷の南側には、土佐藩も下屋敷を構えていました。
現在は大井公園となっていて、その一角に第15代土佐藩主山内容堂の墓があるのですが・・・。
残念ながら、震災以来立入禁止となっていました。
大井公園から第1京浜に架かる歩道橋を渡ると、ゴールの京急鮫洲駅です。

今日のおみやげは、旧東海道南品川宿にある和菓子鷲子(とりのこ)の串だんごです。(上)
-ちよ散歩39旧東海道品川宿・おわり-
 旅です。
旅です。






 旅をよろしくお願いします。
旅をよろしくお願いします。










 旅、今回は初詣がてら今戸神社に参拝に行きます。
旅、今回は初詣がてら今戸神社に参拝に行きます。 散歩でちょうど4年前に一度行っています。
散歩でちょうど4年前に一度行っています。