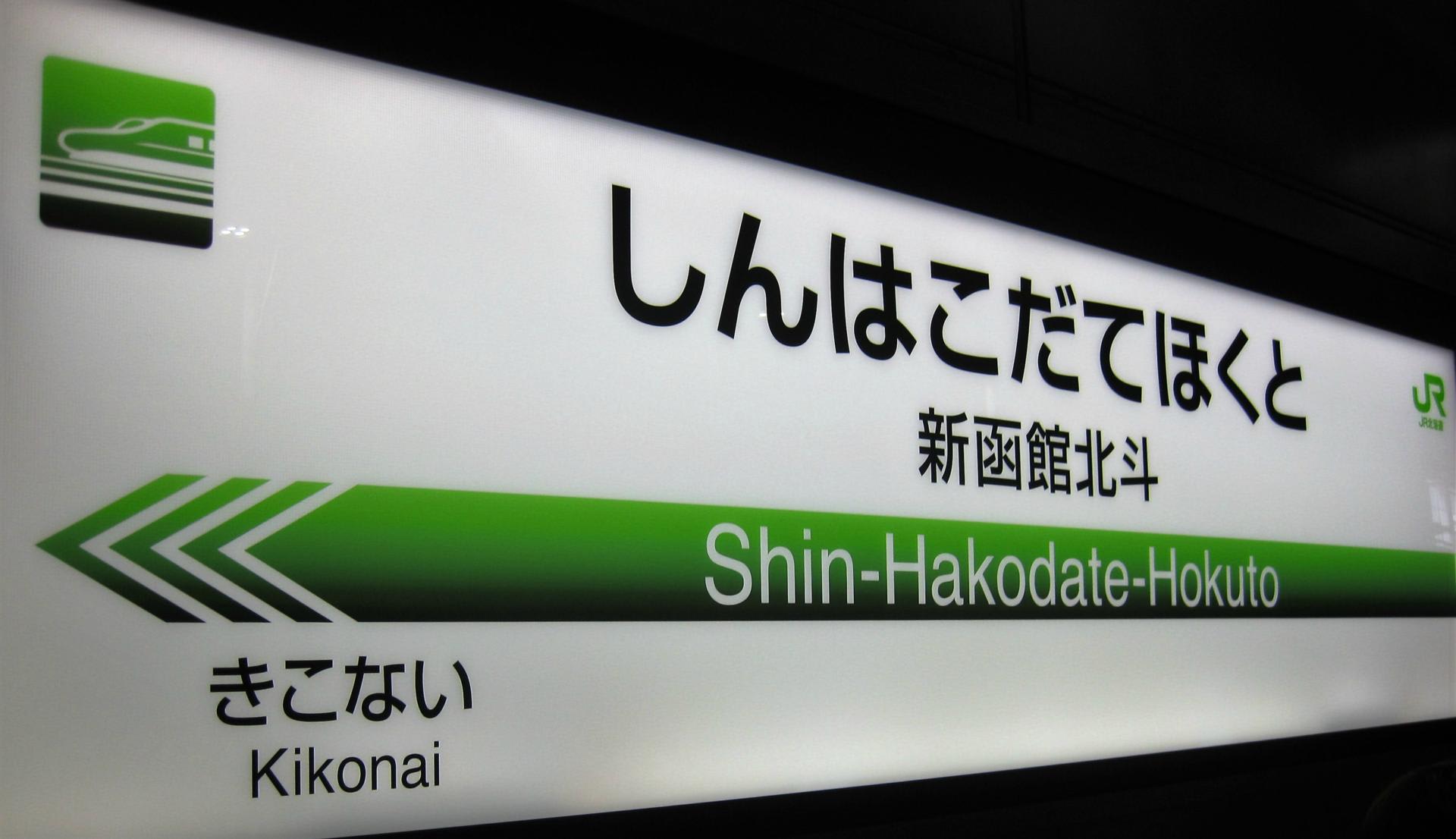ちよ 旅、今回は隅田川と荒川を繋ぐ岩淵水門を見に行きます。
旅、今回は隅田川と荒川を繋ぐ岩淵水門を見に行きます。
岩淵水門のある岩淵は、岩槻街道の江戸から来るとひとつめの宿場になります。
将軍が日光参詣の際使用されたことから、岩槻街道は日光御成道(にっこうおなりどう)とも呼ばれました。

その岩槻の宿場にあるのが、大観音様がいる正光寺です。(上)
8年前に来た時は、周りには何もなく空き地の中に観音様だけが立っていました。
現在では、本堂その他が再建されています。

荒川の土手を行くと、岩淵水門が見えてきます。(上)
左の赤い水門が旧岩淵水門(通称赤水門)で、右の青い水門が現在の岩淵水門(青水門)です。
さて水門に行く前に、土手の麓にある荒川知水資料館で知識を仕入れます。


資料館の前に展示してあるものは、船堀閘門(ふなぼりこうもん)頭頂部です。(左上)
閘門とは、水位に高低差がある河川などの間に船の行き来を行うため設置された施設です。
船堀閘門は荒川放水路と新中川の間に造られましたが、1979(昭和54)に撤去されました。
もうひとつ展示されているのは、京成押上線旧荒川橋梁基礎杭です。(右上)
この松杭は、新橋梁に切り替わるまで約75年間橋を支える基礎として地中に埋まっていました。

荒川放水路と旧岩淵水門の完成を記念して、工事関係者が建てた記念碑です。(上)
度重なる洪水被害を受けてきた隅田川・荒川沿いでは、抜本的な治水対策として人工河川の開削が急がれました。
1911(明治44)に着手され、想像を絶する苦難のうえに1930(昭和5)に完成したのが荒川放水路です。
名称は1965(昭和40)荒川放水路は荒川に、荒川本流の通称隅田川は正式に隅田川となりました。



荒川放水路事業の一環として、荒川と隅田川の分かれる地点に造られたのが旧岩淵水門(赤水門)です。(上)
1916(大正5)に工事は始まり、1924(大正13)に竣工しました。
この時、荒川放水路と岩淵水門の工事責任者に任命されたのが青山 士(あおやま あきら)です。
彼は自費でパナマ運河工事に唯一の日本人技師として参加し、世界最先端の土木技術を学んできました。
赤水門は、すでに役目を終えています。


赤水門を抜けた小島にあるのが、鉄のオブジェ「月を射る」です。(左上)
河川敷に設置することを条件に公募した、荒川リバーアートコンテスト特賞作品です。
この作品は無垢の鉄棒を溶断し、一本づつ積み上げて制作しています。(右上)



旧岩淵水門(赤水門)の老朽化ゃ地盤沈下のため、1982(昭和57)約300m下流に造られたのが現在の岩淵水門(青水門)です。(上)
平常時では、全面開放して船の通行確保と隅田川の水質浄化に役立っています。
また増水時には、水門を閉めて荒川の水が隅田川に流入するのを防いでいます。
こうして荒川放水路と岩淵水門の完成により、隅田川・荒川沿いの人たちは洪水から解放され一気に都市化が進みます。

岩淵水門から隅田川下流を見渡せば、高層ビル群の向こうにしっかりと東京スカイツリーが見ることができます。(上)
今日のおみやげは、なしです。
―ちよ旅15岩淵水門・おわり―