
六本木一丁目の泉屋(せんおく)博古館分館という美術館を初めて訪ねた。分館というから、本館があるはずで、調べたら、それは京都市左京区の鹿ヶ谷というところにあるそうだ。東京の分館は平成14年に設立されたそうだから、知らない人も多いと思う。住友コレクションは、一に中国の古代青銅器、二に中国絵画、そして、その他に日本画、陶磁器、工芸品など、となるそうだ。だから、今回の展示は、住友コレクションの中では、マイナーな分野の展覧会となる。
”近代日本画にみる東西画壇”というテーマで、東京、京都、大阪の画家たちの作品が、ふたつの展示室に並べられている。はじめ、ざっとみて、また、ゆっくりとみた。江戸は粋、京は雅、大阪は婀娜(あだ)だという、この微妙な違いを感じとって下さい、という案内があったから、そうゆう観点でみてみたのだ。まず、大阪の”婀娜”ってなんだ、と頭をくるくる回してみて、歌謡曲の、♪婀娜な年増を誰が知ろ♪(東京行進曲)を思いついた。すると色っぽいということだ(汗)。これが正しいのかどうか、分からないが、そう思って、大阪画壇の絵をみると、そういう面もたしかにある。上島鳳山の十二月美人(前期、後期半分ずつ展示してある)は、たしかに、婀娜な娘さん達だった。ちらし絵も飾っている。ぼくは、今回、これが一番気に入った作品だ。小冊子”近代日本画(泉屋博古館)”も買ったので、その中からの写真を載せる。

でも、その他の作品は、七賢人だとか、春秋花鳥とか、柘榴白鸚鵡図とか色気を感じるものはなかった。でも、花鳥風月にも”婀娜な”と感じる感性をもつ人もいるのかもしれない。ただ。ぼくは、少なくとも七賢人には色気を感じなかった(笑)。大阪画壇コーナーでは、ぼくのような素人には、知らない画家さんばかりだったけれど、有名画家とどこが違うのだ、というくらいの技量の優れた作品が多かった。有名になるかどうかは、きっと、どの分野でも紙一重で、ほとんど運とコネ(爆)で決まるないかと改めて感じた。
柘榴白鸚鵡図(山田秋坪)

京都画壇には有名画家の竹内栖鳳の”禁城松翠”や富岡鉄斎の”掃蕩俗塵図”も良かったが、木島桜谷の華やかな菊花図の屏風(赤い菊花と少し混じる白菊、深緑の葉と少し混じる淡い緑の葉が金色の地に映えていた)や、先日、出光美術館”日本美術のヴィーナス”展でみた小杉放菴の”天のうづめの命”と同じ場面を描いた、原田西湖の”乾坤再明”も良かった。こちらの天のうづめの命はおっぱいは隠していた。これが京の”雅”のだろうか(爆)。
禁城松翠(竹内栖鳳)

乾坤再明(原田西湖)

東京画壇には、ぼくの好きな、東山魁夷の、北欧風景を描いた”スオミ”と、夕暮れの雪景色を描いた”雪暮”が展示されていた。どちらも初見だったが、暗い感じがして、それほどいいとは思わなった(期待値が高いので;笑)。狩野芳崖は恐い顔をした”寿老人”を描いていた。あの優しい”悲母観音”とは対極のものだ。人も、恐い時もあれば、優しいときもある、天だって、晴れるときもあれば、嵐のときもある、それでいいのだ、酒さえ飲めれば

菊地容斎の絵巻物も楽しかった。狐の嫁入りは聞いたことはあるが、鼠の嫁入りは聞いたことがない。ここでは、狐と鼠の両方が嫁入りする行列を、鳥獣戯画みたいな感じで描いている。軽快な筆使いが快い。


結局、三都市間の微妙な雰囲気の差は、ぼくの能力では判別できなかったけれど、十分、楽しむことができた。近くに、前日、記事にした大倉集古館やこんな美術館もあるので、今度は三点セットで出掛けてみよう。




















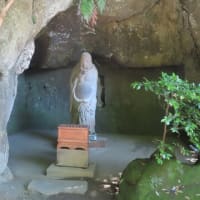




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます