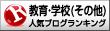「格差是正」4月2日
『仏 義務教育3歳から 移民層念頭に「格差是正」』という見出しの記事が掲載されました。記事によると『フランスで義務教育の開始年齢が現在の6歳から3歳に引き下げられる見通しとなった。移民層などを念頭に幼児期の「教育格差」の是正を目的』だそうです。一度に3歳も、とその大胆な取り組みには驚きを禁じ得ませんが、『教職員組合からは義務教育の開始年齢を2歳とするよう求める声もある』そうで、そもそも我が国とは状況も発想も異なるようです。
実は我が国でも、義務教育の開始年齢を早めるという施策が話題になったことがあります。長期政権を敷いた小泉純一郎氏の後継総裁を決める自民党の総裁選に、谷垣貞一、麻生太郎、安倍晋三の3氏が争ったときのことです。この総裁選では、教育政策も注目を集め、麻生氏が、義務教育の1年前倒しを提起したのです。
私はそのとき、麻生氏の主張には反対の立場を表明しました。教員の育成配置、学校施設の増設・改築、学習指導要領の作成、幼稚園教育要領の改訂などの実務的な課題が山積していることはもちろんですが、より根元的な理由で疑念を表したのです。
当時とは状況が変わっている面もありますが、家庭の経済状況によって、子供が受けることが出来る「教育格差」の問題は、より深刻になっており、今後我が国でも、義務教育の開始年齢を早めることが主要な教育課題として再浮上する可能性があります。そこで、十数年が経ち、少し時代状況と合わない面もありますが、参考までに当時のブログ内容を再掲したいと思います。長文ですが悪しからず。
「学校は何をするところか」と問い直してみる必要がある
家庭の教育力が低下しているために、本来家庭で行うべき躾を学校で行おうというのが、麻生太郎氏の主張です。家庭の教育力の低下は事実だと思います。家庭の教育力の低下を考えるために、某全国紙のコラムを引用してみます。
「先日、公園にいた家族連れに唖然とした。赤ん坊の母親である若い女が泣き止まぬ子に『うるせえ、殺すぞ』と言い放つのだ。赤ん坊の祖母は、連れの年配女性に『乱暴なのは言葉だけよ』と言い訳する。女性が『殺すという言葉はひどいわ』と言っても『最近の子はしょうがないのよ』で終わり。そりゃアナタすり替えってもんでしょ。その若い女の親に『最近』か?と突っ込みたくなる。祖母は私と同年代。彼女が最も罪深い存在だ。
後日、仕事先の女性が『私も大泣きする子どもに殺すぞって言う母親見た!』と言うのでまた驚く。『殺すぞ』なんて絶対に親の発する言葉ではない。殺伐とした言葉は、急速に心の温度を下げる。意味が分からぬと思って侮るなかれ。響きは心に深く刻まれ、意味が分かればより傷つく。
子を産んだから親なのではなく、善悪をわきまえ、優しさをもつ人間に育んでこそ、親と名乗れるのだ。少子化が話題だが、数より質の少子化が心配!」。
私自身は、幼い我が子に「殺すぞ」という言葉を投げつけ、平然としている親を見たことはありませんが、そうした親がいることについては驚きません。多くの保護者と接してきた中で、この人だったら我が子に「殺すぞ」と言いかねないな、と感じさせる保護者に会うことはよくあることだったからです。
保護者が、こうした言動をとる理由は様々です。この子がいるから自分の時間がもてない。この子に私の生活を侵害する権利はないはずだ。というような被害者意識が「殺すぞ」という言葉になって表れることもあるでしょう。
また、「子どもとはいえ他人(母親である自分も他人の一人)を不快にさせたら罰を受けるべきだ」「泣いたり騒いだりしないと約束してあったのに約束を破ったから、躾のためにも厳しく対応すべきだ」「周囲の人に迷惑をかけてはいけないということを教えるチャンスだから強く叱る」など、教育上の配慮だと主張する人もいるかもしれません。さらには、「普段は温かく接しているから、子どもとの信頼関係はこんなことぐらいでは傷付かない」と言う人もいるかもしれません。
子どもを育てるということは、食事を与え、寝る場所を用意し、寒暑を防ぐ衣類を提供するといった物理的なことだけを意味するのではありません。子どもに心の居場所を与え、精神的に安定させることが重要なのです。心の居場所がある状態とは、何があっても、自分がどんなことをしても、この人だけは自分を見捨てないし、自分の味方だと思える人が存在するということです。そしてほとんどの場合、この「絶対的な味方」とは「親」なのです。
なお、ここで言う「絶対的な味方」というのは、我が子を盲信し、どんなときでも我が子が正しいとするような態度を指すのではありません。我が子の悪い点はきちんと認め、その上で、それでも「我が子は、我が子であるがゆえに自分にとってはかけがえのない存在である」という保護者の姿勢を意味します。
殺人事件の犯人である我が子に対して「罪を認め、被害者の遺族が許してくれるまで、二十年でも三十年でも刑務所に入って罪を償ってほしい。私はお前が許されて出てくるのを待ち続ける。世間のすべての人にとってお前は冷酷な殺人鬼かもしれないが、私にとってはかけがえのない我が子だ」と言えるような心の在り方を指しているのです。繰り返しになりますが、本当の家庭教育とは、保護者が子どもにとっての「絶対的な味方」であることなのです。
それに対して学校を含む社会は、敵もいれば味方もいるし、味方といってもその場の状況で敵に変わるかもしれないという、子どもにとって息の抜けない緊張を強いられる場所なのです。この「緊張の場」で生き抜いていくためには、あるときは思いっきり甘え、無条件で自分という存在が認められる家庭での安息の時間が必要なのです。伸びすぎたゴムがやがて切れてしまうことのないように、緊張を緩める場が不可欠なのです。
しかし、「殺すぞ」と言う親の元では、子どもは緊張を解き、心の傷を癒すことができません。そうして心の中に少しずつストレスを溜めていき、臨界点に達したとき、爆発するのです。
「授業中、教室内を歩き回ったり、奇声を発したりする小一の女児がいます。彼女は注意されただけで怒りが沸点に達し『うるせえ、ババア』などという言葉を吐きます」。これは、教育ボランティアとして問題行動のある児童のサポートをしている人からの投稿の一部です。
この女児のような子どもの特徴は、「沸点」がだんだんと低くなっていくことです。初めは、きつく叱ったときにだけ「キレ」ていたものが、穏やかに諭しても「キレ」るようになり、やがて教員や大人が視線を向けただけで「キレ」るようになっていくのです。あたかも、伸びたままのゴムの弾性が低下しもろくなっていくように。
現在では、こうした行動を見せる子どもがいない学校を探す方が難しいくらいです。そして、こうした行動をとる子どもへの対応に学校や教員は大きな労力を費やすとともに、自らの子育ての責任を認めようとしない保護者との対応に徒労感を募らせているのです。教員も人間です。無限のエネルギーや情熱をもっているわけではありません。こうした子どもと保護者への対応に疲れ果てたしわ寄せは、授業の準備不足、子どもと接するときの余裕のなさという形で他の子どもに及んでいくのです。
「教員は一人一人の子どもを大切に」と言われます。しかし、これは理想を述べたに過ぎません。集団教育を基本とした我が国の学校では、ある一定水準の家庭教育を前提にシステムがつくられています。つまり、学校でのストレスを癒す場として家庭が機能しており、教員との行き違いや友達とのトラブルなどで痛めた心を家庭で癒して、翌朝には元気で登校するという形を暗黙の了解事項として成り立ったシステムなのです。この前提が崩壊している中で、学校や教員にのみ努力を強いるような考え方は現実的ではありませんし、何の解決にもつながりません。
さて、義務教育の前倒しについてです。このことは、小学校の教育機能を麻痺させてしまいます。まず、保護者の心理の問題があります。今までは、実質的には学校に子育てを委ねながらも、心の中では「私は、親の務めを果たしてはいないのでは」という引け目を感じていた保護者が、「四歳からの躾は学校の責任」→「勉強だけでなく躾も学校の責任」という考え方になり、今まで以上に子育ての手を抜き、自分の責任を棚に上げて、権利として堂々と学校に注文をつけるということになるからです。学校は、今まで以上に自己中心的な保護者との対応に多くの労力を費やすことになるでしょう。そして、家庭はますます教育力を低下させ、本来の姿である「外で受けたストレスを癒す場」としての機能を失い、「キレ」る子どもが激増するのです。
また、「躾も学校で」という流れの行き着く先は、「子育てはすべて学校で」です。私がこんなことを言うと、「考えすぎ」「親はそこまで無責任ではない」「親には子どもに対する愛情がある」などと反論する人がいることでしょう。私は、そんな楽観的にはなれません。また、あるコラムを抜粋してみましょう。
「前略~『私の朝食はコーヒーだけ。娘(七歳)は食べたり食べなかったりするので用意しない。食べたいとお父さんのを摘んでいる』『長男(九歳)と次男(七歳)は小学生になって朝食を食べたがらなくなったので用意しない。喉が渇いていると自分で麦茶や牛乳を出して飲んでいく』『休日は私も寝坊したいので、長男(十三歳)は食べずに野球に行った。下の子どもたち(六歳・四歳)は大好きなハンバーガーを食べに行ったみたい』などと主婦が言う。家族から要望がなければ、時間がきても食事は用意されなくなってきているようだ。
『私は夫が帰ってきて『食べる』と言わなければ、夕食の準備を始めない』と言い、子どもたちが騒ぐと好きなラーメンや肉まんを与えて終わりにする主婦もいる。『いつも子どもたちにお腹が空いたと煩く言われてから、仕方なく夕食の準備に立ち上がる』と言う主婦もいる。お菓子でお腹をいっぱいにした子どもには夕食が用意されないケースも珍しくない。~中略~
『私は嫌がるものを無理に食べさせないし、子どもが食べたがるように料理したりもしないので、あるモノから食べたいものだけを摘んでいる』と言う主婦の子どもたち(八歳・四歳)は、偏食が多いため好きなカップ麺ばかり食べている。
『ウチは食べたい人の自己申告制』と言い、味噌汁も要望した人にしか出さない家庭や、『子どもは牛乳を飲まないときがあるから、私から飲まないかと聞いたり出してやったりはしない』と、甘い菓子パンだけで子どもたち(二歳・五歳・七歳)の昼食にしている家庭もある。『いちいち言って食べさせるのは私が疲れるから』『子どもに食べなさいと言うのは、私にパワーがいるから』言わないのだそうだ。無理させられないのは『子ども』よりも『私』らしい」
今回取り上げたのは、現代家庭問題研究者岩村暢子氏の「食卓から見る家族の変容」という寄稿です。ここに描かれている食卓の光景は、私にとっては、寒々しく、家族という言葉を使うことさえも躊躇われるものです。しかも、岩村氏は、「このような食傾向を示す家族が、(平成十七年の)調査ではついに三十代主婦家庭の半数を超えた」と書いています。
この章の初めに、私は、「子どもを育てるということは、食事を与え、寝る場所を用意し、寒暑を防ぐ衣類を提供するといった物理的なことだけを意味するのではありません」と書きました。実際には、最も基本的な「食」についてさえ、こうしたお寒い現状なのです。既に、朝食を食べてこない子どものために、学校で朝食を提供する試みが一部で始まっています。そして、保護者には好評だということです。東京都の多くの自治体では、放課後も学校の施設で子どもを預かるシステムが取り入れられています。そのうち、学校で入浴したり宿泊したりできるようにと求める声が上がることでしょう。そうなってから、「学校とは何をするところなのか」「教員は何をする人なのか」と問い直しても手遅れなのです。「義務教育の前倒し」は、我が国の小学校制度を根本から変えてしまう「危険性」のある施策なのです。もちろん、麻生太郎氏が、こうした事態を見越した上で、そのきっかけとして「義務教育の前倒し」を主張しているのなら話は別ですが。
義務教育の前倒しは、学校教育と家庭教育との望ましい共存の在り方以外にも、学校施設の問題、現在の小学校とは全く異なる教育内容を指導する教員の育成の問題、既存の幼稚園・保育園との整合性の問題、教員増による給与負担増という財政問題、与野党で意見の対立している教育基本法改正の問題など、実施に当たって解決しなければならない問題があり、どれ一つをとってみても大きな課題ですが、総理大臣がその気になれば、五~六年で解決できないわけではありません。そうした意味では、学校というところの存在意義、原点を揺さぶる「危険性」こそ最大の問題点だと思います。
個々の家庭は私的な領域であり、公権力が関与することはできないし、するべきではないというのが我が国の行政の考え方です。それは正しいと思います。しかし、家庭の問題を放置して、国民の目に見える形での対策が打ち出しやすい学校に対してだけ、表面的な改革を進めるのはもう止めにしてほしいものです。
たとえ時間がかかろうとも、我が国の地域社会の在り方、子育て世代の就業の在り方など家庭を取り巻く環境の整備に力を注いでほしいと思います。
goo blog お知らせ
カテゴリー
- 我が国の教育行政と学校の抱える問題(3496)
- Weblog(2147)
最新コメント
- badmintonmusume/強制せずに成り立つか
- badmintonmusume/経験とノウハウ再評価を
- aki/末端では…
- badmintonmusume/きっとわざとやっている
- 香菜子先生@上から目線の無責任発言かもしれないけれど・・・/メリットではなくデメリット
- ivie_left/便利になってもそれだけでは
- ヨシ/一人はみんなのために
- ブログ主/「当たり前」が難しい
- 菊池 浄/「当たり前」が難しい
- コトタマ/受け継ぐものは
カレンダー
バックナンバー
ブックマーク
- goo
- 最初はgoo