内田樹「反知性主義者たちの肖像」(2016年東大国語第一問)
一段落(1・2・3)
1 ホーフスタッターはこう書いている。
反知性主義は、思想に対して無条件の敵意をいだく人びとによって創作されたものではない。まったく逆である。教育ある者にとって、もっとも有効な敵は中途半端な教育を受けた者であるのと同様に、指折りの反知性主義者は通常、思想に深くかかわっている人びとであり、それもしばしば、aチンプな思想や認知されない思想にとり憑(つ)かれている。反知性主義に陥る危険のない知識人はほとんどいない。一方、ひたむきな知的情熱に欠ける反知識人もほとんどいない。
(リチャード・ホーフスタッター『アメリカの反知性主義』田村哲夫訳、強調は引用者)
2 この指摘は私たちが日本における反知性主義について考察する場合でも、つねに念頭に置いておかなければならないものである。反知性主義を駆動しているのは、単なるbタイダや無知ではなく、ほとんどの場合「ひたむきな知的情熱」だからである。
3 この言葉はロラン・バルトが「無知」について述べた卓見を思い出させる。バルトによれば、無知とは知識の欠如ではなく、知識に飽和されているせいで未知のものを受け容れることができなくなった状態を言う。実感として、よくわかる。「自分はそれについてはよく知らない」と涼しく認める人は「自説に固執する」ということがない。他人の言うことをとりあえず黙って聴く。聴いて「得心がいったか」「腑に落ちたか」「気持ちが片づいたか」どうかを自分の内側をみつめて判断する。ア〈 そのような身体反応を以てさしあたり理非の判断に代えることができる人 〉を私は「知性的な人」だとみなすことにしている。その人においては知性が活発に機能しているように私には思われる。そのような人たちは単に新たな知識や情報を加算しているのではなく、自分の知的な枠組みそのものをそのつど作り替えているからである。知性とはそういう知の自己刷新のことを言うのだろうと私は思っている。個人的な定義だが、しばらくこの仮説に基づいて話を進めたい。
1 反知性主義とは
思想に敵対する人の創作
↑ ではなく
↓
思想にとり憑かれている人
↓
知識人(思想を持つ) … 誰もが反知性主義に陥る危険性
ホーフスタッター『アメリカの反知性主義』より引用
2 ホーフスタッター → 日本にもあてはまる
反知性主義を駆動するものは
怠惰・無知
↑ ではなく
↓
「ひたむきな知的情熱」 ※「 」がついていることに注意
3 無知とは
知識の欠如
↑ ではなく
↓
知識の飽和 → 未知を受け容れられない状態(byロラン・バルト)
「自分はそれについてはよく知らない」と涼しく認める人
↓
他人の言うことをとりあえず黙って聴く
↓
《 「得心がいったか」「腑に落ちたか」「気持ちが片づいたか」どうかを自分の内側をみつめて 》《 判断する 》。
∥
ア《 そのような身体反応を以て 》さしあたり《 理非の判断に代える 》ことができる人
∥
「知性的な人」
∥
知性が活発に機能している
∥
(新たな知識や情報を加算しているのではなく)
自分の知的な枠組みそのものをそのつど作り替えている
∥
知の自己刷新
∥
知性
(一)「そのような身体反応を以てさしあたり理非の判断に代えることができる人」(傍線部ア)とはどういう人のことか、説明せよ。
どのような人を「知性的な人」と筆者は考えているのかをまとめる問題。
いろんなことを知っている人、その豊かな見識ゆえに頭がよさそうに見える人を、私達は知性的と見なしがちだ。
しかし、筆者はちがった見方を提示する。すでにたくさん「持っている」人手はなく、いくらでも「受け入れられる」人が知性ある人だと述べる。
一般的な知識人は、自分がすでに持っているたくさんの知識情報にもとづいて、理非の判断を行う。
筆者の言う「知性的な人」は、未知のことがらを虚心坦懐に受け入れて、身体がどう反応するかを大切にするという。
結果として、自分の知の枠組みをそのつど作り替えることになる。
「知」とは、たんに多くの知識。情報を頭に詰め込むことではないよ、という大学の先生のメッセージがまっすぐに伝わっている文章である。
同時に、内田樹先生が主張する「身体知」の有効性も感じられる。
「近代的知」に対するアンチテーゼとしてのそれだ。
そういう意味で、「近代的価値観の見直し」という、現代評論の王道としてのテーマもふまえられている。
(一)解答例
未知の知識や情報を虚心に受け入れ、身体的に納得するかどうかでその理非を判断し、絶えず自分の知の枠組みを作り替えることができる人。










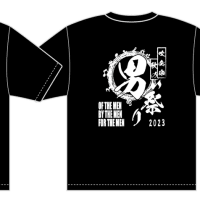




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます