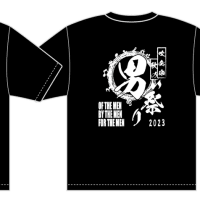「べし」の意味の覚え方は「すいかとめて」で教えている。
す(推量)・い(意志)・か(可能)・と(当然)・め(命令)・て(適当)の6種をおぼえなさいと。
この覚え方は全国的にオーソドックスで他にはないのかなと思っていたが、最近になって他のパターンを知った。
娘の学校では「べしっとかいすぎとめてんか」とおぼえるという。
さらに昨日聞いたのは「てめいすぎとかよ」というものだ。
これだと「ぎ(義務)」とか「よ(予定)」も入り、なかなかすぐれものだ。
ただし埼玉県は杉戸町(市?)を知らないと、何それ?ということになる。
ためしにネットで検索してみたら、やはりベースは「すいかとめて」だけど、他にもいろいろあることを知った。
みんないろいろ工夫しているのだ。
ただし、「べし」の意味の骨格は「当然」である。
「む」のちょっと強いものみたく理解されがちだけど、「とにかく未確定だ、先の話だ」という「む」と、「もうそのことがおこるのは当然だ、今にもおきる」というニュアンスの「べし」とは異なる。
なので、接続の仕方も異なる。
「む」は「ず」や「まし」の仲間で、「まだ」おこってないグループで未然形接続。
「べし」は「らむ」「なり(推定)」の仲間で「今」を表すグループ。なので、終止形接続をする。
「すでに」を表す「き」「けり」「けむ」は連用形接続。
接続の仕方も、意味との関連を意識すると多少はおぼえやすいかもしれない。
まあ、接続はおぼえなくてもいいけどね。
いつも声に出して読んでさえいれば、何形接続なんてのは自然に覚える。
「り」は「さみしいり」とか言い、さ(サ変)み(未然形)し(四段)い(已然形)に接続する「り」とかいちおうは教える。
でも本来は、たとえば「咲きあり」を短く「咲けり」と言った結果、「り」が助動詞に見えるようになったものだ。
だから「咲けり」の「咲け」は已然形でも命令形でもない。
「り」が何形接続なんですか、なんて言うこと自体がナンセンスだ。
なんかよくわかんないけど「り」の上には「e音」があると感じられればいい。
す(推量)・い(意志)・か(可能)・と(当然)・め(命令)・て(適当)の6種をおぼえなさいと。
この覚え方は全国的にオーソドックスで他にはないのかなと思っていたが、最近になって他のパターンを知った。
娘の学校では「べしっとかいすぎとめてんか」とおぼえるという。
さらに昨日聞いたのは「てめいすぎとかよ」というものだ。
これだと「ぎ(義務)」とか「よ(予定)」も入り、なかなかすぐれものだ。
ただし埼玉県は杉戸町(市?)を知らないと、何それ?ということになる。
ためしにネットで検索してみたら、やはりベースは「すいかとめて」だけど、他にもいろいろあることを知った。
みんないろいろ工夫しているのだ。
ただし、「べし」の意味の骨格は「当然」である。
「む」のちょっと強いものみたく理解されがちだけど、「とにかく未確定だ、先の話だ」という「む」と、「もうそのことがおこるのは当然だ、今にもおきる」というニュアンスの「べし」とは異なる。
なので、接続の仕方も異なる。
「む」は「ず」や「まし」の仲間で、「まだ」おこってないグループで未然形接続。
「べし」は「らむ」「なり(推定)」の仲間で「今」を表すグループ。なので、終止形接続をする。
「すでに」を表す「き」「けり」「けむ」は連用形接続。
接続の仕方も、意味との関連を意識すると多少はおぼえやすいかもしれない。
まあ、接続はおぼえなくてもいいけどね。
いつも声に出して読んでさえいれば、何形接続なんてのは自然に覚える。
「り」は「さみしいり」とか言い、さ(サ変)み(未然形)し(四段)い(已然形)に接続する「り」とかいちおうは教える。
でも本来は、たとえば「咲きあり」を短く「咲けり」と言った結果、「り」が助動詞に見えるようになったものだ。
だから「咲けり」の「咲け」は已然形でも命令形でもない。
「り」が何形接続なんですか、なんて言うこと自体がナンセンスだ。
なんかよくわかんないけど「り」の上には「e音」があると感じられればいい。