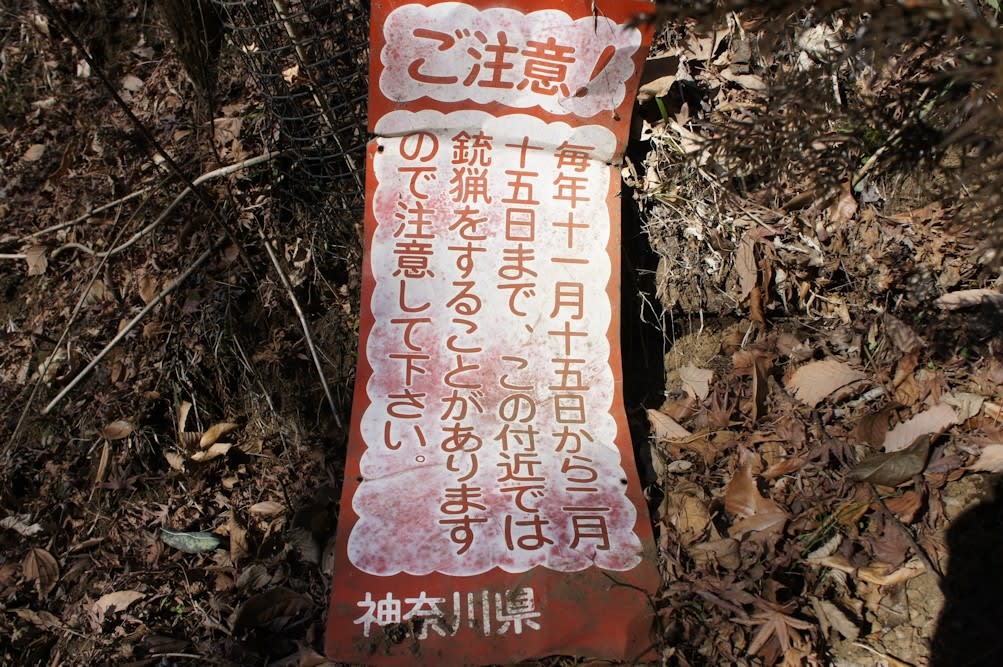三浦半島の走水海岸でトビに襲われたというレポートです(2024年2月23日)。
横須賀美術館に行こうと思って、京急馬堀海岸駅で下車、バスの時間を見たらだいぶ待ちそうだったので、美術館まで約4kmの道を歩くことにしました。

京急馬堀海岸駅から海辺に出ると、「うみかぜの路」馬堀海岸遊歩道が海沿いを通っていて、観音崎まで続いています。遊歩道はこの護岸の海側を通っています。

天気がいい日です。向うには横須賀の町や猿島が見えます。

このあたりは海水の透明度が高くて、海底がきれいに見えています。

海岸にはなぜか、オオバンやカモ類がいました。ふだんは淡水域に住んでいる鳥たちですが、ここで何をしているのでしょうか。

走水海岸にある走水水源地公園に入ります。右側に並んでいるのは桜の木です。
ここでベンチに座って海を見ながら、スパムおにぎりを食べ始めました。2、3分たった頃でしょうか、突然後ろから来た何者かにおにぎりを投げ飛ばされました。一瞬、間をおいて、私は「ヤラレタ」と声を出していました。目にも止まらないスピードでトビが飛んできて、おにぎりを地面に落として、飛び去ったのです。私の体にはまったく触れずに、傷つけずに、スマートな早業でした。そして私は心のなかで「おみごと」と叫んでいました。

地面に落としたおにぎりを宙に投げてやって、トビが取りに来たところを撮影しました。トビは一発でおにぎりを奪って逃げることはできなかったので、①食べ物を突き飛ばす、②地面に落ちたのを採って逃げる、という2段階作戦に切り替えたはずです。


さっきまでトビなんて1羽もいなかったのに、今や私の真上を多くのトビたちが飛び回っています。トビの視力は8~10といわれていますし、非常に正確かつ敏捷な飛行能力を持っています。見えてる世界・生きてる世界が、ヒトとは全く違うんだなと思わされます。

さて、歩を進めます。波崎緑地展望デッキの近くからは、さっきの走水水源地公園や遠く横須賀の町などが望めます。

横須賀美術館に着きました。目的は、「生誕120周年 サルバドール・ダリ -天才の秘密-(2025.2.8~4.6)」を見ることでした。わたしよりちょうど60年上の人だから、おじいちゃんくらいのかんじ。

この美術館は、2024年度プリツカー賞受賞者の山本理顕さんが設計しました。ミュージアムショップには、理顕さんグッズのコーナーも作られていました。

とってもカッコいいおじいちゃん、ダリは私が昔から好きな画家です。見かけによらず、極めて繊細な心の持ち主だけれど、大胆に生きました。今回の展示は、諸橋近代美術館所蔵品を中心とした作品だったそうです。福島県の諸橋近代美術館にはなかなか行けなかったので、手軽に見れるよい機会でした。ただ、大型で濃密な作品はそんなに多くはなかった印象です。