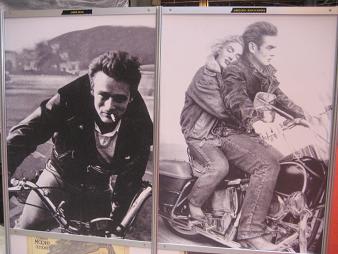もう少しプロフィールや実像を公開したほうが、親しみが持てていい・・・そういうアドバイスを頂いたこともあるのですが、ブログには匿名性があっていいのではという勝手な思い込みと、照れ屋なものですから、あまり公表していませんでした。
でも、もう少しだけご紹介することにしました。
このブログへ訪問していただいている方の中に、フリーのライターがいらっしゃるのですが、その方の企画記事の一環として私の早期退職を取り上げていただく事になりました。その記事が6日発売の『読売ウィークリー』に掲載されたそうです。自ら早期退職を選び、第二の人生を楽しんでいる人たちといったテーマで、その中にいく人かのケースが紹介されるそうですが、その一人に取り上げていただいています。まだ掲載誌は見ていないのですが、きっと実物以上に素敵にまとめていただいているのではと、恥ずかしいような、嬉しいような・・・もしよろしかったら、お読みいただければと思います。
時々、仕事を辞めてパリに住むにはどうすればいいのか、という問い合わせも頂くのですが、そうしたご質問にも、私以外の他のお二人のケースも含め、「40代からできる『アーリーリタイアメント』という選択」という記事全体が参考になるのではないかと思います。
書店ではもちろん、ネットからの購入申し込みも可能なようです。
http://info.yomiuri.co.jp/mag/yw/
と、これで終えてしまうと、写真なしになってしまいます。今まで写真なしは、1年半近く前、カメラを盗まれたときだけ。何か写真を、と思うのですが、『読売ウィークリー』はまだですし、困った・・・

この写真にしましょう。卒業した大学が今年、創立百周年なんだそうです。仙台出身でパリに住んでいる方から頂いたものですが、こうした記念の羊羹があるんだそうです。「漱石文庫」というのは、私が学生の頃からあったと思います。漱石の蔵書、日記などを弟子の小宮豊隆が自ら勤めていた大学に寄贈したものだとか。
仙台には大学の4年間住んでいました。小池真理子氏の作品に『無伴奏』という小説がありますが、その舞台になった喫茶店・無伴奏にはよく通っていました。どんなに詰めても20人入らないんじゃないかというくらいの、小さな喫茶店。古いビルの地下で、バロックやルネッサンス音楽がいつも流れていました。音楽といえば、3年か4年の頃、さとう宗幸の『青葉城恋唄』が大ヒット。青葉通りや定禅寺通りの欅並木が本当にきれいでした。
・・・個人的思い出にふけってしまいそうですので、このへんで。
↓「励みの一票」をお願いします!
すぐ下の文字をクリックすると、ランキングにアクセスし、投票になります。
人気blogランキングへ
でも、もう少しだけご紹介することにしました。
このブログへ訪問していただいている方の中に、フリーのライターがいらっしゃるのですが、その方の企画記事の一環として私の早期退職を取り上げていただく事になりました。その記事が6日発売の『読売ウィークリー』に掲載されたそうです。自ら早期退職を選び、第二の人生を楽しんでいる人たちといったテーマで、その中にいく人かのケースが紹介されるそうですが、その一人に取り上げていただいています。まだ掲載誌は見ていないのですが、きっと実物以上に素敵にまとめていただいているのではと、恥ずかしいような、嬉しいような・・・もしよろしかったら、お読みいただければと思います。
時々、仕事を辞めてパリに住むにはどうすればいいのか、という問い合わせも頂くのですが、そうしたご質問にも、私以外の他のお二人のケースも含め、「40代からできる『アーリーリタイアメント』という選択」という記事全体が参考になるのではないかと思います。
書店ではもちろん、ネットからの購入申し込みも可能なようです。
http://info.yomiuri.co.jp/mag/yw/
と、これで終えてしまうと、写真なしになってしまいます。今まで写真なしは、1年半近く前、カメラを盗まれたときだけ。何か写真を、と思うのですが、『読売ウィークリー』はまだですし、困った・・・

この写真にしましょう。卒業した大学が今年、創立百周年なんだそうです。仙台出身でパリに住んでいる方から頂いたものですが、こうした記念の羊羹があるんだそうです。「漱石文庫」というのは、私が学生の頃からあったと思います。漱石の蔵書、日記などを弟子の小宮豊隆が自ら勤めていた大学に寄贈したものだとか。
仙台には大学の4年間住んでいました。小池真理子氏の作品に『無伴奏』という小説がありますが、その舞台になった喫茶店・無伴奏にはよく通っていました。どんなに詰めても20人入らないんじゃないかというくらいの、小さな喫茶店。古いビルの地下で、バロックやルネッサンス音楽がいつも流れていました。音楽といえば、3年か4年の頃、さとう宗幸の『青葉城恋唄』が大ヒット。青葉通りや定禅寺通りの欅並木が本当にきれいでした。
・・・個人的思い出にふけってしまいそうですので、このへんで。
↓「励みの一票」をお願いします!
すぐ下の文字をクリックすると、ランキングにアクセスし、投票になります。
人気blogランキングへ