一昨年の夏に遠くへ行ってしまった友だちが、「これ、なんか良いよ」というメッセージとともに、Twitterの「中澤系bot」のリンクを僕に送って来た。それが、中澤系の短歌との出会いだった。副腎白質ジストロフィーという難病に侵され、二〇〇九年にこの世を去ったという彼の遺した短歌は、システムに支配された社会で孤立する個々人の諦観やかなしみを、平坦で変化のない日常生活の風景を、独特の語彙で切り取って見せる。
3番線快速電車が通過します理解できない人は下がって
とるべきだ ミルクの瓶のふた常にはがし損ねた日々をもろとも
裏側を向いたまんまのコインでもコインはコイン十分なほど
生きるなら生きよ個別に閉じかけのドア一人だけ抜け出せる幅
中澤系の短歌には、作者の感情や表情というものがはっきりと見えてこない。残酷なまでにニュートラルで、匿名的だ。もちろん、匿名的であると言っても、それは作品が凡庸で没個性的であると言う意味では全くない。彼の作品は三十一音の世界において、複雑化されたシステムの中で極端に均質化され、代替可能な部品として際限なく摩耗していく我々――「匿名的な存在」にならざるを得ない人間の姿を、表象することに成功しているのだ。中澤系の短歌は、現代の日本で生活する者なら誰しもが触れる機会があるような一場面を、繊細かつ奥行きのある言葉を用いて鮮やかに置換していく。だが、歌を重ねていった先で彼が目にした地平は、加速していくシステムから逃れることが不可能な「終わらない」現実だった。中澤系は無限に続いていく世界を前にしても臆することなく、その「終わらなさ」を表現していった。
正統な手続きを経たのちにさえ衰弱死という結末がある
述べられていないものには意味がない沈黙の向こうにはなにもない
サンプルのない永遠に永遠に続く模倣のあとにあるもの
ぼくたちはこわれてしまったぼくたちはこわれてしまったぼくたちはこわ
「資本主義の終わりより、世界の終わりを想像するほうがたやすい」とジジェクは言った(らしい)。あらゆる「終わり」は既に語られ尽くした。我々は甘美な感傷に浸りながら「終わり」を語るのではなく、この現実を覆う閉塞感の本質である、「終わらなさ」と対峙しなければならない。「最後の日」を夢想する終末論者たちのささやかな期待など意に介すこともなく世界は延命し、そうして今日と同じような明日がやってくる。かつて、中森明夫は80年代末期に「すべては終わった/もう新しいものなどない」と書いた。90年代には阪神淡路大震災と地下鉄サリン事件が起こり、中澤系にも強い影響を与えた社会学者の宮台真司は「終わりなき日常」を提唱した。中澤系はそうした時代の空疎で不透明な空気を、明晰な理性と敏感過ぎるほどの詩的感覚を通して汲み取り、そしてたったひとりで「なにもない」「永遠に続く」世界と向き合った歌人だった。中澤系の見たもの、見ようとしたもの、見ることができなかったもの。彼の短歌は、ひとつの大きな課題として後世の読者に読み継がれていく。










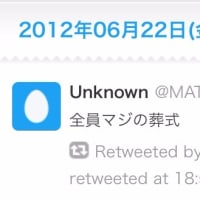
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます