年齢とともに、好きな詩人が変わってゆくことがある。また、年齢に関係なく、好きであることが、いつまでも変わらない 詩人もいる。好きであることの中身(意味)には、多義的な要因があるだろう。例えば、最近の私は三好達治の詩に親近感を持っている。三好の詩が内包する言葉の韻律が心地よく、とても好ましいのだ。もちろん、それだけではない。自然や日常を素材とした抒情的な世界にこころを動かされ、惹きつけられるのである。特に『測量船』の、「春の岬」、「乳母車」、「雪」、「甃のうへ」、「少年」とつづく詩篇は、完璧な詩句の構成のもと、韻律と言葉の美しさが内包されている。これらの詩篇を誰かが口ずさむと、それに唱和して、思わず口ずさみたくなる雰囲気が、詩自身に備わっている。
短歌を創作し始めてしばらくした頃だろうか。吉本隆明の初期評論「「四季」派の本質――三好達治を中心に――」を読んで、「四季」派について考えさせられた。吉本はこの評論で、「「四季」派の抒情詩の本質が、社会の支配体制と、どんな対応関係にあったのか」、「「四季」派の戦争詩は、かれらのどんな現実認識から生みだされたのか」を分析している。なぜなら、「こういう問題が解けないかぎり、詩は恒久的に、その時々の社会秩序の動向を、無条件に承認したうえで成立する感性的な自慰にしかすぎないからである」というのが吉本の主張である。
吉本の「「四季」派の本質」は、以下の言葉によって結論づけられる。「「四季」派の詩人たちが、太平洋戦争の実体を、日常生活感性の範囲でしかとらえられなかったのは、詩の方法において、かれらが社会に対する認識と、自然に対する認識とを区別できなかったこととふかくつながっている。権力社会もかれらの自然観のカテゴリーにくりこまれてくる対象であり、権力社会と権力社会との国際的な抗争も、伝統感性を揺り動かす何かにすぎない」。「日本の恒常民の感性的秩序・自然観・現実観を、批判的にえぐり出すことを怠って習得されたいかなる西欧的認識も、西欧的文学方法も、ついにはあぶくにすぎないこと――これが「四季」派の抒情詩が与える最大の教訓の一つであることをわたしたちは承認しなければならない」と。
本稿は、「私の好きな詩人」について書くエッセイなので、吉本の論にはこれ以上触れないが、当時、四季派の詩を愛読していた私には、かなりショックな論考であった。その後、長く、三好達治の詩を読むことからは遠ざかっていた。三好の詩をあらためて頻繁に繙くようになったのは、二〇一七年の約一年間、八木重吉へのオマージュを捧げた詩歌作品を創作したことが切っ掛けである。重吉の詩集を繙きながら、ときどき三好の詩にも手を伸ばすことがあった。歌集『重吉』(現代短歌社 二〇一九年)を上梓した以後の私の短歌には、三好の詩の影響を受けた作品が何首かある。その中には、私の気がついていないところで、影響を受けている歌もあるだろう。多くが三好の四行詩からの影響である。
馬
茶の丘や
桔皐
馬
梅の花
第二詩集『南窻集』
この詩には、蕪村の俳画や俳句の影響が見られる。余分なものがそぎ落とされ、四行詩が成立するぎりぎりのところで作られている。格助詞の「の」、と間投助詞の「や」以外、すべて名詞で構成された詩である。
また、短歌を四行詩に構成した作品もある。
路傍
路にそへる
小窓の中の かはたれに
けふも動ける
馬の臀見ゆ
同
いつも、散歩で見ていた情景ではないか。それが、ある日、即興的に短歌(四行詩)になったのだろう。
『南窻集』には、友人の梶井基次郎を哀悼した「友を喪ふ」四篇が収録されている。その中の一篇には、俳句が挿入された詩がある。
路上
巻いた楽譜を手にもつて 君は丘から降りてきた 歌ひながら
村から僕は帰つてきた 洋杖を振りながら
……ある雲は夕焼のして春の畠
それはそのまま 思ひ出のやうなひと時を 遠くに富士が見えて ゐた
「巻いた楽譜」は、梶井が高校時代から親しんでいたムソルグスキーではないかという。「ある雲は夕焼のして春の畠」、回想の中に、哀感の滲む俳句が自然に挿入されている。
三好の第三詩集『閒花集』、第四詩集『山果集』も四行詩集である。これらの詩集には、フランシス・ジャムの影響があるといわれている。が、その韻律は、和歌や俳句のしらべによるものが大きいだろう。『南窻集』には、心に残るしらべの詩が多い。それらの詩は、知識で作ったものではなく、天性の資質によるものである。詩(うた)を読む人の心の中で、脈々と伝えられてきたものが、鮮やかな耀きを放っている。詩の韻律の中からは、そのような囁きが聞こえてくる。
土
蟻が
蝶の羽をひいて行く
ああ
ヨットのやうだ
*
本
蝶よ 白い本
蝶よ 軽い本
水平線を縫ひながら
砂丘の上を舞ひのぼる
第五詩集『霾』収録の「大阿蘇」も懐かしい。私立学校で教鞭を執っていた頃、教科書に載っており、年毎に生徒と読んだ一篇である。
大阿蘇
雨の中に馬がたつてゐる
一頭二頭仔馬をまじへた馬の群れが 雨の中にたつてゐる
雨は蕭々と降つてゐる
馬は草をたべてゐる
尻尾も背中も鬣も ぐつしよりと濡れそぼつて
彼らは草をたべてゐる
草をたべてゐる
(以下略)
雨に濡れる一群の馬を、じっと見つめている、雨の中の三好の眼差しに惹きつけられる。繰り返される「ゐる」の韻律が、言葉そのものの美しさを引き出してゆく。口語自由詩に独特のリズム感を内在させたすぐれた一篇である。
三好の詩は、どの時代も好きだが、最近好んで読んでいる詩集は、第十二詩集『花筐』である。福井県三国時代の書き下ろし詩集で、萩原朔太郎の妹アイに捧げられている。雅文体の四行詩が中心の詩集である。短歌を創作する前に読むと、詩の言葉のリズムが、なぜか短歌の韻律としっくりとしてくる。
遠き山見ゆ
―序にかへて
遠き山見ゆ
遠き山見ゆ
ほのかなる霞のうへに
はるかにねむる遠き山
遠き山々
いま冬の日の
あたたかきわれも山路を
降りつつ見はるかすなり
(中略)
いま冬の日の
あたたかきわれも山路を
降りつつ見はるかすなり
はるかなる霞の奥に
彼方に遠き山は見ゆ
彼方に遠き山は見ゆ
「遠き山見ゆ」と「遠き山は見ゆ」のリフレインが、遙か遠き思い出を呼びよせ、言葉にならない詩性が、波のように遠くから打ちよせてくる。詩のリズムの心地よさに誘われながら、いつの間にか詩の世界へと同化してゆく。
言葉と韻律が創りだす抒情世界にこころを遊ばせ、漢字とひらがなのバランスが秘める文字のリズムに感嘆させられる。
かへる日もなき
かへる日もなきいにしへを
こはつゆ艸の花のいろ
はるかなるものみな青し
海の青はた空の青
*
桃の花さく
桃の花さく裏庭に
あはれもふかく雪はふる
明日をなき日と思はせて
くらき空より雪はふる
*
山なみとほに
山なみ遠に春はきて
こぶしの花は天上に
雲はかなたにかへれども
かへるべしらに越ゆる路
私は三好の四行詩を読みながら、短歌を作る心もちを整える。三好の詩を読んでいる内に、短歌の韻律が呼び覚まされ、言葉を求めて外の世界へと誘われてゆく。四行詩の魔術師に、いつの間にか魔術をかけられているのである。
最近発表した自作の中から、三首を引用したい。三好の詩集を読んだことが反映している。
すみゆける思惟のあをさをふくみもちいしぶみにちるふゆの薔薇なり
ひさかたの日をくぐりゆくことの葉にみず影うつるかたぶく壁に
ふゆぞらのこゑにであひてうつそみの夢より歌をとげることの葉
「未来」二〇二〇年二月号「ゆめの戸」より










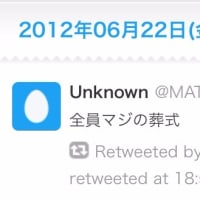
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます