何年か前、古書店で「はあ~」と唸って買った本が『天野忠随筆選』(編集工房ノア)という本でした。どちらかというと心の赴くままも良しとする随筆と言葉を選んで選んで記述する詩という行為は相容れないような気もしますが、とにかく詩人の随筆は頗る面白く心地よかったのです。それから、棚で眠っていた『天野忠詩集』(永井出版企画)を折に触れ手に取るようになったのですが、どういう経緯で購入したのかよく覚えていません。この詩集が発行された当時、私は19歳という若造で天野忠さんの詩を理解して(好んで)いたとは思えず、そこがどうも不思議なんですね。
天野忠さんは1961年に詩集「クラスト氏のいんきな唄」を自費出版され、後に増補し詩集「動物園の珍しい動物」として上梓されています。「架空のイギリスの船乗りでたぶん詩人でもあるクラスト氏の詩を訳す」という体裁をとったことで、天野忠さん独自の年齢観死生観が自在に書けるようになったのではないかと思います。同詩集の末尾の詩を引きます。
あーあ
最後に
あーあというて人は死ぬ
生まれたときも
あーあというた
いろいろなことを覚えて
長いこと人はかけずりまわる
それから死ぬ
わたしも死ぬときは
あーあというであろう
あんまりなんにもしなかったので
はずかしそうに
あーあというであろう。
シニカルともアイロニカルとも呼べる詩ですが、その冷めた視線の先、視野には詩人自身が含まれています。そういう詩がたくさんあります。かといって茨木のり子さんのようにまっとうに宣言するでもなく、長田弘さんのように思慮深く前を向くのでもなく、また抒情的な暗誦性に優れているわけでもありません。「自身」を巡る言葉はどちらかと言えば情けなく、情けない世界に寄り添い、それから俯瞰し、愛おしく批評的に扱っています。こういう言葉、詩を好むようになった理由は、やはり私自身が歳を取ったからですが、だからと言ってこのように表現できるものではありません。とりわけ「情けなさに寄り添う」というのは難しいことです。
この原稿を書くために少し調べていたら詩集名となった詩「動物園の珍しい動物」がニコニコ動画にアップされていました。http://www.nicovideo.jp/watch/sm18132327バックにはいま若い人たちにも人気のあるバンド、クラムボンの鍵盤奏者、原田郁子さんの音楽が用いられています。動画のイラストも詩に合っていて切なく、どうも前述した若造が好んでいたとは思えない云々、というような物言いは甚だ時代からずれているやもしれません。










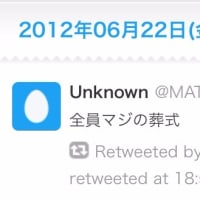
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます