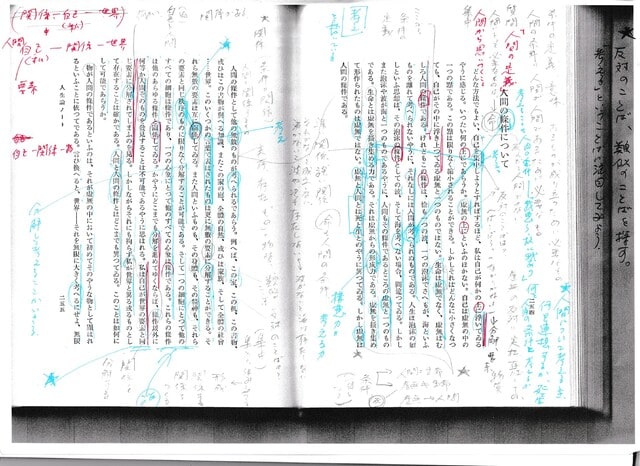渡ひろこ『柔らかい檻』(竹林館、2022年08月15日発行)
詩集を読みながら、この詩の感想を書こうと思い、付箋を挟んでおく。私はたいてい付箋だけではなく、メモを書き残すのだが、渡ひろこ『柔らかい檻』にはメモがない。付箋だけがある。「迎え火」「シンクロニシティ」「忘却」。「迎え火」は56ページ、つまり途中に付箋が挟んである。何を書きたかったのだろうか。思い出せない。
ふとお供えを見やると
ついさっきなみなみと淹れたばかりのお茶が
湯呑み茶碗半分にまで減っている
茶碗のふち一杯だったのに…
「嗚呼、きっと会いに来てくれたんだね」
大好きだった玄米茶
湯気をそっと啜っていったのだろう
知らぬ間に痕跡を残していった母
名残惜しいのか 送り火はなかなか点かなかった
いま思うのは、「名残惜しいのか 送り火はなかなか点かなかった」という行のなかにある、「主語の交錯」である。名残惜しいのは、だれ? 母? それとも作者? 「送り火」をつけるのは作者である。そうであるなら、「名残惜しい」の主語はやはり作者であるのか。まだまだ帰ってほしくない。ここにいてほしい。しかし、ふつうは黄泉の国から帰って来た母が、この世が名残惜しくてなかなか帰れない、のだと思う。その母の気持ちと、作者の気持ちが交錯する。「文体が乱れる」というと言い過ぎなのかもしれないが、このちょっとわからない部分、正確に読もうとすると、何が正確か断定することがむずかしい部分、こういうところが、私は好きだ。
ちょっと、作者になった気持ちになる。
書くというとは、何から何までわかって書くわけではない。書きながら、何かを発見し、あ、これを書きたいと思ったとき、いままで書いていたことをふと忘れ、飛躍するような瞬間がある。それが、読んでいて、あ、ここだな、と感じる。そういうことば。
だから、というと変だけれど。
今年も母を乗せた灯籠が
小名木川をゆっくり流れていく
堪えきれない想いがはらはらと落ちて
水面に小さな波紋を描いては消えていった
堪えきれずに落とした涙が川面に波紋をつくり、消えていく。美しいね。でも、それは美しすぎるというか、美しさがわかりすぎてしまって、何か「ゆらぎ」がないのが、妙に残念な気がするのだ。
「シンクロニシティ」は
私も思わず柩の花を掬ったが、手を差し入れても奥行きが深く底に届かない。
掻き混ぜても花びらが舞い散るだけで、亡骸は何処にもなかった。
夢の描写なのだが、柩の底まで手を入れる。さらに掻き混ぜる。この動作(肉体の動き)が、とても不気味である。夢のなかでしかできないことだろう。少なくとも、私は、現実にはそういうことはしないなあ。だからこそ、この「手を差し入れても奥行きが深く底に届かない。/掻き混ぜて」という手の動きが鮮明に迫ってくる。
夢のつづきで言うなら、私は、そこで目が覚めるだろう。
でも渡は、そこでは目を覚まさない。そのことが、忘れられなくて、たぶん付箋を挟んだのだと思う。
「忘却」は「秘め事」を隠しておく詩である。
いつの日か発掘され
真っ二つに割れたなら
右は曖昧な手のひらに
左は寡黙な唇に
この「手のひら」と「唇」の対比がいいなあ、実際にあったんだろうなあ、と思う。つまり、手のひらが曖昧に動き、そのとき唇は声を出さずに、手のひらの動きのつづきを待っている。それが「秘め事」。そのあとにつづいて起きたことよりも、と私は思う。エロチックな、はじまりの一瞬。それから先は、まあ、たいてい同じだからね。
**********************************************************************
★「詩はどこにあるか」オンライン講座★
メール、skypeを使っての「現代詩オンライン講座」です。
メール(宛て先=yachisyuso@gmail.com)で作品を送ってください。
詩への感想、推敲のヒントをメール、ネット会議でお伝えします。
★メール講座★
随時受け付け。
週1篇、月4篇以内。
料金は1篇(40字×20行以内、1000円)
(20行を超える場合は、40行まで2000円、60行まで3000円、20行ごとに1000円追加)
1週間以内に、講評を返信します。
講評後の、質問などのやりとりは、1回につき500円。
★ネット会議講座(skypeかgooglemeet使用)★
随時受け付け。ただし、予約制。
週1篇40行以内、月4篇以内。
1回30分、1000円。
メール送信の際、対話希望日、希望時間をお書きください。折り返し、対話可能日をお知らせします。
費用は月末に 1か月分を指定口座(返信の際、お知らせします)に振り込んでください。
作品は、A判サイズのワード文書でお送りください。
少なくとも月1篇は送信してください。
お申し込み・問い合わせは、
yachisyuso@gmail.com
また朝日カルチャーセンター福岡でも、講座を開いています。
毎月第1、第3月曜日13時-14時30分。
〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前2-1-1
電話 092-431-7751 / FAX 092-412-8571
*
オンデマンドで以下の本を発売中です。
(1)詩集『誤読』100ページ。1500円(送料別)
嵯峨信之の詩集『時刻表』を批評するという形式で詩を書いています。
https://www.seichoku.com/user_data/booksale.php?id=168072512
(2)評論『中井久夫訳「カヴァフィス全詩集」を読む』396ページ。2500円(送料別)
読売文学賞(翻訳)受賞の中井の訳の魅力を、全編にわたって紹介。
https://www.seichoku.com/user_data/booksale.php?id=168073009
(3)評論『高橋睦郎「つい昨日のこと」を読む』314ページ。2500円(送料別)
2018年の話題の詩集の全編を批評しています。
https://www.seichoku.com/user_data/booksale.php?id=168074804
(4)評論『ことばと沈黙、沈黙と音楽』190ページ。2000円(送料別)
『聴くと聞こえる』についての批評をまとめたものです。
https://www.seichoku.com/user_data/booksale.php?id=168073455
(5)評論『天皇の悲鳴』72ページ。1000円(送料別)
2016年の「象徴としての務め」メッセージにこめられた天皇の真意と、安倍政権の攻防を描く。
https://www.seichoku.com/user_data/booksale.php?id=168072977
問い合わせ先 yachisyuso@gmail.com