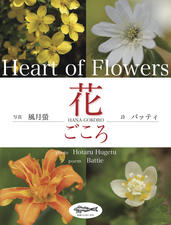LOVEで、ROCKで、SPIRITUALな詩人バッティの、今日の心の現像。
(Twitter→jakoushee)
バッティの☆作業日誌☆in 青森
しまった,せっかくの休日がプロレス動画で(笑。
せっかくの休日だから,
たまっている本を読んでいくかっっっ,のはずが
「そういえば,レインメーカーってデカいのか?」という疑問を
もってしまったばかりに,棚橋vsオカダの試合をみてしまい,
youtubeの右側の欄の秋山による全日三冠流出をみてしまった。
うう,このあと,ケアと大森の試合も見たくなるじゃないか,
そうだ,動画流しながら,読書すればいい(笑。
そこまでして読むなら読まなくてもよさそうなものだが,
とにかく目を通すって,大事だからな。
よーし,秋山,いくぜっっっっっっっっっ。
たまっている本を読んでいくかっっっ,のはずが
「そういえば,レインメーカーってデカいのか?」という疑問を
もってしまったばかりに,棚橋vsオカダの試合をみてしまい,
youtubeの右側の欄の秋山による全日三冠流出をみてしまった。
うう,このあと,ケアと大森の試合も見たくなるじゃないか,
そうだ,動画流しながら,読書すればいい(笑。
そこまでして読むなら読まなくてもよさそうなものだが,
とにかく目を通すって,大事だからな。
よーし,秋山,いくぜっっっっっっっっっ。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
春樹論12(笑。
今日は,池袋に斎藤さっこちゃんのライブみにいく予定なのに,
雨,だよねえ。
春樹論もちょうど雨のところにさしかかってます。
章名も,週刊誌の広告みたいな感じ(笑。
■ 雨と射精、乾燥した性器
『ノルウェイの森』においては、セックスは性愛としてのセックスと思慕としてのセックスとに〈分割〉され、思慕の表現行為としてのセックスは雨抜きでは成就不能なものとして位置づけられている。
二人が散歩デートをするようになって、一年も経たないころ、直子の二十歳の誕生日がやってくる。僕は直子のアパートに誕生日祝いのケーキを持って行く。直子は、ずっと話を止めず、時間が遅くなるというので僕が帰ろうとすると泣き止まず、僕はずっと直子が泣きやむのをまっていたが、彼女は泣き止まなかった。その夜、僕ワタナベは直子と寝る。
直子は僕からの、「君が好きだ」というただ一言を待ちながら話を続けていたのである。もし、その言葉が来るならば、直子は「死んだ友人キヅキの恋人」から「僕の恋人」へと名義変更され、死の世界から生きていく世界への橋を渡る事ができた。しかし、僕はそうしなかった。そうしなかっただけではなく、キヅキとの性的関係も尋ねて橋を焼き払ってしまう。
直子は、自分が生きていく世界として期待したこの街にはいられないことを改めて知らされ、幼馴染キヅキのそばの冥府へと帰省することを決心する。
直子は生きている間、その透明な肉体を僕に預けようとするが、頻繁な性的交渉は可能ではない。それはただ一度、雨に守護されたなかで可能になったものである。
『ノルウェイの森』はたくさんの射精シーンを持っているが、僕と直子との性交は実は一度しかなく、僕と緑との性交にいたっては一度たりとも行われてはいない。それなのに、たくさんの射精が行われるのは、僕が女性たちの指や口や、自分自身の指で何度も射精しているからである。
僕と直子との性交を可能にしたのは、ただ一度だけ直子が濡れたからである。彼女の性器は、常に乾燥している。幼なじみのキズキとの性交の試みのときにも、僕が直子の療養所にいったときにも、彼女の性器は常に乾燥していて、男性性器を受け入れることができなかった。では、直子の性器を濡らしてくれたものは何か、雨である。村上春樹の小説にとって、雨が何であるかは、『1973年のピンボール』に戻れば明らかになる。
■雨の句読点、天空の喪章
水は、この惑星の覆いであるときには海と呼ばれて重宝され、不可視の水蒸気となり可視の雲となったときには不吉な天候として忌まわしく思われ、そして細分化され再び地上に戻ってくるときには、雨と呼び慣わされて、乾いたものであるわれわれを濡らすものとして嫌われている。
『雨はただ大地と大空とを結ぶ連結符だけを形づくっているのではなく』(フランシス・ポンジュ)、確かに、もっと重要な役割を果たしているのだ。特に、村上春樹の小説世界の中では。雨は破線として、死者たちの新世界となってしまった天と、生きているわれわれが快楽と苦悩の狭間を往還する地上とを結んでいる。
『1973年のピンボール』では、配電盤の葬式のために貯水池に行く日曜日、細かい雨が降っている。雨の降る中、僕と双子とが車に乗っている。いつもは饒舌な双子も黙っており、三人の間には静寂が支配している。そしてまるで、葬式への参列者のように犬が歩き回っている中を、クラクションを鳴らしながら僕らは進んでいく。
喪に服す者たちへと降り注ぐ永遠に続くような冷たい雨。雨とは、彼らの周囲に広がっていこうとする感情を、ひとつずつ区切り終わらせて地上へと振り落としていく液体の句読点である。それは墜落する喪章であり、失われた時間への通底符であり、感傷を許す恩赦でもある。であるがゆえに雨は、カップルを抱き寄せて世界から隔離し、遮断された二人分の身体がやっと入るくらいのごく親密な場所を保護することのできる性交の守護神なのだ。
雨,だよねえ。
春樹論もちょうど雨のところにさしかかってます。
章名も,週刊誌の広告みたいな感じ(笑。
■ 雨と射精、乾燥した性器
『ノルウェイの森』においては、セックスは性愛としてのセックスと思慕としてのセックスとに〈分割〉され、思慕の表現行為としてのセックスは雨抜きでは成就不能なものとして位置づけられている。
二人が散歩デートをするようになって、一年も経たないころ、直子の二十歳の誕生日がやってくる。僕は直子のアパートに誕生日祝いのケーキを持って行く。直子は、ずっと話を止めず、時間が遅くなるというので僕が帰ろうとすると泣き止まず、僕はずっと直子が泣きやむのをまっていたが、彼女は泣き止まなかった。その夜、僕ワタナベは直子と寝る。
直子は僕からの、「君が好きだ」というただ一言を待ちながら話を続けていたのである。もし、その言葉が来るならば、直子は「死んだ友人キヅキの恋人」から「僕の恋人」へと名義変更され、死の世界から生きていく世界への橋を渡る事ができた。しかし、僕はそうしなかった。そうしなかっただけではなく、キヅキとの性的関係も尋ねて橋を焼き払ってしまう。
直子は、自分が生きていく世界として期待したこの街にはいられないことを改めて知らされ、幼馴染キヅキのそばの冥府へと帰省することを決心する。
直子は生きている間、その透明な肉体を僕に預けようとするが、頻繁な性的交渉は可能ではない。それはただ一度、雨に守護されたなかで可能になったものである。
『ノルウェイの森』はたくさんの射精シーンを持っているが、僕と直子との性交は実は一度しかなく、僕と緑との性交にいたっては一度たりとも行われてはいない。それなのに、たくさんの射精が行われるのは、僕が女性たちの指や口や、自分自身の指で何度も射精しているからである。
僕と直子との性交を可能にしたのは、ただ一度だけ直子が濡れたからである。彼女の性器は、常に乾燥している。幼なじみのキズキとの性交の試みのときにも、僕が直子の療養所にいったときにも、彼女の性器は常に乾燥していて、男性性器を受け入れることができなかった。では、直子の性器を濡らしてくれたものは何か、雨である。村上春樹の小説にとって、雨が何であるかは、『1973年のピンボール』に戻れば明らかになる。
■雨の句読点、天空の喪章
水は、この惑星の覆いであるときには海と呼ばれて重宝され、不可視の水蒸気となり可視の雲となったときには不吉な天候として忌まわしく思われ、そして細分化され再び地上に戻ってくるときには、雨と呼び慣わされて、乾いたものであるわれわれを濡らすものとして嫌われている。
『雨はただ大地と大空とを結ぶ連結符だけを形づくっているのではなく』(フランシス・ポンジュ)、確かに、もっと重要な役割を果たしているのだ。特に、村上春樹の小説世界の中では。雨は破線として、死者たちの新世界となってしまった天と、生きているわれわれが快楽と苦悩の狭間を往還する地上とを結んでいる。
『1973年のピンボール』では、配電盤の葬式のために貯水池に行く日曜日、細かい雨が降っている。雨の降る中、僕と双子とが車に乗っている。いつもは饒舌な双子も黙っており、三人の間には静寂が支配している。そしてまるで、葬式への参列者のように犬が歩き回っている中を、クラクションを鳴らしながら僕らは進んでいく。
喪に服す者たちへと降り注ぐ永遠に続くような冷たい雨。雨とは、彼らの周囲に広がっていこうとする感情を、ひとつずつ区切り終わらせて地上へと振り落としていく液体の句読点である。それは墜落する喪章であり、失われた時間への通底符であり、感傷を許す恩赦でもある。であるがゆえに雨は、カップルを抱き寄せて世界から隔離し、遮断された二人分の身体がやっと入るくらいのごく親密な場所を保護することのできる性交の守護神なのだ。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
春樹論11(笑。
飲んでたら,遅くなった(笑。
うち飲みだけど,うちのうち飲みは長いんだよっっっっ。
さて,今夜の春樹論は恋愛と性欲の分別だよ。
混在させて平気な奴は,脳天気でいいけどなぁっっっっ(笑。
■ 性欲の分別、臨界の傍ら
『ノルウェイの森』では、僕ワタナベと死んだ友人の恋人であった直子とは、二人の距離を具体的に歩くことで実測していく。東京の街を歩き回り、コーヒーを飲んで休み、また歩いて食事をして別れるということを繰り返しているこの段階で、僕の中にやっと〈好感〉の感情が生じてくる。〈白紙〉の僕は、ただ時間と行為とを経て、書き込まれるのを待っている。自分の方から書き込みに行くことはない。
「しかし僕と直子の関係も何ひとつ進歩がないというわけではなかった。少しずつ少しずつ直子は僕に馴れ、僕は直子に馴れていった。夏休みが終って新しい学期が始まると直子はごく自然に、まるで当然のことのように、僕のとなりを歩くようになった。」(『ノルウェイの森』)
〈白紙〉の僕が、とうとう彼女のそばにさえ近づきもしなかったので、直子の方から妥協して寄ってきたのだが、それを僕は〈好感〉から〈馴れ〉への進歩として、「一人の友だちとして認めてくれたしるし」として解釈している。
その直子に好きな女の子はいないのかと尋ねられたとき、〈白紙〉でありながら性欲だけが活性化している僕は、別れた女の子と寝るのは好きだったと回想し、心の中に殻があるからだと思う。だが実は〈白紙〉の僕ワタナベには想定されている殻さえもなく、誰をも愛することができない。緑との関係でさえ、恋愛ではない。そして勃起的存在のまま『ノルウェイの森』の中で女性を物色し、性欲のはけ口として女性を資源化して有効活用している。
しかし、なぜ、村上春樹という小説家はこのように性欲をきちんと分別する必要があるのだろうか。彼は、恋愛と性欲が混同して用いられることに我慢ができないのだ。彼は、僕と鼠とを分離したように、要素の混在する事象を純粋化することによって、それぞれの臨界へとその存在を引き上げていく。その締めあげの作業の過程が苦行に似ているため、小説は頻繁に悲劇化し、宗教の傍へと隣接していくのである。
うち飲みだけど,うちのうち飲みは長いんだよっっっっ。
さて,今夜の春樹論は恋愛と性欲の分別だよ。
混在させて平気な奴は,脳天気でいいけどなぁっっっっ(笑。
■ 性欲の分別、臨界の傍ら
『ノルウェイの森』では、僕ワタナベと死んだ友人の恋人であった直子とは、二人の距離を具体的に歩くことで実測していく。東京の街を歩き回り、コーヒーを飲んで休み、また歩いて食事をして別れるということを繰り返しているこの段階で、僕の中にやっと〈好感〉の感情が生じてくる。〈白紙〉の僕は、ただ時間と行為とを経て、書き込まれるのを待っている。自分の方から書き込みに行くことはない。
「しかし僕と直子の関係も何ひとつ進歩がないというわけではなかった。少しずつ少しずつ直子は僕に馴れ、僕は直子に馴れていった。夏休みが終って新しい学期が始まると直子はごく自然に、まるで当然のことのように、僕のとなりを歩くようになった。」(『ノルウェイの森』)
〈白紙〉の僕が、とうとう彼女のそばにさえ近づきもしなかったので、直子の方から妥協して寄ってきたのだが、それを僕は〈好感〉から〈馴れ〉への進歩として、「一人の友だちとして認めてくれたしるし」として解釈している。
その直子に好きな女の子はいないのかと尋ねられたとき、〈白紙〉でありながら性欲だけが活性化している僕は、別れた女の子と寝るのは好きだったと回想し、心の中に殻があるからだと思う。だが実は〈白紙〉の僕ワタナベには想定されている殻さえもなく、誰をも愛することができない。緑との関係でさえ、恋愛ではない。そして勃起的存在のまま『ノルウェイの森』の中で女性を物色し、性欲のはけ口として女性を資源化して有効活用している。
しかし、なぜ、村上春樹という小説家はこのように性欲をきちんと分別する必要があるのだろうか。彼は、恋愛と性欲が混同して用いられることに我慢ができないのだ。彼は、僕と鼠とを分離したように、要素の混在する事象を純粋化することによって、それぞれの臨界へとその存在を引き上げていく。その締めあげの作業の過程が苦行に似ているため、小説は頻繁に悲劇化し、宗教の傍へと隣接していくのである。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )