ようやく蝉が鳴きはじめました。今年は遅かったですね。やはり夏はこれ、いい音色です。
閑(しずか)さや 岩にしみ入る 蝉の声
言わずと知れた芭蕉さんの句ですけれど、「確かにそうですね」と頷きたくなるような言葉の妙。「暑き日を 海に入れたり 最上川」なども表現の妙に思わず感心してしまいますが、夏の句で一番心に響くのはやはり、
夏草や 兵(つわもの)どもが 夢の跡(あと)
でしょうか。背景に義経の最期があるからかもしれません。
芭蕉は「平家物語」に造詣が深く、特に木曽義仲を愛した人でしたが、義経に対しても同情の念はあったようです。「夏草や…」の句は義経の最期の地、高館(たかだち)での吟であり、杜甫(とほ)の「国破れて山河在り…」で始まる「春望」を踏まえて無常観溢れる句になっています。
 安宅の関跡(日本各地にはたくさんの義経伝説がある)
安宅の関跡(日本各地にはたくさんの義経伝説がある)
頼朝は、何の逆心もない弟をどうして殺さなければならなかったのでしょうか。よく言われるのは、義経が朝廷から勝手に官位をもらってしまったことですが、当時はまだ武家の世とはいえませんし、後白河院の意向を拒むことなどできなかった筈です。頼朝だって後白河院の命に従って平家追討軍を送ったわけですから、寛容な心があれば許してやることもできた筈。無論、北条氏の思惑もあったでしょうけれど、私はどうもこの頼朝が好きになれません。鎌倉は好きですけれど…。
その昔、頼朝は清盛に助けられたにも拘わらず、平家を滅ぼしてしまった裏切り者です。己が裏切り者であるが故に、人を信じられなかったのだという説がありますが、それも一理はあるでしょう。嘘ばかりついている人が、他人の言葉を信じられないのと同じです。人間、平気で嘘をつくようではいけません。
また人に騙されたりすると人を信じられなくなりますけれど、やはり人は信じたいもの、信じられるものであって欲しいですね。
さてその頼朝さんですが、彼は自分の親族を多く殺しています。従兄弟にあたる木曽義仲の長男義高を人質にとり、名目上は自分の娘大姫の婿としますが、義仲追討の院宣が下されるとこれを討ち、義高も殺してしまいます。成人して自分に恨みを抱くことを恐れたんですね。義高を慕っていた大姫は精神を病み、早世してしまいます。そしてご存知の如く義経を追いつめて殺し、静御前が身ごもっていた子を男児であると見極めるや、生まれると同時に殺しています。コワッ!
さらに野心のかけらもない弟範頼(のりより)まで疑い、彼が何度も起請文を差し出して忠誠を誓ったにも拘わらず、死に追いやってしまうのです。
頼朝という人は本当に人が信じられなかったんですね。ある意味、可哀想な人です。
それに引き換え、平家一門は一族で殺しあうこともありませんでしたし、人の情けを知る人も多くいました。それなりの教養を身につけた美しい公達も多かったのですが、みな海の底に沈んでしまったのは残念なことです。勝てば官軍ですけれど、賊軍になったからといって悪い人ばかりではありません。敵であっても立派な人間はいるものです。戦は多くの人材を失います。良いことなどひとつもありません。
 マイホームページ
マイホームページ
閑(しずか)さや 岩にしみ入る 蝉の声
言わずと知れた芭蕉さんの句ですけれど、「確かにそうですね」と頷きたくなるような言葉の妙。「暑き日を 海に入れたり 最上川」なども表現の妙に思わず感心してしまいますが、夏の句で一番心に響くのはやはり、
夏草や 兵(つわもの)どもが 夢の跡(あと)
でしょうか。背景に義経の最期があるからかもしれません。
芭蕉は「平家物語」に造詣が深く、特に木曽義仲を愛した人でしたが、義経に対しても同情の念はあったようです。「夏草や…」の句は義経の最期の地、高館(たかだち)での吟であり、杜甫(とほ)の「国破れて山河在り…」で始まる「春望」を踏まえて無常観溢れる句になっています。
 安宅の関跡(日本各地にはたくさんの義経伝説がある)
安宅の関跡(日本各地にはたくさんの義経伝説がある)頼朝は、何の逆心もない弟をどうして殺さなければならなかったのでしょうか。よく言われるのは、義経が朝廷から勝手に官位をもらってしまったことですが、当時はまだ武家の世とはいえませんし、後白河院の意向を拒むことなどできなかった筈です。頼朝だって後白河院の命に従って平家追討軍を送ったわけですから、寛容な心があれば許してやることもできた筈。無論、北条氏の思惑もあったでしょうけれど、私はどうもこの頼朝が好きになれません。鎌倉は好きですけれど…。
その昔、頼朝は清盛に助けられたにも拘わらず、平家を滅ぼしてしまった裏切り者です。己が裏切り者であるが故に、人を信じられなかったのだという説がありますが、それも一理はあるでしょう。嘘ばかりついている人が、他人の言葉を信じられないのと同じです。人間、平気で嘘をつくようではいけません。
また人に騙されたりすると人を信じられなくなりますけれど、やはり人は信じたいもの、信じられるものであって欲しいですね。
さてその頼朝さんですが、彼は自分の親族を多く殺しています。従兄弟にあたる木曽義仲の長男義高を人質にとり、名目上は自分の娘大姫の婿としますが、義仲追討の院宣が下されるとこれを討ち、義高も殺してしまいます。成人して自分に恨みを抱くことを恐れたんですね。義高を慕っていた大姫は精神を病み、早世してしまいます。そしてご存知の如く義経を追いつめて殺し、静御前が身ごもっていた子を男児であると見極めるや、生まれると同時に殺しています。コワッ!
さらに野心のかけらもない弟範頼(のりより)まで疑い、彼が何度も起請文を差し出して忠誠を誓ったにも拘わらず、死に追いやってしまうのです。
頼朝という人は本当に人が信じられなかったんですね。ある意味、可哀想な人です。
それに引き換え、平家一門は一族で殺しあうこともありませんでしたし、人の情けを知る人も多くいました。それなりの教養を身につけた美しい公達も多かったのですが、みな海の底に沈んでしまったのは残念なことです。勝てば官軍ですけれど、賊軍になったからといって悪い人ばかりではありません。敵であっても立派な人間はいるものです。戦は多くの人材を失います。良いことなどひとつもありません。
 マイホームページ
マイホームページ











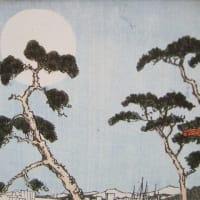







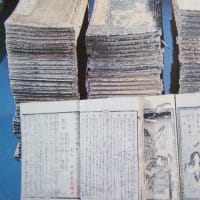
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます