歓喜のダイブでおぼれた2人を救助しようと水死 琵琶湖(朝日新聞) - goo ニュース
まさか、ボート部員が泳げない訳はあるまい。
先にダイブした2人が溺れ、救助しようとした1人が溺れたのだから、
溺れて然るべき状況であったはずなのだが、この記事からは全く分からない。
あるいは、入賞のみならず、酒にも酔っていたのであろうか。
1984年、ちょうど私が生まれた年に、東大山中湖事件があったが、
夜に酔っ払った状態でボートを漕ぎ出したことが原因だったという。
いずれにせよ、救いようのない大惨事である。
-------------------------
この記事を読んでいて、『列子』黄帝篇にある寓話を思い出した。
孔子の高弟顔回が、「舟を漕ぐことは、学習で身につくものですか」と渡し守に尋ねたところ、渡し守はこのように答えた。
「可。能游者可也,善游者數能(できる。泳げる者には漕ぐことを教えられるし、泳ぎが上手い者なら何回か練習すればすぐできるようになる)」
顔回はにわかには理解できず、孔子にこの意味について尋ねた。
すると、孔子は、このように説明した。
「能游者可也,輕水也。善游者之數能也,忘水也(泳げる者には漕ぐことを教えられるというのは、水を恐れないからである。泳ぎが上手い者なら何回か練習すればすぐできるようになるというのは、水のことを忘れるからである)」
「彼視淵若陵,視舟之覆猶其車卻也(泳ぎの上手い者にとって、淵は丘と変わりがないし、舟がひっくり返ることなど、車が後ろに戻ってしまうことと大差ない)」
舟を漕げるようになるための条件として、「水を軽んず(水を恐れない)」や「水を忘る(水のことを忘れる)」といったことが挙げられている。つまり、水に対する恐怖心を取り払わなければ、舟を漕げるようにはならない、というのが『列子』の主張なのである。
(なお、蛇足ながら、『荘子』や『列子』など道家系の文献に登場する孔子の言動は、道家が自らの都合の良いように創作したものに過ぎない、と考えるのが普通である。)
-------------------------
先日琵琶湖で溺れてしまった彼らは、舟を漕げるのだから、少なくとも「能く泳ぐ者(泳げる者)」であり、もしかすると「善く泳ぐ者(泳ぎが上手い者)」であったのかもしれない。
それでも溺れてしまったのは、「水を軽ん」じた、もしくは「水を忘」れたためであろう。
『列子』の本義とは外れるが、奇しくも言葉尻は一致する。
くれぐれも、水への恐怖心を失ってはならない。
まさか、ボート部員が泳げない訳はあるまい。
先にダイブした2人が溺れ、救助しようとした1人が溺れたのだから、
溺れて然るべき状況であったはずなのだが、この記事からは全く分からない。
あるいは、入賞のみならず、酒にも酔っていたのであろうか。
1984年、ちょうど私が生まれた年に、東大山中湖事件があったが、
夜に酔っ払った状態でボートを漕ぎ出したことが原因だったという。
いずれにせよ、救いようのない大惨事である。
-------------------------
この記事を読んでいて、『列子』黄帝篇にある寓話を思い出した。
孔子の高弟顔回が、「舟を漕ぐことは、学習で身につくものですか」と渡し守に尋ねたところ、渡し守はこのように答えた。
「可。能游者可也,善游者數能(できる。泳げる者には漕ぐことを教えられるし、泳ぎが上手い者なら何回か練習すればすぐできるようになる)」
顔回はにわかには理解できず、孔子にこの意味について尋ねた。
すると、孔子は、このように説明した。
「能游者可也,輕水也。善游者之數能也,忘水也(泳げる者には漕ぐことを教えられるというのは、水を恐れないからである。泳ぎが上手い者なら何回か練習すればすぐできるようになるというのは、水のことを忘れるからである)」
「彼視淵若陵,視舟之覆猶其車卻也(泳ぎの上手い者にとって、淵は丘と変わりがないし、舟がひっくり返ることなど、車が後ろに戻ってしまうことと大差ない)」
舟を漕げるようになるための条件として、「水を軽んず(水を恐れない)」や「水を忘る(水のことを忘れる)」といったことが挙げられている。つまり、水に対する恐怖心を取り払わなければ、舟を漕げるようにはならない、というのが『列子』の主張なのである。
(なお、蛇足ながら、『荘子』や『列子』など道家系の文献に登場する孔子の言動は、道家が自らの都合の良いように創作したものに過ぎない、と考えるのが普通である。)
-------------------------
先日琵琶湖で溺れてしまった彼らは、舟を漕げるのだから、少なくとも「能く泳ぐ者(泳げる者)」であり、もしかすると「善く泳ぐ者(泳ぎが上手い者)」であったのかもしれない。
それでも溺れてしまったのは、「水を軽ん」じた、もしくは「水を忘」れたためであろう。
『列子』の本義とは外れるが、奇しくも言葉尻は一致する。
くれぐれも、水への恐怖心を失ってはならない。










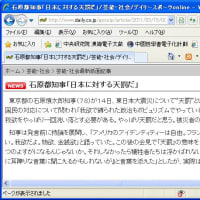

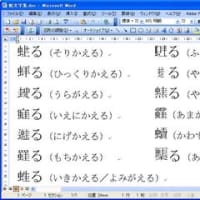
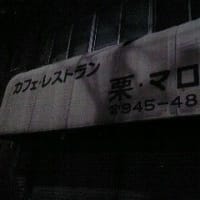

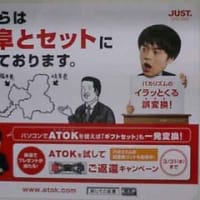

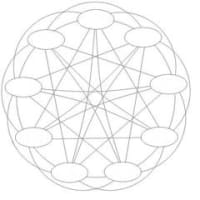
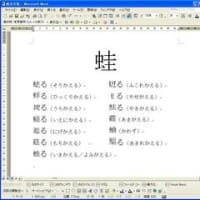

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます