自分が何を専門にしているのかを他人に話す時、
「中国哲学」「古代中国の思想」と言っても反応がいまいちな場合、
私はよく「まぁ、具体的には所謂”漢文”を読む仕事です」と言う。
非常に語弊があるし、実際に多大な誤解を伴うのだが、普段していることを手っ取り早くイメージしてもらい、更には、早くこの話題を片付けたい場合に、この手が簡便なのである。
「漢文を読む」と言われると、普通の人は、振り仮名や送り仮名、「レ点」や「一二点」といった返り点の類が施されたものを訓読したことを思い出すと思うが、私が普段読んでいるのは、そういう日本的加工が一切なされていない「白文」と呼ばれるもので、句読点すらないものも珍しくない。
漢文というのは、少なくとも古代の中国人が書いた文章というのは、本来はそういうものなのだ。
反対に言えば、中等教育の授業で読む「漢文」というのは、8割程度は既に日本語に訳されているものなのである。つまり、授業でいくら優秀でも、外国語としての漢文を読解する能力を習得することはあまり期待できない。
更に言えば、漢文の授業で教鞭を取る教師たちも、その多くは、やはりその能力がない。漢文教師というのは単なる国語科教員に過ぎない。国語科の教員免許を取得するために必要な漢文読解能力など、無いに等しい。古代中国の文献に関わる専門分野で研究をしていたならともかく、そうでなければ漢文読解能力を身につける機会がほとんど無いまま大学を卒業してしまう。(ひどい言い方をしているようだが、これは事実である。しかし、私はそれでも彼らを尊敬している。自分の専門外のことを生徒に教えるために、彼らは大変な努力を払い、大変なプレッシャーに耐えて教壇に立っているのだから。)
つまり、現在の中等教育では、どうやっても、外国語としての漢文が読めるようにはならない。
付け加えれば、もしも、多大な努力を払って、外国語としての漢文を何とか読めるようになったとしても、それで現代中国語が読めるようになるわけではない。というのは、漢文は基本的に古代語であり、当然ながら現代語とはかなり異なるからである。日本語でも、例えば一人のフランス人が『源氏物語』の原文を読めるからと言って、彼が村上春樹を読めるとは限らないだろう。
では、中等教育で漢文を教えるのは、意味がないことなのだろうか。
私はそうではないと思う。
確かに、古代中国語を読む能力も、現代中国語を読む能力も、期待できない。
訓読の規則に従って送り仮名や「レ点」が施された、まさに中等教育用漢文と謂うべきものを読めるようになるだけで、実際的な語学能力は一切身につかない。
しかし、漢文教育の意味というのは、実際的な語学能力とは別のところにある。
それは、白文であれ返り点だらけであれ完全に和文に書き下されたものであれ、そういった漢文もしくは漢文由来の日本語は、紛れも無く我々の文化の重要な一部であり、それを無視してはならないものだということである。
古来、日本人は中国から大量の書物を取り入れ、それを読んで来た。
そもそも、初期にはあらゆる文書は漢文で書かれたし、仮名文字の発明以降も多くのものが漢文で書かれた。
こういった経緯から、言語・文学・倫理など、様々な精神活動が漢文によって直接・間接の影響を被って来た。
日本語の中に漢文由来の要素が大量に含まれていること。
日本人の手になる漢詩文はもちろん、『枕草子』の中にある中国の故事、『平家物語』が何故「漢文調」と呼ばれるのか、といったこと。
倫理規範や価値意識、国家観や芸術観に於いて、中国の典籍の影響がどれだけ大きかったのか。
こういった事柄は、いずれも、自らで漢文にあたってみないと分からない。
『徒然草』や『奥の細道』を読んでおかなければならないのと同様の理由で、
『論語』や『老子』、あるいは唐詩の類にも触れておくべきなのである。
また、日本語の語彙のセンス、あるいはリズム感といったものも、
漢文訓読の影響を多大に受けている。
直接に漢文訓読をしたことがなくても、漱石や芥川といった人々を通じて、
あるいは漱石や芥川の文章の影響を受けた人の言葉を通じて、
我々には、漢文訓読の感覚を肌で身につけているのではないか。
私はこういったことを「伝統」と呼ぶのだが、
「伝統」の上で成り立っている言語感覚を洗練させるのにも、
「伝統」を深い部分で支えてきた漢文訓読に触れることが役に立つように思う。
つまり、これらのような意味があるからこそ、
外国語としての漢文ではなく、国語としての漢文訓読を学ぶべきなのである。
中国人から見ても西洋人から見ても奇怪なものであるし、現代に於いて実用に供する技術とは思えないが、
日本人はこの漢文訓読という方法に拠って中国由来の語彙・論理・観念・価値観を取り入れ、日本化して来たのである。
魚を得れば筌は忘れ、兎を得れば蹄は忘れ、甚だしくは「狡兎死して走狗煮らる」という喩えすらあるけれど、「伝統」を承け継ぐということについて言えば、筌蹄を失うべきではない。
我々の奥底に、朧気でよく見えないが、しかし確かに存在する伝統的感覚というものを、目に見える形で確認する。この作業が、中等教育の漢文科目が果たすべき役割なのである。だからこそ、中国語がまるで専門外の国語科教員たちに漢文教育が託されているのではないだろうか。
以前、英語教育についての問題で「国語教育が云々」という話が提起されたことがあった。
これについて、私は別の日記の中で述べたように、まるで筋違いな意見だと思っているのだが、
少し残念なのは、「最近の日本語の乱れ」を気にするのであれば、
もうちょっと古文・漢文教育の重要性について議論を深めて欲しかった。
なお、蛇足ながら、同じ理屈で、
西洋文学の翻訳物を国語科で扱うことにも意味があると思う。
例えば、シェークスピアは原文で読まないと本来の意図が分からない、とはよく言われるが、
それでも、原文の意図を損ねながら翻訳されたものを我々は読み、
そこで得られた知識や感覚によって、日本語による新たな文学作品が生まれている。
「生きるべきか、死ぬべきか。それが問題だ」等は、既に人口に膾炙した言葉となっていて、それがネタとなった表現も多い。
こういった著名な翻訳作品に多く触れることも、やはり重要なのではないだろうか。
少なくとも、以前にも書いたが、ギャグの元ネタが分かるというのは、大事な教養のように思う。
「中国哲学」「古代中国の思想」と言っても反応がいまいちな場合、
私はよく「まぁ、具体的には所謂”漢文”を読む仕事です」と言う。
非常に語弊があるし、実際に多大な誤解を伴うのだが、普段していることを手っ取り早くイメージしてもらい、更には、早くこの話題を片付けたい場合に、この手が簡便なのである。
「漢文を読む」と言われると、普通の人は、振り仮名や送り仮名、「レ点」や「一二点」といった返り点の類が施されたものを訓読したことを思い出すと思うが、私が普段読んでいるのは、そういう日本的加工が一切なされていない「白文」と呼ばれるもので、句読点すらないものも珍しくない。
漢文というのは、少なくとも古代の中国人が書いた文章というのは、本来はそういうものなのだ。
反対に言えば、中等教育の授業で読む「漢文」というのは、8割程度は既に日本語に訳されているものなのである。つまり、授業でいくら優秀でも、外国語としての漢文を読解する能力を習得することはあまり期待できない。
更に言えば、漢文の授業で教鞭を取る教師たちも、その多くは、やはりその能力がない。漢文教師というのは単なる国語科教員に過ぎない。国語科の教員免許を取得するために必要な漢文読解能力など、無いに等しい。古代中国の文献に関わる専門分野で研究をしていたならともかく、そうでなければ漢文読解能力を身につける機会がほとんど無いまま大学を卒業してしまう。(ひどい言い方をしているようだが、これは事実である。しかし、私はそれでも彼らを尊敬している。自分の専門外のことを生徒に教えるために、彼らは大変な努力を払い、大変なプレッシャーに耐えて教壇に立っているのだから。)
つまり、現在の中等教育では、どうやっても、外国語としての漢文が読めるようにはならない。
付け加えれば、もしも、多大な努力を払って、外国語としての漢文を何とか読めるようになったとしても、それで現代中国語が読めるようになるわけではない。というのは、漢文は基本的に古代語であり、当然ながら現代語とはかなり異なるからである。日本語でも、例えば一人のフランス人が『源氏物語』の原文を読めるからと言って、彼が村上春樹を読めるとは限らないだろう。
では、中等教育で漢文を教えるのは、意味がないことなのだろうか。
私はそうではないと思う。
確かに、古代中国語を読む能力も、現代中国語を読む能力も、期待できない。
訓読の規則に従って送り仮名や「レ点」が施された、まさに中等教育用漢文と謂うべきものを読めるようになるだけで、実際的な語学能力は一切身につかない。
しかし、漢文教育の意味というのは、実際的な語学能力とは別のところにある。
それは、白文であれ返り点だらけであれ完全に和文に書き下されたものであれ、そういった漢文もしくは漢文由来の日本語は、紛れも無く我々の文化の重要な一部であり、それを無視してはならないものだということである。
古来、日本人は中国から大量の書物を取り入れ、それを読んで来た。
そもそも、初期にはあらゆる文書は漢文で書かれたし、仮名文字の発明以降も多くのものが漢文で書かれた。
こういった経緯から、言語・文学・倫理など、様々な精神活動が漢文によって直接・間接の影響を被って来た。
日本語の中に漢文由来の要素が大量に含まれていること。
日本人の手になる漢詩文はもちろん、『枕草子』の中にある中国の故事、『平家物語』が何故「漢文調」と呼ばれるのか、といったこと。
倫理規範や価値意識、国家観や芸術観に於いて、中国の典籍の影響がどれだけ大きかったのか。
こういった事柄は、いずれも、自らで漢文にあたってみないと分からない。
『徒然草』や『奥の細道』を読んでおかなければならないのと同様の理由で、
『論語』や『老子』、あるいは唐詩の類にも触れておくべきなのである。
また、日本語の語彙のセンス、あるいはリズム感といったものも、
漢文訓読の影響を多大に受けている。
直接に漢文訓読をしたことがなくても、漱石や芥川といった人々を通じて、
あるいは漱石や芥川の文章の影響を受けた人の言葉を通じて、
我々には、漢文訓読の感覚を肌で身につけているのではないか。
私はこういったことを「伝統」と呼ぶのだが、
「伝統」の上で成り立っている言語感覚を洗練させるのにも、
「伝統」を深い部分で支えてきた漢文訓読に触れることが役に立つように思う。
つまり、これらのような意味があるからこそ、
外国語としての漢文ではなく、国語としての漢文訓読を学ぶべきなのである。
中国人から見ても西洋人から見ても奇怪なものであるし、現代に於いて実用に供する技術とは思えないが、
日本人はこの漢文訓読という方法に拠って中国由来の語彙・論理・観念・価値観を取り入れ、日本化して来たのである。
魚を得れば筌は忘れ、兎を得れば蹄は忘れ、甚だしくは「狡兎死して走狗煮らる」という喩えすらあるけれど、「伝統」を承け継ぐということについて言えば、筌蹄を失うべきではない。
我々の奥底に、朧気でよく見えないが、しかし確かに存在する伝統的感覚というものを、目に見える形で確認する。この作業が、中等教育の漢文科目が果たすべき役割なのである。だからこそ、中国語がまるで専門外の国語科教員たちに漢文教育が託されているのではないだろうか。
以前、英語教育についての問題で「国語教育が云々」という話が提起されたことがあった。
これについて、私は別の日記の中で述べたように、まるで筋違いな意見だと思っているのだが、
少し残念なのは、「最近の日本語の乱れ」を気にするのであれば、
もうちょっと古文・漢文教育の重要性について議論を深めて欲しかった。
なお、蛇足ながら、同じ理屈で、
西洋文学の翻訳物を国語科で扱うことにも意味があると思う。
例えば、シェークスピアは原文で読まないと本来の意図が分からない、とはよく言われるが、
それでも、原文の意図を損ねながら翻訳されたものを我々は読み、
そこで得られた知識や感覚によって、日本語による新たな文学作品が生まれている。
「生きるべきか、死ぬべきか。それが問題だ」等は、既に人口に膾炙した言葉となっていて、それがネタとなった表現も多い。
こういった著名な翻訳作品に多く触れることも、やはり重要なのではないだろうか。
少なくとも、以前にも書いたが、ギャグの元ネタが分かるというのは、大事な教養のように思う。










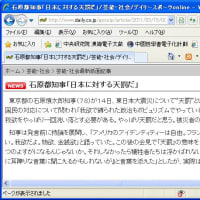

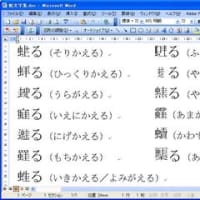
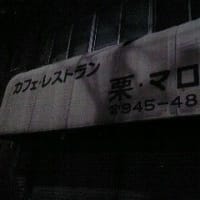

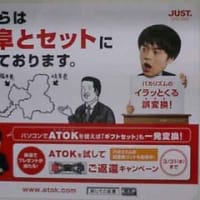

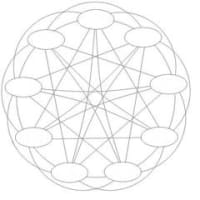
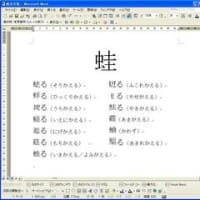

それと、私は外国語としての漢文と漢式和文(変体漢文といえばH准教授ですね?)の違いすら先日まで知らず、その違いをpingさんに教えていただいたとき、変な話ですが新鮮な驚きがありました。この「驚き」に触れることも必要ですよね。
先の大戦の時、日本では「敵性言語」として英語由来の言葉を悉く廃絶して、「ベースボール」は「野球」、「ストライク」は「よし」、「ゴールデンバット」は「金鵄」に置き換えました。しかし、当時、中国も敵国であったはずなのに、中国語を和文に置き換えることは遂にできませんでした。それどころか、大日本帝国憲法も教育勅語も、完全に漢文訓読調。
(文学史上、漢文の影響を抜け出そうとした和文文学の傑作は本居宣長『古事記伝』ですが、大変に読みにくい)
漢文の授業というのは、中国から入って来た漢文を、日本人がどのように加工して日本語に吸収して行ったのかのプロセスを紹介するものだと思います。