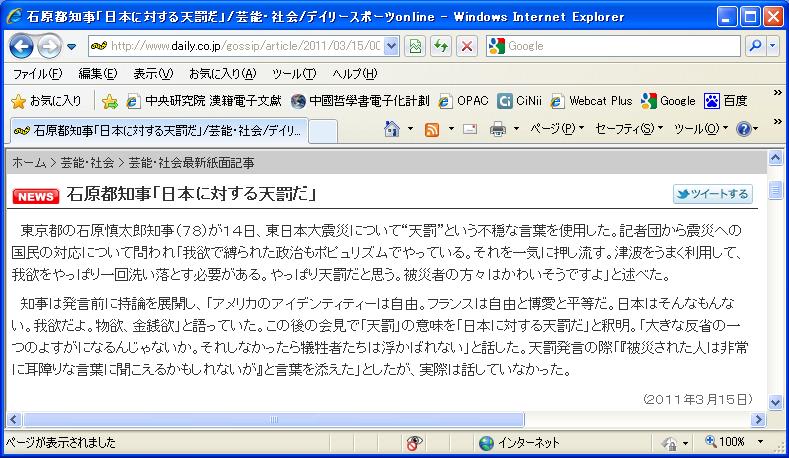「参院選に関心ある」81%…読売調査(読売新聞) - goo ニュース
明日・明後日は用事があるので、一昨日のうちに投票は済ませて来た。
別に昨日や今日行っても良かったのだが、大して考えが変わるとも思われなかったので、早めに権利を行使しておいた。
悲惨なことと不快なことだったら、私は不快なことの方を選びたいが、選挙の時に不快なことを唱える政治家は少ない。どの政治家の言うことも、耳に障らない抽象論に留まり、具体的には何も分からない。
その原因は恐らく我々の側にあって、減点法で彼らの政治を評価するからだろう。何か一つ大きな欠点や失敗があると、すぐにコケる。だから、臆病な候補者たちの主張は、どれも大して意味のない抽象的なお題目に終始し、結果、政治の議論は全然進まない。
要するに、悲惨なことと悲惨なことのどちらを選ぶかという苦肉の選択なのである。
○財政再建
現政権は「事業仕分け」なんてことをやっているが、思ったより効果は上がっていない。これは当たり前で、元々、それぞれの事業は、それぞれの分野でそれなりに意味があると思って行っているものだからである。それを素人が評価しようなどというのが、おかしい。とある数学者が「カラシニコフは一丁30ドルで買える」と言って自動小銃費用の削減を迫ったらしいが、自衛隊と山岳ゲリラを一緒にするべきではなかろう。ただ、旧来の政権が踏み込めなかったところを見直そうとする姿勢は評価できる。
「増税の前に徹底的な支出削減」と訴える政党は多いが、「全体で何%」「公務員を何%」とだけいうのは、全く意味をなさない。予算争奪競争が激化するだけで、仮に無理矢理配分を決めたとしても、その後の行政パフォーマンスが落ちる。
そもそも、支出削減というのは、現場の人間の協力がなければ不可能なのに、ことさらに「政治家vs官僚」のような姿勢を出そうとするのがおかしい。官僚はお金が欲しくて残業するわけではないし、タクシー券を使いたくて終電を逃すわけではない。天下り先のために外注することもあるのかもしれないが、ほとんどは業務上必要だから予算を使うのであるし、あるいは、翌年以降の予算のために予算消化を行うのである。
支出削減を目指すとすれば、まずは、官僚・公務員の負担を減らすシステム改革である。ややこしい計算やあちこちとの交渉、繁雑な書類作成が必要な仕組みを、なるべくシンプルにする。機材も部署の壁を越えて共有化できるものは共有化して、なるべく減らしたい。
巨大プロジェクトを数個潰すわけではなく、無数の細かい無駄を削っていくのだから、この見直しは、カツマーが各部署・各地方をめぐっていちいち対決するわけにはいかない。現場の人間との協力が必要である。
だから、システム改造によって、パフォーマンスを落とさずに業務効率化・予算削減を果たした事業、部署、省庁の人々には、削減具合に応じて、多額のボーナスを出すべきである。それは、金銭で釣ることも去ることながら、彼らの業務を高く評価することでやる気を持ってもらうということにも繋がる。
しかし、残念ながら、「公務員に財政削減ボーナス金を出す」という策を唱える候補者は見当たらない。
○税制改革
消費税増税が今回の目玉で、菅氏が谷垣氏の主張に相乗りして進めようとしている(普天間問題から焦点をずらそうという目論みだ、という分析もあるが、そういう意味もあると思う。そして、それは倫理的にはよろしくないが、戦略としては適切である)。
逆進性をどうするか、というのが目下の問題であるが、それは徴税の仕組みで工夫するのではなく、やはり、行政サービスで考慮すべきであろう。食品の税率は云々、何とかの場合は云々、といちいち複雑にしていたら、役所の仕事が増える。役所の仕事が増えるということは、つまり財政の悪化につながるということである。
消費税は一律にして、その分、「パンとサーカス」なり、介護ニューディールなり、貧乏人に恩恵のあるペイバックをすれば良い。消費税は貧乏人に負担が大きい、というが、金持ちだって多額の消費税を払っている。金を多く持っていたって、使わなければ意味が無い。多く使えば、多く消費税を払うのだ。
共産党なんかは、金持ち優遇税制・大企業減税をやめるべきだ、という。理想論としては正しい。しかし、金持ちや大企業に多額の所得税・法人税を迫れば、外国に出て行ってしまうのが現状である。
弱小企業を保護する、というのであれば、消費税免税範囲を、今の売上高一千万円から一億円くらいに引き上げるのはありかもしれない。
先日、日曜討論を見ていたが、こういう話はなく、議論はすれ違っていた。
○資源・環境問題
二酸化炭素削減問題では、「日本はもう雑巾を絞りきった状態」という話をよく聞く。麻生さんが国際会議で、「05年ベースで削減」と発言して失笑を買っていたのは記憶に新しい。
前の東大総長小宮山宏(コミー)は、企業は省エネ努力を十分にしてきたが、一般家庭ではまだまだ無駄を省く余地があると述べ、小宮山ハウスの普及を訴えている。小宮山ハウスにそれほどの効果があるのなら、政府が是非報奨金をもっと出して普及に努めるべきであろう。
二酸化炭素以上に問題なのは、資源獲得競争である。はっきり言って、北方領土や竹島、東シナ海ガス田なんて問題で争っている場合ではない。官民一体で、レアメタルやリン鉱石の獲得に努めなければならない。
マニフェストを眺めると、自民党のみ「資源外交の強化」と書いてある。これは評価できる。
○農業
90年代以降、自民党は農業を切り捨てているし、民主党もその系譜を継いでいる。見るべきものは少ない。
しかし、海外の大農業地帯の中には、地下水を汲み上げて生産を行っているところも多く、それが早晩行き詰まることは確実である。また、リン鉱石の枯渇から、化学肥料を前提とした農業モデルも、そろそろ怪しい。
もし愛国者を自認する人がいるとすれば、農業安全保障の重要性を考えるべきであろう。自給率の向上や、海外資源に依存しない農業モデル、あるいはウクライナあたりで日本輸出用に農地を買い占めておくのも手である。
ところで、民主党政権の大きな失点に、口蹄疫があるが、私は、あれは全て民主党が悪いとは考えない。10年近く前の自民党政権ではうまく押さえ込んだが、今回は、それとは初期症状が異なる。マニュアルの想定外だったのである。
強いて言えば、初期段階で、マニュアルを過信して見過ごした医者の責任となるが、それも気の毒であろう。口蹄疫かどうか確信もできず、マニュアルもないのに、自分の判断で農家に「あなたのところの牛は全て処分しなさい」とは言いにくい。
なお、五月に外遊した農相は間抜けだが、その間、業務は福島氏に引き継いでいる。福島氏の失点とも言える。
○外国人参政権
これははっきりいって、意味がよくわからない。「参政権が欲しければ帰化しろ」という意見はよくみるし、筋は通っている。永住権との違いを挙げれば、日本国籍を取得すると、母国の国籍を失うことと、名前を変える必要があること、くらいである。
また、「大量にどこかに移住し、そこの選挙を牛耳って、某国のための政治を行うから危険だ」という意見もみるが、これは的を射ていない。そこまでの意図があったら、現在の状況下でも、みんなで日本国籍を取得して同じことをすれば良い。何も、外国人参政権のような目立つまねをする必要は無い。
なお、「外国人参政権反対。帰化の条件も厳しくすべし」という主張も見られる。これは、私は賛成するわけではないが、「外国人参政権を認めると、某国のために外国人たちが動き出すから危険」という説よりは、筋は通っている。
ともあれ、要するに、こういう政策案は、在日の人たちのロビー活動・選挙活動を受けたものであろう。合衆国の政治家がユダヤ人ロビイストのためにイスラエルをひいきするのと同じことである。
政治というのは、大局を見なければならない。碁に喩えれば、小さい場所はほどほどにして、大きい場所に先着することが重要である。時には石を見捨てるという非人道的戦略も必要となる。そういえば、小沢氏は与謝野氏から囲碁を習ったらしいが、政治にはあまり反映されていないように思う。
また、最近は、政治化には行儀の良い善人だらけで、また我々有権者も減点法で評価するから、どうも小粒である。間抜けな善人よりも、用意周到な悪党の方が、政治家としては優れている。収賄くらいの悪行は大した問題ではない。
と、早めに権利を行使したから、言いたい放題言ってみた。
J.K.ガルブレイス
「記憶力の悪さほど、政治の世界で重宝なものはない。政治の世界においては、もの忘れの才ほど珍重されるものはない。政治は可能性の芸術ではない。悲惨なことと不快なことのどちらかを選ぶかという苦肉の策である。」