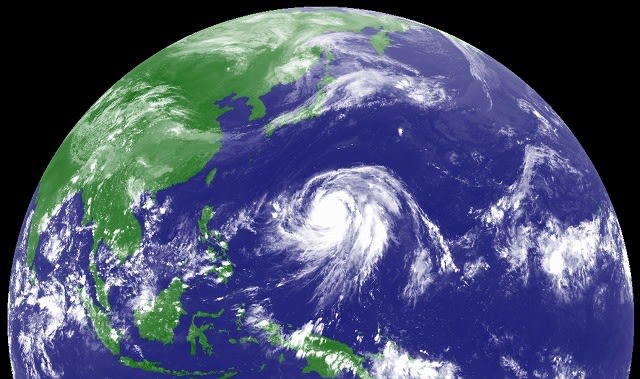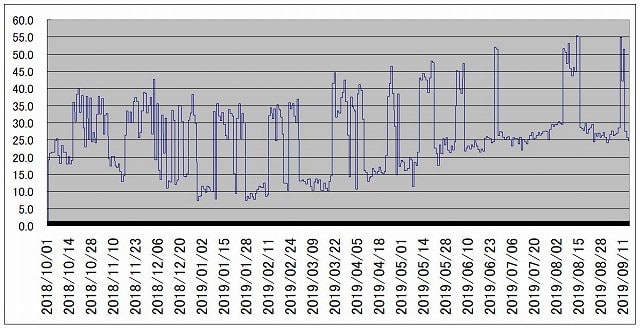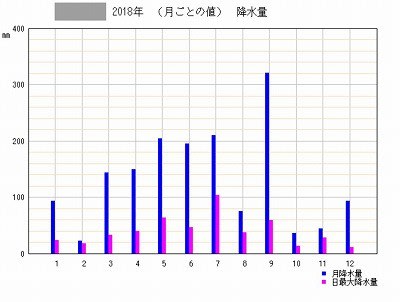家内と5泊7日でトルコ・イスタンブールに滞在して街を散策してきました。いままで単独都市で滞在したのはパリで4泊したのが一番長かったのですが、今回は5泊で最長です。イスタンブールは古くは東ローマ帝国の首都コンスタンチノープルと呼ばれ、その後オスマン・トルコの首都となりアタチュルク革命後にイスタンブールとなる変遷を経て、イスラム的なものとキリスト教的なものが混在した実に奥深く魅力的な街です。
街は大きく分けてボスポラス海峡の東側・アジア地区と西側のヨーロッパ地区、ヨーロッパ地区も新市街と旧市街が金角湾で隔てられ、それを有名なガラタ橋が繋いでいます。

最初に泊まったホテルは旧市街にあるブルーハウスホテルでアヤソフィア寺院やブルーモスクに歩いて5分という便利な場所でした。夜に着いて翌朝人けの少ない時間に散策に出かけたのですが、いきなりの巨大モスクに対面してオーと息をのむような感じでした。日本の東大寺の何倍もあるようなモスクがそこら中にボコボコ立ってるんですから恐れ入ります。

モスクの内部は無料で見学できるのですが、今でも日に5回アザーンというお祈りの呼びかけを大音量で流し信者はメッカの方向に向かってお祈りをする場所なのでドレスコードが厳しく規定されています。といっても男は長ズボンであれば普段の格好で入れますが女性はミニスカートとかノースリーブは厳禁で頭にスカーフを巻かないと入れてもらえません。内部はカトリック教会のようなゴテゴテとした装飾は無くメッカの方向を示すミフラーブがあるだけでドームの広大な空間が広がっています。

イスタンブールの街を五日間ウロウロした訳ですが最初に出会ったのがこの猫
とにかく猫の多い街で至る所でニャーニャーやってます。野良猫なんだけど痩せてなくて毛並みが艶々してて綺麗な猫ばかり。街の人たちが餌をやってるところをシバシバ目撃しました、猫は人が近づいても全然気にしません、みんなが猫好きなんですね。ここの猫はオイオイとかシーシーとか言っても全然反応しません。ところがピシピシッと言うと全員面白いくらいにこっちを見ます。
僕が何でイスタンブールに行きたかったかというと、20代のころ月刊プレイボーイという高級エロ雑誌があって開高健の”オーパ”とかと共に、藤原新也の全東洋街道・オールオリエンタルロードという紀行を数カ月にわたって載せていて、その中の次の文章に引かれたのです。
”イシュケンベ・チョルバス ー羊の腸のスープー は羊の腸を茹でて、それをまな板の上で細かく砕き、大きな鍋にぶち込んで、多少塩味をきかせて煮込んだだけというだけの単純なものだが、これが妙に複雑な味を放つのは、腸の油脂の持つ独特のチーズ臭い匂いと、腸の中にこびりついている糞が茹でられて、その発酵成分が何かえらく老獪な酸っぱみを漂わすためである 腕前の良いコックは、ほとんど屈託のない笑顔で羊の腸をしごき、この腸の微妙な加減に手心を加えるという途方もない裏取引をやっている。” 藤原新也・全東洋街道
これを読んで以来、いつかこのスープを飲んでやろうと思い続け、40年経ってやっと念願がかなった訳だが...

最初に行った店はタクシム広場のそばにあるLaleという小奇麗なレストランで、ここはこのスープが名物ということでガイドブックなどで紹介されている。早速オーダーして食した訳ですが、なんか違う... 味が上品すぎるのです。ウーン、まあこんなものかと自分を納得させようと思ったのですがなんとなく腑に落ちない。
ところがホテルをオリエンタル急行の終着駅であるシルケジ駅のそばのユーロスター・ホテルに替わってウロウロしてると、食べ物屋ばかり集まってる横丁があり、そのドン突き奥まったところのロカンタ・バルカンという店でとうとう本物に出会いました。


この写真左上のギトギトスープがそれ。老獪にして複雑、病みつきになりそうな奥深い味わい、40年間の思いが通じた気分です。このバルカンという店、客引きなど一切なしで繁盛してて安くて旨い(^ω^)/ 大体の観光場所のレストランで食うと二人で100リラ(約2千円)くらい、セブンヒルズの屋上レストランなんか本当に不味い料理をちょっと食っただけで160リラなんて取るのに、このバルカン様では上の写真の料理を指さしで選んで、二人で満腹になってたったの40リラ(800円)おまけに本物のイシュケンベに出会える稀有な存在です。イスタンブールを訪れたら是非行ってみてください、シルケジの食い物横丁のドン突きです。
食い物の話ついでにもう一つの名物、ガラタ橋のサバサンド
これも藤原新也 ”少年は油にすすけた顔の中の、幾分黄ばんだ目で私を見つめていた。少年の腕にはマッチ売りの少女が持っているような、手籠を何倍も大きくした籠がかかっていて、その中に揚げたブリの切り身がたくさん折り重なっている。ここトルコでも、冬のブリは寒ブリに違いあるまいと思い、私はそのひと切れをフランスパンにはさんだものを買った。寒気の中でその揚げ魚の切り身は温かく美味であった。私は夢中でその朝食を口に入れた。”
これが40年前の話だが、今ではすっかり名物サバサンドは岸壁につながれた船の上で盛大に焼かれ、皆の胃袋に直行している。
このサバサンドがあるガラタ橋は、土日は凄い人出でおまけに橋の上から竿を出して並んで魚釣りをしてる。
ガラタ橋から新市街に渡り、丘を登るとガラタ塔があり、
その上からはガラタ橋と旧市街が一望できる。
あと、グランバザールの迷路も圧巻 迷い彷徨いアラブを体感できます。

バザールに続く問屋街

魚屋もあります。

回る宗教舞踏 セマーも見ました
ローマ時代の水道橋、街の北西にあるベオグラードの森から市内の地下貯水池に水を引いている。

スレイマニエ・モスクの夜景

という事で、語るに尽きぬイスタンブールの旅でした。
追記;
藤原新也の40年前のトルコは、寒くて貧しくて薄汚れたトルコだが今は全然違う。これは中国でもインドでもベトナムでもフィリピンでも韓国でも起こっていることだが、日本をはじめ先進国と言われた国々が行き詰っている間に、水が高きから低きに流れるがごとく、これらの国々は人々の旺盛な欲望を満たすために発展し追いついてきている。ただ、見た目の豊かさの裏でごみ箱をあさる若者や、幼子を抱えた若いアラブの母親や老婆の物乞いの姿も見かける。発展と貧富の格差そして高齢化、人にその解決の手立てはあるのだろうか