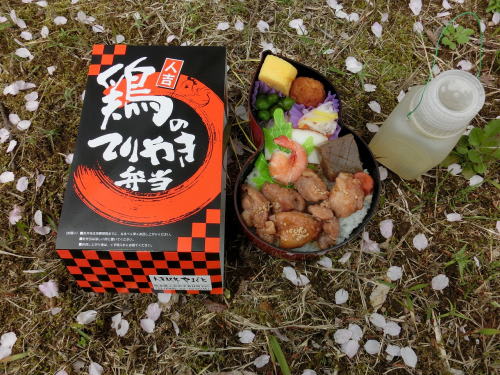おもろ歌唱者終焉の地 「 赤犬子宮 」



赤犬子 ( あかいんこ )
昔、読谷山間切楚辺村の 《 屋嘉 》 に、チラーという大変美しい娘がいた。
その娘には大変可愛がっている赤犬がいた。
ある年、長い早魃が続き村の井戸はすべて枯れ果てて、村人は大変困っていた。
そんなある日、赤犬が全身ずぶ濡れになって戻ってきた。
赤犬はチラーの前で吠え立てて、着物の裾を口でくわえて引っ張って行った。
この日照りに犬がずぶ濡れになってくるのはおかしいと思ったチラーは、さっそく後について行くと、
その赤犬は南側の洞窟に入って行った。
しばらくすると、赤犬は再びずぶ濡れになって戻ってきたので、
びっくりしたチラーは急いで家に戻り、そのことをみんなに話した。
それから洞窟の中に水があることが分かり、早魃をしのぐことができた。
これが暗川発見の由来である。
それ以前は楚辺は水不足のためにミーハガーが多かった。
しかし、赤犬が暗川を発見してからは、楚辺にはミーハガーはいなくなってしまった。
又、この美しいチラーは、村中の若者の憧れの的であったが、
チラーの心を見事に射止めたのは、 《 大屋 》 のカマーであった。
ところが二人の幸せそうな様子を妬んだ村のある若者が、嫉妬のあまりカマーを殺してしまった。
チラーは愛するカマーを失った悲しさのあまり、毎日泣いて暮らしていた。
そんなチラーの悲しい心を慰めてくれたのが、以前から可愛がっていた赤犬であった。
カマーを殺した若者は、チラーが暗川へ水汲みに行くことを知っていた。
かねてから機会を狙っていた若者は、ある日、暗川に先回りして、チラーがくるのを待ち構えていた。
何も知らないチラーは、暗川の入り口付近までさしかかった時に、
急に気分が悪くなり、その場に座り込んでしまった。
そこへたまたま通りかかったのが若者の妹であった。
そこに座り込んでいるチラーを見て、いたわって家に帰し、代わりに自分が暗川へ水汲みに行った。
なかで待ち構えていた若者は、入ってきた女をてっきりチラーだと思い、無理矢理に犯してしまった。
やがて外に出て見ると、なんと二人は兄妹であることに気付いた。
恥ずかしさと恐ろしさのあまりに、その兄妹はその場で自害してしまった。
その頃、チラーはカマーの子を身ごもっていた。
しかし、カマーは親が決めた縁談でもないし、今はすでに亡き人である。
身ごもっているとはおかしい、赤犬の子を身ごもってしまったんでは、という噂がたちまち村中に広まった。
そして、とうとう村にいることもできずに、チラーは行方をくらましてしまった。
その後、何ヵ年か後に両親は、チラーが伊計島にわたっているという噂を耳にして、娘を訪ねて行った。
しかし、両親に逢うことを恥じたチラーは、男の子を残したまま自害してしまった。
両親は悲しみながら、我が娘をその地に葬って、男の子は一緒に楚辺村に連れ帰った。
この子が後の赤犬子である。
成人した赤犬子は、ポタボタと雨の落ちる音を聞いてひらめき、
クバの葉柄で棹を作り、馬の尾を弦にして、三線を考え出した。
その後赤犬子は三線を弾きながら、歌をうたって村々を旅するのであった。
その旅の途中、北谷村にさしかかった時に、喉が乾いたので、水を乞うためにある農家に立ち寄った。
するとそこには4歳くらいの子どもがいた。
「 おまえのお父さんは何処に行ったかごと尋ねると、 「 ユンヌミ取りに。 」 と答えた。
今度は 「 おまえのお母さんは何処に行ったか。 」 と尋ねると、
「 冬青草 夏立枯かりに。 」 と答えた。
ところがさすがの赤犬子も意味が分からずに、どういうことかと尋ねたら、
「 お父さんは松明り ( トゥブシ ) 取りに。 」 、 「 お母さんは麦刈りに 」 と答えた。
すっかり感心した赤犬子は、再びその農家を訪ねて両親に、
「 あなた方の子は、普通の人より特に優れた知能を持っているから将来は坊主にしてやれ。 」 と
言い残して去って行った。
この子が後の 「
北谷長老 」 であったという。
それから赤犬子が中城の安谷屋を旅している時に、大変喉が渇いた。
近くを通りがかった子どもに、 「 大根をくれ 」 と言うと、
持っていた大根の葉っぱも取り、皮も剥いで、食べやすいように切って赤犬子に渡した。
「 この子どもはきっと偉い人になるだろう。 」 と言ったら、その子どもは後の
中城若松になった。
又、国頭方面を旅している時に、恩納村瀬良垣にさしかかった。
その時におなかがすいていたので、海辺で船普請をしている船大工に物乞いをしたところ、
むげに断わられてしまった。
それで瀬良垣の船を、 「 瀬良垣水船 」 と名付けた。
その足で谷茶に向い、そこでも同じように物乞いをした。
するそこの船大工は、丁寧にもてなしてくれた。
それで谷茶の船を、 「 谷茶速船 」 と名付けた。
その後、赤犬子が予言した通りに、瀬良垣の船は沈んでしまい、谷茶の船は爽快に水を切って走った。
そのことに大変怒ってしまった瀬良垣の船大工たちは、赤犬子を殺そうと後を追ってきた。
そこで現在の赤犬子宮のある場所に追い詰められた赤犬子は、そこの岩に杖を立てて昇天してしまった。
又、赤犬子はその他に唐から麦・豆・粟・ニービラなどを持ち帰り、それを沖縄中に広めた。
赤犬子が嘉手納を歩いている時に、道も悪く疲れていたので転んでニーピラを落としてしまった。
それで赤犬子は、 「 この土地にはニ-ピラは生えるな。 」 と言ったので、
嘉手納にはニ-ピラは生えなくなったということである。
また、赤犬子は三線歌謡の創始者と伝えられるが、おもろには三線は出て来ないので疑問である。
琉歌の 「 歌と三味線の昔始まりや犬子音あがりの神の御作 」 というのは後世の作詞である。
楚辺では、昔から赤犬子を琉球古典音楽の始祖、或いは五穀豊穣の神として奉り、
毎年9月20日には、 「 赤犬子スーギ 」 として盛大に執り行っている。