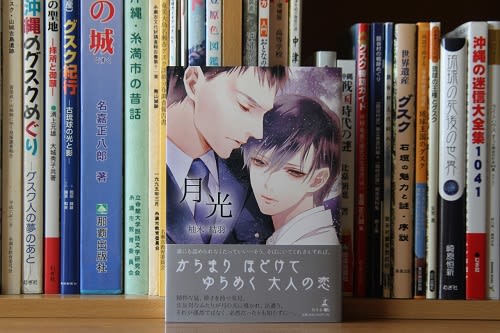豊島与志雄出生之地碑
福岡県朝倉市甘木出身の豊島与志雄は、
ヴィクトル・ユーゴーの 「 レ・ミゼラブル 」 や、
ロマン・ロランの 「 ジャン・クリストフ 」 の翻訳家として知られているほか、
幻想味を帯びた心理小説や戯曲、随筆。
さらには評論などに多くの作品を残している。
戦後は日本ペンクラブの再建にも尽力を注いだ。
『 天狗笑 』 は、大正15年 ( 1926年 ) に、
「 赤い鳥 」 に発表されたもので、
自然豊かな村を舞台に、子どもたちが人間の格好をした天狗と
無邪気に遊ぶ光景を描いた童話である。
天狗という異形のものを自然の神秘として表し、
無垢な心と先入観にとらわれない自由な精神をうたっている。
「 むかし、ある山裾に、小さな村がありました。
村のうしろは、大きな森から山になってゐまして、
前は、広い平野に美しい小川が流れてゐました。
村の人たちは、平野をひらいて穀物や野菜を作ったり、
野原に牛や馬を飼ったりして、
たのしく平和にくらしてゐました 」
一人息子だった与志雄は、邸内の樹齢数百年の楠の大木でよく遊び、
寝るときは祖母から昔話を聞いて育った。
後年、彼はそのことを 「 中に出てくるものは、
人間をはじめ、鳥や獣や虫や魚など、さまざまでした。
それらの話を思い出すと、今でもあたたまるかんじがします 」 と記している。
与志雄が生まれた旧朝倉郡福田村 ( 現・朝倉市小隈 ) は、
佐田川と小石原川に挟まれた穀倉地帯で、
『 天狗笑 』 の舞台となった場所である。
そんな与志雄の生家横には 「 生誕碑 」 が建っている。
豊島与志雄 ( とよしまよしお ) は、
福岡県朝倉郡福田村大字小隈(現 朝倉市小隈)の士族の家に生まれる。
福岡県中学修猷館、第一高等学校を経て東京帝国大学文学部仏文科卒業。
東京帝大在学中の1914年(大正3年)に、芥川龍之介、菊池寛、久米正雄らと
第3次『新思潮』を刊行し、その創刊号に処女作となる「湖水と彼等」を寄稿し注目される。
1915年(大正4年)、東京帝大卒業。
1917年(大正6年)、生活のため、新潮社に中村武羅夫を訪ねて仕事を貰ったのが、
『レ・ミゼラブル』の翻訳であった。
これがベストセラーになり、大金を得た。
この翻訳は今も何度か改訂を経て岩波文庫で読み継がれている名訳である。
こうして、翻訳が主で創作が従の活動が続く。
1923年(大正12年)、法政大学法文学部教授となる。
1925年から再び旺盛な創作活動が始まる。
1927年(昭和2年)〜1928年(同3年)、『レ・ミゼラブル』の再刊で再び印税多量に入る。
1932年(昭和7年)、明治大学文芸科教授となる。
1934年(昭和9年)、法政大学で野上豊一郎と森田草平の対立激化、解雇される。
1936年(昭和11年)、河出書房の編集顧問となる。
1938年(昭和13年)、再び法政大学教授となる。
戦後は、第二次世界大戦により活動を停止していた日本ペン倶楽部(当時の会名)の再建に尽力し、
1947年2月、再建された日本ペンクラブの幹事長に就任する。
1949年(昭和24年)、法政・明治両大学を辞職、法政大学名誉教授。
同年、日本芸術院会員となる。
1952年(昭和27年)、旧訳『ジャン・クリストフ』が売れ、莫大な印税が入る。
1955年(昭和30年)6月18日、心筋梗塞のため死去。享年64。
主な著書に、 「 生あらば 」 「 野ざらし 」 「 山吹の花 」 などがある。