中津藩士から幕臣に取り立てられ、維新後は在野にあって教育活動に専念した福沢諭吉は、その著書『痩我慢の説』において、勝海舟と榎本武揚を痛切に批判しています。
勝も榎本も、維新後、明治政府に仕えて高位顕職を得ています。福沢はこのことが気に入らなかったようです。
幕臣として幕府の要職につき、幕府のために働いた者は、その幕府への忠節を貫いて隠棲するのが筋である、と説き、勝と榎本を痛烈に批判しているわけです。
福沢はこの著書を勝と榎本に送ったそうです。それに対し、勝は
「ご批判はごもっとも、なれど出処進退は自分で決めるものであり、それについての評価はどうぞご自由に」
と、突き放し、一方の榎本は
「当方近頃は大変忙しく、ご返事はまた後日」
と適当に受け流し、その後の返答は一切なかったといいます。
勝海舟は無役の旗本でしたが、その才を買われて取り立てられ、幕府の要職を歴任し、最終的には西郷隆盛との会談による、江戸城無血開城を成し遂げます。
その後も新政府に乞われ、勝は新政府の要職を歴任、爵位を授与されるまでに至ります。
榎本武揚は幕臣の子として生まれ、昌平坂学問所、海軍伝習所等で学問を学び、その才を買われてオランダに留学、当時最新の学問と技術を習得し、帰国後は幕府海軍の指揮官となり、戊辰戦争の際には幕臣を率いて北海道・函館に上陸し、旧幕臣のための「蝦夷共和国」を名乗り、総裁に就任します。
函館戦争に敗れたあと、敵将黒田清隆に乞われて北海道開拓使に出仕、その後新政府においていくつもの大臣職を歴任するほどまでに出世しました。
実は勝や榎本に限らず、旧幕臣の要職にあったものが、新政府に出仕している例はいくつもあるのです。
明治政府は、決して薩長土肥のみによって、その権益が独占されていたわけではなかったのです。
適材適所、それは旧幕臣であろうとも変わらず対象とされた。
こういうところが、明治維新の特色と言えるのかも知れませんね。
勝にしろ榎本にしろ、自ら猟官運動を行って地位を得たわけではありません。あくまでも、新政府側から「乞われた」のです。
初めは固辞したでしょう。しかしそれでも是非にと乞われれば、断り続けることは困難だったでしょう。
自分の才能を買われているわけですから、悪い気はしないだろうし、それに、自分の持っているものが某かのお役にたてるものならば、
もう一度、「御国」のために働きたい。
そのように思ったのだろうと、想像します。
葛藤はあったろうと思います。榎本などはその責任の下に多くの人命を失わせてもいる。そのことを思えば、果たして自分がのうのうと新政府のために働いてよいものなのか?
その葛藤、苦悩がいかばかりのものであったのか、私には考えも及ばないことです。
福沢の言うことも分かるんですよね。それはそれで、一人の人間の生き方として立派だし、美しさ、崇高さをも感じさせます。
しかし、榎本や旧幕臣達が苦悩の末に新政府へ出仕することを選んだ行為も、これはこれで、
「御国」のために働きたい、己の身を捧げたいという
やはり「崇高」な想いがあったのではないか。
いやいや、糊口をしのぐ手っ取り早い手段だからでしょ?栄達が得られるかもしれないし。
確かにそれもあるでしょう。
そういう方もおられたでしょう。
福沢も、勝や榎本にそういう感を持っていたからこその批判だった。
表面だけを見れば、確かにそのようにも見えますね。
しかし、幕府のためにそれこそ命懸けの働きを示した勝や榎本が、果たして栄達だけのために、新政府に働き口を求めるものでしょうか?
私にはそちらの方が、よほど信じがたいように思えます。
勝や榎本が本当はなにを思っていたのか、それは御本人以外には誰にも分からないことです。
しかし私は、新国家建設に邁進する日本国にあって、己の出来ることをしたい、御国のために役立ちたい。
そのような想いがあったからこそではなかったか。
私はそう、信じたいですねえ。
それは、旧幕臣であったからこその、
「誇り」だったのかも知れません。












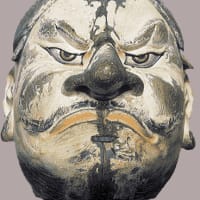







天は人の上に人を作らず、が美辞麗句で天皇でさえも批判していたのかも、、、、なんて。
勝海舟、かっけーなぁ。
斎藤一もなんで好きかって、新撰組批判あったろうに、淡々と生き続けたのよね。明治を。
勝や榎本のあしらい方がなんかいいよね。ちゃんと説明すればいいじゃん?とか思う人もいるかも知れないけど、くどくど言い訳がましいことを言うようなことではないよね。
サムライ、だよねえ。