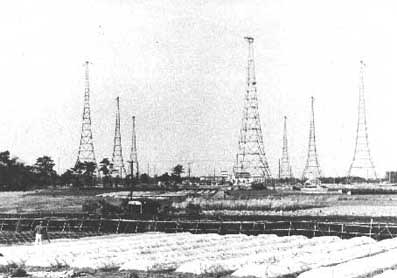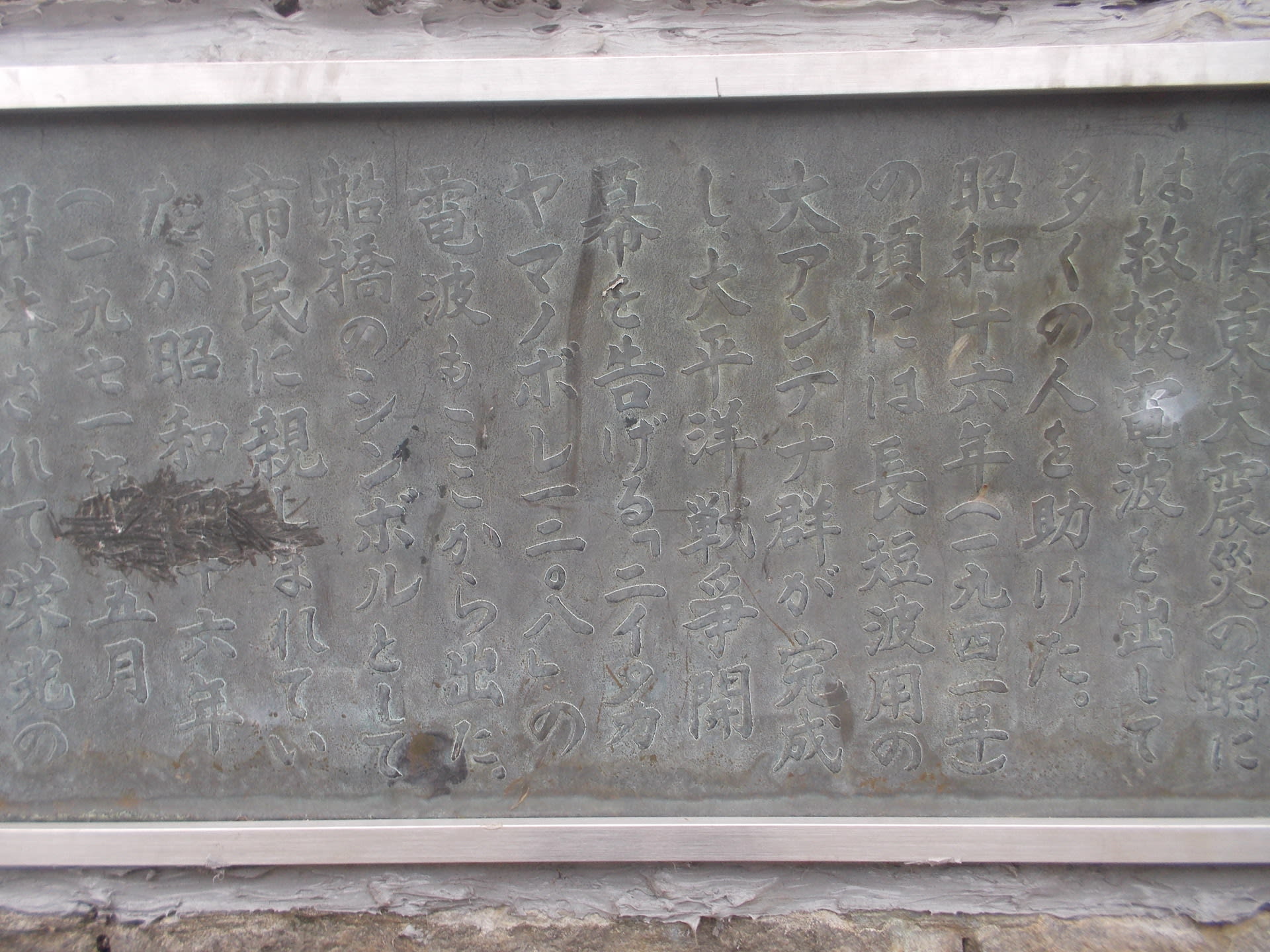↑城山砲台があった現館山城
州ノ埼海軍航空隊は1943年(昭和18)6月、全国でただ1つの兵器整備練習航空隊で現在の館山市笠名から大賀の一帯にあった。その中心に小さな「天神山」があるがここには「コンクリート防空壕跡」があるようだがみつけられなかった。次回もう一度探してみよう。
現在の館山海上技術学校前に「海員学校」があったとされるが今は海上自衛隊の宿舎になっている。また、州ノ埼航空隊を南北に「トロッコ軌道」があったが今は国道を縦断する細い道ではあるが残っており、当時存在したことを想像させる。トロッコ軌道の端は山側にやや登る「射撃場」、「土塁式掩体壕」があったのでそのための軌道だったのだろう。
山の西側には「戦闘指揮所地下壕」や「本土決戦128高地抵抗拠点」跡があるようだ。やはり戦局が悪くなっていたので決戦の準備をしていたのだろう。次回のウォーキングには行ってみたいところだ。
民間の建物になるが旧鈴木邸と赤門残っている。赤門は現在は赤門整形外科内科として存在している。
いずれにせよ、次回はこれまで行けなかった館山の旧海軍関連施設跡をまた訪ねてみようと思う。
↓下の写真をクリックすると大きくなります。

↑天神山



↑トロッコ軌道があった道




↑鈴木邸と赤門

↑小高記念館