一日中雨の一日でした。
量的にはそんなに激しいと言うことも無く、ずっと降りしきると言うのでもありませんが
霧のような時もありサァーッと降ることもありました。
 京都市西京区大原野小塩町というと「えっ?ここも京都市?」と思うくらいの位置、
京都市西京区大原野小塩町というと「えっ?ここも京都市?」と思うくらいの位置、
長岡京市から西へ山を登ったところ、山を越えれば大阪府高槻市となる場所。
竹の林をグングン登って行ったところに西国三十三観音霊場 第二十番 札所
西山宮門跡 善峯寺(善峰寺)がある。
山門をくぐるとこの時期はまず石楠花(しゃくなげ)が迎えてくれる。



春先は枝垂れ桜から始まって石楠花・牡丹・躑躅(ツツジ)・芍薬(芍薬)と順番に咲く。
躑躅を除けば美人の立ち姿・座姿・歩く姿と例えられる花が咲く。
夏もサツキ・紫陽花(アジサイ)・百日紅(サルスベリ)・高砂百合(タカサゴユリ)と続き
秋は秋明菊と紅葉、冬は南天と山茶花(サザンカ)に雪景色と一年中楽しめる花の寺。
ちょうど今は桜が終わり紅葉の若葉や花しかなく訪れる人も少ないので、境内の改修を
されています。



日本一の松があると聞いてどんなに立派な物かと高さ・大きさを想像して見ると・・・


なんとなんと横に長~~~い! 遊龍の松 と言うらしい。
ここは江戸時代の五代将軍綱吉の母であられた桂昌院ゆかりの寺。
幼少のころから母と共に善峯寺にご奉仕され、将軍の母となられてからは 数々の美・芸術価値の高い品をご寄進された。
数々の美・芸術価値の高い品をご寄進された。
春と秋に観音堂(本堂)の南横に建つ「寺宝館・文殊堂」にて特別展を
開催している。
五代将軍綱吉やその母・桂昌院は「生類憐れみの令」を代表として
悪政の代表のように言われているが、お寺の説明によると全く違うという。
晴れ渡った日なら京都盆地も一望できるのであろうが、小雨に煙る空模様では
視界が白く遮られて眺めと言うような景色ではありませんでした。















 はクリックするとPDFページに飛びます。
はクリックするとPDFページに飛びます。
 」ぐらいには思っていただけるかも? かなぁ。
」ぐらいには思っていただけるかも? かなぁ。

 どちらも行き止まりの短い通り、
どちらも行き止まりの短い通り、 北東向きに。
北東向きに。 する場所にこの通りの最後の寺
する場所にこの通りの最後の寺
























 やっぱり位置が違う
やっぱり位置が違う

 あった。
あった。


 ココ
ココ















 京都府立医大病院の一階にある
京都府立医大病院の一階にある






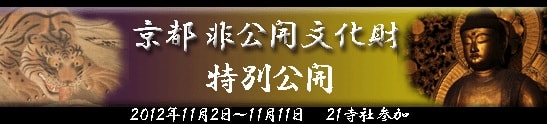 のお話。
のお話。




 なんとか覗いてみたくなる。
なんとか覗いてみたくなる。







 15分とかからずに行ける」と答えると
15分とかからずに行ける」と答えると 』
』

 「
「










 で京都へ と言うことで案内役。
で京都へ と言うことで案内役。 東福寺塔頭 天得院 桔梗を愛でる特別拝観 6/15(金)~7/17(火)
東福寺塔頭 天得院 桔梗を愛でる特別拝観 6/15(金)~7/17(火) 妙心寺塔頭 東林院 沙羅の花を愛でる会 6/15(金)~7/1(日)
妙心寺塔頭 東林院 沙羅の花を愛でる会 6/15(金)~7/1(日)














 湯葉・とうふ
湯葉・とうふ の文字がアチコチに。
の文字がアチコチに。












