辺境の惑星、べノム――。
ライラット系に住む多くのものにとって、その名を口にするとき、それは『地獄』とほぼ同じ意味合いで使用された。岩石と砂塵以外のものはまるで見当たらず、樹木はおろか、雑草の一本さえ生えることのない、不毛の大地。金属を腐食させる酸の海と、惑星全体を厚くおおう酸の雲のせいで、この惑星に進入したが最後、機体は腐食し、みずからの体も機体と同様にこの星の上で腐りはてる運命となる。同じ理由で、送り込まれた惑星探査機も、ものの数分で用を成さなくなる。
コーネリアにおいて、惑星間航行用のプラズマエンジンが実用化されたことを契機に、ライラット系の住民たちは星をこえたつながりを持つようになった。これまでは未知の存在であった他惑星の住人たちと出会い、理解を深めていった。理解が深まる過程はかならずしも友好的なものだけではなく、むしろ血のにおいがする手段が当然のようにとられていた。……だがそれも、いつしか終わることとなった。星の住人達は争うこと、血を流すことに疲れはて、平和協定をむすんだ。歴史に大きな傷を残しはしたが、これからの歴史は、これまでに壊してしまったものを修復し、生まれ住む星の違うもの同士が手に手をとりあって紡いでゆく歴史になるはずだった。
あの男が現れるまでは。
惑星間航行が可能になって100年以上の年月が流れても、この惑星だけは、依然として『地獄』という認識のまま変わることはなかった。いつしかべノムは、犯罪者達に最後の時を迎えさせるための処刑場、追放の地となっていた。数日分のみの食料と水だけを備えたカプセル、そこに押し込められた囚人たちが、べノムの大気圏外から惑星上に投下された。パラシュートが開きカプセルがゆっくりと落下してゆく数分のあいだ、カプセルの中の囚人はみな一様に、外に広がっているであろう地獄の景色を思い描いた。そして、地上に落下したカプセルを開いて景色を目の当たりにしたとき、やはり一様に、頭のなかにあった地獄に行けたほうがずっとマシだったと思わずにいられないのだ。まさにここはこの世の地獄だった。命あるものが踏み入ることのできる世界ではなかった。絶対なる死が支配する領域であった。
あの男が現れるまでは。

















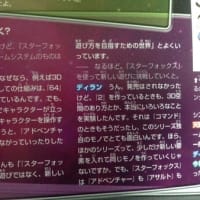
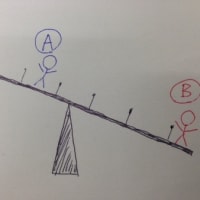

 ファルコの続きが早く読みたいです
ファルコの続きが早く読みたいです これからもがんばってください
これからもがんばってください