小浜逸郎様
お久しぶりです。
今日やっと『大前研一トンデモ「デフレ」理論』をアップできました。一回のアップ文字数が1万字までなので、2回に分けてアップしました。
*『大前研一トンデモ「デフレ」理論』の原稿書きのために時間が取られているので、メールの返事が一週間ほど遅れることを小浜氏に伝えていました。
分量が膨大で、細い話も出てくるし、みなさんが読んでくれるのか心配していたところ取りあえずアップ当日に900弱のアクセスがあり、ホッとしています。ツイッターにいろいろと反響の言葉も寄せられていて、ささやかながら喜びをかみしめています。しかし、喜んでばかりもいられません。非合理的な経済政策のありさまは変わっていないのですから。
さて、小浜さんの前回のメールについて思いつくままに述べます。
ちょっと前のことですが、大森荘蔵におけるデカルト的二分法ののり超えの試みのまずい点についての、小浜さんのお話、印象深く残っています。
小浜さんの言葉を、私なりに言いかえると次のようになります。
人は実存において主客の交流する形容詞的な世界像を生きている。そこから、分析的に主観と客観とが析出されることにもなる。また、主語が析出されることにもなる。そのことには一定の有効性・レーゾンデートル(存在理由の意―編者注)がある。かといってその二分法を絶対的な真理とするのはおかしい。そのリゴリズム(過剰な厳格主義の意―編者注)から、世界観の硬直化・貧困化が生じることになるからである。見上げた青空が美しいと感じるとき、その美を、私の主観に還元するのは誤っている。世界はもっと豊かな相貌をしているはずだから。他方、大森氏のように主観=心を客観=物にそっくりそのまま投げ出そうとするのも、物に神性を見出そうとする感性を保持する日本人としてその気持ちを分からなくもないが、哲学的には同じく誤っている。
短歌を読み味わうということは、人が本当のところどのようにこころを世界に開いて(あるいは閉じて)生を織り成しているのかを内側からやわらかく辿りなおすプロセスなのではなかろうか。一級の感性の痕跡としての名歌には、そのような実存が凝縮された形でありありと表出されている。だから、それに大真面目になって取り組むことには、文学的な価値はもちろんのこととして、思想的な価値もある。
さらに、哲学的な価値も、と言いたいところですが、私には荷が重すぎるので、ここは代わりに小浜さんに「そうだ」と言ってほしいところです。
そんな感じになります。私にかろうじてできるのは、小浜さんの、主客二分法を真ん中で超えようとする思想的・哲学的な展開を、主に文学の側から重ね描きすることなのではないかと思います。
思想的な構えの核心のところで、私は小浜さんから大きな影響を受けていることを再認識しました。ここから、自分なりのパロール(個性的な語りの意―編者注)をどう展開するのかが今後の私の課題、ということになるのでしょう。まあ、いい年なのであまり悠長なことも言ってられないのですが。
〉厳密に言えば、貴兄の今回の論は、「日本人の感性は素晴らしく、微妙で独特であり、そう簡単にガイジンなどにわかるはずがない、わかってもらっては困る」と言いたい気持ちと、「私たちはそれでも、よりよい訳、よりよい批評などを目ざしているところから見て、究極的な理想として、分かり合えるはずだ」という理念との両面を唱えていることになると思います。論理的にはこれは矛盾するのでは?
まったくそのとおりであると思います。一方では、普遍性への志向性を、表現に向かおうとする自分に確かに感じるのですが、他方では、日本人の感性が素晴らしい云々ということよりも、欧米人が抜きがたく抱えている(ように感じられる)「絶対的なもの」への激しい志向性に対する違和感と、助詞・助動詞に代表される日本語のニュアンスが結局は欧米人に伝わらないのではないかという断絶感とがあります。
後者については前回申し上げたので、今回は前者(すなわち、欧米人が抜きがたく抱えている「絶対的なもの」への激しい志向性に対する違和感―編者注)について述べます。
私は若い頃に、文学青年にありがちなことなのですが、ドストエフスキーにのめり込んでいた一時期があります。倫理的な思想に基づいて老婆を殺したラスコーリニコフが、かえって倫理問題について不器用に執拗に悩むことになり、結局は頭を抱え込んできりきり舞になって一少女に跪(ひざまづ)いてしまう姿に共感を覚えたりはしたのですが、それとは逆にどうしても分からなかったことがありました。
確か『カラマーゾフの兄弟』のイワンが大審問官のところで「神がいなければすべてが許される」というテーゼを提示し、それについて深く思い悩む自分の姿をアリョーシャに晒しますね。
イワンの悩みは、理屈ではそれなりに分かるような気がするのです。でも、神という唯一神あるいは絶対を失うことによる世界崩壊への畏れ・おののきの深度をまったく共有できないと当時も思いましたし、いまでもそうです。
とはいうものの、他方では、表現するという行為そのものに、時代や民族の違いを超えた普遍への志向性が不可避的に織り込まれているとも考えているのです。特に、良い音楽を聞いたときにそれを強烈に感じます。
むろん私は、文字表現の普遍性をも信じます。信じようとしています。しかし、ときどきどうしようもない壁や断絶を感じることがある、ということです。これは、未だにあまりうまく処理できていないことです。
「批評の基準」についていま思うのは、洋の東西を問わず、優れたエコノミストについて語っているとき、私は、文芸批評を展開している面白さとほとんど同じものを感じているということです。文学者とエコノミストでは世界を写し取り、切り取るツールが違うのはもちろんです。
しかし、優れたエコノミストには、強烈で魅力的な個性があります。それが、こまかい経済学的な「さかしら」を伸びやかにのりこえて、彼らが経済の言葉で世界を語り、自己を語る哲人あるいは表現者の面持ちに近づいてくる源になっているように感じています。経済エッセーについては、もっともっと書き込んで、予備知識抜きでも読み手が楽しめるようなものを書けたらなと思っています。
市民化された経済学。これって、一般国民が主権を本気で担おうとすれば必要になってくるものですね。その課題を自分の力の及ぶ分だけでも担うことができれば、といささかなりと思いはじめています。まずは、自分がちゃんと経済の基本を分かっていることが最低基準ですね。ブログで私見を公開する気持ちには、誤った認識があればそれを読み手に率直に正してほしい、ということもあるのです。
〉欧米圏の生活意識と言語との関係に精通しているわけではない私たちには、そもそも公平な比較というのは不可能なのではないでしょうか。そのことも押さえておく必要があると思うのです。
おっしゃる通りです。ここを見過ごすと異文化についてバランスの悪いことを言ってしまいそうですね。適切なアドバイスとして受けとめます。
日本語の特性のご指摘については、特に⑤にはっとさせられました。
〉⑤またまた関連するのですが、「辞」に関するかぎり、いろいろと品詞分類がなされてはいるものの、音韻が同じならばそこに込められた生活感情、生活思想はアルカイックな時代では同じだったのではないか
助詞にはそれぞれ、おそらくもともとのなにか核になるような意味合いがあるのでしょう。それをつきつめると面白いことになるような気がします。なんとなくですが、身体性に深く関わる生活感情・宗教感情・宇宙感覚に根ざしているものが多いのではないかと感じます。
ちょっとずれますが、語源って、本当に興味深いと思います。
たとえば、「いかづち」。「いか」は「いかつい」「いかめしい」の「いか」に通じているようで、形容詞「厳し」の語幹だそうです。「づ」は助詞の「つ」で、「ち」は、「おろち(大蛇)」「みなち(水霊)」「つち(土)」「ち(血)」の「ち」と同じく人並み外れた過剰な生命力・霊力を意味するそうです。漢字を当てれば「厳つ霊」となるとのこと。つまり、畏怖・敬服の念を起こさせるスーパー・パワーの意で、大蛇とか神様とかをばくぜんと指していたのが、後に、雷を特に指す言葉になったそうです。これは、むかし塾を経営していたときに雇っていた女の先生が国文学出身で、万葉集の話をしているときに教えてくれたことです。古代の人々の生活感情を垣間見る思いがしませんか。雷はおそらく「神(あるいは上)鳴り」で、その読み方に古代の痕跡を留めているのではないでしょうか。
とりとめもないのですが、今日はこんなところで。
*****
シリーズの10回目です。これでとりあえず終了です。小浜逸郎氏には、内容の確認・精査で多大のお手数をおかけしました。ありがとうござます。また、あまり一般的とは言えないテーマに最後までおつきあいいただいた皆様には心から感謝申し上げます。
しばらく時勢と一定の距離を置いて、小浜氏との対話に心静かに没頭しました。これからまた、喧騒の渦巻く「娑婆」に戻って、声の続く限り咆哮しようと思っています。なにせ、もともとブログ名が「オレにも言わせろ」というお世辞にも上品とは言えないものですから。らしく、しなくちゃね。
☆☆☆☆☆
美津島明様
「大前研一批判」、読みました。ただただ感嘆いたしました。エネルギーとスピードがすごいですね。とはいえ、やはり私の経済音痴は克服できないので、前半に関しては美津島さんの論理についていくのがやっとです。自分で見破ってみろと言われたら、たぶんできないと思います(だまされてしまいそうです)。
ただ、後半の大前のひどさについては、私でもわかりました。要するに彼は「デフレ不況」の状況認識を同語反復しているに過ぎないのに、あたかも正当な因果関係論理であるかのように偽装しているということですよね。そうして「少子化」などという受け狙いの「自然現象」を、何の根拠もなく飛躍した「原因」として持ってきて、説得力があるかのように大衆を欺瞞している、ということだと思います。
ひとつ、緊急時には、マクロ経済を動かすことが唯一可能な中央集権(時には独裁)こそが必要とされるのだ、という理念的な正当性は十分理解できるのですが、そういう正論をきちんと理解し、実行にまでもっていける政権担当者や優秀な官僚の出現をいまの日本で期待できるのか、という点で、国民は絶望感と不安を深めており、まさにそのために、大前や橋下のようなインチキ野郎たちに付け込む隙を与えてしまっていると思うのですが、この点についてはいかがでしょうか。
いやいや、この質問が美津島さんの現在の闘志に冷水を浴びせることになるのではないかと恐れます。無視していただいてけっこうです。
それにしても、美津島さんのこの間の仕事は一級の価値があると、私は身びいき抜きで思っているので、何とか「本」の形で報われるといいですね。これまで出版社四社の編集者に紹介はしているのですが(みな消費税増税反対論者です)、まだお声はかかりませんか(笑)。でも、私などが動いても限界があります。これだけ力のある論考なら、編集者の誰かが必ずマークしているはずで、もしそうでないなら、編集者全体が衰弱している証拠でもあります。切ない状況ですね。
「ブログ異論」のやり取りに関しては、さっそくに誠実なお返事を頂き、恐縮です。大森荘蔵に対する私の批判をよくご理解いただき、しかも的確に、手際よくまとめてまでくださるとは。
大森については、じつはもっと根本的な批判をしており、言哲で彼を紹介した折にはけっこうイカレていた部分もあったのですが、よくよく読んでみた後のいまの時点では、7:3くらいの割合で、この人はダメだなと思っています。いわゆる「哲学者」特有の視野の狭さを示しており、また、戦後思想の限界も露出しているようです。彼の「心」論などは、すでに60年も前に和辻が、まるで事態を予見していたかのように、完膚なきまでに粉砕しているのです。この事実は、戦後思想家、丸山、吉本、大森と、戦前の思想家、和辻、小林、時枝を比較した場合、戦前のほうがずっと優れていた、という残念な結果として現われています(というのは、まあ、私個人の恣意的な評価ですが)。
この評価が正しいとすると、そこにはどうも社会状況的な理由がありそうです。それについてはそんなにきちんと考えていないので、また機会を改めて。
今回、言葉の問題について、いろいろと有意義な示唆を与えていただいたのですが、それについてお返しをしていると、また相当時間をかけなくてはならないので(それは私にとっても必要なことでもありますから、煩をいとうているわけではありません)、少々待っていただいて、続編を送ります。
*****
小浜逸郎様
ご返事ありがとうござます。追加がおありとのことですが、とりあえず返信いたします。
〉前半に関しては美津島さんの論理についていくのがやっとです。自分で見破ってみろと言われたら、たぶんできないと思います(だまされてしまいそうです)。
これは、けっこうショックでした。プロの読み手の小浜さんに苦労をかけてしまうような読み物だったら、一般人には到底無理、ということになるでしょう。「市民のための経済学」などとブチ上げておいて、情けないこと限りない。
まだまだ、経済について分かっていないことが多いのでしょう。分かっていないから、読む人に負担をかけてしまうのでしょう。本当に分かっている人は、アダム・スミスのようにごく平易な言葉使いで世界の見方をひっくり返してしまいますね。
私には、分かっていないことを分かっていないと認めるだけの率直さがまだ残っていますから、できうるかぎり善処いたします。ご指摘、ありがとうございます。
〉ただ、後半の大前のひどさについては、私でもわかりました。要するに彼は「デフレ不況」の状況認識を同語反復しているに過ぎないのに、あたかも正当な因果関係論理であるかのように偽装しているということですよね。そうして「少子化」などという受け狙いの「自然現象」を、何の根拠もなく飛躍した「原因」として持ってきて、説得力があるかのように大衆を欺瞞している、ということだと思います。
おっしゃるとおりです。これだけ明晰に批判の論点を整理していただけると助かります。もし、大前氏が大真面目にこんな論理の破綻したことを堂々と自信を持って言っているのであれば、彼は普通の意味で頭が良くない人であることになってしまいます。もし、ワザと論理のめちゃくちゃな論を世に垂れ流して一定の効果が生じるのを期しているのであれば、悪質なソフィストと言えるでしょう。どちらが正しくても、彼のデフレ論は殲滅されなければなりません。影響が大きすぎるので。
〉ひとつ、緊急時には、マクロ経済を動かすことが唯一可能な中央集権(時には独裁)こそが必要とされるのだ、という理念的な正当性は十分理解できるのですが、そういう正論をきちんと理解し、実行にまでもっていける政権担当者や優秀な官僚の出現をいまの日本で期待できるのか、という点で、国民は絶望感と不安を深めており、まさにそのために、大前や橋下のようなインチキ野郎たちに付け込む隙を与えてしまっていると思うのですが、この点についてはいかがでしょうか。
私は、そういう人が現に少なからずいるのではないかと思っています。国会議員さんの中に(民主党の中においてさえも)、そういう人は散見されます。名前を挙げると、私が知っているだけでも、民主党系では馬淵澄夫、金子洋一、宮崎岳志、松原仁(心意気を買って)、長妻元厚労省相(リターンマッチの情念を期待して)、新潟県の泉田知事(とても賢い人です)、自民党系では、森まさこ、西田昌司、山谷えり子、稲田朋美、高市早苗、林芳正、共産党では佐々木憲昭、たちあがれ日本では平沼さんと園田さん(いずれも年を食っていますが)などそうそうたるメンバーがそろっています。ただし、彼らにはいまのところ実権がまったくない。それこそが問題ですね。彼らの周りには、想像ですが、良質な官僚たちが集っているはずです。だから、世論の援護射撃が必要なのではないかと思っています。良き世論の形成は、まともな知識人の仕事のうちとても大切なものですね。
〉それにしても、美津島さんのこの間の仕事は一級の価値があると、私は身びいき抜きで思っているので、何とか「本」の形で報われるといいですね。これまで出版社四社ほどに紹介はしているのですが(みな消費税増税反対論者です)、まだお声はかかりませんか(笑)。でも、私などが動いても限界があります。これだけ力のある論考なら、編集者の誰かが必ずマークしているはずです。
そこまでしていただいているとは。言葉もないくらいに感謝します。出版の話があればそれはもちろん掛け値なしに嬉しいです。けれども、それがなくてもこのブログはやり続けようと思っています。小浜さんのように声援していただける方がいらっしゃるので、心強いこと限りない思いです。
〉この事実は、戦後思想家、丸山、吉本、大森と、戦前の思想家、和辻、小林、時枝を比較した場合、戦前のほうがずっと優れていた、という残念な結果として現われています(というのは、まあ、私個人の恣意的な評価ですが)。この評価が正しいとすると、そこにはどうも社会状況的な理由がありそうです。それについてはそんなにきちんと考えていないので、また機会を改めて。
これは、日本思想のとてつもなく大きな問題であるような気がします。戦後思想の「思い込み」を木っ端微塵にしてしまうとてつもない知的「暴力」を感じます。このことと、「戦後日本の唯一の達成は、人命尊重のヒューマ二ズムが一般国民において根付いたこと」という、私が小浜さんと共有している戦後評価とはメダルの表と裏のように感じています。
言葉の問題については、小浜さんからの追伸があるとのことなので、今回は触れない方がいいようですね。
*****
美津島明さま
まず、私が、美津島さんの論理についていくのがやっとだった、と申し上げたことについて。
> これは、けっこうショックでした。プロの読み手の小浜さんに苦労をかけてしまう ような読み物だったら、一般人には到底無理、ということになるでしょう。「市民のための経済学」などとブチ上げておいて、情けないこと限りない。
プロの読み手、と評価してくださることはありがたいのですが、こと経済に関しては、基礎もわかっていない本当にダメな読み手なのですよ。なんとケインズもほとんど読んでないので、あきれた読み手でしょう。単純にそういう私固有の理由で苦戦したということなので、書き手である美津島さんがそんなに謙虚にならなくていいと思いますよ。貴兄は、これまでの論考で、田村秀男さんの論理を援用しつつ、やさしくわかりやすく、繰り返し繰り返し噛み砕き、しかも面白く書いてくださっているので、デフレ時の増税がいかに国際常識、経済学の常識にも背反するナンセンスであるかについては、十分理解できているつもりです。
> もし、大前氏が大真面目にこんな論理の破綻したことを堂々と自信を持って言っているのであれば、彼は普通の意味で頭が良くない人であることになってしまいます。もし、ワザと論理のめちゃくちゃな論を世に垂れ流して一定の効果が生じるのを期しているのであれば、悪質なソフィストと言えるでしょう。どちらが正しくても、彼のデフレ論は殲滅されなければ なりません。影響が大きすぎるので。
これはどちらかと問われれば、やっぱり前者なのではないかな、と思います。ことほどさように、心理が同時多元的に作用する経済という魔界に、論理の楔を打ち込むのは、けっこう難しいのではないでしょうか(音痴の自分を自己正当化しているみたいですが(笑))。
現実に切り込むための人間の論理の道具というのは、「因果関係論理」と「二元論」と、二元論の克服としての(やや怪しげな)「弁証法」くらいしかない。ことに現在のような金融資本が主役で、その動きが実体経済と遊離してしまっている時代になると、何を「因」として押さえれば適切な分析となるのかは、私などにはお手上げです。専門家であるはずの経済学者たちの結論も、ずいぶん前からバラバラですよね。
で、この問題(何をポイントとして重要視すべきか)は、この魔界に究極的な「真理」の力学が隠れているというよりは、むしろ新しい経済思想を創造するという問題なのではないか、と、素人の私などは考えてしまいます。つまり、「価値自由の法則」を貫く分析などはありえず、分析がそのまま、一つの価値観、思想の提示になるのではないか、と。
美津島さんもおそらくその線に沿って論を展開されていると思います。前回の、「市民化された経済学」の創出に闘志を燃やす文面にも、今回のメールにもその気迫を感じましたので、どうぞ私の水差しなど気にせずに突き進んでください。わかる人にはちゃんとわかるように書かれていると思います。
ただ、経済となると、やはり「音痴」が多いのも事実で、みんな理解(創造的理解)を諦めているようで、だからこそ「専門家」と称する百鬼夜行の世界になってしまうのですね。こういう世界で鬼たちをなぎ払い、説得力ある論理、理論を打ち立てるのは、さぞかしたいへんだろうなと推察いたします。それでもがんばっている美津島さんの情熱と心意気に改めて心から声援を送ります。
中央権力を、責任をもって担いうる人がいるのかという問題について。
> 私は、そういう人が現に少なからずいるのではないかと思っています。ただし、彼らにはいまのところ実権がまったくない。 それこそが問題ですね。彼らの周りには、想像ですが、良質な官僚たちが集っているはずです。 だから、世論の援護射撃が必要なのではないかと思っています。 良き世論の形成は、まともな知識人の仕事のうちとても大切なものですね。
まったくそのとおりですね。こういう大切な原則を再認識させてくれたことに関して、とても心強いものを感じます。加えて、貴兄がよく政治家の言論を調べているのに感心しました。
蛇足ですが、今日たまたまラジオで国会質疑を聞いていて、どうも自民党の心ある議員たちは、「消費税増税」が悪政であり、財政再建よりも景気刺激策のほうがはるかに喫緊の課題だということにうすうす気づき始めているのではないか、という印象を持ちました(ただし、増税が税収入の増加に繋がらないという肝心な点を質疑で公然と指摘する人は誰もいないようです)。といって、自民党全体でいまさら増税路線を引っ込めることはできないので、この党はジレンマに陥っている感じです。
戦前の思想家のほうが優れているという私の指摘について。
> これは、日本思想のとてつもなく大きな問題であるような気がします。このことと、「戦後日本の唯一の達成は、人命尊重のヒューマ二ズムが一般国民において根付いたこと」という、私が小浜さんと共有している戦後評価とはメダルの表と裏のように感じています。
これもそのとおりですね。ここはとても考えどころのような気がします。粗雑な類推ですが、苛酷な帝政ロシアで、世界最高水準の文学が生まれましたね。戦後の冷戦下の日本では、一人ひとりは必死にがんばっては来たのだが、無意識のうちにその大局的な構造に安住して(東か西か、左か右かのどちらかに依存して)、本当の創造性が殺がれてしまい、ついに混乱、中途半端、矛盾した思想しか生み得なかったのではないか、と、そんなふうに思います。ここに、敗北の後遺症としての生命価値の過剰な(と、今回はあえて言いますが)尊重という傾向も絡んできますよね。
この間話し合ってきたことと矛盾するようですが、艱難、汝を玉にす、とか、家貧にして孝子いづ、というようなことが、ある特定社会の内部でも一定程度までは成り立つような気がするのですが(あくまで、これは比喩としてです)。もっとも、北朝鮮で優秀な思想が生まれつつあるとはとても思えませんが(笑)。
さて、たまたまロシア文学に触れたところで、先の貴兄の問題意識の一つにうまく接触できたようです。
> 確か『カラマーゾフの兄弟』のイワンが大審問官のところで「神がいなければすべてが許される」というテーゼを提示し、それについて深く思い悩む自分の姿をアリョーシャに晒しますね。イワンの悩みは、理屈ではそれなりに分かるような気がするのですよ。でも、神という唯一神あるいは絶対を失うことによる世界崩壊への畏れ・おののきの深度をまったく共有できないと当時も思いましたし、いまでもそうです。
このご指摘については、二つのことを考えました。
①イワンは、一見悪魔的なことを言うように見えて、きわめて知性的・倫理的なキャラですね。アリョーシャの信仰があまりに初々しく素朴なので、それに対する近代的な懐疑を意識的に対置して、ギリシャ正教の風土における「神」問題の難しさ、ややこしさを喚起させたのだと思います。ドストエフスキーの緊張感ある内的な対話を聞く思いがします。
ところで、「大審問官」のくだりで印象的なシーンが二つあります。粗相をした幼女が親からウンチをなすり付けられてトイレに閉じ込められ、泣きながら「神ちゃま」と手を合わせるケースを取り上げて、「こんな神様なんか犬に食われろだ」とイワンが言う場面が一つ。もう一つは、異端糾問の盛んなセビリアにイエスがひそかに現われたのを大審問官が見破り、「お前は大衆というものを過大評価しすぎて彼らに自由を与えたつもりだが、彼らは自由よりはパンを欲するのだ。お前は余計なことをした」という意味のことを言ってイエスを非難し、イエスはそれに言葉では答えずただ接吻を返した、とありますね。
イワンは、簡単に言えば、「内面の自由」とか「絶対的理想」の象徴としての「神」と、現実の生活感情、欲求、慣習、道徳、情愛などのリアリティとを鋭く対置させて、そういう論理形式によって自分の悩みを表現していたのだと思います。そう考えると、文化的な違和感は多少あるかもしれないけれど、吉本さんが「関係の絶対性」なる観念の前で佇立(ちょりつ)したのと同じで、けっこう普遍的な思想テーマを突き出していると思うのですよ。
*「関係の絶対性」は、故吉本隆明氏の『マチウ書試論』にある言葉です。吉本思想に関心を持つ人たちの間で、とても有名な言葉でもあります。この、詩的直観に貫かれた言葉の意味については、論者の数だけの受けとめ方があるというよりほかはありません。差し当たり、倫理的な孤立を強いられた者が、自らの反逆の根拠を求めるうちに突き当たらざるをえない思想的難所を指し示す言葉であると申し上げておきます。私見によれば、近代日本で初めてそれに突き当たった存在は、二葉亭四迷『浮雲』の主人公文三です。(編者注)
②文化的な違和感の問題ですが、私は最近、親鸞をやっていて、つくづく思うのですが、鎌倉仏教、ことにひたすら称名念仏を勧める浄土教のそれは、限りなく一神教に近いという印象を持ちます。偶像崇拝に対する否定的な言及もあるし、依拠している、大乗仏典の浄土三部教のうち、ことに観無量寿経において浄土のすばらしいありさまを五感による想像力を駆使して絢爛と描き出したシーンに対しては、法然も親鸞もほとんどまったく興味を示していないのですね。阿弥陀様への深い信仰心だけが、唯一のよりどころです。私には、この絶対信仰のあり方は、イエス、ルター、カルヴァンなどと共通していると思えてなりません。
これは不思議といえば不思議で、というのは、遣唐使廃止以後の平安の世では、鎖国に近い状態が三百年も続き、あまり文化の東西交流が盛んな時代ではなかったにもかかわらず、その閉鎖的な日本で仏教が独自の発展を遂げ、その究極的な結果として末法思想の極限としての法然・親鸞の登場となったわけです。イエスの登場、原始キリスト教の成立と時を隔てること、およそ千年です。
で、何が言いたいかというと、橋爪・大澤両氏の『ふしぎなキリスト教』は、ことさら日本人の感性にとってユダヤ=キリスト教、イスラム教などがいかに「ふしぎ」に見えるかというその秘密を読み解くというところに主眼を置いた本ですが、いま私が述べたことを考慮に入れると、じつはそんなに「ふしぎ」ではなく、ちょうどヨーロッパに発したとされる「近代文明」なるものが、今では全世界に広がって(たとえば公式的な場面でのスーツ、椅子、テーブル)、どこでも同じような方向に向かっているのと同じように、この東西共通の現象には、一種の歴史的必然のようなものがあるのではないか、ということです。その心は、と問われるなら、一応、ヘーゲルの言う「人間はみな自由を求め、それを現実化していく存在だ」という本質規定に求められるのではないでしょうか。こう考えると、先の貴兄の、イワンの悩みに対する違和感、西洋の言語文化に対する壁や断絶感(もちろん、私もそれを共有していますよ)も、多少は減殺されるのではないでしょうか。
言語の問題について。
> ちょっとずれますが、語源って、本当に興味深いと思います。
そのとおりですね。これに続く、「いかづち」の解釈、とてもおもしろいですね。これを読んで、柳田がけっこうこの種のことをやっていたのを思い出しました。彼が指摘していたのでおぼえているのは、「柵(さく)」「迫(さこ)」「境(さかい)」などが、村のはずれの極まったところ、テリトリーの内側と外側を隔てるところ、という概念で共通しているという例です。これらは、地名、人名などにも反映しています。長野県に佐久という土地がありますね。境港、大阪府堺市などもたぶん同じでしょう。
考古学的な根拠はありませんが、私が思いつきで引いてきた例に、「話す」「離す」「放つ」は、語源的に同じではないかということ、「語る」と「騙る」は両者相まって言語の本質を言い当てているのではないかということ、また、これはまだ言っていませんが、「音」「訪れる」は、もともと同じ概念ではないかということ、などです。
こう考えてくると、「辞」にかぎらず、「詞」においても、古代人の生活感情からして共通していると感じられた概念には共通の音韻を当てた、ということもかなりの程度で言えそうな感じがしてきますね。ただ、この種の問題に興味を持ち出すと、前にも書きましたが、怠け者で教養のない私としては、なんだか途方もないことに手をつけてしまうような気がして、正直、げんなり、です(笑)。
今日は、このくらいで。
*****
美津島明さま
ブログエントリー42と43、(「非ケインズ効果」についての議論―編者注)読みました。前回のお返事を待たずに、もう一つ送ります。
いやいや、美津島さんの敵たちの飛躍した論理(没論理)、ひどいものですね。特に、国民が政府の財政危機を本気で心配しているとか、増税によって長い目で見れば景気は回復するなどといった滅茶苦茶な展開、どうしようもないですね。
政府、財務省、日銀は、言ってみれば貸主をだまして借金を踏み倒そうとしている狡猾な借主と同じで、詐欺師や泥棒の手口と変わらないと言っても過言ではありませんね。彼らのフトコロ事情を、どうして貸主である一般国民が心配してやらなくてはならないのでしょう。
この人たちの最大の問題は簡単なことで、要するに、普通の国民の生活意識、生活感覚に対する想像力をまったく喪失しているということでしょう。でも経済学って、本来、国民一人ひとりの生活を豊かにするにはどうすればよいか、という問題意識から生まれた学問ですよね。それが権力村に媚びるだけのこんなていたらくでは、ほんとうに学問の名が泣きますね。
経済言論界における逆境にめげず、がんばってください。味方も少しずつ増えていると思います。三橋貴明さんが、貴兄が引用されているのと同じ趣旨の新刊を出したようですね。
『日本は「国債破綻」しない! ソブリンリスクとデフレ経済の行方』実業之日本社
お久しぶりです。
今日やっと『大前研一トンデモ「デフレ」理論』をアップできました。一回のアップ文字数が1万字までなので、2回に分けてアップしました。
*『大前研一トンデモ「デフレ」理論』の原稿書きのために時間が取られているので、メールの返事が一週間ほど遅れることを小浜氏に伝えていました。
分量が膨大で、細い話も出てくるし、みなさんが読んでくれるのか心配していたところ取りあえずアップ当日に900弱のアクセスがあり、ホッとしています。ツイッターにいろいろと反響の言葉も寄せられていて、ささやかながら喜びをかみしめています。しかし、喜んでばかりもいられません。非合理的な経済政策のありさまは変わっていないのですから。
さて、小浜さんの前回のメールについて思いつくままに述べます。
ちょっと前のことですが、大森荘蔵におけるデカルト的二分法ののり超えの試みのまずい点についての、小浜さんのお話、印象深く残っています。
小浜さんの言葉を、私なりに言いかえると次のようになります。
人は実存において主客の交流する形容詞的な世界像を生きている。そこから、分析的に主観と客観とが析出されることにもなる。また、主語が析出されることにもなる。そのことには一定の有効性・レーゾンデートル(存在理由の意―編者注)がある。かといってその二分法を絶対的な真理とするのはおかしい。そのリゴリズム(過剰な厳格主義の意―編者注)から、世界観の硬直化・貧困化が生じることになるからである。見上げた青空が美しいと感じるとき、その美を、私の主観に還元するのは誤っている。世界はもっと豊かな相貌をしているはずだから。他方、大森氏のように主観=心を客観=物にそっくりそのまま投げ出そうとするのも、物に神性を見出そうとする感性を保持する日本人としてその気持ちを分からなくもないが、哲学的には同じく誤っている。
短歌を読み味わうということは、人が本当のところどのようにこころを世界に開いて(あるいは閉じて)生を織り成しているのかを内側からやわらかく辿りなおすプロセスなのではなかろうか。一級の感性の痕跡としての名歌には、そのような実存が凝縮された形でありありと表出されている。だから、それに大真面目になって取り組むことには、文学的な価値はもちろんのこととして、思想的な価値もある。
さらに、哲学的な価値も、と言いたいところですが、私には荷が重すぎるので、ここは代わりに小浜さんに「そうだ」と言ってほしいところです。
そんな感じになります。私にかろうじてできるのは、小浜さんの、主客二分法を真ん中で超えようとする思想的・哲学的な展開を、主に文学の側から重ね描きすることなのではないかと思います。
思想的な構えの核心のところで、私は小浜さんから大きな影響を受けていることを再認識しました。ここから、自分なりのパロール(個性的な語りの意―編者注)をどう展開するのかが今後の私の課題、ということになるのでしょう。まあ、いい年なのであまり悠長なことも言ってられないのですが。
〉厳密に言えば、貴兄の今回の論は、「日本人の感性は素晴らしく、微妙で独特であり、そう簡単にガイジンなどにわかるはずがない、わかってもらっては困る」と言いたい気持ちと、「私たちはそれでも、よりよい訳、よりよい批評などを目ざしているところから見て、究極的な理想として、分かり合えるはずだ」という理念との両面を唱えていることになると思います。論理的にはこれは矛盾するのでは?
まったくそのとおりであると思います。一方では、普遍性への志向性を、表現に向かおうとする自分に確かに感じるのですが、他方では、日本人の感性が素晴らしい云々ということよりも、欧米人が抜きがたく抱えている(ように感じられる)「絶対的なもの」への激しい志向性に対する違和感と、助詞・助動詞に代表される日本語のニュアンスが結局は欧米人に伝わらないのではないかという断絶感とがあります。
後者については前回申し上げたので、今回は前者(すなわち、欧米人が抜きがたく抱えている「絶対的なもの」への激しい志向性に対する違和感―編者注)について述べます。
私は若い頃に、文学青年にありがちなことなのですが、ドストエフスキーにのめり込んでいた一時期があります。倫理的な思想に基づいて老婆を殺したラスコーリニコフが、かえって倫理問題について不器用に執拗に悩むことになり、結局は頭を抱え込んできりきり舞になって一少女に跪(ひざまづ)いてしまう姿に共感を覚えたりはしたのですが、それとは逆にどうしても分からなかったことがありました。
確か『カラマーゾフの兄弟』のイワンが大審問官のところで「神がいなければすべてが許される」というテーゼを提示し、それについて深く思い悩む自分の姿をアリョーシャに晒しますね。
イワンの悩みは、理屈ではそれなりに分かるような気がするのです。でも、神という唯一神あるいは絶対を失うことによる世界崩壊への畏れ・おののきの深度をまったく共有できないと当時も思いましたし、いまでもそうです。
とはいうものの、他方では、表現するという行為そのものに、時代や民族の違いを超えた普遍への志向性が不可避的に織り込まれているとも考えているのです。特に、良い音楽を聞いたときにそれを強烈に感じます。
むろん私は、文字表現の普遍性をも信じます。信じようとしています。しかし、ときどきどうしようもない壁や断絶を感じることがある、ということです。これは、未だにあまりうまく処理できていないことです。
「批評の基準」についていま思うのは、洋の東西を問わず、優れたエコノミストについて語っているとき、私は、文芸批評を展開している面白さとほとんど同じものを感じているということです。文学者とエコノミストでは世界を写し取り、切り取るツールが違うのはもちろんです。
しかし、優れたエコノミストには、強烈で魅力的な個性があります。それが、こまかい経済学的な「さかしら」を伸びやかにのりこえて、彼らが経済の言葉で世界を語り、自己を語る哲人あるいは表現者の面持ちに近づいてくる源になっているように感じています。経済エッセーについては、もっともっと書き込んで、予備知識抜きでも読み手が楽しめるようなものを書けたらなと思っています。
市民化された経済学。これって、一般国民が主権を本気で担おうとすれば必要になってくるものですね。その課題を自分の力の及ぶ分だけでも担うことができれば、といささかなりと思いはじめています。まずは、自分がちゃんと経済の基本を分かっていることが最低基準ですね。ブログで私見を公開する気持ちには、誤った認識があればそれを読み手に率直に正してほしい、ということもあるのです。
〉欧米圏の生活意識と言語との関係に精通しているわけではない私たちには、そもそも公平な比較というのは不可能なのではないでしょうか。そのことも押さえておく必要があると思うのです。
おっしゃる通りです。ここを見過ごすと異文化についてバランスの悪いことを言ってしまいそうですね。適切なアドバイスとして受けとめます。
日本語の特性のご指摘については、特に⑤にはっとさせられました。
〉⑤またまた関連するのですが、「辞」に関するかぎり、いろいろと品詞分類がなされてはいるものの、音韻が同じならばそこに込められた生活感情、生活思想はアルカイックな時代では同じだったのではないか
助詞にはそれぞれ、おそらくもともとのなにか核になるような意味合いがあるのでしょう。それをつきつめると面白いことになるような気がします。なんとなくですが、身体性に深く関わる生活感情・宗教感情・宇宙感覚に根ざしているものが多いのではないかと感じます。
ちょっとずれますが、語源って、本当に興味深いと思います。
たとえば、「いかづち」。「いか」は「いかつい」「いかめしい」の「いか」に通じているようで、形容詞「厳し」の語幹だそうです。「づ」は助詞の「つ」で、「ち」は、「おろち(大蛇)」「みなち(水霊)」「つち(土)」「ち(血)」の「ち」と同じく人並み外れた過剰な生命力・霊力を意味するそうです。漢字を当てれば「厳つ霊」となるとのこと。つまり、畏怖・敬服の念を起こさせるスーパー・パワーの意で、大蛇とか神様とかをばくぜんと指していたのが、後に、雷を特に指す言葉になったそうです。これは、むかし塾を経営していたときに雇っていた女の先生が国文学出身で、万葉集の話をしているときに教えてくれたことです。古代の人々の生活感情を垣間見る思いがしませんか。雷はおそらく「神(あるいは上)鳴り」で、その読み方に古代の痕跡を留めているのではないでしょうか。
とりとめもないのですが、今日はこんなところで。
*****
シリーズの10回目です。これでとりあえず終了です。小浜逸郎氏には、内容の確認・精査で多大のお手数をおかけしました。ありがとうござます。また、あまり一般的とは言えないテーマに最後までおつきあいいただいた皆様には心から感謝申し上げます。
しばらく時勢と一定の距離を置いて、小浜氏との対話に心静かに没頭しました。これからまた、喧騒の渦巻く「娑婆」に戻って、声の続く限り咆哮しようと思っています。なにせ、もともとブログ名が「オレにも言わせろ」というお世辞にも上品とは言えないものですから。らしく、しなくちゃね。
☆☆☆☆☆
美津島明様
「大前研一批判」、読みました。ただただ感嘆いたしました。エネルギーとスピードがすごいですね。とはいえ、やはり私の経済音痴は克服できないので、前半に関しては美津島さんの論理についていくのがやっとです。自分で見破ってみろと言われたら、たぶんできないと思います(だまされてしまいそうです)。
ただ、後半の大前のひどさについては、私でもわかりました。要するに彼は「デフレ不況」の状況認識を同語反復しているに過ぎないのに、あたかも正当な因果関係論理であるかのように偽装しているということですよね。そうして「少子化」などという受け狙いの「自然現象」を、何の根拠もなく飛躍した「原因」として持ってきて、説得力があるかのように大衆を欺瞞している、ということだと思います。
ひとつ、緊急時には、マクロ経済を動かすことが唯一可能な中央集権(時には独裁)こそが必要とされるのだ、という理念的な正当性は十分理解できるのですが、そういう正論をきちんと理解し、実行にまでもっていける政権担当者や優秀な官僚の出現をいまの日本で期待できるのか、という点で、国民は絶望感と不安を深めており、まさにそのために、大前や橋下のようなインチキ野郎たちに付け込む隙を与えてしまっていると思うのですが、この点についてはいかがでしょうか。
いやいや、この質問が美津島さんの現在の闘志に冷水を浴びせることになるのではないかと恐れます。無視していただいてけっこうです。
それにしても、美津島さんのこの間の仕事は一級の価値があると、私は身びいき抜きで思っているので、何とか「本」の形で報われるといいですね。これまで出版社四社の編集者に紹介はしているのですが(みな消費税増税反対論者です)、まだお声はかかりませんか(笑)。でも、私などが動いても限界があります。これだけ力のある論考なら、編集者の誰かが必ずマークしているはずで、もしそうでないなら、編集者全体が衰弱している証拠でもあります。切ない状況ですね。
「ブログ異論」のやり取りに関しては、さっそくに誠実なお返事を頂き、恐縮です。大森荘蔵に対する私の批判をよくご理解いただき、しかも的確に、手際よくまとめてまでくださるとは。
大森については、じつはもっと根本的な批判をしており、言哲で彼を紹介した折にはけっこうイカレていた部分もあったのですが、よくよく読んでみた後のいまの時点では、7:3くらいの割合で、この人はダメだなと思っています。いわゆる「哲学者」特有の視野の狭さを示しており、また、戦後思想の限界も露出しているようです。彼の「心」論などは、すでに60年も前に和辻が、まるで事態を予見していたかのように、完膚なきまでに粉砕しているのです。この事実は、戦後思想家、丸山、吉本、大森と、戦前の思想家、和辻、小林、時枝を比較した場合、戦前のほうがずっと優れていた、という残念な結果として現われています(というのは、まあ、私個人の恣意的な評価ですが)。
この評価が正しいとすると、そこにはどうも社会状況的な理由がありそうです。それについてはそんなにきちんと考えていないので、また機会を改めて。
今回、言葉の問題について、いろいろと有意義な示唆を与えていただいたのですが、それについてお返しをしていると、また相当時間をかけなくてはならないので(それは私にとっても必要なことでもありますから、煩をいとうているわけではありません)、少々待っていただいて、続編を送ります。
*****
小浜逸郎様
ご返事ありがとうござます。追加がおありとのことですが、とりあえず返信いたします。
〉前半に関しては美津島さんの論理についていくのがやっとです。自分で見破ってみろと言われたら、たぶんできないと思います(だまされてしまいそうです)。
これは、けっこうショックでした。プロの読み手の小浜さんに苦労をかけてしまうような読み物だったら、一般人には到底無理、ということになるでしょう。「市民のための経済学」などとブチ上げておいて、情けないこと限りない。
まだまだ、経済について分かっていないことが多いのでしょう。分かっていないから、読む人に負担をかけてしまうのでしょう。本当に分かっている人は、アダム・スミスのようにごく平易な言葉使いで世界の見方をひっくり返してしまいますね。
私には、分かっていないことを分かっていないと認めるだけの率直さがまだ残っていますから、できうるかぎり善処いたします。ご指摘、ありがとうございます。
〉ただ、後半の大前のひどさについては、私でもわかりました。要するに彼は「デフレ不況」の状況認識を同語反復しているに過ぎないのに、あたかも正当な因果関係論理であるかのように偽装しているということですよね。そうして「少子化」などという受け狙いの「自然現象」を、何の根拠もなく飛躍した「原因」として持ってきて、説得力があるかのように大衆を欺瞞している、ということだと思います。
おっしゃるとおりです。これだけ明晰に批判の論点を整理していただけると助かります。もし、大前氏が大真面目にこんな論理の破綻したことを堂々と自信を持って言っているのであれば、彼は普通の意味で頭が良くない人であることになってしまいます。もし、ワザと論理のめちゃくちゃな論を世に垂れ流して一定の効果が生じるのを期しているのであれば、悪質なソフィストと言えるでしょう。どちらが正しくても、彼のデフレ論は殲滅されなければなりません。影響が大きすぎるので。
〉ひとつ、緊急時には、マクロ経済を動かすことが唯一可能な中央集権(時には独裁)こそが必要とされるのだ、という理念的な正当性は十分理解できるのですが、そういう正論をきちんと理解し、実行にまでもっていける政権担当者や優秀な官僚の出現をいまの日本で期待できるのか、という点で、国民は絶望感と不安を深めており、まさにそのために、大前や橋下のようなインチキ野郎たちに付け込む隙を与えてしまっていると思うのですが、この点についてはいかがでしょうか。
私は、そういう人が現に少なからずいるのではないかと思っています。国会議員さんの中に(民主党の中においてさえも)、そういう人は散見されます。名前を挙げると、私が知っているだけでも、民主党系では馬淵澄夫、金子洋一、宮崎岳志、松原仁(心意気を買って)、長妻元厚労省相(リターンマッチの情念を期待して)、新潟県の泉田知事(とても賢い人です)、自民党系では、森まさこ、西田昌司、山谷えり子、稲田朋美、高市早苗、林芳正、共産党では佐々木憲昭、たちあがれ日本では平沼さんと園田さん(いずれも年を食っていますが)などそうそうたるメンバーがそろっています。ただし、彼らにはいまのところ実権がまったくない。それこそが問題ですね。彼らの周りには、想像ですが、良質な官僚たちが集っているはずです。だから、世論の援護射撃が必要なのではないかと思っています。良き世論の形成は、まともな知識人の仕事のうちとても大切なものですね。
〉それにしても、美津島さんのこの間の仕事は一級の価値があると、私は身びいき抜きで思っているので、何とか「本」の形で報われるといいですね。これまで出版社四社ほどに紹介はしているのですが(みな消費税増税反対論者です)、まだお声はかかりませんか(笑)。でも、私などが動いても限界があります。これだけ力のある論考なら、編集者の誰かが必ずマークしているはずです。
そこまでしていただいているとは。言葉もないくらいに感謝します。出版の話があればそれはもちろん掛け値なしに嬉しいです。けれども、それがなくてもこのブログはやり続けようと思っています。小浜さんのように声援していただける方がいらっしゃるので、心強いこと限りない思いです。
〉この事実は、戦後思想家、丸山、吉本、大森と、戦前の思想家、和辻、小林、時枝を比較した場合、戦前のほうがずっと優れていた、という残念な結果として現われています(というのは、まあ、私個人の恣意的な評価ですが)。この評価が正しいとすると、そこにはどうも社会状況的な理由がありそうです。それについてはそんなにきちんと考えていないので、また機会を改めて。
これは、日本思想のとてつもなく大きな問題であるような気がします。戦後思想の「思い込み」を木っ端微塵にしてしまうとてつもない知的「暴力」を感じます。このことと、「戦後日本の唯一の達成は、人命尊重のヒューマ二ズムが一般国民において根付いたこと」という、私が小浜さんと共有している戦後評価とはメダルの表と裏のように感じています。
言葉の問題については、小浜さんからの追伸があるとのことなので、今回は触れない方がいいようですね。
*****
美津島明さま
まず、私が、美津島さんの論理についていくのがやっとだった、と申し上げたことについて。
> これは、けっこうショックでした。プロの読み手の小浜さんに苦労をかけてしまう ような読み物だったら、一般人には到底無理、ということになるでしょう。「市民のための経済学」などとブチ上げておいて、情けないこと限りない。
プロの読み手、と評価してくださることはありがたいのですが、こと経済に関しては、基礎もわかっていない本当にダメな読み手なのですよ。なんとケインズもほとんど読んでないので、あきれた読み手でしょう。単純にそういう私固有の理由で苦戦したということなので、書き手である美津島さんがそんなに謙虚にならなくていいと思いますよ。貴兄は、これまでの論考で、田村秀男さんの論理を援用しつつ、やさしくわかりやすく、繰り返し繰り返し噛み砕き、しかも面白く書いてくださっているので、デフレ時の増税がいかに国際常識、経済学の常識にも背反するナンセンスであるかについては、十分理解できているつもりです。
> もし、大前氏が大真面目にこんな論理の破綻したことを堂々と自信を持って言っているのであれば、彼は普通の意味で頭が良くない人であることになってしまいます。もし、ワザと論理のめちゃくちゃな論を世に垂れ流して一定の効果が生じるのを期しているのであれば、悪質なソフィストと言えるでしょう。どちらが正しくても、彼のデフレ論は殲滅されなければ なりません。影響が大きすぎるので。
これはどちらかと問われれば、やっぱり前者なのではないかな、と思います。ことほどさように、心理が同時多元的に作用する経済という魔界に、論理の楔を打ち込むのは、けっこう難しいのではないでしょうか(音痴の自分を自己正当化しているみたいですが(笑))。
現実に切り込むための人間の論理の道具というのは、「因果関係論理」と「二元論」と、二元論の克服としての(やや怪しげな)「弁証法」くらいしかない。ことに現在のような金融資本が主役で、その動きが実体経済と遊離してしまっている時代になると、何を「因」として押さえれば適切な分析となるのかは、私などにはお手上げです。専門家であるはずの経済学者たちの結論も、ずいぶん前からバラバラですよね。
で、この問題(何をポイントとして重要視すべきか)は、この魔界に究極的な「真理」の力学が隠れているというよりは、むしろ新しい経済思想を創造するという問題なのではないか、と、素人の私などは考えてしまいます。つまり、「価値自由の法則」を貫く分析などはありえず、分析がそのまま、一つの価値観、思想の提示になるのではないか、と。
美津島さんもおそらくその線に沿って論を展開されていると思います。前回の、「市民化された経済学」の創出に闘志を燃やす文面にも、今回のメールにもその気迫を感じましたので、どうぞ私の水差しなど気にせずに突き進んでください。わかる人にはちゃんとわかるように書かれていると思います。
ただ、経済となると、やはり「音痴」が多いのも事実で、みんな理解(創造的理解)を諦めているようで、だからこそ「専門家」と称する百鬼夜行の世界になってしまうのですね。こういう世界で鬼たちをなぎ払い、説得力ある論理、理論を打ち立てるのは、さぞかしたいへんだろうなと推察いたします。それでもがんばっている美津島さんの情熱と心意気に改めて心から声援を送ります。
中央権力を、責任をもって担いうる人がいるのかという問題について。
> 私は、そういう人が現に少なからずいるのではないかと思っています。ただし、彼らにはいまのところ実権がまったくない。 それこそが問題ですね。彼らの周りには、想像ですが、良質な官僚たちが集っているはずです。 だから、世論の援護射撃が必要なのではないかと思っています。 良き世論の形成は、まともな知識人の仕事のうちとても大切なものですね。
まったくそのとおりですね。こういう大切な原則を再認識させてくれたことに関して、とても心強いものを感じます。加えて、貴兄がよく政治家の言論を調べているのに感心しました。
蛇足ですが、今日たまたまラジオで国会質疑を聞いていて、どうも自民党の心ある議員たちは、「消費税増税」が悪政であり、財政再建よりも景気刺激策のほうがはるかに喫緊の課題だということにうすうす気づき始めているのではないか、という印象を持ちました(ただし、増税が税収入の増加に繋がらないという肝心な点を質疑で公然と指摘する人は誰もいないようです)。といって、自民党全体でいまさら増税路線を引っ込めることはできないので、この党はジレンマに陥っている感じです。
戦前の思想家のほうが優れているという私の指摘について。
> これは、日本思想のとてつもなく大きな問題であるような気がします。このことと、「戦後日本の唯一の達成は、人命尊重のヒューマ二ズムが一般国民において根付いたこと」という、私が小浜さんと共有している戦後評価とはメダルの表と裏のように感じています。
これもそのとおりですね。ここはとても考えどころのような気がします。粗雑な類推ですが、苛酷な帝政ロシアで、世界最高水準の文学が生まれましたね。戦後の冷戦下の日本では、一人ひとりは必死にがんばっては来たのだが、無意識のうちにその大局的な構造に安住して(東か西か、左か右かのどちらかに依存して)、本当の創造性が殺がれてしまい、ついに混乱、中途半端、矛盾した思想しか生み得なかったのではないか、と、そんなふうに思います。ここに、敗北の後遺症としての生命価値の過剰な(と、今回はあえて言いますが)尊重という傾向も絡んできますよね。
この間話し合ってきたことと矛盾するようですが、艱難、汝を玉にす、とか、家貧にして孝子いづ、というようなことが、ある特定社会の内部でも一定程度までは成り立つような気がするのですが(あくまで、これは比喩としてです)。もっとも、北朝鮮で優秀な思想が生まれつつあるとはとても思えませんが(笑)。
さて、たまたまロシア文学に触れたところで、先の貴兄の問題意識の一つにうまく接触できたようです。
> 確か『カラマーゾフの兄弟』のイワンが大審問官のところで「神がいなければすべてが許される」というテーゼを提示し、それについて深く思い悩む自分の姿をアリョーシャに晒しますね。イワンの悩みは、理屈ではそれなりに分かるような気がするのですよ。でも、神という唯一神あるいは絶対を失うことによる世界崩壊への畏れ・おののきの深度をまったく共有できないと当時も思いましたし、いまでもそうです。
このご指摘については、二つのことを考えました。
①イワンは、一見悪魔的なことを言うように見えて、きわめて知性的・倫理的なキャラですね。アリョーシャの信仰があまりに初々しく素朴なので、それに対する近代的な懐疑を意識的に対置して、ギリシャ正教の風土における「神」問題の難しさ、ややこしさを喚起させたのだと思います。ドストエフスキーの緊張感ある内的な対話を聞く思いがします。
ところで、「大審問官」のくだりで印象的なシーンが二つあります。粗相をした幼女が親からウンチをなすり付けられてトイレに閉じ込められ、泣きながら「神ちゃま」と手を合わせるケースを取り上げて、「こんな神様なんか犬に食われろだ」とイワンが言う場面が一つ。もう一つは、異端糾問の盛んなセビリアにイエスがひそかに現われたのを大審問官が見破り、「お前は大衆というものを過大評価しすぎて彼らに自由を与えたつもりだが、彼らは自由よりはパンを欲するのだ。お前は余計なことをした」という意味のことを言ってイエスを非難し、イエスはそれに言葉では答えずただ接吻を返した、とありますね。
イワンは、簡単に言えば、「内面の自由」とか「絶対的理想」の象徴としての「神」と、現実の生活感情、欲求、慣習、道徳、情愛などのリアリティとを鋭く対置させて、そういう論理形式によって自分の悩みを表現していたのだと思います。そう考えると、文化的な違和感は多少あるかもしれないけれど、吉本さんが「関係の絶対性」なる観念の前で佇立(ちょりつ)したのと同じで、けっこう普遍的な思想テーマを突き出していると思うのですよ。
*「関係の絶対性」は、故吉本隆明氏の『マチウ書試論』にある言葉です。吉本思想に関心を持つ人たちの間で、とても有名な言葉でもあります。この、詩的直観に貫かれた言葉の意味については、論者の数だけの受けとめ方があるというよりほかはありません。差し当たり、倫理的な孤立を強いられた者が、自らの反逆の根拠を求めるうちに突き当たらざるをえない思想的難所を指し示す言葉であると申し上げておきます。私見によれば、近代日本で初めてそれに突き当たった存在は、二葉亭四迷『浮雲』の主人公文三です。(編者注)
②文化的な違和感の問題ですが、私は最近、親鸞をやっていて、つくづく思うのですが、鎌倉仏教、ことにひたすら称名念仏を勧める浄土教のそれは、限りなく一神教に近いという印象を持ちます。偶像崇拝に対する否定的な言及もあるし、依拠している、大乗仏典の浄土三部教のうち、ことに観無量寿経において浄土のすばらしいありさまを五感による想像力を駆使して絢爛と描き出したシーンに対しては、法然も親鸞もほとんどまったく興味を示していないのですね。阿弥陀様への深い信仰心だけが、唯一のよりどころです。私には、この絶対信仰のあり方は、イエス、ルター、カルヴァンなどと共通していると思えてなりません。
これは不思議といえば不思議で、というのは、遣唐使廃止以後の平安の世では、鎖国に近い状態が三百年も続き、あまり文化の東西交流が盛んな時代ではなかったにもかかわらず、その閉鎖的な日本で仏教が独自の発展を遂げ、その究極的な結果として末法思想の極限としての法然・親鸞の登場となったわけです。イエスの登場、原始キリスト教の成立と時を隔てること、およそ千年です。
で、何が言いたいかというと、橋爪・大澤両氏の『ふしぎなキリスト教』は、ことさら日本人の感性にとってユダヤ=キリスト教、イスラム教などがいかに「ふしぎ」に見えるかというその秘密を読み解くというところに主眼を置いた本ですが、いま私が述べたことを考慮に入れると、じつはそんなに「ふしぎ」ではなく、ちょうどヨーロッパに発したとされる「近代文明」なるものが、今では全世界に広がって(たとえば公式的な場面でのスーツ、椅子、テーブル)、どこでも同じような方向に向かっているのと同じように、この東西共通の現象には、一種の歴史的必然のようなものがあるのではないか、ということです。その心は、と問われるなら、一応、ヘーゲルの言う「人間はみな自由を求め、それを現実化していく存在だ」という本質規定に求められるのではないでしょうか。こう考えると、先の貴兄の、イワンの悩みに対する違和感、西洋の言語文化に対する壁や断絶感(もちろん、私もそれを共有していますよ)も、多少は減殺されるのではないでしょうか。
言語の問題について。
> ちょっとずれますが、語源って、本当に興味深いと思います。
そのとおりですね。これに続く、「いかづち」の解釈、とてもおもしろいですね。これを読んで、柳田がけっこうこの種のことをやっていたのを思い出しました。彼が指摘していたのでおぼえているのは、「柵(さく)」「迫(さこ)」「境(さかい)」などが、村のはずれの極まったところ、テリトリーの内側と外側を隔てるところ、という概念で共通しているという例です。これらは、地名、人名などにも反映しています。長野県に佐久という土地がありますね。境港、大阪府堺市などもたぶん同じでしょう。
考古学的な根拠はありませんが、私が思いつきで引いてきた例に、「話す」「離す」「放つ」は、語源的に同じではないかということ、「語る」と「騙る」は両者相まって言語の本質を言い当てているのではないかということ、また、これはまだ言っていませんが、「音」「訪れる」は、もともと同じ概念ではないかということ、などです。
こう考えてくると、「辞」にかぎらず、「詞」においても、古代人の生活感情からして共通していると感じられた概念には共通の音韻を当てた、ということもかなりの程度で言えそうな感じがしてきますね。ただ、この種の問題に興味を持ち出すと、前にも書きましたが、怠け者で教養のない私としては、なんだか途方もないことに手をつけてしまうような気がして、正直、げんなり、です(笑)。
今日は、このくらいで。
*****
美津島明さま
ブログエントリー42と43、(「非ケインズ効果」についての議論―編者注)読みました。前回のお返事を待たずに、もう一つ送ります。
いやいや、美津島さんの敵たちの飛躍した論理(没論理)、ひどいものですね。特に、国民が政府の財政危機を本気で心配しているとか、増税によって長い目で見れば景気は回復するなどといった滅茶苦茶な展開、どうしようもないですね。
政府、財務省、日銀は、言ってみれば貸主をだまして借金を踏み倒そうとしている狡猾な借主と同じで、詐欺師や泥棒の手口と変わらないと言っても過言ではありませんね。彼らのフトコロ事情を、どうして貸主である一般国民が心配してやらなくてはならないのでしょう。
この人たちの最大の問題は簡単なことで、要するに、普通の国民の生活意識、生活感覚に対する想像力をまったく喪失しているということでしょう。でも経済学って、本来、国民一人ひとりの生活を豊かにするにはどうすればよいか、という問題意識から生まれた学問ですよね。それが権力村に媚びるだけのこんなていたらくでは、ほんとうに学問の名が泣きますね。
経済言論界における逆境にめげず、がんばってください。味方も少しずつ増えていると思います。三橋貴明さんが、貴兄が引用されているのと同じ趣旨の新刊を出したようですね。
『日本は「国債破綻」しない! ソブリンリスクとデフレ経済の行方』実業之日本社












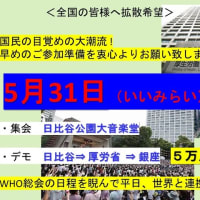














※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます