当ブログにたびたびコメントをいただいている由紀草一氏から、次のようなメールをいただきました。
『週間文春』の12月6日号が、反安倍特集をしたのをご存じですか。ここに出ていた議論のうち、経済問題について、美津島さんに、反論をお願いしたいのです。ご迷惑なら、もとより強要はできません(迷惑だなんて、とんでもありませんーブログ主人)。
もっとも、この同じ『週刊文春』の連載エッセイ「宮崎哲弥の時々砲弾」には、「私は阿倍晋三総裁率いる自由民主党の政策を全面的に支持しているわけではない。しかしその金融政策論は大筋で間違っていない」とありまして、結果として「両論併記」になっているのですが。まあ目立つところにあるのは安倍金融政策批判で、この立場の論はほぼ出そろっているのではないかと思います。
以下に煩を厭わず、動員された言論人の言葉を引用します。引用はすべて、P.27~28の、「主婦・年金生活者直撃 安倍不況がやって来る」からです。
で、週刊文春に動員された言論人の発言は以下の通りです。通し番号は、私が便宜上つけたものです。①~⑦の論者の一行紹介は由紀草一氏によるものです。
①大手銀行アナリスト(誰だ?)の言葉。全体のリードとして。
安倍氏の経済政策に関する発言には、二つの問題があります。まず言う通りインフレターゲットが達成できるのか。仮に、達成できたとしても日本経済が壊滅的な打撃を受ける。どちらにもせよ、この経済政策が“安倍総理”の致命傷になるでしょう。
②小幡績慶大大学院準教授による、インフレターゲットが達成された場合の悲観的な見通し。
投資家は、資産を現金からインフレに強い不動産や株式に移すので、地価や株価が上昇する「資産インフレ」が起こります。例えば、持ち家の人はウハウハでしょうが、賃貸の人は大変です。家賃は上がるが賃金は上がりませんから。貧富の格差が拡大するでしょう。
③経済ジャーナリスト荻原博子による、同じく悲観的な見通し。
インフレは、物価と同じように賃金も上がらなければ、増税と一緒です。ただ国際競争が激しい経済情勢で物価と同じように賃金を上げられるかと言えば、かなり難しいでしょう。また年金も物価と同じようには上がりません。派遣で働く人たちや、年金生活者などは大きな打撃を受けます。
安倍さんが総理だった06年から07年は、いざなぎ景気を超える戦後最長の景気拡大期間で、富裕層は好況でしたが、民間給与は下がりっぱなしでした。この十年で平均給与は四十万円も減っています。給料に跳ね返らない景気回復が、前回と同じように起こるかもしれません。
④荻原博子による、円安危惧論。
これまでは、円高で輸入物資が安く入ってくるから、生活が助かっていた面もあります。今年、アメリカは五十六年ぶりの大干ばつで、小麦や大豆などの穀物の値段が上がっている。円安になれば、当然高くなります。
⑤藻谷浩介日本総研主席研究員による、同じく円安危惧論。
安倍さんには経済の現実が見えていない。いま日本の貿易収支は赤字ですが、原因は円高による輸出減ではなく、原油・ガス価格の上昇による輸入増です。円安になれば、この赤字が拡大します。過度の金融緩和で国債金利が上がれば、国債の価格が下がり、銀行や年金基金は大幅な評価損を抱えます。国債や年金、さらには政府財政の破綻へとつながる政策を、自民党総裁が主張しているのです。日本のメルトダウンも極まったと思いました。
⑥市場関係者(また誰だかわからない)による株価上昇懐疑論
上げの要因は外資系の資金。ヘッジファンドにとって変化はビジネスチャンスですから、日本に資金を投じています。ただ、彼らは選挙を利用して煽るだけ煽って、自民党政権が誕生した瞬間に売りに転じて株価は急落するとの見方がある。この株価は、実体経済には反映されないと見ています。
⑦最初のアナリスト(だから誰だよ)による締めの言葉。
安倍氏の経済政策をそのまま実行することは、日本国民をモルモットにした壮大な社会実験です。うまくいく可能性もゼロとは言いませんが、失敗する確率の方が圧倒的に高く、またその代償、国債暴落やハイパーインフレは日本を壊滅させる。リターンに比して、リスクが大きすぎるのです。
この記事に名を連ねた経済学者やエコノミストの名を、みなさん、よく覚えておいてください。彼らはみな不純な動機で一般国民をたぶらかすデマ・ゴークです。その理由を、①~⑦までを順に取り上げることで説明しましょう。
まず、①から。この人本当に「大手銀行アナリスト」なんでしょうか。「インフレターゲットが達成できるのか」なんて言っていますけれど、インフレターゲット政策(以下、インタゲ政策と略称)は、すでに先進国をふくむ世界27カ国で実施されている、ごく常識的な経済政策です。この場合、ユーロ圏17カ国は一国としてカウントしています。だから、実質世界の46カ国がこの政策を実施していることになります。先進国でインタゲを実施していないのは、なんと日本だけなのです。それは、デフレを堅持したいからとしか思えないという切り口で日本の経済政策(この場合、金融政策の主体としての日銀)の異常さを指摘する論者は、良質なメディアにはゴマンといます。一般国民に知らされていないだけのことです。それゆえ(当ブログでたびたび指摘してきたことですが)、ごく平均的な日本人の間で、「政府・日銀は、適切な経済政策によって、物価水準をコントロールできる」という考え方が常識になっていないという情けない事態を招いているのです。だから、この論者のように「仮に、達成できたとしても日本経済が壊滅的な打撃を受ける」というコケおどしが効くと思い込むことができるのです。残念なことですが、日本人は、経済現象を自然現象として受けとめる段階にとどまっています。その意味で、その経済感覚は、縄文人レベルと言わざるをえません。それをこの論者は(すなわち文春は)啓蒙するのではなく、悪用しているフシがあります。罪深い所業です。天罰が当たってもちっとも不思議ではありません。
次に②。小幡績(おばたせき)氏は、1992年に東京大学経済学部を主席で卒業し、大蔵省に入省した秀才中の秀才です。しかし、ハートのない軽薄才子の常で、日本の権力構造に即したことしか絶対に言おうとしません。つまり、心根は「長いものには巻かれろ」の百姓根性の持ち主なのです。長いものの最たるものはもちろんアメリカです。TPP議論が活発だった去年の夏頃、「賛成するヤツも反対するヤツもみんなバカ」と言い放ちました。そうやって、強力な反対論を一挙に無化することでTPP推進派を利するという瞬間的な高等戦術ができてしまう曲者です。だから、彼のコメントは話半分に聞き流してしまえばよいのです。ここでは二つ指摘しておくにとどめます。一つ目。彼はここで「インタゲは貧富の格差を拡大する」という、耳慣れない「新説」を披露しています。もし、本気でそう言っているのなら、彼はこの新しい学説を、学者としてきちんと実証的に説明する必要があります。おそらく、言いっぱなしになるのでしょうが。二つ目。彼はここで、経済を破壊する悪性インフレと良好で活発な経済活動をもたらすマイルドな2~3%のインフレとを意図的に混同しています。それは、インタゲ政策に関して無知な一般国民の知的状況の上にあぐらをかいた不届きな所業です。バカは騙すに限る、とても思っているのでしょうか。好悪で言えば、私はこういう性根の腐ったインテリ男が大嫌いです。年の功で、そういうことが分かってしまうのです。
次に③。「経済ジャーナリスト」ってなんなのでしょうね。荻原博子氏はマスメディアへの露出度の高い人です。おそらく「女性ならではの生活者目線」が主婦層を中心になんとなく受け入れられているのでしょう。論調としては、デフレ下での生活防衛はいかにあるべきかというレベルに終始しているのではないでしょうか。デフレがいいとか悪いとかはひとまず置いておく、というスタンスです。こういう「庶民サヨク」「経済サヨク」的な人に対して、言いたいのはただ一つ。分からないことに余計な口を挟むな。挟むなら、ちゃんと勉強をしてからにしろ、ということです。
それにしても、この人、滅茶苦茶を言います。「この十年で平均給与は四十万円も減っています」と言っていますが、これこそ、デフレの弊害の最たるものなのです。つまり、物価の下落を上回る率で可処分所得が減るから、デフレは恐ろしいのです。だからこそ、その流れを阻止するために、安倍総裁はインタゲ政策の断行を打ち出しているのです。安倍総裁本人が繰り返しそう言っています。その言葉は、荻原氏の耳には届いていないのでしょうか。安倍総裁の経済政策に反対する理由が、安倍総裁が実施しようとしている経済政策の根拠にもなっているというあべこべな批判は勘弁してほしいものです。はっきり言って、頭、悪すぎ。
「安倍さんが総理だった06年から07年は、いざなぎ景気を超える戦後最長の景気拡大期間で、富裕層は好況でしたが、民間給与は下がりっぱなしでした」というコメントにも看過できないものがあります。彼女の指摘する「実感なき景気回復」(「景気拡大」ではありません)は、2002年の2月から07年の10月までの69か月間続きました。そのなかで、最初の約55か月間は、しゃにむにグローバル化を進めた小泉内閣の時期にあたります。そうして、しゃにむにグローバル化を進めたことが、下がりっぱなしの民間給与を招いたのです。小泉内閣を引き継いだ安倍内閣が、過激なグローバル化路線を軌道修正して、国民経済に立脚した「実感できる経済成長」路線を歩もうとしたことは、その施政方針演説から分かります。(http://mdsdc568.iza.ne.jp/blog/entry/2921368/)小泉政権の経済政策と安倍内閣のそれとを雑駁にひとくくりにして論じるのはやめてほしいものです。「経済ジャーナリスト」ってなんなのでしょうね。
次に④。ご丁寧に、またもや荻原博子氏の登場です。彼女はここで、安倍総裁のインタゲ政策に難癖をつけるためだけに苦し紛れにひねり出された感のある「円安危惧論」を開陳します。いまはまだ、円高基調を完全には脱していません。そうして、円高の弊害は、パナソニック・シャープ・エルビータメモリの苦境を通じて最近いやというほどわたしたちは見せつけられたばかりではないですか。円高は雇用を奪うのです。企業の海外移転を加速化するのです。だから円安の心配は、日本経済を滅ぼしかねない円高を完全に脱してからにすればいいでのです。日照りのさかなにまだ襲ってきてもいない洪水の襲来を心配するのは、愚かな杞憂にほかなりません。円高のままで小麦や大豆などの穀物の高騰の影響が出てくると、日本経済は不況下の物価高、すなわちスタグフレーションの脅威にさらされかねません。その方がよっぽど困った事態でしょうに。円高を放置するのは極めて危険なことなのです。こうやって論じてみると、この荻原という人、いない方が国民にとっては好ましいようですね。人騒がせなんですよ、この人。
次は⑤。この藻谷浩介という人は、ベストセラー『デフレの正体』の著者です。インターネットで検索してみたら、本書で「生産年齢人口の激減と高齢者が激増する『人口の波』がデフレの正体だ」という珍説を主張しているそうです。良心的な識者たちから、デフレからの脱却ができないことを舌鋒鋭く責められまくっている日銀の白川総裁が泣いて喜びそうな「学説」ですね。しかし、これはトンデモ話の類にほかなりません。この説では、世界の先進国がデフレに陥らずに、なぜ日本だけが長年に渡ってデフレに陥っているのかがクリアに説明できないからです。世界の先進諸国の中央銀行がインタゲ政策を採用しているのに対して、日銀だけがそれを採用せずに、事実上のデフレターゲット政策を実施しているから、というのが妥当な説明の仕方であると、私は考えています。そうして、「デフレの正体」などとおどろおどろしい言い方をする必要などまったくなくて、デフレとは「モノの価値よりおカネの価値が高くなってしまっている現象」と定義すれば足ります。その点、いわゆるリフレ派の言うことが妥当であると私は考えています(雇用の確保のためにはそれだけでは足りませんが)。とすると、デフレから脱却するためには、おカネをどんどん刷って、おカネの価値を下げれば、すなわち、大胆な量的緩和を断行すればよいことになるのは理の当然、となりますね。だから、日本は金融政策に関してはグローバル・スタンダードを採用すればいいだけのことなのです。安倍総裁は、世界的な視野において、要するにごく常識的なことをきっぱりと言っているだけ、というわけ。こういうトンデモ系の人から、「安倍さんには経済の現実が見えていない」などと言われても、安倍さんは困っちゃうでしょうね。
で、今度は「円安危惧論」ですか。この人は、よっぽど珍説好きなのでしょう。「いま日本の貿易収支は赤字ですが、原因は円高による輸出減ではなく、原油・ガス価格の上昇による輸入増です。円安になれば、この赤字が拡大します。」これ、論理が破綻しています。だって、円安になれば輸出増になるでしょう。それはなし、という前提で貿易赤字が拡大すると言われても、どうやって信じればいいのでしょうか。デマもほどほどにしてほしいものです。「過度の金融緩和で国債金利が上がれば」と軽く言ってくれていますが、「過度の金融」とはいったいどれほどの規模の緩和を指しているのでしょうか。もし、インフレ目標2%を達成するまで大胆に量的緩和を実施し続けることを「過度」と言っているのであれば、世界46か国がやっていること、すべて「過度」になります。それでいいのでしょうかね。だったら、藻谷氏は現実に実施されているインタゲ政策を全否定しなければならないことになります。できますか、正直なところ。
「国債金利が上がれば、国債の価格が下がり、銀行や年金基金は大幅な評価損を抱えます」と庶民を脅していますけれど、それはデフレが続けば、の話でしょう。インタゲが効けば、円安になり、それを好感して株価が上がります。そうすると、銀行の資金運用の対象が国債以外に大きく広がるので、国債金利の上昇はそれほど大きな問題でなくなりますよね。年金はその資金が株式市場で運用されるので、株価が上がれば、年金の財源も豊かになりますね。政府にとっても、円安になり株価が上がり、設備投資が盛んになって、家計の収入が増えれば、名目GDPの成長率が上がり、税収が増えるので、インタゲが効くのはいいことです。だから政府・日銀は、名目GDPの成長率(4%が黄金率と言われています)が国債金利の上昇率を上回る状態がキープされるように注意深く経済政策をオペレートする必要があります。つまり、インフレ率が目標の2%を保持しているかどうかに細心の注意を払い続けなければならないのです。いいかえれば、実質GDP成長率2%+インフレ率2%=名目GDP成長率4%が達成されるようにマクロ経済を誘導するわけです。そうすれば、財政は破綻するどころか、おおいに再建が進むことになります。そう考える私からすれば、藻谷氏の「国債や年金、さらには政府財政の破綻へとつながる政策を、自民党総裁が主張しているのです。日本のメルトダウンも極まったと思いました」という発言に、いささか脅迫神経症的な不健全さ、精神状態の過剰さが感じられるような気がしないでもないのですが、はて。
⑥については、そう考える人がいる可能性は否定できませんが、それで?としか言いようがありません。安倍総裁のインタゲ政策の主張によって、実際に円安になり株価高になったことをなるべく小さく見積もらんがために無理やりそういう意見を引っ張ってきて並べてみた、というだけのことではありませんか?
最後に⑦。やはり登場しました、「国債暴落やハイパーインフレ」。これは100%ありえません。これらが起こるのは、デフォルト(政府としての対外的な債務不履行)が起こったり、戦争や革命で生産設備が破壊され尽くしたりしたときだけです。90数%内債の日本国債がデフォルトする可能性はゼロです。だから、これらの文言が散見される文章は悪質なデマだと判断して間違いありません。分かりやすい目印ですね。
ひとつだけ付け加えておきましょう。日銀はすでに十分に量的緩和を行っている、という意見があります。これにインタゲ政策の実施の有無という視点から批判を加えてみます。日銀は今年の2月に、いやいやながらも「1%目途」を発表しました。これを安住前財務相は「インフレターゲットと思っている」と評価しました。しかしながら、インタゲ政策を採用している国で「1%」などという低い数値を目標として掲げている例は皆無です。これには理由があります。消費者物価指数は、上ブレが1%ほど生じるという統計学的な欠点が避けがたいのです。だから、「1%目途」は事実上の0%になってしまう可能性を技術的に排除できません。それゆえ、通常「2%」以上の目標設定をするのです。また、日銀の「1%目途」の場合、達成の時期が明確にされていません。で、達成しなかった場合の責任を問われることもありません。また、どうやって1%を達成するのかの具体的説明をする責任も負っていません。そんな無責任なインタゲ政策を実施している国は世界のどこにもありません。だから、日銀の「1%目途」は残念ながら、到底インタゲ政策といえた代物ではないのです。だから、日銀がすでに十分に量的緩和を実施している、というのは絵空事なのです。まったくもって、ふざけた話です。そういうふざけた話が生じる余地のある現日銀法を改正しようというのは、実は当たり前のことなのです。
由紀さん、こんなところです。
それにしても、週刊文春よ。国民作家にして文芸春秋社の生みの親、菊池寛が草葉の陰で泣いているぞ。こんな、国民をたぶらかすような腐った悪質な雑誌を作るために、オレは文春を生み育てたんじゃない、と。
『週間文春』の12月6日号が、反安倍特集をしたのをご存じですか。ここに出ていた議論のうち、経済問題について、美津島さんに、反論をお願いしたいのです。ご迷惑なら、もとより強要はできません(迷惑だなんて、とんでもありませんーブログ主人)。
もっとも、この同じ『週刊文春』の連載エッセイ「宮崎哲弥の時々砲弾」には、「私は阿倍晋三総裁率いる自由民主党の政策を全面的に支持しているわけではない。しかしその金融政策論は大筋で間違っていない」とありまして、結果として「両論併記」になっているのですが。まあ目立つところにあるのは安倍金融政策批判で、この立場の論はほぼ出そろっているのではないかと思います。
以下に煩を厭わず、動員された言論人の言葉を引用します。引用はすべて、P.27~28の、「主婦・年金生活者直撃 安倍不況がやって来る」からです。
で、週刊文春に動員された言論人の発言は以下の通りです。通し番号は、私が便宜上つけたものです。①~⑦の論者の一行紹介は由紀草一氏によるものです。
①大手銀行アナリスト(誰だ?)の言葉。全体のリードとして。
安倍氏の経済政策に関する発言には、二つの問題があります。まず言う通りインフレターゲットが達成できるのか。仮に、達成できたとしても日本経済が壊滅的な打撃を受ける。どちらにもせよ、この経済政策が“安倍総理”の致命傷になるでしょう。
②小幡績慶大大学院準教授による、インフレターゲットが達成された場合の悲観的な見通し。
投資家は、資産を現金からインフレに強い不動産や株式に移すので、地価や株価が上昇する「資産インフレ」が起こります。例えば、持ち家の人はウハウハでしょうが、賃貸の人は大変です。家賃は上がるが賃金は上がりませんから。貧富の格差が拡大するでしょう。
③経済ジャーナリスト荻原博子による、同じく悲観的な見通し。
インフレは、物価と同じように賃金も上がらなければ、増税と一緒です。ただ国際競争が激しい経済情勢で物価と同じように賃金を上げられるかと言えば、かなり難しいでしょう。また年金も物価と同じようには上がりません。派遣で働く人たちや、年金生活者などは大きな打撃を受けます。
安倍さんが総理だった06年から07年は、いざなぎ景気を超える戦後最長の景気拡大期間で、富裕層は好況でしたが、民間給与は下がりっぱなしでした。この十年で平均給与は四十万円も減っています。給料に跳ね返らない景気回復が、前回と同じように起こるかもしれません。
④荻原博子による、円安危惧論。
これまでは、円高で輸入物資が安く入ってくるから、生活が助かっていた面もあります。今年、アメリカは五十六年ぶりの大干ばつで、小麦や大豆などの穀物の値段が上がっている。円安になれば、当然高くなります。
⑤藻谷浩介日本総研主席研究員による、同じく円安危惧論。
安倍さんには経済の現実が見えていない。いま日本の貿易収支は赤字ですが、原因は円高による輸出減ではなく、原油・ガス価格の上昇による輸入増です。円安になれば、この赤字が拡大します。過度の金融緩和で国債金利が上がれば、国債の価格が下がり、銀行や年金基金は大幅な評価損を抱えます。国債や年金、さらには政府財政の破綻へとつながる政策を、自民党総裁が主張しているのです。日本のメルトダウンも極まったと思いました。
⑥市場関係者(また誰だかわからない)による株価上昇懐疑論
上げの要因は外資系の資金。ヘッジファンドにとって変化はビジネスチャンスですから、日本に資金を投じています。ただ、彼らは選挙を利用して煽るだけ煽って、自民党政権が誕生した瞬間に売りに転じて株価は急落するとの見方がある。この株価は、実体経済には反映されないと見ています。
⑦最初のアナリスト(だから誰だよ)による締めの言葉。
安倍氏の経済政策をそのまま実行することは、日本国民をモルモットにした壮大な社会実験です。うまくいく可能性もゼロとは言いませんが、失敗する確率の方が圧倒的に高く、またその代償、国債暴落やハイパーインフレは日本を壊滅させる。リターンに比して、リスクが大きすぎるのです。
この記事に名を連ねた経済学者やエコノミストの名を、みなさん、よく覚えておいてください。彼らはみな不純な動機で一般国民をたぶらかすデマ・ゴークです。その理由を、①~⑦までを順に取り上げることで説明しましょう。
まず、①から。この人本当に「大手銀行アナリスト」なんでしょうか。「インフレターゲットが達成できるのか」なんて言っていますけれど、インフレターゲット政策(以下、インタゲ政策と略称)は、すでに先進国をふくむ世界27カ国で実施されている、ごく常識的な経済政策です。この場合、ユーロ圏17カ国は一国としてカウントしています。だから、実質世界の46カ国がこの政策を実施していることになります。先進国でインタゲを実施していないのは、なんと日本だけなのです。それは、デフレを堅持したいからとしか思えないという切り口で日本の経済政策(この場合、金融政策の主体としての日銀)の異常さを指摘する論者は、良質なメディアにはゴマンといます。一般国民に知らされていないだけのことです。それゆえ(当ブログでたびたび指摘してきたことですが)、ごく平均的な日本人の間で、「政府・日銀は、適切な経済政策によって、物価水準をコントロールできる」という考え方が常識になっていないという情けない事態を招いているのです。だから、この論者のように「仮に、達成できたとしても日本経済が壊滅的な打撃を受ける」というコケおどしが効くと思い込むことができるのです。残念なことですが、日本人は、経済現象を自然現象として受けとめる段階にとどまっています。その意味で、その経済感覚は、縄文人レベルと言わざるをえません。それをこの論者は(すなわち文春は)啓蒙するのではなく、悪用しているフシがあります。罪深い所業です。天罰が当たってもちっとも不思議ではありません。
次に②。小幡績(おばたせき)氏は、1992年に東京大学経済学部を主席で卒業し、大蔵省に入省した秀才中の秀才です。しかし、ハートのない軽薄才子の常で、日本の権力構造に即したことしか絶対に言おうとしません。つまり、心根は「長いものには巻かれろ」の百姓根性の持ち主なのです。長いものの最たるものはもちろんアメリカです。TPP議論が活発だった去年の夏頃、「賛成するヤツも反対するヤツもみんなバカ」と言い放ちました。そうやって、強力な反対論を一挙に無化することでTPP推進派を利するという瞬間的な高等戦術ができてしまう曲者です。だから、彼のコメントは話半分に聞き流してしまえばよいのです。ここでは二つ指摘しておくにとどめます。一つ目。彼はここで「インタゲは貧富の格差を拡大する」という、耳慣れない「新説」を披露しています。もし、本気でそう言っているのなら、彼はこの新しい学説を、学者としてきちんと実証的に説明する必要があります。おそらく、言いっぱなしになるのでしょうが。二つ目。彼はここで、経済を破壊する悪性インフレと良好で活発な経済活動をもたらすマイルドな2~3%のインフレとを意図的に混同しています。それは、インタゲ政策に関して無知な一般国民の知的状況の上にあぐらをかいた不届きな所業です。バカは騙すに限る、とても思っているのでしょうか。好悪で言えば、私はこういう性根の腐ったインテリ男が大嫌いです。年の功で、そういうことが分かってしまうのです。
次に③。「経済ジャーナリスト」ってなんなのでしょうね。荻原博子氏はマスメディアへの露出度の高い人です。おそらく「女性ならではの生活者目線」が主婦層を中心になんとなく受け入れられているのでしょう。論調としては、デフレ下での生活防衛はいかにあるべきかというレベルに終始しているのではないでしょうか。デフレがいいとか悪いとかはひとまず置いておく、というスタンスです。こういう「庶民サヨク」「経済サヨク」的な人に対して、言いたいのはただ一つ。分からないことに余計な口を挟むな。挟むなら、ちゃんと勉強をしてからにしろ、ということです。
それにしても、この人、滅茶苦茶を言います。「この十年で平均給与は四十万円も減っています」と言っていますが、これこそ、デフレの弊害の最たるものなのです。つまり、物価の下落を上回る率で可処分所得が減るから、デフレは恐ろしいのです。だからこそ、その流れを阻止するために、安倍総裁はインタゲ政策の断行を打ち出しているのです。安倍総裁本人が繰り返しそう言っています。その言葉は、荻原氏の耳には届いていないのでしょうか。安倍総裁の経済政策に反対する理由が、安倍総裁が実施しようとしている経済政策の根拠にもなっているというあべこべな批判は勘弁してほしいものです。はっきり言って、頭、悪すぎ。
「安倍さんが総理だった06年から07年は、いざなぎ景気を超える戦後最長の景気拡大期間で、富裕層は好況でしたが、民間給与は下がりっぱなしでした」というコメントにも看過できないものがあります。彼女の指摘する「実感なき景気回復」(「景気拡大」ではありません)は、2002年の2月から07年の10月までの69か月間続きました。そのなかで、最初の約55か月間は、しゃにむにグローバル化を進めた小泉内閣の時期にあたります。そうして、しゃにむにグローバル化を進めたことが、下がりっぱなしの民間給与を招いたのです。小泉内閣を引き継いだ安倍内閣が、過激なグローバル化路線を軌道修正して、国民経済に立脚した「実感できる経済成長」路線を歩もうとしたことは、その施政方針演説から分かります。(http://mdsdc568.iza.ne.jp/blog/entry/2921368/)小泉政権の経済政策と安倍内閣のそれとを雑駁にひとくくりにして論じるのはやめてほしいものです。「経済ジャーナリスト」ってなんなのでしょうね。
次に④。ご丁寧に、またもや荻原博子氏の登場です。彼女はここで、安倍総裁のインタゲ政策に難癖をつけるためだけに苦し紛れにひねり出された感のある「円安危惧論」を開陳します。いまはまだ、円高基調を完全には脱していません。そうして、円高の弊害は、パナソニック・シャープ・エルビータメモリの苦境を通じて最近いやというほどわたしたちは見せつけられたばかりではないですか。円高は雇用を奪うのです。企業の海外移転を加速化するのです。だから円安の心配は、日本経済を滅ぼしかねない円高を完全に脱してからにすればいいでのです。日照りのさかなにまだ襲ってきてもいない洪水の襲来を心配するのは、愚かな杞憂にほかなりません。円高のままで小麦や大豆などの穀物の高騰の影響が出てくると、日本経済は不況下の物価高、すなわちスタグフレーションの脅威にさらされかねません。その方がよっぽど困った事態でしょうに。円高を放置するのは極めて危険なことなのです。こうやって論じてみると、この荻原という人、いない方が国民にとっては好ましいようですね。人騒がせなんですよ、この人。
次は⑤。この藻谷浩介という人は、ベストセラー『デフレの正体』の著者です。インターネットで検索してみたら、本書で「生産年齢人口の激減と高齢者が激増する『人口の波』がデフレの正体だ」という珍説を主張しているそうです。良心的な識者たちから、デフレからの脱却ができないことを舌鋒鋭く責められまくっている日銀の白川総裁が泣いて喜びそうな「学説」ですね。しかし、これはトンデモ話の類にほかなりません。この説では、世界の先進国がデフレに陥らずに、なぜ日本だけが長年に渡ってデフレに陥っているのかがクリアに説明できないからです。世界の先進諸国の中央銀行がインタゲ政策を採用しているのに対して、日銀だけがそれを採用せずに、事実上のデフレターゲット政策を実施しているから、というのが妥当な説明の仕方であると、私は考えています。そうして、「デフレの正体」などとおどろおどろしい言い方をする必要などまったくなくて、デフレとは「モノの価値よりおカネの価値が高くなってしまっている現象」と定義すれば足ります。その点、いわゆるリフレ派の言うことが妥当であると私は考えています(雇用の確保のためにはそれだけでは足りませんが)。とすると、デフレから脱却するためには、おカネをどんどん刷って、おカネの価値を下げれば、すなわち、大胆な量的緩和を断行すればよいことになるのは理の当然、となりますね。だから、日本は金融政策に関してはグローバル・スタンダードを採用すればいいだけのことなのです。安倍総裁は、世界的な視野において、要するにごく常識的なことをきっぱりと言っているだけ、というわけ。こういうトンデモ系の人から、「安倍さんには経済の現実が見えていない」などと言われても、安倍さんは困っちゃうでしょうね。
で、今度は「円安危惧論」ですか。この人は、よっぽど珍説好きなのでしょう。「いま日本の貿易収支は赤字ですが、原因は円高による輸出減ではなく、原油・ガス価格の上昇による輸入増です。円安になれば、この赤字が拡大します。」これ、論理が破綻しています。だって、円安になれば輸出増になるでしょう。それはなし、という前提で貿易赤字が拡大すると言われても、どうやって信じればいいのでしょうか。デマもほどほどにしてほしいものです。「過度の金融緩和で国債金利が上がれば」と軽く言ってくれていますが、「過度の金融」とはいったいどれほどの規模の緩和を指しているのでしょうか。もし、インフレ目標2%を達成するまで大胆に量的緩和を実施し続けることを「過度」と言っているのであれば、世界46か国がやっていること、すべて「過度」になります。それでいいのでしょうかね。だったら、藻谷氏は現実に実施されているインタゲ政策を全否定しなければならないことになります。できますか、正直なところ。
「国債金利が上がれば、国債の価格が下がり、銀行や年金基金は大幅な評価損を抱えます」と庶民を脅していますけれど、それはデフレが続けば、の話でしょう。インタゲが効けば、円安になり、それを好感して株価が上がります。そうすると、銀行の資金運用の対象が国債以外に大きく広がるので、国債金利の上昇はそれほど大きな問題でなくなりますよね。年金はその資金が株式市場で運用されるので、株価が上がれば、年金の財源も豊かになりますね。政府にとっても、円安になり株価が上がり、設備投資が盛んになって、家計の収入が増えれば、名目GDPの成長率が上がり、税収が増えるので、インタゲが効くのはいいことです。だから政府・日銀は、名目GDPの成長率(4%が黄金率と言われています)が国債金利の上昇率を上回る状態がキープされるように注意深く経済政策をオペレートする必要があります。つまり、インフレ率が目標の2%を保持しているかどうかに細心の注意を払い続けなければならないのです。いいかえれば、実質GDP成長率2%+インフレ率2%=名目GDP成長率4%が達成されるようにマクロ経済を誘導するわけです。そうすれば、財政は破綻するどころか、おおいに再建が進むことになります。そう考える私からすれば、藻谷氏の「国債や年金、さらには政府財政の破綻へとつながる政策を、自民党総裁が主張しているのです。日本のメルトダウンも極まったと思いました」という発言に、いささか脅迫神経症的な不健全さ、精神状態の過剰さが感じられるような気がしないでもないのですが、はて。
⑥については、そう考える人がいる可能性は否定できませんが、それで?としか言いようがありません。安倍総裁のインタゲ政策の主張によって、実際に円安になり株価高になったことをなるべく小さく見積もらんがために無理やりそういう意見を引っ張ってきて並べてみた、というだけのことではありませんか?
最後に⑦。やはり登場しました、「国債暴落やハイパーインフレ」。これは100%ありえません。これらが起こるのは、デフォルト(政府としての対外的な債務不履行)が起こったり、戦争や革命で生産設備が破壊され尽くしたりしたときだけです。90数%内債の日本国債がデフォルトする可能性はゼロです。だから、これらの文言が散見される文章は悪質なデマだと判断して間違いありません。分かりやすい目印ですね。
ひとつだけ付け加えておきましょう。日銀はすでに十分に量的緩和を行っている、という意見があります。これにインタゲ政策の実施の有無という視点から批判を加えてみます。日銀は今年の2月に、いやいやながらも「1%目途」を発表しました。これを安住前財務相は「インフレターゲットと思っている」と評価しました。しかしながら、インタゲ政策を採用している国で「1%」などという低い数値を目標として掲げている例は皆無です。これには理由があります。消費者物価指数は、上ブレが1%ほど生じるという統計学的な欠点が避けがたいのです。だから、「1%目途」は事実上の0%になってしまう可能性を技術的に排除できません。それゆえ、通常「2%」以上の目標設定をするのです。また、日銀の「1%目途」の場合、達成の時期が明確にされていません。で、達成しなかった場合の責任を問われることもありません。また、どうやって1%を達成するのかの具体的説明をする責任も負っていません。そんな無責任なインタゲ政策を実施している国は世界のどこにもありません。だから、日銀の「1%目途」は残念ながら、到底インタゲ政策といえた代物ではないのです。だから、日銀がすでに十分に量的緩和を実施している、というのは絵空事なのです。まったくもって、ふざけた話です。そういうふざけた話が生じる余地のある現日銀法を改正しようというのは、実は当たり前のことなのです。
由紀さん、こんなところです。
それにしても、週刊文春よ。国民作家にして文芸春秋社の生みの親、菊池寛が草葉の陰で泣いているぞ。こんな、国民をたぶらかすような腐った悪質な雑誌を作るために、オレは文春を生み育てたんじゃない、と。










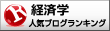

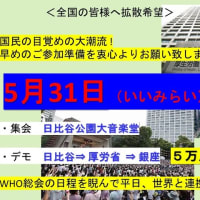
















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます