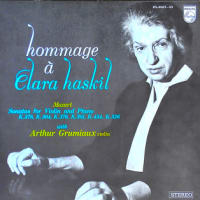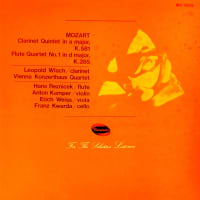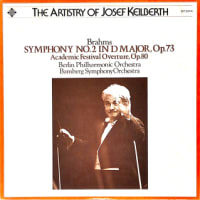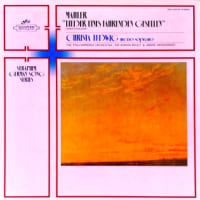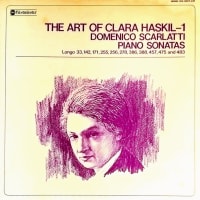ショパン:練習曲op.10(第1曲~第12曲)
練習曲op.25(第1曲~第12曲)
ピアノ:サンソン・フランソワ
録音:1958年9月~1959年2月
LP:東芝音楽工業 AB 7664
これは、フランスの名ピアニストのサンソン・フランソワ(1924年―1970年)が、1958年9月~1959年2月にかけてモノラル録音したLPレコードである。これまで、このLPレコードを何回聴いたか記憶に留めないほど聴き続けた私にとっては、正にかけがえのない一枚のレコードなのである。ちょうど、録音時期が、モノラルからステレオの移行時期に当たり、残念ながらモノラル録音になってしまった。もし、これがステレオ録音で残されたのなら、ショパンの練習曲集で、今もってこれを凌駕し得る録音はないと私は考えている。ショパンの練習曲は、作品10が18歳~22歳、作品25が23歳~30歳の時に書かれたとされている。ここでのフランソワの演奏は、男性的で激情的な高ぶりを見せたかと思えば、突如、詩情味たっぷりにショパンの世界を描き上げる。自由奔放さが随所に表れ、少しの躊躇もなく自分の感情を鍵盤上に叩き付けるのだ。そこにはリスナーに対する少しの妥協もなく、自分の思った通りのショパン像を形づくって行く。猪突猛進と言えばその通りなのだが、芸術家としての確固とした信念がそうさせたことが、手に取るように分かるので、少しの違和感も感じさせない。来日時のサンソン・フランソワの演奏を聴いた音楽評論家の野村光一氏(1895年―1988年)は次のように書き残している。「1956年に初めて来日したとき、フランソワはショパンとリスト、プロコフィエフなどをレパートリーにして音楽界を催していた。演奏は、ソ連のギレリスなどと類似していて、腕に任せて一気呵成に弾きまくる、派手で、強行な弾きぶり、いわば力演型、張り切り型というべきものであった。けれども、共に力感に重点を置きながら、フランソワはギレリスと異なって、力より響きに音を移行させる感性に強かったようである。・・・その結果、音楽の掴み方もすべて直感的になっていた感なきにしもあらだったのである。でも、それが聴衆に新鮮な感覚と官能を喚起させて、彼らをたちまち陶酔の域に誘い込んだのは疑うまでもない」(「ピアニスト」音楽之友社)。このLPレコードは、モノラル録音と最初に書いたが、聴いていて決して聴きづらいというほどでなく、フランソワのピアノタッチはよく捉えられている。フランソワのような詩的でしかも激情的な演奏をするピアニストは、現在ほとんどいなくなってしまった。聴いていてドキドキするピアニスト、そしてハラハラする、あまりに人間的なピアニスト、それがサンソン・フランソワであった。(LPC)