森羅万象、政治・経済・思想を一寸観察 by これお・ぷてら
花・髪切と思考の
浮游空間
カレンダー
| 2025年8月 | ||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| 1 | 2 | |||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 31 | ||||||||
|
||||||||
goo ブログ
最新の投稿
| 8月6日(土)のつぶやき |
| 8月5日(金)のつぶやき |
| 6月4日(土)のつぶやき |
| 4月10日(日)のつぶやき |
| 2月10日(水)のつぶやき |
| 11月12日(木)のつぶやき |
| 10月26日(月)のつぶやき |
| 10月25日(日)のつぶやき |
| 10月18日(日)のつぶやき |
| 10月17日(土)のつぶやき |
カテゴリ
| tweet(762) |
| 太田光(7) |
| 加藤周一のこと(15) |
| 社会とメディア(210) |
| ◆橋下なるもの(77) |
| ◆消費税/税の使い途(71) |
| 二大政党と政党再編(31) |
| 日米関係と平和(169) |
| ◆世相を拾う(70) |
| 片言集または花(67) |
| 本棚(53) |
| 鳩山・菅時代(110) |
| 麻生・福田・安倍時代(725) |
| 福岡五輪幻想(45) |
| 医療(36) |
| スポーツ(10) |
| カミキリムシ/浮游空間日記(77) |
最新のコメント
| Unknown/自殺つづくイラク帰還自衛隊員 |
| これお・ぷてら/7月27日(土)のつぶやき |
| 亀仙人/亀田戦、抗議電話・メールなど4万件突破 |
| inflatables/生活保護引き下げ発言にみる欺瞞 |
| これお・ぷてら/10月2日(火)のつぶやき |
| THAWK/10月2日(火)のつぶやき |
| これお・ぷてら/10月2日(火)のつぶやき |
| THAWK/国民の負担率は低いというけれど。 |
| THAWK/10月2日(火)のつぶやき |
| THAWK/[橋下市政]健康を奪い財政悪化招く敬老パス有料化 |
最新のトラックバック
ブックマーク
| ■ dr.stoneflyの戯れ言 |
| ■ machineryの日々 |
| ■ えちごっぺのヘタレ日記 |
| ■ すくらむ |
| ■ 代替案 |
| ■ 非国民通信 |
| ■ coleoの日記;浮游空間 |
| ■ bookmarks@coleo |
| ■ 浮游空間日記 |
過去の記事
検索
| URLをメールで送信する | |
| (for PC & MOBILE) | |
消費税を考える
増税の核心は、もちろん消費税です。かつては消費税増税のために、直間比率なるものをもちだし、直接税にくらべ間接税の割合が低いといってきました。ところが、その後の「税制改革」によって所得税の累進率を下げ、法人税の減税をつづけたために、この口実をいまではもちいることができません。
そこで、目的税、しかも国民が反対しにくいだろうといって、社会保障目的税にと強調しています。
社会保障をどう支えていくのか、その議論はたしかに必要です。消費税で社会保障を支えようという考えは、所得の高低を社会保障や税制度で是正しようとする再分配の考え方に立てば、矛盾します。消費税の負担割合は所得の低い人ほど高くなるからです。
消費税という選択肢しか残されていないわけではありません。歳入、歳出を見直せば、あらためるべきものがある。そして、消費税を導入するには他に理由がある、と考えるのです。
自公だけでなく民主党も消費税を選択した今、それでよいのか、国民が判断しなければなりません。
以下に消費税に関連する本年のエントリーを列記しました。
■よろしければクリックを ⇒
■ブログ村ランキングもお願い⇒![]()
方便のつかいみち-社会保障目的の消費税増税 (12月26日)
消費税導入をあおる朝日社説 (12月21日)
消費税増税;気脈通じる自民、民主。 (11月26日)
社会保障目的などとごまかすな;消費税。 (10月16日)
大企業が消費税を歓迎するワケ (8月12日)
消費税増税が待っている;知ってる? 人頭税石 (7月5日)
方便のつかいみち-社会保障目的の消費税増税
 社会保障を支えるための財源は消費税以外にはないのか。これが大きな論点になってきた。
社会保障を支えるための財源は消費税以外にはないのか。これが大きな論点になってきた。政府は消費税増税が既定の路線であるかのようにいうし、自民税調、政府税調も同様で、まるで選択肢は他にないといわんばかりの合唱を繰り返している。そこに、民主党が加わった。
同党は消費税増税を公約にかかげることを決めたそうである。
同党の「08年度税制改革大綱」では、消費税を社会保障目的税にすることを前提に、「(将来的に)引き上げ幅や使途を明らかにして国民の審判を受け、具体化する」と明記している。
<民主税制大綱>消費税上げの検討を示唆 道路財源は一般化
筋道ははっきりしている。すでに11月、自民党と民主党が消費税増税で気脈を通じていることにふれたけれど(参照)、それがあらためて公にされたということである。こと消費税にかぎっていえば、「連立」はすでにできあがっている。しかも、民主党もまた社会保障目的税だという。
したがって、つぎに、社会保障目的税とはいったい何かということも重要な第二の論点にしなければならない。

社会保障を支える財源をどう確保するのかは解決しなければならない重要な問題である。社会保障関連費は一般会計の4分の1を占める。この間の構造改革がすすむなかで、政府は自然増分の抑制までうちだし、これが今日もつづいている。こんな背景があるし、舛添厚労相が社会保障費の抑制は限界にきていると繰り返しいうのは、「改革」という名で抑制をつづけてきた担当省の率直な思いといえるのかもしれない。社会保障制度の見直しによる歳出削減は現実的には相当の困難がともなうというわけである。別の言葉でいうのなら、「改革』路線は矛盾に直面しているといえる。最近の生活保護見直しの撤回、後期高齢者医療制度の見直しを思い起こせばよい。参院選後の状況がそれらを加速している。
だから、重要なのは、社会保障の財源を何によって、つまりどんな税金で支えるのかという話になる。政府は、真意なのかどうかは措くとして、それに消費税をあてようというわけだ。
歳入・歳出をすべて見直し、不要不急のものはないか、論議すればよいと思うのだが、政府は共産党などの野党が指摘するように、手をつけない「聖域」をつくってきた。当ブログでは、たとえばそれは歳出での軍事費、思いやり予算、歳入では企業減税、大資産家への優遇税制などを指している。どこに手をつけるか、国民が選択すべきときを迎えている。
つぎの点からも検討が必要だ。
社会保障を支えるには消費税の税率をあげるしかないと政府は考えているようだが、日本より社会保障という点で先行するヨーロッパが消費税を社会保障目的税として位置づけているかといえばそうではない。ヨーロッパでは、社会保障給付が伸びたときも、社会保険料(の引き上げ)で対応している。社会保険料こそ、その使途を社会保障に限るわけだから、社会保障目的のれっきとした財源である。消費税を増やして対応したのではない。いうまでもなく事業主の負担割合は日本より高い。

 第二の重要な論点は、消費税を社会保障目的税にするとはいったい何かということである。
第二の重要な論点は、消費税を社会保障目的税にするとはいったい何かということである。
野口悠紀雄氏が自らのホームページで、すでに社会保障目的税化について厳しい批判をくわえている(消費税の増税目的税化は欺瞞)。氏の立場から、簡潔な説明で論点が整理されている。
氏の結論は「社会保障目的税化」とは、消費税増税を行ないやすくするための方便というものだが、これ以上の説明は要しない。氏の言葉を借りて、あえて付け加えれば、「消費税を社会保障費にあてる」と観念することの実質的な意味は、消費税の増税(の一部)を社会保障費増以外に用いるのを見えにくくすることなのである。
このように、政府の考えていることは、社会保障をやり玉にあげながら、実はそれ以外の歳出に結果的にふりむけることにある。
たとえば、これまで消費税の導入・増税によって公的負担の面で最大の恩恵を受けたのは財界だと結論づけることができる。1989年に導入された消費税の税収は累計で175兆円。この年以降、法人税率は42%から30%まで12%も引き下げられた。06年度までの法人課税の減収は合計で160兆円というのだから、消費税収の大部分が法人課税の減収に吸い込まれた形になっている。結局は、増税のゆくえとはこんなものである。
政府は国民を欺くことをやめよ。
■よろしければクリックを ⇒
■ブログ村ランキングもお願い⇒![]()
消費税導入をあおる朝日社説

朝日の社説は、あえて重要な点を欠落させている。
社説の核心は、①消費税の増税は避けられない、②消費税は福祉の財源に適している(*1)、の二つだと思う。以下にあげる消費税の「欠点」をうめるために、社説が提言するなかには、生活必需品の税率を下げるなどいくつかの修正が施されているが、消費税にたいする朝日の基本的認識をもちろん変えるものではない。
欠落しているのは、たとえば増税は避けられないというが、企業減税や思いやり予算などをまったく考慮していないことにも表れている。要するに、朝日もまた、この領域を「聖域」視していて、まったく政府の立場とかわりはしない。
税金をどこからとり、どこに配分するのかという問題は、いうまでもなくすぐれて政治的で、階級的である。
この間、構造改革という名で「がまん」が求められる一方で、増税を強いられてきたのは庶民であった。アウトラインをみるとおよそつぎのようなものだ。
所得税の累進性が弱められた。税率がフラット化されたわけである。そして、消費税増税によって、増税分は、企業減税にもっていかれた形になっている。また、最近の定率減税の廃止は記憶に新しいだろう。その際、廃止によって浮いた財源を、基礎年金財源として積み立てると政府はいいながら、積み立てられた額は予定を大幅に下回っていた事実も記憶に留めておいてよい。
いいたいのは、この間の自民党政治の税収奪-とあえていわせてもらう-が、庶民にむけられてきたということである。その一方では、財界・大企業や高額所得者への手厚い減税政策がとられてきたという事実である。
だから、あえて税制が今後、どのように変わっていくのかに無関心ではいられないのだ。

ふりかえってみると、小泉後を引き継いだ安倍前首相は、小泉氏がやらなかった消費税増税を参院選前にうちだした。けれど、選挙をひかえて、秋口から論議を開始するといって、消費税が争点になることをむろん避けてきた。福田首相は、就任後まもなく消費税増税も事実上明らかにしたし、政府税調・香西泰会長もこれに言及してきた。ただし、議論は、周知のように増税の理由づけのために、常に社会保障目的という言葉が付け加えられているという特徴がある。
消費税がどのようなものか明らかにするために、つぎの3つの点でみてみたい。
1.消費税はどのような税か
2.消費税導入は財界の念願であったこと
3.租税理念を変質させてきたこと
1点目については、当ブログで数回ふれてきた。簡単にくりかえすと、消費税は、人を選ばない。「平等」に扱う。なんとなくよいではないかと思えてしまうが、税を負担する力(担税力)は一様ではないので、税はこれでは困るのだ。フラット化したとはいえ、所得に応じて高くなる所得税と比較するとちがいは歴然である。
だから、消費税は逆進性が問題になる。所得の低い人ほど負担割合が高くなるということだ。
大企業にとっては、少しも痛くはない。消費税を負担するのは消費者。企業や業者は税負担者ではない。
そして、税収が大きいことも特徴だ。消費税は物価に上乗せされるため、物価を引き上げる。物価があがると、消費税の税収はまたあがるのだ。現にデータによれば、1990年度1%あたり税収は1.5兆円、2006年度にはこれが2.6兆円にはねあがっている。
戦後、日本の税体系はシャウプ勧告によって、直接税である所得税、法人税、相続税、富裕税を中心に、個別の間接税がそれを補完する形とされた。勧告は1950年のことだ。当時の政治状況が反映されていると思うことは、所得税を中心とする直接税が民主主義に対する国民の意識を高め、もちろん所得再分配の機能を高めるし、反インフレの作用をもつと考えられてきたことだ。一方で当時の取引高税のような間接税は廃止された。広く大衆から徴収されるため、重税感と税金を払うという感覚がともなわないために、当時は国民は政治から遠ざかると考えられたらしい。
勧告の発効にともない、すぐに財界では勧告の「直接税中心主義」への反発がはじまる。そして、1956年には政府税調答申で売上税が盛り込まれ、付加価値税にその後言及し、ついに竹下内閣のときに消費税が導入された。1989年である。
橋本内閣時代に税率が5%に引き上げられ今日に至っている。
この変遷のなかで、ちょうどシャウプ勧告から50年になる2000年、政府税調は消費税増税をうたう一方で、消費税導入以来、大きく減税されてきた法人税が「基幹税」からはずされている。当時、税調会長だった石弘光は、企業には選挙権がないと言い放っている。石は思惑を隠そうともせず、「何よりも重要なのは特定の人の税負担を重くするのではなく、できるだけ多くの人に何らかの形で負担してもらうことである」「どうせ税を支払わねばならないなら、痛みなく取ってもらいたいというのが、日本人の性癖」と強弁した。
いまや政府与党、財界だけでなく、野党の一部をも巻き込み消費税増税へひた走りつつある。朝日の社説もその潮流にのったものといえる。
かつては日本の税制の、直間比率(*2)をもちいて消費税導入が叫ばれた。いまや日本はヨーロッパ並みの直間比率である。5.5対4.5程度だといわれている。
こんな伏線もあって、社会保障目的というのだが、すぐに分かることだけれど、税金はどの支出にも巡り巡っていく。社会保障だけに限られるわけではない。
いったい消費税を社会保障目的税にしている国が世界にあるのか。
話をもどす。以上のように朝日社説は、歴史的にみて、消費税が財界が求めてきたものであること、さらに財界の負担を軽くし、庶民の負担を重くするところに意図があって、導入後は財界・企業の減税が連続している事実からも、目をそらしている。歴史はまさにこの税をめぐる攻防が政治的、階級的であることを教えている。
その意味で朝日は明確に支配層の側に立場を置いているといえる。
■よろしければクリックを ⇒
■ブログ村ランキングもお願い⇒![]()
*1;社会保障は、租税制度などと同じように、所得の高い者から低い者への所得移転の機能を持っています。この所得再分配が必要だとする立場からみると、消費税はこれとは反対の性質をもっています。すなわち、消費税は文中に記したように、低所得者ほど負担割合が高いのです。朝日は(消費税は)税収が安定しているため福祉の財源に適しているというのは、まったく的はずれでしょう。
*2;直接税と間接税の税収の割合。従来は、直接税7、間接税3といわれていました。消費税の導入の一方で、所得税の税率変更等でこの差が縮まっています。
PS;coleoの日記;浮游空間に同文を公開しています。
ガソリン税の前に-企業の税負担に着手せよ。
ガソリン税上乗せ、民主は「撤廃」 党税制大綱に明記へ(朝日新聞)
国民にはよくみえない道路特定財源の揮発油税(ガソリン税)を一般財源化することは賛成ですし、その上乗せ分をどのようにするのか、そこは論点の一つで決着をつけなければなりません。
一方で思うのは、税の論議で避けてとおっている重要な論点があるということです。当ブログで繰り返しのべている、企業減税に一度メスを入れるべきだということです。
 企業減税は聖域ではありません。今朝の「サンデーモーニング」でも、この間の企業減税がつづき、企業が一方で膨大な利益をあげ、国民の中でも年収が1000万円以上の層と年収200万円以下の層がともに増えている格差の広がりに言及していました。メディアもこのように指摘する企業減税。税負担の面で、企業の負担をもっと強めてよいと思うのです。
企業減税は聖域ではありません。今朝の「サンデーモーニング」でも、この間の企業減税がつづき、企業が一方で膨大な利益をあげ、国民の中でも年収が1000万円以上の層と年収200万円以下の層がともに増えている格差の広がりに言及していました。メディアもこのように指摘する企業減税。税負担の面で、企業の負担をもっと強めてよいと思うのです。
ところが、日本経団連は、以下にみるようにさまざまな企業優遇が税制度上もあり負担が軽減されているのに、いっそうの法人減税を要求してきました。その一方で経団連は、消費税増税を要求しつづけ、国民に負担を強いてきたのです。結果的に庶民への増税分がほとんど法人減税に匹敵する規模でした。
その際、財界がもちだすのは、日本の法人税が外国とくらべて高いという理由です。けれど、これは実際どうなのでしょうか。
日本の税率は、地方税をふくむ実効税率をみると、アメリカやドイツと同程度です。日本が異常に高いということではありません(上表、数字は%)。その上、ヨーロッパ諸国は、社会保険料の事業主負担が日本より高いところが多いのです(下表)。経団連は、法人税率をもちだだして、それが高いと「国際的競争力がなくなる」と宣伝しましたが、根拠がないのではないでしょうか。
| 法人所得課税 | 事業主負担 | |
|---|---|---|
| 日本 | 3.8 | 4.5 |
| アメリカ | 2.2 | 3.4 |
| イギリス | 2.9 | 3.7 |
| ドイツ | 1.6 | 6.9 |
| フランス | 2.8 | 11.0 |
税制度上は、たとえば、2003年度から導入された研究開発減税というものがあります。売上に占める研究開発費の比率に応じて、研究開発費の8~10%を法人税から税額控除するものです。大企業ほど限度額いっぱいまで控除を受けているといわれています。そのほか、外国税額控除や配当益金不算入などもあって、これらは大企業の実際の税負担を大きく引き下げているのが実情です。だから、上表では実効税率が39.54%とありますが、実際はこれを大きく下回っています。
根拠もなく他国とくらべ法人負担が高いと大企業がいい、法人税減税を要求し国民に負担を転嫁している実態は、ゆがんだ税制といえるでしょう。むしろ競争力を弱めているのは、大企業の権益のみを追求し、国民の生活を疲弊させることにこそあると私は思います。企業に社会的責任というものがあるのなら、それにふさわしい税負担をすべきです。
道路特定財源問題もむろん解決しなければならない課題にちがいはありません。その際にも、大企業の負担、税優遇を聖域とはせず、まず歪みをただし、応分の負担を求めていくことを欠いてはなりません。
■よろしければ、応援のクリックを ⇒
■ブログ村ランキング、こちらもお願い⇒![]()
注;表は『経済』07年4月号をもとに改変した。
PS;自民税調の津島氏は以下のように、社会保障目的で消費税増税を導入すべきと繰り返しのべています。
消費税は社会保障税とすべき=津島自民党税調会長
自民党税制調査会の津島雄二会長は9日の民放テレビ番組で「消費税は社会保障税としてはっきり性格を決めるべきだ」と述べ、社会保障財源として目的税化すべきとの考えを示した。
番組終了後、津島会長は記者団に対し、消費税の目的税化を与党税制改正大綱で明記するかどうかは「思案のしどころ」と述べ、明記する方向性に含みを持たせた。
与党は13日に2008年度税制改正大綱をまとめる。08年度改正での消費税引き上げは見送る方針を固めているが、大綱では、将来の税率引き上げに向けた道筋を示す方向で調整している。
(追記・12月10日)
消費税増税;気脈通じる自民、民主。
消費税増税にむけて明確にレールが敷かれつつあります。この一大事にこそ民主党に踏ん張ってほしいのですが、あにはからんや、以下のとおりの実情がある。
08年の配偶者控除見直しは見送り、自民税調会長が表明
自民党税制調査会の津島雄二会長は25日、NHKのテレビ番組に出演し、政府税制調査会(首相の諮問機関)が提案した、専業主婦のいる世帯に有利になっている所得課税の配偶者控除の縮小など各種控除の見直しについて、「税制全体を見直すときならいいが、今度の改正でやる気持ちはない」と述べ、2008年度税制改正では見直さない考えを明らかにした。
負担増は09年度改正以降に先送りすることになる。一方、財政力が弱い地方自治体に国の税収の一部を回す地方交付税については「増やす方向で(政府に)検討してもらっている」と述べ、08年度予算では07年度より手厚くすべきだとの考えを示した
消費税については「社会保障税に、はっきりすべきだ」と明言し、社会保障費の財源に充てる目的税にすべきだとの考えを強調した。民主党税制調査会の藤井裕久会長も「(民主党は)完全に目的税化しようとしている」と述べ、消費税の社会保障目的税化で意見が一致した。
注目したいのは後段です。どうやら自民、民主は税でも気脈を通じているようです。
もっとも民主党はこれまでも消費税増税を政策としてもかかげていました。
出(歳出)はここではいったん横に措くことにしますが、入(歳入)、とくに税をどこからとるのか、大いに議論されてよいのではないでしょうか。
税負担について大企業は企業の負担割合が高い、競争力が落ちると常々、口にします。そうでしょうか。けっして日本の企業の負担割合が高いのではない。こんな口実で大企業を優遇する税制度になってきた結果、この間、消費税増税分がそっくりそのまま企業減税に化けていった経過があります。
税は本来、所得の再分配機能をもつといわれていますが、日本のこの間の税制「改正」は、むしろ本来の税の機能に背をむけてきたといえそうです。よく例にあげられるように、たとえばトヨタは膨大な利益をあげ、世界一、二を争う自動車メーカーです。
大企業に応分の負担をさせることが必要だと思います。
一致しているという社会保障目的に特化した消費税増税。社会保障という特定の目的に使うというわけです。こんなのまやかしだと、率直に思います。自公政権がやってきたことをふりかえると、定率減税廃止の際、そこで浮いた財源は基礎年金の財源にあてるというものでしたが、現に積み立てた額は微々たるものではありませんか。
そもそも消費税は、税負担の点でみれば、社会保障の観点と真っ向から対立するものでしょう。なぜなら、消費税負担率は低所得者ほど高いというのですから。
民主党が消費税増税になぜ賛成するのか。大企業に税負担を求めることがなぜできないのか。つまるところ、それは、自民党と同じように、大企業からの企業献金をきっぱり断れないところに起因するでしょう。政党の運営資金で、国家からの政党助成金と大企業からの企業献金がかなりのウエイトを占め、それに依拠する政党は、その政策もまた、企業の意向を受けざるをえない。それだけでなく、政権交代をいえばいうほど、大企業との穏便な関係を志向する方向に向かうのでしょう。
しかし、ほんとうに国民の立場に立つというのなら、党の運営もまた、国民からの浄財に依拠したものに抜本的にかえていく、そんな決意が民主党には求められるのです。それはしかし、ほとんど無理といってもいいのでしょう。
■よろしければ、応援のクリックを ⇒
■ブログ村ランキング、こちらもお願い⇒![]()
PS;民主党の姿勢はおそらく以下にかかわっています。
財界の総本山である日本経団連は、03年から“通信簿”方式の「献金促進」策を導入、企業献金の増加をはかっています。これは、日本経団連が政党の“通信簿”をつけて献金のガイドラインをつくり、良い“成績”をとった政党への献金を企業に呼びかけるというもの。財界・大企業いいなりの政治をおこなわせるために、カネでつろうという魂胆です。これは、買収ともいえるもので、無批判であってはならないと思うのです大企業ばかりが大儲けし、格差を広げ、国民に負担と犠牲を負わせることが、企業のはたすべき社会的貢献でしょうか。企業・団体献金は、即刻禁止すべきです。
【関連エントリー】
社会保障目的などとごまかすな;消費税。
社会保障目的などとごまかすな;消費税。
舛添氏はすでに同主旨のことをのべていたので、その見解をあらためて示したことになる。
最近、彼が語ったのは以下の内容だった。
社会保障費の自然増2200億円の圧縮について、「やれるかと言われると、もうほぼ限界に達しているという認識はある。2008年度、09年度と考えたとき、やはり見直すべきとの雰囲気は、総裁選の時の自民党内にもあった」と述べ、毎年度、機械的に2200億円を圧縮すべきとする考え方は見直す必要があるとの考えを示した。(10月1日)
http://www.healthnet.jp/syukan/pages/2007/10/sf000010_1.htm
しかし、これをまともに受け取るのは足元をすくわれそうな気配だ。厚労相はちゃんと、つぎのように言葉をついでいる。
負担も考えないといけない。
社会保障の特定目的での消費税ということも一つの選択肢で考えてよいと思う。
本音はここにあるといえるのかもしれない。福田首相は所信表明演説でも消費税導入の意思を明確にしていたし。
けれど、だれでも分かるとおり、消費税は低所得者ほど負担割合が高くなる。たとえば10000円の商品を買えばその5%、500円の消費税を消費者は負担しないといけない。現在は食品にも消費税がかかる。月収20万円の人の負担割合が同200万円の人と単純に比べた場合、10倍なのは明らかだろう。
これは低所得者ほど重い逆進性といわれ、所得税が高所得者ほど税率が高くなっている(累進性)のと異なる。
社会保障の精神が、高所得者から低所得者への再分配の機能を果たすところにあると考えるならば、消費税は社会保障とは相容れない税金だといえる。
悪くいえば、舛添氏の答弁は、羊頭をかかげて狗肉を売るようなものだ。
なんども繰り返しているが、財源をどうするのか、国民が本格的に議論する時期にきている。
安倍首相が参院選の争点にするのを避け、いまの時期に後継の福田氏がそれを持ち出すという光景に、この税金のいかがわしさを感じる。消費税を単刀直入にもちだせば国民の反発が免れない。何よりも政府与党はそのことを知っているからだ。だから、社会保障を隠れ蓑にしようという魂胆である。
消費税導入後、何が起こったのか。端的にいえば、国民が負担した税金で、財界・大企業の膨大な減税分を穴埋めしているという構図だ。
もっと怒ってよいのではないか、国民は。財界だけがほくそえむ税制は拒否しないといけないだろう。それを覆い隠す、社会保障目的の消費税がよいのかどうか、判断しなければならないのは国民でもある。
■よろしければクリックを ⇒

■ブログ村ランキングもお願い⇒
大企業が消費税を歓迎するワケ
一方で、こんなニュースを目にすると、がぜん怒りがこみ上げてこようというものです。消費税の還付額が一月で8690億円にもなる。
消費税還付、6月は過去最高の8690億円(読売新聞)
そもそもの消費税のしくみを考えてみると……
| 消費税額=「売り上げにかかった消費税額」-「仕入れにかかった消費税額」 |
これを、事業者が税務署に納税する仕組みです。
たとえば大企業も税務署に消費税を納税します。が、「仕入れで払った消費税」は、「売り上げにかかった消費税」、つまり消費者から集めた消費税から差し引かれてしまい、大企業自身の負担にはならない。この場合、実際に消費税を負担しているのは、この大企業の製品を買った消費者です。
逆に、「売り上げ」より「仕入れ」の方が大きくて、差し引いてマイナスになった場合は、逆に税務署から企業に支払われる(還付される)ことになります。工場を新設したときや、輸出企業の場合(輸出分は消費税が免税)に、還付が発生します。
この場合「仕入れ」は、原料や部品の購入の場合だけではなく、商品の運送費や倉庫代、工場の家賃、水光熱費、派遣労働者の派遣料など、およそ生産にかかわる必要な商品やサービスの購入のすべてが、「仕入れ」にみなされます。
その上、大企業の中には、部品などを納入する下請け中小業者などに「消費税分の単価切り下げ」を押し付け、仕入れの際に実質的には消費税を払っていない場合が指摘されることが、往々にしてあります。この場合も帳簿上は消費税を払った計算になり、売り上げにかかった消費税から引くことができるのです。消費者と下請け業者が消費税を二重に負担する結果となり、税務署に納税されない分が大企業の「益税」になってしまいます。
大企業が消費税、消費税と歓迎するのは、増税されても自分は少しも困らないどころか、逆に税金が懐に入るからだと考えていいのではないでしょうか。
■よろしければ、応援のクリックを ⇒
■ブログ村ランキング、こちらもお願い⇒![]()
PS;はてなダイアリー(ここ)には、誤った主張としてわざわざ紹介があります。たしかに引用されているサイトの説明不足は否めないようです。しかし、本来、消費税というしくみでは大企業が基本的に税金を払わず、税金の差額分(上の囲み)を手中にすることがむしろ重要でしょう。
はてなダイアリー【輸出戻し税】;http://d.hatena.ne.jp/keyword/%CD%A2%BD%D0%CC%E1%A4%B7%C0%C7
安倍首相;「消費税は上げない」とは言ってない?!
安倍晋三首相は5日夜、日本テレビの番組で「私たちは秋に抜本的な税制改正を行う。消費税を上げないなんてひと言も言っていない」と述べ、秋の税制改正論議で消費税率の引き上げを含めて検討する考えを示した。2009年度に基礎年金の国庫負担率を2分の1に引き上げる財源を問われたのに答えた。
消費税を巡って首相はこれまで「税制改革の本格的、具体的な議論を行うのは秋以降になる」などと述べるにとどめており、引き上げの方向をにじませる表現は避けてきた。参院選を控えた時期の発言だけに論議を呼びそうだ。
首相はまずは歳出削減を徹底すべきだとの考えを強調。そのうえで「私は決して消費税から逃げるつもりはない。ただ今の段階で何パーセント引き上げると言ってしまえば、緩んでしまう」と語った。
昨日のエントリー;消費税増税が待っている;知ってる? 人頭税石で消費税を取り上げたので、驚きました。余りに符合する。
何かがある、こう疑いました。
やはり久間辞任に公明党がからんでいると指摘する向きもあって、私が疑うのはその線です。つまり、公明党からの圧力も考えられるという推測です。
なぜなら、首相が語るように、そして昨日エントリーで指摘したように、消費税導入のいまの口実は、基礎年金財源にあてるというもの。
けれど、これは定率減税廃止の際、公明党がこれで生まれる財源を基礎年金財源にあてがうということを増税のいいわけにしてきたのです。それで公明党は「増税戦犯」ともマスコミからも指摘されたいきさつがあります。公明党は「基礎年金の財源に活用。将来は国民に還元」と説明してきたのですが、これが積み上げられていないといけないのに、積み上げられていないのです。極論すれば詐欺行為にも等しいといえるでしょう。
増税の旗をふったのは公明党
だから、選挙対策上は、ここにたいする批判をかわさないと、公明党は厳しいわけです。だとすれば、自民党が浮かび上がる可能性も少なくなってくるでしょう。そのために、消費税を財源とふれざるをえなかったのです。
選挙前に増税を語ることは避けたい、しかし、後ろからは「戦犯」の批判が飛んでくる。こんな窮状にたたされた苦肉の策ともいえるかもしれません。こんな推測も可能なのではないでしょうか。
それならば、増税をやる自民、公明にはもちろんノー。そして野党の中で消費税増税を可とするところにもあわせてノンをつきつけなければなりません。

■ブログ村ランキング、こちらもお願い⇒
【関連エントリ】
「骨太の方針」;いちばんの狙いは何か
消費税増税が待っている;知ってる? 人頭税石
身長が、いまのメートル法でいえば143cm以上の男女に、のちに年齢基準にかわり、15歳から50歳までに課税されたそうです。税として、男性は栗などの穀物、女性は上布を貢納させられたといいます。
発端は薩摩藩に支配され、税を支払わなければならなくなり、財政的に困窮した王朝が定めたもの。宮古島では、人頭税石と同じ背の高さになると課税されたというわけです。
島民にとって過酷であったはずの人頭税は、それでも年齢や身長などの一定の制限があった。消費税は赤ん坊から高齢者まで、すべての人を対象にした税金。人頭税より過酷な税金です。
6月には住民税の増税に私たちは驚きました。並行して、消えた年金にたいする不安が襲いました。
自公政権は、参院選後、消費税の導入の糸口を見出そうとしています。
小泉前首相は自分の任期中に消費税の導入はないといってのけましたが、やり残した仕事を引き継ぐかのように、「逃げず、逃げ込まずの姿勢でのぞむ」といったのが安倍首相です。選挙後の秋に議論をはじめ、来年3月までに結論を出す予定なのです。尾身財務大臣はすでに、方向性が出れば来年1月からの国会に法案を提出する意向を示しています。
だから、消費税にたいする各党の姿勢にも目をむけざるをえません。
消費税導入の理由とされてきたものを整理すると……
- 財界の要求は、法人税をさらに減税すること。その財源として消費税増税が見込まれること。この方向が今年はじめの経団連・御手洗ビジョンであらためて示されました(*)。政党には献金をちらつかせ、これを実行させようというものです。
- 2009年の基礎年金の国庫負担を現在の3分の1から2分の1に引き上げるための財源にあてる
- 国の地方への補助金、交付金などを減らす引き換えに地方消費税をふやすため
しかし、そもそも消費税は最終的には消費者である国民が負担します。ですから、低所得者ほど負担率が高い大衆課税です。逆進性をもつ税金です。
一方で、大企業は実質的に税金を他に転嫁するわけですから、負担はゼロです。ましてや、導入の理由に法人税減税をあげるわけですから、二重に国民への負担を押し付けるものといえないでしょうか。
基礎年金は消費税でまかなうという口実がありますが、しかし、5000万件という膨大な数の年金が不明なわけです。こんなずさんな運営で、消費税を基礎年金にあてるでは通用しないといっても過言ではないでしょう。
これまで消費税論議の歴史をふりかえってみると、ときどきの与党、そして民主党など野党からも、社会保障を目的として消費税を導入するという考え方が出されてきました。基礎年金にあてるというのもこの延長線上の議論です。
社会保障への公的責任を強調するのは左翼だとするとらえ方もあるようです。が、税をどこに分配するかという問題と、税をどこからとるかという問題とは、すなわち同じことをちがった切り口で表現しているにすぎないと私には思われます。
そのことが、今の局面にもっとも鮮やかに映しだされているような気がします。
それは、御手洗ビジョンが隠すことなく語っています。
消費税は1%税率を上げれば2兆4000億円の税収が入る。これを誰が負担し、誰のもとに渡るのか。財界は、これを分捕り、庶民に負担を押し付けようとしている。はっきりとした階級的対立がここにある。
年金、住民税の怒りを今度は消費税増税反対へ。
■よろしければ応援のクリックを⇒

■ブログ村ランキング、こちらもお願い⇒
*「御手洗ビジョン」 -大企業の横暴勝手表す
増税の旗をふったのは公明党
これを打ち消すのに必死の公明党。
そこで、公明党自身が作成した「反論資料」をみてみたいと思います。
公明党ホームページ;変わる税と社会保障 Q&Aでは次の説明があります。
その1、その2
その1では、税源移譲にしぼって説明したつもりでしょう。納税額に変化がないことを強調しています。だが、現に税源移譲でも負担増が発生しています。前年の所得をもとに計算する住民税は、一定の収入を得ていた人が、ことし収入を大幅に減らしたような場合、住民税の増加だけがふりかかる。税源移譲で「増税」になる人は数百万人に上るとみられています。こうなることは、ほとんど周知徹底されていません。
そして、その2。
定率減税廃止によって得られる財源は、公明党によれば、「基礎年金の財源に活用。将来は国民に還元」と説明。しかし、これが積み上げられていないといけないのに、積み上げられていないのです(下記関連エントリー)。
同党は、これまで以下のように宣伝していたのです。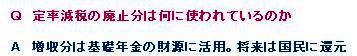
=====
定率減税縮減で生じる財源 年金国庫負担上げに充当 与党年金協で確認
井上政調会長は「定率減税の縮減・廃止は、わが国の経済社会の動向を踏まえつつ、今後の与党税調や政府・与党間の議論を踏まえて行われるものだが、少なくとも(従来からの公明党の主張通り)それで生じた財源は国庫負担引き上げに充てることを改めて確認した」と述べた。
編集メモ(公明新聞2・23)
自民党は最後まで明確な財源に踏み込まず、民主、共産両党は「公共事業の削減」などと十年一日のごとく非現実的で無責任な財源論に逃げ込んだ。
これに対して公明党は、既に政府内で「景気の動向次第で定率減税は廃止」と言われていた事態を重視。定率減税の打ち切りを座して待つのではなく、基礎年金財源に活用すれば、年金負担の軽減につながり、国民に還元されるとの結論に至ったことも、周知の事実である。
このように、定率減税をただ廃止するのではなく国民に還元する道筋を付けた公明党を「増税戦犯」呼ばわりするとはお門違いも甚だしい。難クセもいいところだ。
=====
以上の2つの引用で明確なわけですが、定率減税という増税をやるため年金財源をもちだしたのです。「国民に還元する道筋を付けた」という以上、それは財源がきちんと積み上げられているのを確かめてからいってこそ生きるもの。「増税戦犯」があたっていないのならば、常日頃「強硬姿勢」も何ら辞さない同党なのに、一切その動きがないのはどうしてか。
反論の余地がないからにすぎません。
今の税制の基本方向は金持ち・大企業優遇の減税、庶民増税。これは、かつての公明党のいってきたことからすれば、断固反対すべきものではないでしょうか。これに反対できない同党は、まさに政権にしがみつく党以外の何者でもないと思えるのです。
どうみても、増税の旗をふったのは公明党なのです。
■よろしければ応援のクリックを⇒ 
■ブログ村ランキング、こちらもお願い⇒![]()
【関連エントリー】
6月から住民税値上げ。税制のあり方はこれでよいのか
住民税増税;日本列島、「怒りの列島」?
そして、サラリーマンも支給日が遅い方でも給与明細がもう届いている頃。
どうでしょうか、随分上がったと実感されるのではないでしょうか。
住民税値上げなどで検索をかけた当ブログへのアクセスがこのところ続いています。
当ブログでは、住民税値上げでエントリーをあげてきましたが、簡単にまとめ直してみます。
■「負担は基本的にかわりません」という宣伝
福岡市が配付しているパンフレットの文言(写真上、クリックすると拡大)をごらんください。
これが、政府の宣伝物も強調する基本パターンです。いかにも、変わらないかのような印象を受けるはずです。福岡市の場合、アンダーラインを施し、強調しています。
総務省ポスターは、「定率減税の廃止などによる影響がありますので、ご留意ください」と小さな字で記載しています。これも、同じように変わらないことを強調。
総務省ポスターは、ここ。
まさに、だましのテクニックではないのか。
■そもそものしくみ
今月からの住民税値上げは、定率減税全廃と税源委譲によるもの。
税源移譲は、国から地方へ3兆円の税源を移すもの。
所得税の税率を下げ、住民税税率を上げます。
ところが、これに定率減税全廃のための増税が加わるのです。
- 住民税(年3.4兆円の増加);定率減税の全廃による増税額 →年間4000億円。税源委譲影響額(増額) →3兆円
- 所得税(年1.7兆円の増加);定率減税全廃による増税額 →年間1.3兆円。税源委譲による減額 →年3兆円
- したがって、6月以降は住民税増額分3.4兆円-所得税減額分1.7兆円の差し引き額1.7兆円が住民税の値上げという形で現れてきます。
■結局、庶民の増税分はどこへいく
- 財務省の計算によると・・・・・・定率減税の廃止で生みだされる財源は3.3兆円今回住民税増税分は1.7兆円
- 企業減税は、今年の予算では・・・・・・減価償却制度の見直し、証券優遇税制の延長で1.7兆円の減税
- だから、定率減税の廃止による増税分はほぼそっくり大企業などの減税分にあてられるということです。
■誰が増税してきた
定率減税を推進したきた公明党は、基礎年金への国庫負担引き上げさせるために定率減税をおこなってきたといわんばかりの宣伝をしています。
しかし、、これはまやかしというもの。
財務省が示しているのは、わずか2200億円を国庫負担引き上げに使うというものです。「百年安心」は嘘っぱち!
増税をすすめたのは、自民、公明の政権です。
役所への問い合わせが殺到しているそうです。増税額に頭にきて抗議する人も。まさに「怒りの列島」と化しているといってもよいようです。
こんなはずではなかった、はもうやめなければなりません。参議院選挙でリベンジです。
■よろしければ応援のクリックを⇒ 
■ブログ村ランキング、こちらもお願い⇒![]()
*共産党ホームページで住民税シミュレーションが可能です。サラリーマンは、ここ。自営業の方などは、ここ。
【関連エントリー】
住民税値上げがやって来た!
6月からの住民税増税はどうなる?
6月から住民税値上げ。税制のあり方はこれでよいのか
住民税値上げがやって来た!
 各世帯に納税通知書が送られてきているようです。
各世帯に納税通知書が送られてきているようです。
私の住む自治体の行政区窓口には問い合わせの電話が殺到しているもよう。
世間では、消えた年金問題で社会保険事務所の混乱ぶりが伝えられていますが、その陰で住民税値上げに驚く住民も決して少なくないようです。
今月からの住民税値上げは、定率減税全廃と税源委譲によるもの。
定率減税の全廃によって、住民税は年間4000億円の増税に加えて、国から地方へ3兆円の税源委譲影響額が加わるために、住民税は年3.4兆円の増加が見込まれています。
一方、所得税は、定率減税全廃による増税1.3兆円分を、税源委譲による年3兆円の減額で吸収し差し引き1.7兆円減額となります。
したがって、6月以降は、住民税増額分3.4兆円-所得税減額分1.7兆円の差し引き額1.7兆円が住民税の値上げという形で現れてきます。
税源の差し替えのために、「所得税+住民税」の負担は基本的には変わりません、と説明している自治体が多いようです。福岡市のパンフレットにもそう記載されています。
しかし、定率減税の全廃のために増税になるのです。
それだけではなく、税源移譲の部分でも増税になることが伝えられています。06年に比べて07年に大幅に所得が減った場合、最大で97500円増加することを総務省が認めたそうです。
通知書をみて値上げ幅にあっと驚く方がおられるかもしれません。サラリーマンは今月の給与明細を確認してみる必要があります。
国民よ、怒れ!
■よろしければ応援のクリックを⇒ 
■ブログ村ランキングにも参加、こちらもお願い⇒![]()
注;福岡市は、「ただし、定率減税の廃止等が同時に行われるため、税源移譲以外の税制改正のために税負担は増えることになります」とただし書きで負担がふえることを明記しています。
6月からの住民税増税はどうなる?
 今月から住民税が上がります。
今月から住民税が上がります。定率減税全廃と税源委譲による個人住民税の値上げです。
定率減税の全廃によって、住民税は年間4000億円の増税に加えて、国から地方へ3兆円の税源委譲影響額が加わるために、住民税は年3.4兆円の増加が見込まれています。
一方、所得税は、定率減税全廃による増税1.3兆円分を、税源委譲による年3兆円の減額で吸収し差し引き1.7兆円減額となります。
したがって、6月以降は、住民税増額分3.4兆円-所得税減額分1.7兆円の差し引き額1.7兆円が住民税の値上げという形で現れてきます。
税源の差し替えなので、「所得税+住民税」の負担は基本的には変わりません、と説明している自治体が多いようですが、そうではありません。定率減税の全廃のために、以下にみるように増税になるといえるでしょう。
上図は、階層ごとに所得税・住民税の総計でどんな影響がでるかを示したものです(図をクリックすると拡大します)。しんぶん赤旗(6・1)で紹介されたものをつくりかえてみました。
表の最右欄に増税のトータル額と住民税額を表していますが、いずれの階層とも増税になっています。朱色部分が昨年12月からの所得税・住民税あわせた増税額。
700万円や1000万円の層にくらべると、より所得の高い1500万円の層でむしろ低い増税額になっているのが特徴でしょう。500万層では、5月までの住民税の190%にもなる大幅増税です。ここにも、高額所得者への減税、庶民増税という、いまの税制の基本的な方向が示されているように感じます。
個人の懐はいずれにせよ「寂しくなる」わけで、これが国内消費にどのように影響するのかも見過ごせないところでしょう。
■よろしければ応援のクリックを⇒

■ブログ村ランキングにも参加、こちらもお願い⇒
【関連エントリー】
6月から住民税値上げ。税制のあり方はこれでよいのか
6月から住民税値上げ。税制のあり方はこれでよいのか
今年に入って税金が安くなったと感じた方もおられるでしょう。現に1月分給与から天引きされる所得税は多くのかたが額面は少なくなっています。しかし、逆に6月から住民税が上がるのです。税源委譲という国から地方へ「税金の差し替え」がおこなわれるためです。だから、多くの人は住民税が約2倍にはねあがる。高齢者は年金課税が強化させるためになかには4倍になる人もでてくるのです。そろそろ届きはじめた通知書をみて、その税額に驚いた人も少なくないかもしれません。
財務省の計算では、定率減税の廃止で生みだされる財源は3.3兆円。今回住民税増税分は1.7兆円。一方、今年の予算では減価償却制度の見直し、証券優遇税制の延長で1.7兆円の減税を盛り込んでいます。
定率減税を推進したきた公明党は、基礎年金への国庫負担引き上げさせるために定率減税をおこなってきたといわんばかりの宣伝をしていますが、これはまやかしというもの。財務省が示しているのは、わずか2200億円を国庫負担引き上げに使うというものです。
だから、定率減税の廃止による増税分はほぼそっくり大企業などの減税分にあてられるということです。
政府は、年金への国庫負担のためには、必要額の8割をまかなうために消費税をふくむ税制の抜本的見直しが必要だといっているのが現状です。
4期も連続して過去最高益を更新する大企業。他方で、我われ一人あたりの給与に関するデータは芳しくありません。11カ月連続して所定内給与は減少。
大企業に富が集中し、庶民のふところは一向に温まらない構図がここにみえてきます。
それは、税制における大企業や金持ちへの減税の一方で、今回の定率減税全廃やこれまでの消費税増税に端的に象徴されるような庶民増税をつづける自民党政治がつくり出した結果だといえないでしょうか。
最近はややトーンダウンしつつあるようですが、景気回復などといわれた割に庶民の懐が温まらず、国内の消費が伸びない一因はここにあるでしょう。
参院選はこの意味で、税制に映し出される政治のあり方を問う、またとない機会ではないかと思うのです。
■よろしければ、応援のクリックを ⇒ 
■ブログ村ランキングに参加、こちらもお願い⇒![]()
石原知事も「一大臣」も同じでは;税制見直し論
ともあれ石原都知事の言動がメディアをにぎあわせています。
法人税収が東京都に集中しすぎているとして、菅総務相が地方間格差是正の税制改正の必要性を強調していることに、石原慎太郎都知事が反発している。「一大臣が言うことじゃない」「東京が転んだら日本が転ぶ」などと批判、国を相手に訴訟を起こしてでも再考を促す考えを示した 。(石原知事、税制見直し論に「一大臣が言うことじゃない」、朝日新聞電子版4・24)
当選後の挨拶回りでは、共産党控室には入りもしなかったそうですから。そして、「借りは返す」という捨て台詞。最も恐れていて、かつその存在すら否定しようと思っている政敵は誰か、この石原氏のふるまいに如実に表れています。
こんな石原氏が、政府を牽制しています。菅総務相にむけて発した言葉は、「一大臣が言うことじゃない」。氏の言葉が正しいのなら、快哉をさけびたいのですが、それはできない。都に入る税金は、金輪際、政府には渡さない、そんな意気込みは感じられるわけですが、つまるところ税制見直しでの都の税収不足がちらついて石原氏は発言しただけのことにすぎません。
けれども、税金は、財界・大企業からも、そして庶民からもとっているわけで、それは国も東京都をふくむ地方自治体も形式的には一緒。問題は、どのように、だれから取るかということです。
その点では、菅氏の発言は、自治体の税収構造を地方消費税のウエイトを高めようといっただけで、同時に法人事業税のウエイトを低めるということです。むろん法人事業税による税収の比率の高いところは打撃をこうむる。
重要なことは、石原氏にしろ、菅氏にしろ、財界をはじめ、もうかっている大企業は応分の負担をすべきという観点には立っていないことでしょう。
財界は、税金負担をいかにして減らそうかと考えているわけで(昨日のエントリー)、法人事業税の廃止という財界の主張は当然、菅氏の頭にあるでしょう。あえていえば、財界の主張を菅氏は繰り返したにすぎません。なるほど財界がいうように消費税率を引き上げ、地方消費税を現行25%(現行は国の消費税率は4%、その4分の1が地方消費税で合計5%)から引き上げれば地方に財源は回る。しかし、負担するのはなんのことはない国民であって、二人とも同じ穴の狢です。もうかってる企業はもっと税金を負担すべきだと、石原氏がいったのなら私も拍手で歓迎したでしょうが。
だから「国の財政のかじ取りが下手くそなために、東京の存在が際だってしまっている」などと石原氏が豪語するのは、ちょっと手前味噌の感じがしてなりません。
実際、かくいう東京都も以前、以下のようにいっていました。
都税収入は、景気の変動を受けやすい法人二税のウエイトが高く、近年の景気の低迷により大きく減少しています。こうした不安定な税収構造に加え、都は地方交付税の不交付団体であり、歳入構造の安定性を確保することが課題となっています。
http://www.zaimu.metro.tokyo.jp/syukei1/zaisei/kouzoukaikaku2.pdf
東京都も景気に左右されてきたのです。景気回復が基調だとしても、石原氏の采配で都のみ景気が回復するなど、考えられることではありません。
ほんとうのかじ取りをいうのならば、やはり儲かっているところから税金をとるという、税制のあり方に立ち返るべきではないでしょうか。累進課税強化と法人優遇税制をあらためるということは、ただちに手をつけてもおかしくはないと私は思うのです。
■よろしければ応援のクリックを⇒ 
| « 前ページ | 次ページ » |

















