
7月8日は、大阪北浜にある老舗料亭「花外楼」へ。




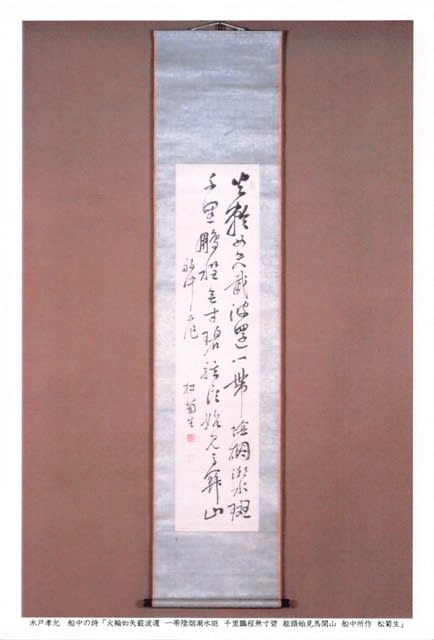
津端道彦 蹴鞠






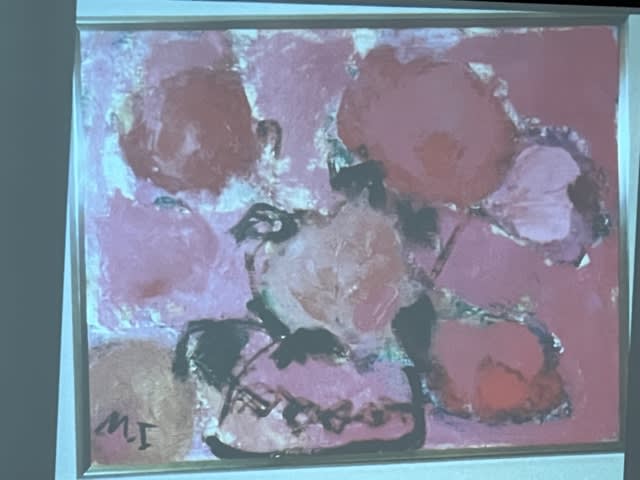

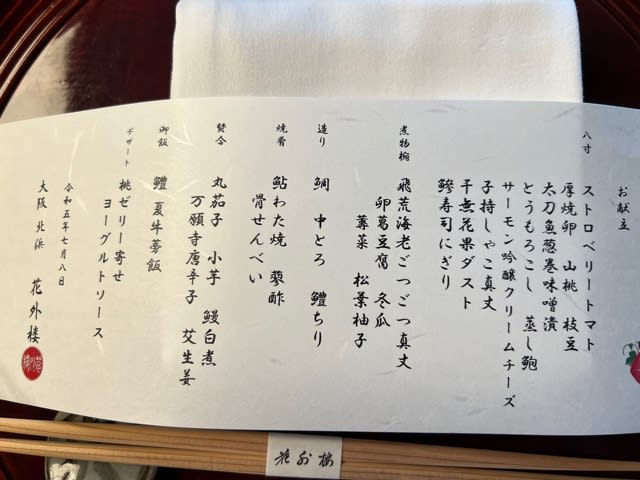



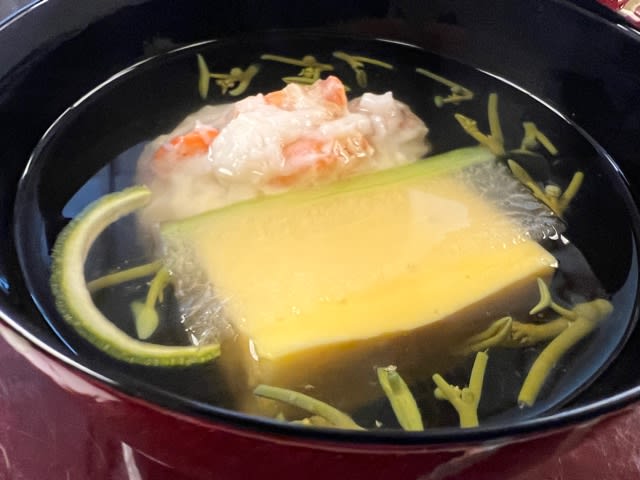












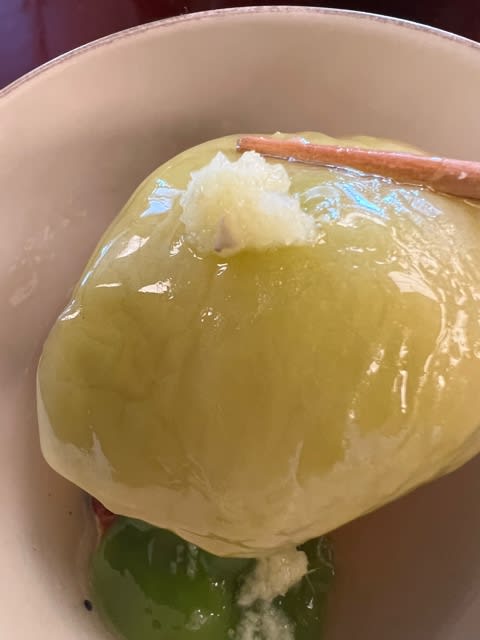










玄関を上がった所には「天神祭のお迎え人形」が飾られています。
「花外楼」の所蔵ではなく、大阪天満宮から貸与されているそうです。
京都の記事をメインに書いていますが、こちら「花外楼」も京都と同様に明治維新に大きな影響を与えた由緒ある場所です




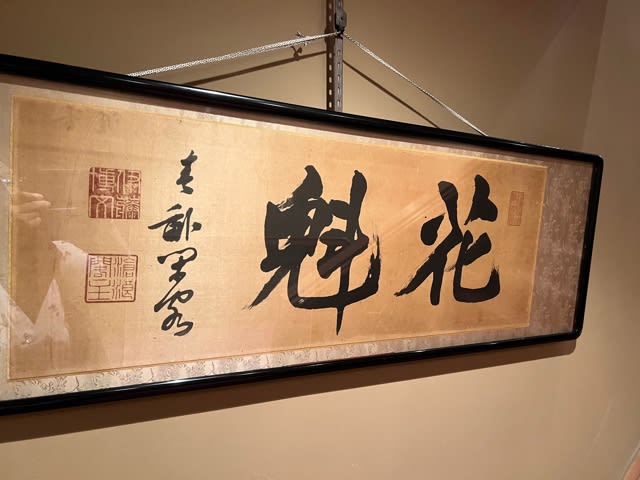

下の写真の扁額は、大阪会議の成功を祝って、木戸孝允が新しく「花外楼」と揮毫したものです。


創業は江戸時代天保年間(1830)と言いますから200年近い歴史があります。

加賀国出身の初代伊助が大阪北浜の現在地に料理旅館「加賀伊」を開いたのが花外楼の始まりです。
幕末には伊助の誠実さが信頼を得て、木戸孝允(後の桂小五郎)ら明治維新の歴史に名を残す志士達の集いの場となりました。


明治8年2月11日に「加賀伊」で行われた「大阪会議」、、、伊藤博文、井上馨の斡旋のもと。薩長土の大久保利通、木戸孝允、板垣退助らが集い、ここに立憲政治体制の基礎が築かれた重要な場所です。
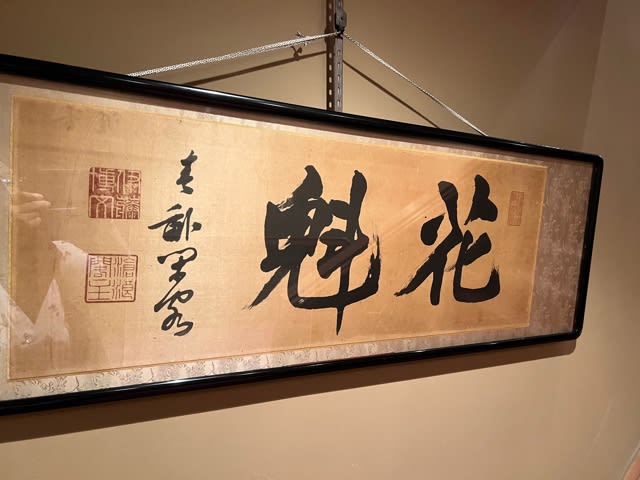

下の写真の扁額は、大阪会議の成功を祝って、木戸孝允が新しく「花外楼」と揮毫したものです。
それ以降、屋号を「加賀伊」から「花外楼」に変えています。

所蔵されている木戸孝允 船中の詩
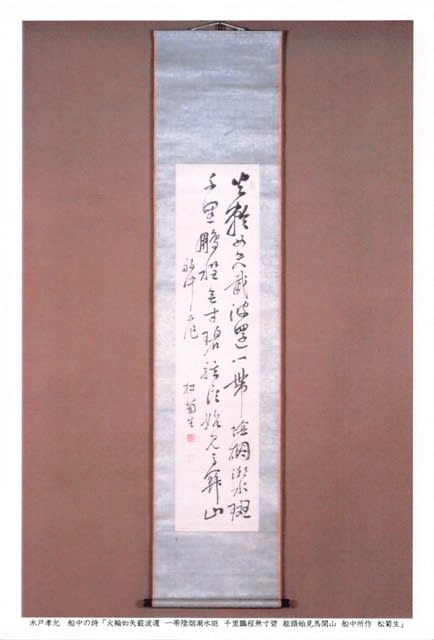
津端道彦 蹴鞠

これから「京の女将さんシリーズ-番外編」で
日本料理「花外楼」五代目女将・徳光正子さんとラジオパーソナリティーでお馴染みの鈴木美智子さんとの対談です。




その後、おふたりの対談があり、洋画家としての"顔"を持つ女将さんの作品のスライドを見ながら作品について、花外楼の歴史についての会話が弾みます。

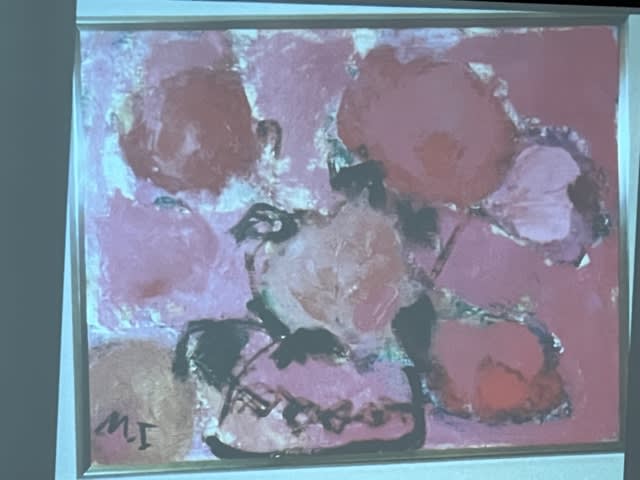

作品が揃うと時折、個展を開かれるそうです。
おふたりの会談が終わり、「花外楼」自慢の会席料理の時間です。
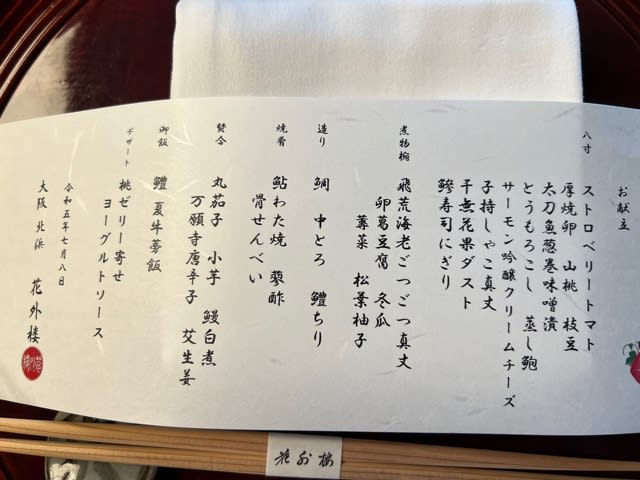


食前酒はノンアルコールの梅酒です。
さっぱりと口の中がリセットされた感じになります。
① 八寸






ストロベリートマトは"食用ほおづき"の事です。
"ほおづき"と言えば観賞用として知られ、"東京浅草のほおづき市"は有名ですね。
食用で食べられる事を初めて知りました。
さすがは「花外楼」さんの八寸だけあり、見た目よし、味よし、食材よしの三拍子が揃っています。
② 煮物椀

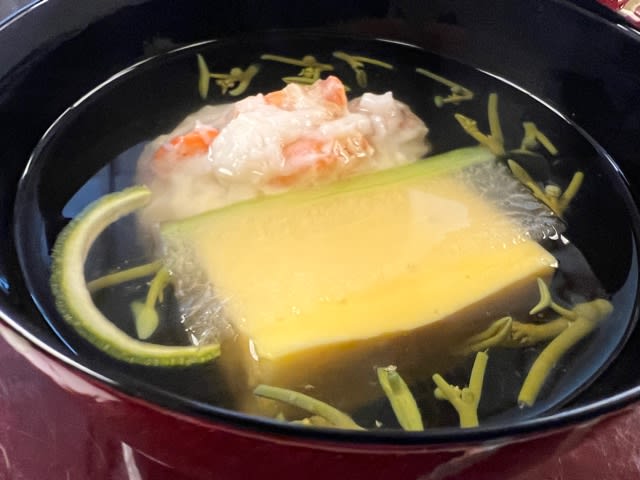

漆塗の器も美しく、お出汁や海老の真薯も絶品です。
③ 造り



鮮度を感じるお造りです。
今から旬を迎える鱧が入っているのも有り難いです。
④ 焼肴




夏の川魚の代表格"鮎"の塩焼きです。
京都では、そのまま出される事がほとんどですがそこは"食いだおれの街"大阪、、、一味違います。
鮎を三枚おろしにし、身の部分と半分に開いた頭は塩焼きに、中骨はカリッと揚げられています。
蓼酢もペースト状で出され、魚とよく絡み、最初はそのままで途中で蓼酢を付けて"味変"して頂きました。
⑤ 焚合




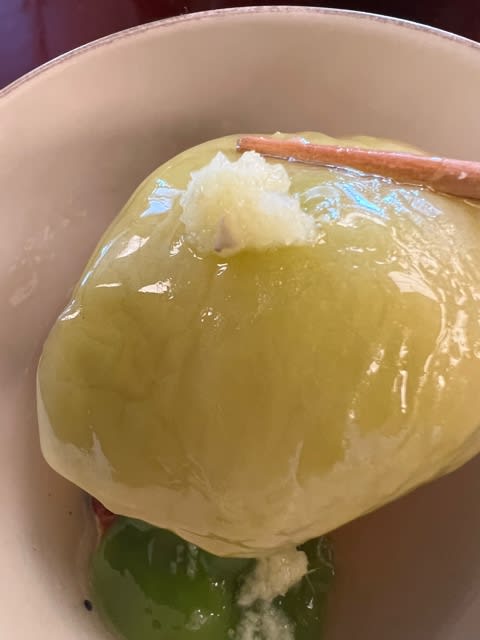
焚合もお出汁の効いた餡が食材と絡み、どれもが非常に美味しいです。
⑥ 御飯




御飯は鱧と夏牛蒡が入った御飯です。
余の美味しさに"おかわり"をお願いしました。
⑥ デザート


これから旬を迎える桃がふんだんに使われたデザートです。
ヨーグルトソースとの相性もバッチリです。
八寸からデザートまで、どの料理も見た目も味覚も素晴らしいものでした。
一品一品に決して手を抜かない、、、老舗たる由縁がここにも息づいていると感じた「花外楼」さんでした。




















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます