
昭和30年代の福岡県の炭坑町を舞台に、貧しいながらも明るく必死に生きる人々の日常と、やがて訪れる過酷な運命を描く骨太なヒューマンドラマ。福岡県出身の辻内智貴による原作を、『愛を乞うひと』の平山秀幸監督、劇作家で脚本家の鄭義信が再び組み、力強く生きる人々の魂のドラマを紡ぐ。小学生の息子と共に炭坑町に戻る主人公に『カムイ外伝』の小雪。福岡市内をはじめ、オールロケで映し出されるエネルギッシュな映像が圧巻。本作は、平山監督、原作者の辻内智貴が福岡県出身であることから、福岡県にて先行公開される。[もっと詳しく]
ご当地映画の枠組みを超えて、幅広く共感させるエッセンスがある。
昭和30年代のある時代の空気を懐古する映画と言う意味では『ALWAYS三丁目の夕日』をすぐに思い浮かべることになる。
『ALWAYS』は昭和33年の首都東京の下町、『信さん』は昭和38年の炭鉱町福岡のある島を舞台にしている。
太平洋戦争の敗北で、日本の主要都市は空襲でほぼ壊滅状態となった。
GHQの統治下にあって、日本がこの瓦礫の山から復興するためには、最低50年はかかるだろうと言われていた。
しかしながら、数百万人の戦争引揚者にみあう食料もなく、腹をすかせた孤児たちがうろつきまわっていた戦後の闇市日本は、朝鮮戦争特需もあり、わずか十年にしてGDPは大きく成長したのである。
1951年には早くも、「経済白書」で戦後は終わったと宣言されたのである。
奇跡の復興と言われるこの十年において、もうひとつ政治の果たした役割も大きかったかもしれない。
ことにジャーナリスト出身で第一次吉田茂内閣の大蔵大臣となった石橋湛山は「傾斜生産方式」と名づけられるが、国の生産の基盤として「炭鉱重視」路線をとったのである。そして鉄鋼と火力発電所が、戦後日本の「国家」政策となったのだ。
『ALWAYS』の東京タワーは鉄の象徴でもあり、そして製鉄所の炉は、石炭をフル回転させていたのである。
『信さん』の舞台となった昭和38年は、すでに「石炭」はその役割を終えつつあった時ともいえる。
昭和28年生まれの僕は、この映画の信さんや守少年と似たような年である。
僕の町には、東京タワーもボタ山もなかったが、どちらの映画にも懐かしさを覚えることになる。
人口が十万にも満たない地方都市ではあるが、駅前には舗装道路が出来、デパートや商店街が整いつつあった頃だ。
一方で、ちょっと駅裏の方は、朝鮮人と被差別が入り組んであり、闇をも含みこんだ得体の知れない匂いがついてまわった。
それなりの家々は三種の神器を手にするようになったが、ぼろぼろのシャツ姿で登校する洟垂れ小僧たちもまだまだ多かったのである。
信さんが鉄人28号の漫画に夢中になったり、守が「少年サンデー」を手にしているのも、なんだか懐かしい。
この頃のボタ山の景色や炭鉱町の共同生活や資本と労働との激しい緊張などを直接には知らない。
しかし、五木寛之の国民文学ともいえる『青春の門』や、佐世保の炭鉱で働いたこともある井上光晴の小説を通じて想像をしたりもした。
あるいは大方の予想を裏切って「晴天の霹靂」のようにユネスコの「世界記憶遺産」の対象となった山本作兵衛の筑豊の炭坑を描いた膨大なスケッチを展覧会で見て、圧倒されたことがある。
もう少し、学生時代に影響を受けたものとしては、九州の「サークル運動」を組織化しようとした「サークル村」運動がある。
谷川雁や森崎和江や上野英信らの論稿を読み漁りながら、その影響が感じられる九州にあった個性豊かな小出版社の本を次々と注文したりしたのを、よく覚えている。
あるいは、もう少し闘争的な文脈でいえば、大学紛争の味気ないアジびらにうんざりして、大正闘争の「SECT6-闘争資料集」をどこからか手に入れて、そのちょっとジャズっぽい文体のアジテーションを模倣したりしながら、自分なりの遅れてきた「工作者宣言」などをしていたことを恥ずかしく思い出す。
『信さん・炭坑町のセレナーデ』は、濃厚にある時代のある地域を舞台とした映画なのだが、近頃の薄っぺらいご当地映画とは一線を画している。
ご当地映画につきものの、とってつけたようなお祭り再現シーンや、観光絵葉書的な暢気な景観シーンがほとんど見当たらないというだけではない。
信さんや守やリー・ヨンナムや美代ら、炭鉱町を舞台にした少年少女たちの少しビターな成長物語なのだが、その年月の過程をほどよい距離をとって抒情詩のように映し出しているからだと思う。
もちろん情緒はあるのだが、それを同じ九州のご当地モノが得意な、たとえば「さだまさし」のような共感のお仕着せのようなものが少ないからなのかもしれない。
都会帰りのわけありの母である美智代(小雪)は炭鉱町では場違いな垢抜けた美しさを持っているが、信さんはとっくに死んでしまった母親への思慕と、思春期の異性への憧憬と、はたまた美智代一家を守護しようとでも言うべき男気のようなものが入り混じった感情を、抱き続けるのである。
物語は美智代と信さんの微妙な関係を縦軸としつつ、滅び行く炭鉱町の哀歓のようなものをセレナーデとして丁寧にエピソードを綴っている。
本当ならば、もっともっと泥泥した人間模様がありそうなものだが、そこは極めて抑制したスケッチのような描写になっている。
平山秀行監督は『しゃべれどもしゃべれども』(07年)でも思ったことなのだが、淡々とした関係の中で微妙な関係のすれ違いを描くのが実にうまいと思う。
また脚本の鄭義信は骨太のテーマであるにもかかわらずちょっとした風景を丁寧に書き込んでいる。
原作の辻内智貴の作品は読んだことがないが、不器用ながら暖かい人物を描くのに才があるらしく、ちゃんと小説を読んでみたい。
「愛しき人へ」というテーマソングを歌う中孝介もよくマッチしていた。
上映時には「ぴあ満足度ランキング一位」となったこの作品。
どう考えても地元福岡以外では受けそうもない主題にもかかわらず、たぶん幅広い観客に受け入れられたのには、それなりの理由があるのである。
kimion20002000の関連レヴュー
『しゃべれどもしゃべれども』











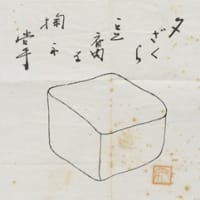


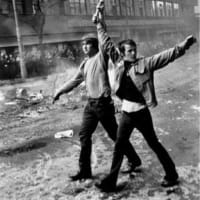



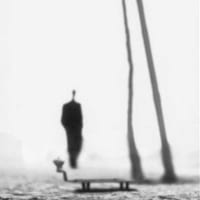

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます