
 姪っ子メグ 今日は大岡山のほうから来たけど、商店街でウォークラリーの人たちがいっぱいだったね。お天気良かったものね、行楽日和。
姪っ子メグ 今日は大岡山のほうから来たけど、商店街でウォークラリーの人たちがいっぱいだったね。お天気良かったものね、行楽日和。 キミオン叔父 わらわら湧いて出たようで。戸越公園から戸越銀座、武蔵小山、西小山、洗足、大岡山をつなぐウォークラリーだよね。商店街では、お店が「おつまみ企画」に参加していて、店前に机を出していたね。
キミオン叔父 わらわら湧いて出たようで。戸越公園から戸越銀座、武蔵小山、西小山、洗足、大岡山をつなぐウォークラリーだよね。商店街では、お店が「おつまみ企画」に参加していて、店前に机を出していたね。 渋谷も人がいっぱいだったね。Bunkamuraあたりもそろそろクリスマスの飾りつけが始まっていたし。Galleryでは、現代木版画家の風鈴丸さんが絵本を出版されたのにちなんで作品展とギャラリートークもやってたね。
渋谷も人がいっぱいだったね。Bunkamuraあたりもそろそろクリスマスの飾りつけが始まっていたし。Galleryでは、現代木版画家の風鈴丸さんが絵本を出版されたのにちなんで作品展とギャラリートークもやってたね。 静岡の育ちで40歳前ぐらいなんだろうけど、なかなか魅力的な女性だね。絵本は『ぎゅうにゅう太郎とまよなかのでんしゃ』か。今回は、インク画や絵具で、いつもの木版とは異なった制作だけど、作品世界は一貫してるね。
静岡の育ちで40歳前ぐらいなんだろうけど、なかなか魅力的な女性だね。絵本は『ぎゅうにゅう太郎とまよなかのでんしゃ』か。今回は、インク画や絵具で、いつもの木版とは異なった制作だけど、作品世界は一貫してるね。 ご本人もお美しい方よね。ちょっと天然っぽい不思議ちゃん的なところもあるし。おじさん、好きなタイプでしょ。サインもらったの?
ご本人もお美しい方よね。ちょっと天然っぽい不思議ちゃん的なところもあるし。おじさん、好きなタイプでしょ。サインもらったの? いやいや恥ずかしくて・・・(笑)。小さい頃から、カラフルな夢を繰り返し見て、彼女の中にその像というか迷宮の王国みたいなものがはっきりとイメージされている。それをあとは取り出すだけなんだよな。キャラの描線は、どこか懐かしいやわらかなタッチで。幻想的でもあるし、ポエジーでもある。ちょっと悲しみもあるし。
いやいや恥ずかしくて・・・(笑)。小さい頃から、カラフルな夢を繰り返し見て、彼女の中にその像というか迷宮の王国みたいなものがはっきりとイメージされている。それをあとは取り出すだけなんだよな。キャラの描線は、どこか懐かしいやわらかなタッチで。幻想的でもあるし、ポエジーでもある。ちょっと悲しみもあるし。 猫をたくさん登場させているね。今回の絵本では、妖精があちこちに登場して、ちょっとジブリの世界みたい。
猫をたくさん登場させているね。今回の絵本では、妖精があちこちに登場して、ちょっとジブリの世界みたい。 この人の木版多色刷りの方は、思っている色を出すためには最低八版必要で、場合によってはあと数版重ねる多色刷り、浮世絵の技法だよね。でもこういうアニミズムの世界と交信できるような女性が、この混沌の世の中をどうやって渡っていくのだろうかって・・・そっちの方が心配になってしまうな。
この人の木版多色刷りの方は、思っている色を出すためには最低八版必要で、場合によってはあと数版重ねる多色刷り、浮世絵の技法だよね。でもこういうアニミズムの世界と交信できるような女性が、この混沌の世の中をどうやって渡っていくのだろうかって・・・そっちの方が心配になってしまうな。




 松涛美術館は「大正イマジュリイ」と題して、明治末から大正にかけての装丁や挿画家やデザイナーの仕事を取り上げている。13人の仕事が展示されていたけど、おじさん、好きな人ばっかりでしょ。
松涛美術館は「大正イマジュリイ」と題して、明治末から大正にかけての装丁や挿画家やデザイナーの仕事を取り上げている。13人の仕事が展示されていたけど、おじさん、好きな人ばっかりでしょ。 ああ、いつもの竹久夢二、高畠華宵、蕗谷虹児、小林かいち、杉浦非水なんかはこれまでも多く見てきたけど、あらためてまとめてみて面白かったクリエイターもいたね。
ああ、いつもの竹久夢二、高畠華宵、蕗谷虹児、小林かいち、杉浦非水なんかはこれまでも多く見てきたけど、あらためてまとめてみて面白かったクリエイターもいたね。与謝野晶子といえば藤島武二の装丁だし、夏目漱石はモダンな橋口五葉、「明星」をデザインしていた広川松五郎や岸田劉生が「白樺派」の雑誌を任されているね。
 この時代に、一気に印刷技術が近代化して、出版物が大衆化して、そこにモダンデザインやアールヌーボー、アールデコの潮流が入ってくるのよね。
この時代に、一気に印刷技術が近代化して、出版物が大衆化して、そこにモダンデザインやアールヌーボー、アールデコの潮流が入ってくるのよね。 明るい時代とばかり言い切れないしね。「大逆事件」もおこり、社会主義者にとっては冬の時代の始まりだった。エロ・グロ・ナンセンスの風潮も出てくる。橘小夢なんかが独特の耽美的、猟奇的な版画を制作している。
明るい時代とばかり言い切れないしね。「大逆事件」もおこり、社会主義者にとっては冬の時代の始まりだった。エロ・グロ・ナンセンスの風潮も出てくる。橘小夢なんかが独特の耽美的、猟奇的な版画を制作している。 第二部は「さまざまな意匠」と称して、この時代のクリエイターを突き動かしていたテーマをいくつもあげている。そこに竹中英太郎なんかの「怪奇美」も入ってくるのね。「ドグラマグラ」の夢野久作のお父さんで、ルポルタージュの竹中労のおじいさんよね。
第二部は「さまざまな意匠」と称して、この時代のクリエイターを突き動かしていたテーマをいくつもあげている。そこに竹中英太郎なんかの「怪奇美」も入ってくるのね。「ドグラマグラ」の夢野久作のお父さんで、ルポルタージュの竹中労のおじいさんよね。 「震災のイマジュリティ」なんかもあって、震災光景がデッサンされ絵葉書なんかになってるんだけど、大丈夫、これ?といった結構悲惨な状景も描かれている。
「震災のイマジュリティ」なんかもあって、震災光景がデッサンされ絵葉書なんかになってるんだけど、大丈夫、これ?といった結構悲惨な状景も描かれている。 そうかと思えば「浮世絵のイマジュリティ」では、日本画の伝統も踏まえた小村雪岱なんかがしゃれた造本装丁で出てくるしね。一挙にデザインという世界が花開いたような時代よね。
そうかと思えば「浮世絵のイマジュリティ」では、日本画の伝統も踏まえた小村雪岱なんかがしゃれた造本装丁で出てくるしね。一挙にデザインという世界が花開いたような時代よね。 それもあと何年かすれば、戦争にひきづられていって、プロパガンダとスローガンの世界に統合されてきて、「欲しがりません、勝つまでは」というイデオロギーに浸されていく。でも大正イマジュリイの作品世界も、そんなに古書なんて買えないから、電子出版の分野で、ちゃんと保存しておいて欲しいよな。
それもあと何年かすれば、戦争にひきづられていって、プロパガンダとスローガンの世界に統合されてきて、「欲しがりません、勝つまでは」というイデオロギーに浸されていく。でも大正イマジュリイの作品世界も、そんなに古書なんて買えないから、電子出版の分野で、ちゃんと保存しておいて欲しいよな。











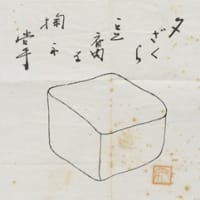


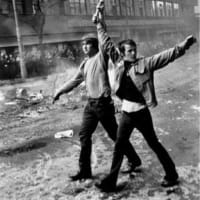



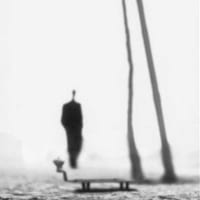

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます