18歳の青年が、量子コンピューター実現等のカギを握る「量子もつれ」を扱った論文を、世界有数の権威ある物理学誌『Physical Review A』に発表した。15歳から量子の世界に取りつかれたという彼の子ども時代等を紹介。物事は一直線に進んだわけではなかった。

アリ・ディコフスキーくん。ワシントンDCから西に約50kmのバージニア州リーズバーグにある自宅にて。Photos: Brendan Hoffman/WIRED
アリ・ディコフスキーは15歳のときに、PBSのドキュメンタリー番組で物質の新たな相であるボース=アインシュタイン凝縮(BEC)の生成に取り組む物理学者たちを知った。そのとき直観に反する量子の世界に魅了され、同時に、人々がこれまで見たことのないものを生涯をかけて作り出すという考えに心を打たれた。
BECは、1920年代にアルベルト・アインシュタインとインドの科学者サティエンドラ・ボースによってその存在を予言されていたもので、固体でも液体でも気体でもない。プラズマでもない。超低温状態でのみ生じ、不可思議な量子力学特性を示すBECは、そのいずれとも異なる物質相であり、複数の原子が集まってひとつの「超原子」として振る舞い、粒子が波のような挙動を示すものだ。
現在18歳になったディコフスキーくんは、BECとはまた別の量子世界の奇妙な現象である量子もつれに関する研究論文を、世界有数の権威ある物理学誌『Physical Review A』に[5月29日付けで]発表した。
共同量子研究所(Joint Quantum Institute)に所属する研究者スティーブン・オルムシェンクを共著者としているが、「すべての力ずくの計算や、その他の細かな作業のほとんどをアリが担当した」とオルムシェンク氏は言う。「確かに彼は若いが、主著者にふさわしい」。(共同量子研究所は、米国立標準技術研究所(NIST)とメリーランド大学カレッジパーク校が共同して運営する研究機関だ。)
この論文は、空間的に離れていて、そして非常に違いの大きいふたつの粒子を、光を使ってもつれ状態にする方法についての理論的解析であり、解析の約90%はあらゆる可能性を試すための「力ずくの計算」からなる。この論文は、技術研究の究極の目標とも呼ばれる量子コンピューター開発の試みに新たな境地を開く内容となっている。
2012年6月8日
量子のもつれの話など、からっきしわからない僕だが、こういう天才少年の話を聞くのは大好きである。
ディスコフスキー君とオヤジさんのお話など、ちょっとした映画のネタになりそうである。
このお話は、実話にもとづいています、とかなんとか。
現代物理学は、超難解な高等数学を操れなくてはならないが、その稀有な才能たちのほとんどは、金融市場にスカウトされている。
彼らが創った金融モデルなど、仲間内の天才以外にはだーれも理解できないのだ。
営業マンたちは、理屈はわからないままに、売り込むだけである。
天才たちは、扱う金額が何京であろうが、なにほどのリアリティもないだろう。
自分が関わった数学モデルで、世界の動きを予測できればいいのだから。
そうして、リーマン・ブラザーズの破綻が現実のものとなったのだ。
ディスコフスキー君は現代のアインシュタインになれるかもしれない。
しかし、アインシュタインも、原爆を生み出すひとりのモンスターとなってしまった。
生涯かけて後悔していたようだが。
ディスコフスキー君の能力は、どちらの世界に向かうのだろうか。












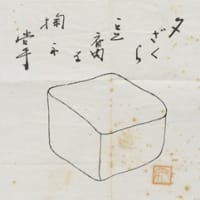


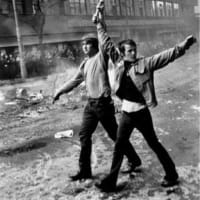



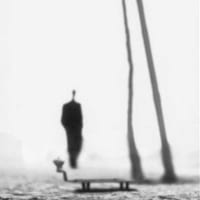

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます