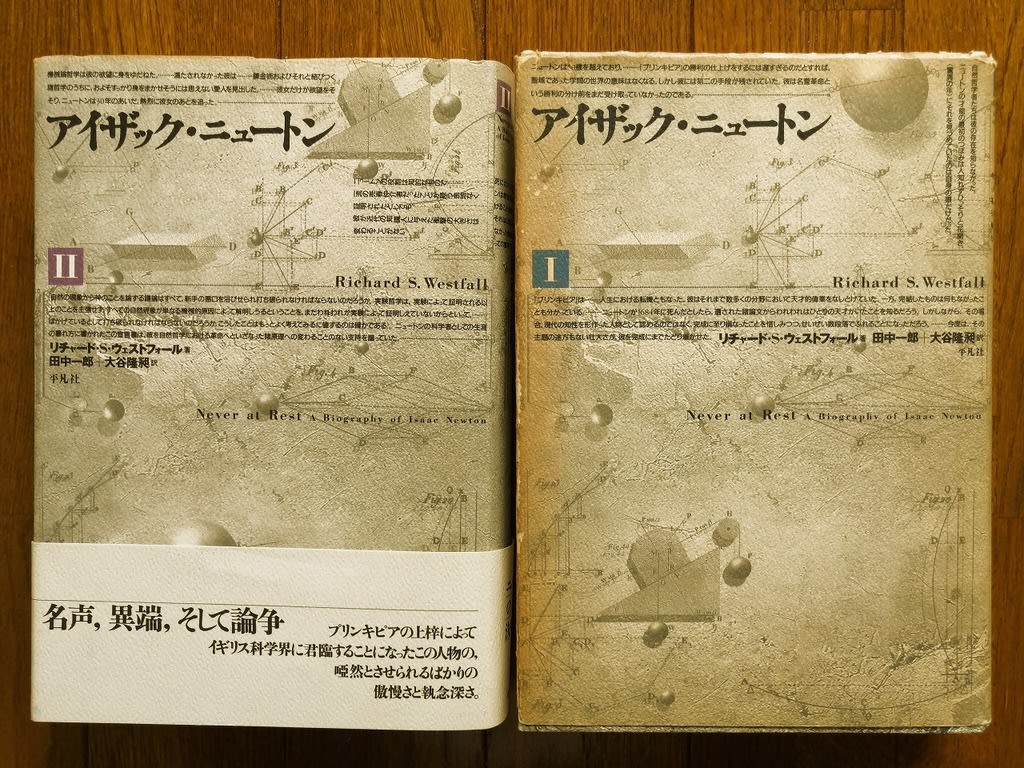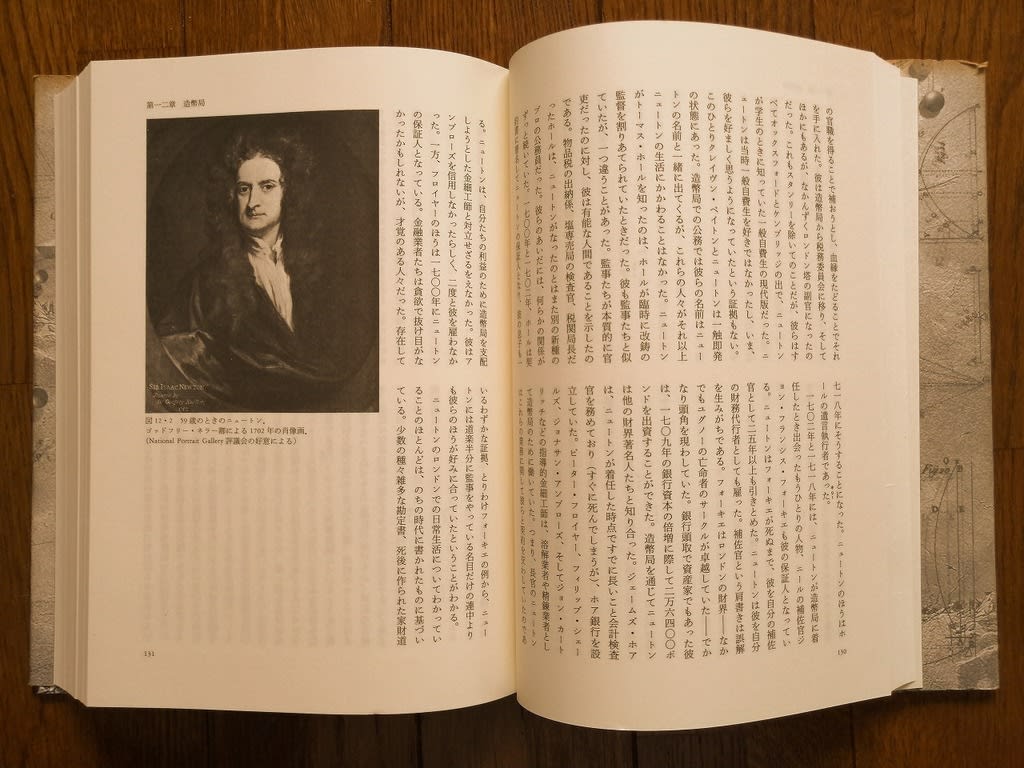サブタイトルが「岩波写真文庫再発見」とある通り、戦後の昭和20年~30年代初めの日本を撮影した写真を集めた本に、赤瀬川源平が自身の体験と当時の様子を綴ったエッセイ。
戦後の生活を知るには、親世代の話を聞くか当時の写真やフィルムを見るしかない。当時の岩波文庫は、様々なテーマを設定して民俗写真を収集した。その写真にまつわる著者の記憶や体験のコメントがとても面白かった。 おそらく当時の写真を見ただけでは何とも思わないだろうが、実体験のコメントをつけるとその写真の持つ意味が大きくなる。これは現代のインスタやFacebookの写真にも言える。芸術写真には言葉は必要ないけれど、スナップ写真には言葉による補足があったほうが良い。
この本で取り上げたテーマは、捕鯨、肖像写真、野球、自動車、蒸気機関車、芸術、電話、造船、馬など。現代では見られなくなった物や風景をピックアップしている。
面白かったのは蛔虫をテーマとした写真。自分も蛔虫体験がある。昭和40年代初めに奄美大島に住んでいたが、当時の奄美は、昭和20年代のような雰囲気だった。電話は数軒に1台しかなく、道路は大半がダートで雨天時は水たまりだらけ、給食はクジラ肉に脱脂粉乳、日本本土とは全く違う世界だった。当然、体内に蛔虫がいるのが普通で、便に白い小さな蛆虫が一緒に出てきたり、ヒモのような蛔虫が肛門から出てきた記憶がある。当時の写真を見ながら著者のユーモラスな文章を読んでいると、当時の記憶が色々と蘇ってきた。でも、こういう昭和の写真集を見て、懐かしさを感じるのは歳を取った証拠なのかもしれない。(^^;)