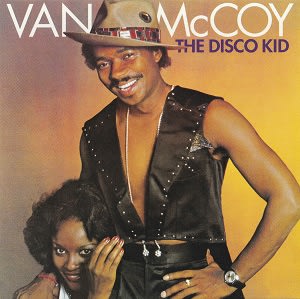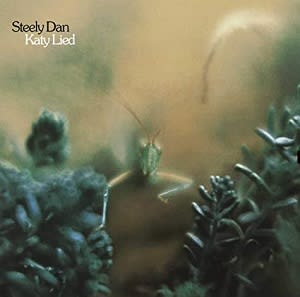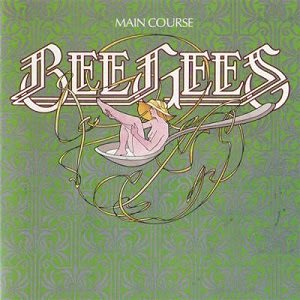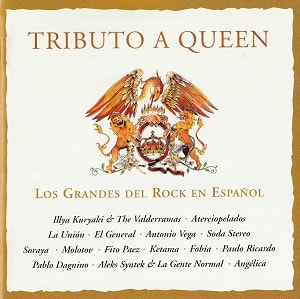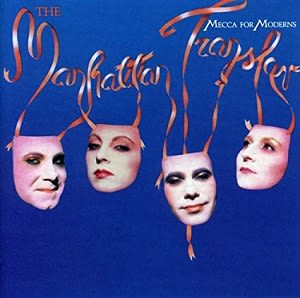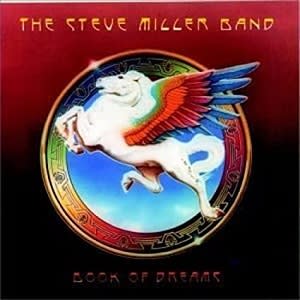これを読んでいる皆さんの中にも、いわゆる時間貸し駐車場を利用される人は多いと思う。僕もしょっちゅう利用している(公私共に)のだが、謎というか不思議な事がある。利用後、自動精算機で料金を支払う際、僕は領収書が必要なので、金を入れてから領収書発行ボタンを押して領収書を受け取るのだが、領収書出口にその領収書が何枚も溜まっている事がよくある。一回の精算に対して領収書は一枚しか出ないので、自分のではない領収書がたくさんある、つまり金は払っても領収書を持って行かない人が多い、という事なのだが、これが非常に謎で、前述したように、領収書は領収書発行ボタンを押さなければ出てこない、つまり領収書が欲しいから発行ボタンを押す訳で、じゃあ何故、わざわざ領収書を要求しているにも関わらず発行された領収書を持って行かないのか。持って行かないのであれば、発行ボタンを押す行為が実に無駄というか無意味である。なのに何故領収書発行ボタンを押すのか。非常ベルであれ呼び鈴であれ、ボタンを見ると押さずにはいられない、という習性の人がよくいるが、それと同じなのか。
とにかくよく分からん。領収書が何枚も溜まってると、自分のがどれなのか分からなくなるので、発行されたら不要でも持ち帰って貰いたいものだ。
領収書というかレシートと言えば、インボイス制度が導入されてあーちゃらこーちゃら言ってるにも関わらず、会計の際レシートをくれない店は今でも結構多い(バーやスナックは別にいいけど)。個人的には、レシートを出さない店って、脱税してますよ、と公言してるように思えて仕方ないので、会計の内容はともかくレシートは発行して欲しい。非課税事業者だからとかいうのはこっちには関係なくて、レシートがある事こそ明朗会計の証しと思うのだが。
という訳で(どーゆー訳で?)最近買ったCDから。

以前にも触れたが、中森明菜の通算10作目のオリジナル・アルバム(1986年発表)の、デビュー40周年を記念した復刻盤である。あの問題作『不思議』の次だったので、一体どういう内容になるのか興味津々だったが、アダルトな雰囲気を漂わせるアルバムとなった。後に物議を醸した竹内まりや作詞・作曲の「駅」が収録されているアルバムでもある。
本作での明菜は、声を張らずに囁くような歌い方に徹していて、AOR的な曲調とアレンジの曲が大半を占めている事もあり、非常に落ち着いたムードである。その分、歌詞が聴き取りにくいというのもあって、賛否は分かれてたような。個人的には、こういうのも、それはそれでいいんじゃないの、なんて感じで聴いていた。今改めて聴いても、その印象に変化はなかった。ただ、やはり気になってしまうのは「駅」なんである。
以前にも書いたけど、本作収録の「駅」を聴いて、作者の竹内まりやの夫である山下達郎が激怒した、という話がある。解釈がひどすぎるという訳だ。達郎は竹内まりや自身の歌でこの曲を発表するように働きかけ、その際はアレンジもやらせてくれ、と頼んだそうな。もちろん、明菜版「駅」に相当な不満があった故である。このことは、竹内まりやのベスト盤のライナーに、達郎自身が書いているらしいので、単なる噂話ではないのだろう。ま、その辺については、好みや感覚の問題でもあり、僕としてはどちらの肩も持つつもりはないのだが、『CRIMSON』に於ける「駅」はちょっと浮いてるように思う。
前述した通り、『CRIMSON』は都会的でアダルトな雰囲気のアルバムだ。制作時のコンセプトが、若い(=当時の明菜と同世代)女性それも都会に住む独身の女性の支持を得る、という事だったらしく、作詞も作曲も全て女性ライターで固め、作曲に関しては全10曲中竹内まりやと小林明子が5曲づつ、編曲は女性ではないが(竹内作品は椎名和夫、小林作品は鷺巣詩郎)、ブックレットの写真と相俟って、コンセプト自体は成功してると思う。けど「駅」はちょっと違う雰囲気だ。決して明るい曲調ではない上に、明菜の囁くような歌い方が「駅」に関しては逆効果で、他の収録曲以上にくぐもったような感じで歌詞が分からない。アレンジも「駅」だけは歌謡曲調になってしまい、コンセプトにそぐわない感じ。これは「駅」が悪いのではなく、「駅」を『CRIMSON』に収録してしまったのが失敗だったのではなかろうか。この曲だけアルバムから外し、歌い方を変えてシングルとして発表した方が良かったような気がする。
聞くところによると、「駅」の竹内まりやによるデモが完璧な出来映えで、明菜は一体どうしたらいいのか、と困ってしまったらしい。だからと言って、あれはないよな。山下達郎の肩を持つつもりはないが(笑)
と、そこを除けば良いアルバムである。実は、本作の竹内まりや提供の5曲のうち、「駅」以外にも一曲やや浮いてる曲があって、それがラストを飾る「ミック・ジャガーに微笑みを」で、タイトルからも想像出来る通り、ロックンロール風の作品で、アルバムのコンセプトとは合わない感じなのだが、ちょっと手を加える事で、無理なくアルバムにはまるようになった。何をしたかというと、女性(明菜か)が部屋で聞いているラジカセからこの曲が流れてくる、とう設定にした訳だね。これが実に大成功。個人的にも、実はこの「ミック・ジャガーに微笑みを」がベスト・トラック要するに推し曲だったりする。途中に♪フーフーと合いの手(笑)が入るのもいい。歌詞はちと他愛もないんだけど^^;
という訳で、色々問題はあれど、明菜が絶好調だった時期のアルバムであり、なんだかんだで内容は素晴らしいと思う。やっぱりこの頃の明菜はいいな。
続いては、

新しいものは知らない・聞いてない・分からない、の3重苦である僕であるが(笑)、現代のアーティストでも、たまに気になるのもあったりするのだ。最近の洋楽だと、ブルーノ・マースとザ・ウィークエンドあたりかな。
で、ザ・ウィークエンドである。↑のスペルが間違ってるよ、と言われそうだが、これは間違いではなく正式な名前である。WeekendではなくWeekndにしたのは、他と差別化したかったから、らしい。ま、詳しい事は知らないけど、ここ10年くらいアメリカでは大人気のバンドというか、エイベル・テスファイ(1990年生まれというから若い)というカナダ出身のシンガー・ソングライターによるプロジェクトである。僕が何故このザ・ウィークエンドを知ってるのかというと、2020年に全米No.1となった「Blinding Lights」をFMで偶然聞いたからだ。一度や二度ではなく、それこそヘビロテ状態で、80’s風というか、ずばり言ってしまうとa-haの「Take On Me」みたいな曲調だったもんで興味を持ち(笑)、他にもFMで何曲か聞いてるうちにCDを買ってしまった、という次第。
で、このCDだが、僕にとっては初めての珍しい仕様になっていて、なんと、ブックレットにアーティスト名はおろか、曲名も作詞作曲やプロデューサー等のクレジットも全く記載されていないのである。従って曲も分からない。知ってるのは「Blinding Lights」だけ。仕方ないので、ネットで曲名と曲順を調べた^^; 全体の印象としては、アップテンポが以外と少なく、静かに展開する曲が多いのだが、曲がしっかりと作られているせいか、退屈することはない。音もほとんどシンセのみ、それも音数が少なくシンプルな作りで、なんかストイックな感じがする。そう、「Blinding Lights」みたいな曲もあるけど、全体的にはストイックな雰囲気のアルバムだ。こういうのって、説教がましいというかスビリチュアル系というか意識高い系というか、そういう方向に走りそうだけど、なかなかのポップセンスのせいか、そっちには向かわずギリギリ踏みとどまってる感じ。ま、とにかく、「Blinding Lights」は良い曲だ(笑) エイベル・テスファイという人、なかなかに才能豊かと見た。
あ、そういや、クイーン+アダム・ランバートの来日公演ドームツアーもそろそろ始まるのかな。行かれる人は是非楽しんできて下さい。僕は行きませんが(笑)