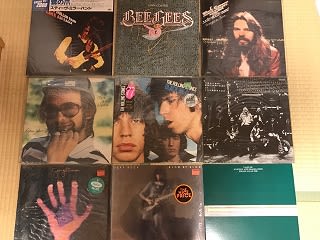先日、マーティン・スコセッシ監督の『沈黙-サイレンス-』を見た。あの有名な遠藤周作の小説が原作である(余談ながら、最近、同じ遠藤周作の小説『真昼の悪魔』がテレビドラマ化されている。偶然?)。遠藤周作は自身もクリスチャンとして知られているけど、その日本人のクリスチャンが書いた重いテーマの作品を、アメリカ人のマーティン・スコセッシ監督がどんな解釈で映画化するのか、結構興味津々だった。キリスト教国家アメリカで、この作品がどう受け止められるのだろう。
遠藤周作の小説は若い頃読んだ。衝撃的だった。ネタバレになるかもしれんが、神のしもべたちが苦しんでいて、神の助けを必要としているのに、神は声すらかけてくれない。本当に神はおられるのか? 本当に神は我々しもべの事を思っていて下さるのか? 本当に神は我々に道を示して下さるのか? 僕のような無宗教とは違い、信徒にとっては重大な問題である。というか、信徒というのは神を信じているのが当たり前であり、その信徒がわずかでも神の存在を疑う、という事自体あり得ないのであり、矛盾した行いなのてあるにもかかわらず、いや矛盾しているからこそ、小説の主人公は苦しみ続ける。これ自体、キリスト教徒として失格と言えるのではなかろうか。アメリカ人は、そういうのを許すのか?
という訳で、『沈黙-サイレンス-』である。ま、確かに、原作同様暗く重い映画だった。キリシタン達をあの手この手で拷問するシーンには、目を背けずにはいられなかった。信徒たちの、そして宣教師たちの苦しみはイヤというほど伝わってくる。宣教師は悩み、苦しむ。自分が転べば(棄教すれば)信徒たちは苦しみから解放される。どうしたらいいのか。でも神は何も言ってくれない。彼の苦しみは果てしなく続く。
ネタバレになるかもしれんが、原作では、悩み苦しんだ末に、この宣教師は棄教し、日本人の僧侶となる。いや、映画でも同じだ。けど、さすがハリウッド映画である。かような、キリスト教徒にとって到底受け入れられない結末を、ただで許す訳にはいかないと見えて、予防線を張ってある。言い訳とか逃げ道とかに言い換えてもいい。その逃げ道(と僕には思えたもの)については、ここでは触れずにおくが、良くも悪くもハリウッドというか、自国民の反感を買わないように手は打っている(笑) さすがに、巨匠マーティン・スコセッシと言えども、その呪縛からは逃れられないようだ。アメリカ人というか、キリスト教徒の業は深い(意味不明)
という訳で、良い映画ではあるものの、手放しでは評価出来ない、中途半端な作品になってしまったのは残念だ。所詮、遠藤周作が小説に書き綴った思いは、日本人だからこそ理解出来る類のものなのか。
あと、ついでに言うと、登場人物の大半は日本人なのだが、ほとんどがカタコトとはいえ英語が喋れる、というのも、ハリウッド映画のお決まりだな、と思った。それと、主人公の宣教師の同僚で一緒に日本に来て、棄教を拒んで死んでいく宣教師が、アンガールズの山根によく似てたなぁ(爆)
ところで、『沈黙』といえば、この曲をご存知の人はどれくらいいらっしゃるのか?
https://www.youtube.com/watch?v=F7W8NWw2HtQ
そう、野口五郎の「沈黙」である。1977年のシングル曲だ。人気絶頂の頃である。この頃の野口五郎は、正に飛ぶ鳥落とす勢い、出す曲出す曲ヒット・チャートを賑わせていた。そんな時期の一曲がこの「沈黙」であり、ツインギターによるイントロのフレーズが印象的だった。確かに、40年近くが経過した今となっては、知る人ぞ知る名曲に過ぎないんだろうな、とは思ってたし、それなりに覚悟(?)はしてたんだけど、こないだ行ったカラオケボックスには、やっぱりこの曲はなかった(笑)
ま、なんたって野口五郎と言えば、「私鉄沿線」であり「甘い生活」であったりする訳で、これらにも顕著なように、哀愁漂うメロディとドラマティックな曲構成の昭和青春歌謡路線なのである。野口五郎自身はギターが得意で、青春歌謡路線ではなく、もっとAOR風の音楽を志向していたのは有名な話だけど、でもやっぱり彼には青春歌謡が似合う。「私鉄沿線」に代表されるように、この手の曲は素人が歌うと平坦になってしまって、なかなか盛り上げる事が出来ない。野口五郎みたいに感動的に歌い上げる、なんて事は不可能。結構難しいのだ。やっぱり五郎って上手いよな、って改めて思う。
僕自身は、この「沈黙」の他、「針葉樹」とか「季節風」とか好きだった。当時は知らなかったけど、「沈黙」の作詞は松本隆で、サビの♪どんな気がする~、というフレーズはディランのあの曲から貰ってきたのか? みたいな事を書いてるのを近年読んだ。松本隆とディランって、切っても切れないのかね(笑)
ところで、さらに「沈黙」と言えば、こんなのもある。
https://www.youtube.com/watch?v=QkqAEjZfVv8
アラン・パーソンズ・プロジェクト(APP)の1979年のヒット曲である。邦題は「Damned If I Do」、後々ヒット・チャートの常連となるAPPであるが、思い起こせばこの曲が初めてのヒット曲だったような気がする。というか、APPってシングルカットするの?なんて驚いた記憶がある。40年近く前のことだが(爆)
ほとんどの人がそうだと思うけど、APPは単発的なプロジェクトだと、僕も思っていた。1976年の『怪奇と幻想の物語~エドガー・アラン・ポーの世界』というアルバム自体、ポーの作品をモチーフにしたコンセプト・アルバムだったし、このアルバムの為だけに、ミュージシャンが集められたのだ、と思っていたのである。なのでその1年後(だったかな?笑)、APPの新譜というのを渋谷陽一の『ヤングジョッキー』で紹介してたのには驚いた。あれ、単発じゃなかったの? って感じ。そしたら、いつの間にか、単発どころか、押しも押されもせぬヒット・メーカーになっていた。人の人生なんて分からないもんだ(意味不明)
数あるAPPのヒット曲の中でも、僕が好きなのは「沈黙」の他、「タイム」「ドント・アンサー・ミー」あたりかな(聞いてません)
さらに「沈黙」というと(もういいです)
遠藤周作の小説は若い頃読んだ。衝撃的だった。ネタバレになるかもしれんが、神のしもべたちが苦しんでいて、神の助けを必要としているのに、神は声すらかけてくれない。本当に神はおられるのか? 本当に神は我々しもべの事を思っていて下さるのか? 本当に神は我々に道を示して下さるのか? 僕のような無宗教とは違い、信徒にとっては重大な問題である。というか、信徒というのは神を信じているのが当たり前であり、その信徒がわずかでも神の存在を疑う、という事自体あり得ないのであり、矛盾した行いなのてあるにもかかわらず、いや矛盾しているからこそ、小説の主人公は苦しみ続ける。これ自体、キリスト教徒として失格と言えるのではなかろうか。アメリカ人は、そういうのを許すのか?
という訳で、『沈黙-サイレンス-』である。ま、確かに、原作同様暗く重い映画だった。キリシタン達をあの手この手で拷問するシーンには、目を背けずにはいられなかった。信徒たちの、そして宣教師たちの苦しみはイヤというほど伝わってくる。宣教師は悩み、苦しむ。自分が転べば(棄教すれば)信徒たちは苦しみから解放される。どうしたらいいのか。でも神は何も言ってくれない。彼の苦しみは果てしなく続く。
ネタバレになるかもしれんが、原作では、悩み苦しんだ末に、この宣教師は棄教し、日本人の僧侶となる。いや、映画でも同じだ。けど、さすがハリウッド映画である。かような、キリスト教徒にとって到底受け入れられない結末を、ただで許す訳にはいかないと見えて、予防線を張ってある。言い訳とか逃げ道とかに言い換えてもいい。その逃げ道(と僕には思えたもの)については、ここでは触れずにおくが、良くも悪くもハリウッドというか、自国民の反感を買わないように手は打っている(笑) さすがに、巨匠マーティン・スコセッシと言えども、その呪縛からは逃れられないようだ。アメリカ人というか、キリスト教徒の業は深い(意味不明)
という訳で、良い映画ではあるものの、手放しでは評価出来ない、中途半端な作品になってしまったのは残念だ。所詮、遠藤周作が小説に書き綴った思いは、日本人だからこそ理解出来る類のものなのか。
あと、ついでに言うと、登場人物の大半は日本人なのだが、ほとんどがカタコトとはいえ英語が喋れる、というのも、ハリウッド映画のお決まりだな、と思った。それと、主人公の宣教師の同僚で一緒に日本に来て、棄教を拒んで死んでいく宣教師が、アンガールズの山根によく似てたなぁ(爆)
ところで、『沈黙』といえば、この曲をご存知の人はどれくらいいらっしゃるのか?
https://www.youtube.com/watch?v=F7W8NWw2HtQ
そう、野口五郎の「沈黙」である。1977年のシングル曲だ。人気絶頂の頃である。この頃の野口五郎は、正に飛ぶ鳥落とす勢い、出す曲出す曲ヒット・チャートを賑わせていた。そんな時期の一曲がこの「沈黙」であり、ツインギターによるイントロのフレーズが印象的だった。確かに、40年近くが経過した今となっては、知る人ぞ知る名曲に過ぎないんだろうな、とは思ってたし、それなりに覚悟(?)はしてたんだけど、こないだ行ったカラオケボックスには、やっぱりこの曲はなかった(笑)
ま、なんたって野口五郎と言えば、「私鉄沿線」であり「甘い生活」であったりする訳で、これらにも顕著なように、哀愁漂うメロディとドラマティックな曲構成の昭和青春歌謡路線なのである。野口五郎自身はギターが得意で、青春歌謡路線ではなく、もっとAOR風の音楽を志向していたのは有名な話だけど、でもやっぱり彼には青春歌謡が似合う。「私鉄沿線」に代表されるように、この手の曲は素人が歌うと平坦になってしまって、なかなか盛り上げる事が出来ない。野口五郎みたいに感動的に歌い上げる、なんて事は不可能。結構難しいのだ。やっぱり五郎って上手いよな、って改めて思う。
僕自身は、この「沈黙」の他、「針葉樹」とか「季節風」とか好きだった。当時は知らなかったけど、「沈黙」の作詞は松本隆で、サビの♪どんな気がする~、というフレーズはディランのあの曲から貰ってきたのか? みたいな事を書いてるのを近年読んだ。松本隆とディランって、切っても切れないのかね(笑)
ところで、さらに「沈黙」と言えば、こんなのもある。
https://www.youtube.com/watch?v=QkqAEjZfVv8
アラン・パーソンズ・プロジェクト(APP)の1979年のヒット曲である。邦題は「Damned If I Do」、後々ヒット・チャートの常連となるAPPであるが、思い起こせばこの曲が初めてのヒット曲だったような気がする。というか、APPってシングルカットするの?なんて驚いた記憶がある。40年近く前のことだが(爆)
ほとんどの人がそうだと思うけど、APPは単発的なプロジェクトだと、僕も思っていた。1976年の『怪奇と幻想の物語~エドガー・アラン・ポーの世界』というアルバム自体、ポーの作品をモチーフにしたコンセプト・アルバムだったし、このアルバムの為だけに、ミュージシャンが集められたのだ、と思っていたのである。なのでその1年後(だったかな?笑)、APPの新譜というのを渋谷陽一の『ヤングジョッキー』で紹介してたのには驚いた。あれ、単発じゃなかったの? って感じ。そしたら、いつの間にか、単発どころか、押しも押されもせぬヒット・メーカーになっていた。人の人生なんて分からないもんだ(意味不明)
数あるAPPのヒット曲の中でも、僕が好きなのは「沈黙」の他、「タイム」「ドント・アンサー・ミー」あたりかな(聞いてません)
さらに「沈黙」というと(もういいです)